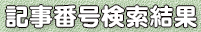… スポンサーリンク …
| [14722] 2003年 5月 5日(月)20:32:14 | ありがたき さん |
| 華のお江戸は八百八町(by平次) | |
[14611]special-weekさん
ところで江戸の範囲ってどこまでだろう?
江戸は拡大し続けた街(町)なので、時期や見方で異なるんでしょうが、例えば「御府内」という江戸の「市街地」の範囲とされる言葉がありますね。
化政文化の真っ只中のお話で、文化元年(1804年)の幕府の定義では、江戸城を中心に四里四方の範囲とされていたそうです。
その後、文政元年(1818年)に目付牧野助左衛門から出された「御府内外境筋之儀」をうけて幕府が地図上に引いた「朱線」で正式に府内外を区別したそうです。おおよその範囲は、南から時計回りに目黒川、神田上水、荒川・石神井川下流、中川で、囲まれた域だそうで。
また「墨引」で町奉行支配の範囲も示され、町奉行・勘定奉行・寺社奉行の「行政上」の区分けがされたとのことです。
ここの皆さんの中にも読んだ方も多いんではないでしょうか、日本実業出版社の「東京の地名のわかる事典」という本で上記のお話に地図入り解説があります。ご参考までに
ところで江戸の範囲ってどこまでだろう?
江戸は拡大し続けた街(町)なので、時期や見方で異なるんでしょうが、例えば「御府内」という江戸の「市街地」の範囲とされる言葉がありますね。
化政文化の真っ只中のお話で、文化元年(1804年)の幕府の定義では、江戸城を中心に四里四方の範囲とされていたそうです。
その後、文政元年(1818年)に目付牧野助左衛門から出された「御府内外境筋之儀」をうけて幕府が地図上に引いた「朱線」で正式に府内外を区別したそうです。おおよその範囲は、南から時計回りに目黒川、神田上水、荒川・石神井川下流、中川で、囲まれた域だそうで。
また「墨引」で町奉行支配の範囲も示され、町奉行・勘定奉行・寺社奉行の「行政上」の区分けがされたとのことです。
ここの皆さんの中にも読んだ方も多いんではないでしょうか、日本実業出版社の「東京の地名のわかる事典」という本で上記のお話に地図入り解説があります。ご参考までに
| [14798] 2003年 5月 6日(火)21:52:53【1】 | Issie さん |
| 本郷もかねやすまでは江戸のうち | |
[14611] special-week さん
[14722] ありがたき さん
「江戸の範囲」については,タイトルのような有名な川柳があります。
「かねやす」というのは当時有名な商店の名前で,1986年当時も化粧品・小間物屋として営業中だったそうです(平凡社『アトラス東京 -地図でよむ江戸~東京』,1986年)。だいたい,現在の本郷3丁目交差点のあたりですね。
一般的な認識としては,中山道口の「かねやす」に加えて,甲州街道口の「四谷大木戸」(現四谷4丁目交差点),奥州街道口の「小塚原」(骨ヶ原;現大関横町交差点=地下鉄三ノ輪駅付近),東海道口の「高輪大木戸」(札の辻=現三田3丁目)あたりが「江戸の極まり」というところだったのではないでしょうか。
江戸時代の行政機構というのは,近代以降の行政システムとは根本的な部分から違う原理で営まれていたので,現代の「東京都」なり「23区」なりと同じ感覚で「江戸の範囲」を規定することはできません。
さしあたり,江戸の「町人町」の区域は「(江戸)町奉行」の管轄,郊外の農村部は「勘定奉行」の管轄,という区分があるわけですが,このあたりの線引きは必ずしも体系的ではない。場合に応じて,かなりの異同があったようです。
「江戸」の市街地内でも,お寺や神社の境内は「寺社奉行」の管轄であり,旗本・御家人屋敷は「目付」の支配,大名屋敷は大名自身を介して「大目付」の管轄,というわけで,一体的・一円的な行政が行われていたわけではありません。
「町」というのは本来,町奉行支配下の町人町の区域での「自治」単位の呼称でした(だから,町人町ではなかった武家屋敷地区には「町名」がなかったのです)。
そのようなわけで,「江戸の範囲」というのは時により場合により,さまざまに変動するものでした。
…といっても,それではあまりに不便なので,江戸時代後期になると「江戸の範囲」をある程度確定しておこう,という動きが生じます。
そうして指定されたのが [14722] で ありがたき さんが紹介されている「朱引き内」であり,「墨引」という線でした。
1989年に東京都が発行した「江戸復元図」によれば,1869(明治2)年の「朱引き線」は,以下の点を通過しています(*印は現在の地名)。
芝札の辻~麻布三之橋~麻布仙台坂~*日赤病院下交差点~*青山学院大学キャンパス~*青山通り~*外苑前交差点~*神宮外苑西縁~*新宿御苑東縁~*市谷富久町交差点~*靖国通り~*市谷住吉町交差点~*地下鉄若松河田駅~*大久保通り~*牛込若松町交差点~*地下鉄早稲田駅~*都立新宿山吹高校~江戸川橋~護国寺外縁~*不忍通り~*千石2丁目バス停~*白山下交差点~*白山1丁目交差点~*日本医大病院南縁~*藪下通り~*団子坂上交差点~*谷中小学校角~*日暮里駅~*下谷柳通り交差点~*千束1丁目交差点~*西浅草3丁目交差点~*浅草馬道交差点~*東浅草1丁目交差点~山谷堀~吾妻橋~北十間川~横十間川~小名木川~大横川~仙台堀川~富岡八幡宮外縁~永代橋
…というわけで,品川宿や内藤新宿(新宿)はもちろん,巣鴨や駒込,新吉原(千束)や洲崎(東陽町)の遊郭や岡場所までもが「江戸の外」なのですね。佃島や石川島も「朱引き」の外なのですが,ここは別扱いだったのでしょう。
江戸,というよりも「東京」の範囲がある程度確定するのは明治維新後,「大区・小区制」を経て1878(明治11)年の郡区町村編制法で「東京15区」の範囲が定められてからのことです。
このときの「15区」の外縁は,1889(明治22)年の「市制・町村制」施行による「東京市」の外縁よりもかなりの凹凸のあるものでした(「15区」の外縁は概ね“朱引き線”よりも外側を通過しています)。
たとえば,市制施行後の「東京市深川区」は横十間川をもって南葛飾郡下の亀戸・大島・砂各村に境することになるのですが,それ以前の「深川区」は竪川や小名木川に沿って東へ延びる区域がある一方,横十間川の西側にも「南葛飾郡」に属する村が存在していました。
下谷の根岸や谷中,牛込と早稲田,青山と渋谷の境界や麻布の外縁についてもかなりの出入りがありました。
したがって,「東京市」の各区を編成するにあたって,旧15区の範囲がそのまま継承されたわけではなく,“郡部”に属していた村々の一部が「東京市○○区」に編入される一方で,「東京市」の範囲からはみ出た「旧○○区」の一部は反対に周辺の郡部各町村に編入されています。
そのような意味では,「東京」の範囲が明確に固定化したのは,ようやく1889年の市制施行時点ということになるのかもしれません。
[14722] ありがたき さん
「江戸の範囲」については,タイトルのような有名な川柳があります。
「かねやす」というのは当時有名な商店の名前で,1986年当時も化粧品・小間物屋として営業中だったそうです(平凡社『アトラス東京 -地図でよむ江戸~東京』,1986年)。だいたい,現在の本郷3丁目交差点のあたりですね。
一般的な認識としては,中山道口の「かねやす」に加えて,甲州街道口の「四谷大木戸」(現四谷4丁目交差点),奥州街道口の「小塚原」(骨ヶ原;現大関横町交差点=地下鉄三ノ輪駅付近),東海道口の「高輪大木戸」(札の辻=現三田3丁目)あたりが「江戸の極まり」というところだったのではないでしょうか。
江戸時代の行政機構というのは,近代以降の行政システムとは根本的な部分から違う原理で営まれていたので,現代の「東京都」なり「23区」なりと同じ感覚で「江戸の範囲」を規定することはできません。
さしあたり,江戸の「町人町」の区域は「(江戸)町奉行」の管轄,郊外の農村部は「勘定奉行」の管轄,という区分があるわけですが,このあたりの線引きは必ずしも体系的ではない。場合に応じて,かなりの異同があったようです。
「江戸」の市街地内でも,お寺や神社の境内は「寺社奉行」の管轄であり,旗本・御家人屋敷は「目付」の支配,大名屋敷は大名自身を介して「大目付」の管轄,というわけで,一体的・一円的な行政が行われていたわけではありません。
「町」というのは本来,町奉行支配下の町人町の区域での「自治」単位の呼称でした(だから,町人町ではなかった武家屋敷地区には「町名」がなかったのです)。
そのようなわけで,「江戸の範囲」というのは時により場合により,さまざまに変動するものでした。
…といっても,それではあまりに不便なので,江戸時代後期になると「江戸の範囲」をある程度確定しておこう,という動きが生じます。
そうして指定されたのが [14722] で ありがたき さんが紹介されている「朱引き内」であり,「墨引」という線でした。
1989年に東京都が発行した「江戸復元図」によれば,1869(明治2)年の「朱引き線」は,以下の点を通過しています(*印は現在の地名)。
芝札の辻~麻布三之橋~麻布仙台坂~*日赤病院下交差点~*青山学院大学キャンパス~*青山通り~*外苑前交差点~*神宮外苑西縁~*新宿御苑東縁~*市谷富久町交差点~*靖国通り~*市谷住吉町交差点~*地下鉄若松河田駅~*大久保通り~*牛込若松町交差点~*地下鉄早稲田駅~*都立新宿山吹高校~江戸川橋~護国寺外縁~*不忍通り~*千石2丁目バス停~*白山下交差点~*白山1丁目交差点~*日本医大病院南縁~*藪下通り~*団子坂上交差点~*谷中小学校角~*日暮里駅~*下谷柳通り交差点~*千束1丁目交差点~*西浅草3丁目交差点~*浅草馬道交差点~*東浅草1丁目交差点~山谷堀~吾妻橋~北十間川~横十間川~小名木川~大横川~仙台堀川~富岡八幡宮外縁~永代橋
…というわけで,品川宿や内藤新宿(新宿)はもちろん,巣鴨や駒込,新吉原(千束)や洲崎(東陽町)の遊郭や岡場所までもが「江戸の外」なのですね。佃島や石川島も「朱引き」の外なのですが,ここは別扱いだったのでしょう。
江戸,というよりも「東京」の範囲がある程度確定するのは明治維新後,「大区・小区制」を経て1878(明治11)年の郡区町村編制法で「東京15区」の範囲が定められてからのことです。
このときの「15区」の外縁は,1889(明治22)年の「市制・町村制」施行による「東京市」の外縁よりもかなりの凹凸のあるものでした(「15区」の外縁は概ね“朱引き線”よりも外側を通過しています)。
たとえば,市制施行後の「東京市深川区」は横十間川をもって南葛飾郡下の亀戸・大島・砂各村に境することになるのですが,それ以前の「深川区」は竪川や小名木川に沿って東へ延びる区域がある一方,横十間川の西側にも「南葛飾郡」に属する村が存在していました。
下谷の根岸や谷中,牛込と早稲田,青山と渋谷の境界や麻布の外縁についてもかなりの出入りがありました。
したがって,「東京市」の各区を編成するにあたって,旧15区の範囲がそのまま継承されたわけではなく,“郡部”に属していた村々の一部が「東京市○○区」に編入される一方で,「東京市」の範囲からはみ出た「旧○○区」の一部は反対に周辺の郡部各町村に編入されています。
そのような意味では,「東京」の範囲が明確に固定化したのは,ようやく1889年の市制施行時点ということになるのかもしれません。
| [33164] 2004年 9月 21日(火)02:26:46 | ryo さん |
| お~江~戸っ!(古っ!) | |
[33148]太白 さん
地図は「西が上」
西が上というのはその方向に天皇の在する京があるという意識のあらわれなのでしょうか?本当は日光の方角(=北)に向けたいと思っていたが、さすがにおそれおおくて・・・私の勝手な想像です。
ちなみに鳥瞰図で書かれた江戸図絵では、西向きに書くことで御城のバックに富士山を描けるなんてメリットがあると聞いたこともあります。
「江戸」の範囲
古い書き込みの引用になりますが、[14798]Issie さん [14722]ありがたき さん あたりが述べておられます。
簡潔にまとめると、江戸の範囲に関して「朱引内」という用語があります。ソース
それまで行政系統(町奉行・寺社奉行など)で解釈がまちまちだったのですが、文政期(1818)に公式見解を定めました。その地図で、朱線で引いた内側を「江戸」と定めたことに由来します。
なお、その地図には墨引の黒線で町奉行の管轄地域も示されています。おおかた朱引より少し狭い範囲ですが、何故か目黒付近で朱引をはみ出しているのが目を引きます。
それにしても、役所のタテ割り行政は今も昔も変わらないようで・・・
話は少し変わりますが、新宿の語源である「内藤新宿」とは、信州高遠藩(絵島事件とコヒガンザクラで有名な)の内藤家の屋敷(現新宿御苑)の一部を用地として開設された、まさに「新」宿であることはここに来る皆様なら常識だと思います。私も知っていました。
しかし、ここは一度廃止された歴史があることまでは知りませんでした。1718(享保3)に民間の要請で開設されたのですが、20年ほどで廃止され、1772年(明和9)に再開されるまで約50年の空白があったとのこと。理由は風紀が大いに乱れたからとのことで、歌舞伎町の源流ここに見る気がします。もっとも、新宿の地名は西遷し、「淀橋」(ヨドバシカメラのヨドバシです)を呑み込んでしまっているので場所は離れていますが。
ソース
地図は「西が上」
西が上というのはその方向に天皇の在する京があるという意識のあらわれなのでしょうか?本当は日光の方角(=北)に向けたいと思っていたが、さすがにおそれおおくて・・・私の勝手な想像です。
ちなみに鳥瞰図で書かれた江戸図絵では、西向きに書くことで御城のバックに富士山を描けるなんてメリットがあると聞いたこともあります。
「江戸」の範囲
古い書き込みの引用になりますが、[14798]Issie さん [14722]ありがたき さん あたりが述べておられます。
簡潔にまとめると、江戸の範囲に関して「朱引内」という用語があります。ソース
それまで行政系統(町奉行・寺社奉行など)で解釈がまちまちだったのですが、文政期(1818)に公式見解を定めました。その地図で、朱線で引いた内側を「江戸」と定めたことに由来します。
なお、その地図には墨引の黒線で町奉行の管轄地域も示されています。おおかた朱引より少し狭い範囲ですが、何故か目黒付近で朱引をはみ出しているのが目を引きます。
それにしても、役所のタテ割り行政は今も昔も変わらないようで・・・
話は少し変わりますが、新宿の語源である「内藤新宿」とは、信州高遠藩(絵島事件とコヒガンザクラで有名な)の内藤家の屋敷(現新宿御苑)の一部を用地として開設された、まさに「新」宿であることはここに来る皆様なら常識だと思います。私も知っていました。
しかし、ここは一度廃止された歴史があることまでは知りませんでした。1718(享保3)に民間の要請で開設されたのですが、20年ほどで廃止され、1772年(明和9)に再開されるまで約50年の空白があったとのこと。理由は風紀が大いに乱れたからとのことで、歌舞伎町の源流ここに見る気がします。もっとも、新宿の地名は西遷し、「淀橋」(ヨドバシカメラのヨドバシです)を呑み込んでしまっているので場所は離れていますが。
ソース
| [33199] 2004年 9月 21日(火)22:51:03【2】 | hmt さん |
| Re:江戸時代の地図を読む | |
[33148]太白さん
この地図が表現する「江戸」の範囲
[33164] ryoさんが「朱引内」のソースとしてリンクされた東京都公文書館のHPには 江戸朱引図 があります。この図には 朱引線(御府内外境)と 町奉行支配境墨筋 とが記載されています。
この「墨引」範囲をたどってみると、東は猿江村のあたり [都営新宿線住吉駅付近] が張り出しているが、その他はほぼ大横川 [三ツ目通りの東の運河] の線です。北は駒込村、西は柏木村・千駄ヶ谷村までが墨引内。そして南は 下高輪町と北品川村の間に墨筋が引かれています。
太白さんの記述はこの「墨引」範囲を指しているようです。
リンク画像は「文政元寅年八月に江戸の範囲確定を評定所で評議し、十二月に老中決済を受けた」という趣旨のことが書いてある右端が切れているのですが、それでも「別紙絵図朱引ノ内ヲ御府内ト相心得」という勘定奉行の公式見解を読み取ることができます。
江戸東京博物館の図録「大江戸八百八町」に収録されている「旧江戸朱引内図」(上記リンク画像と同じ)から、朱引の内側に記入されている村の名を読みとってみました。
南品川町、下大崎村、上大崎村、白金村、中豊沢村、上豊沢村、上渋谷村、隠田村、代々木村、角筈村、鳴子宿、戸塚村、上落合村、長崎村、上板橋村、下板橋村、瀧川村、堀ノ内村、上尾久村、下尾久村、町屋村、三河島村、小塚原町、千住町組中川町、木下村、木下川村、葛西川村、亀戸村、小名木村、萩・又兵衛新田、中里新田村、八郎衛門新田、太郎兵衛新田
ryoさんもご指摘になっていますが、朱引の外にある中目黒村と下目黒村だけが町奉行支配の「墨引内」として突出しています。
ところで、[14798] Issieさんが紹介された
1989年に東京都が発行した「江戸復元図」によれば,1869(明治2)年の「朱引き線」は,以下の点を通過しています
の範囲は、文政元年の朱引の範囲より明らかに縮小されています。「御一新」による見直しがあったのでしょうか?
西が上になります。この描き方は、江戸時代の江戸の地図に共通しています。
上記の江戸朱引図は、東が上になっていますね。
もっとも、同じく東京都公文書館の「江戸府内朱引図」 (乾と坤)は、西が上です。こちらは墨引線がありません。
江戸切絵図は、御城の方角が上になっているものが多いように思いますが、そうでない図もあります。
石川島に人足寄場が設置された18世紀末
鬼平で知られる長谷川平蔵宣以が、1790年に開設した石川島の人足寄場は、技術習得、精神教育、資金提供を通じて収容者の社会復帰を図る施設でした。
新大橋は歴史がある
両国橋の「大橋」に対して「新大橋」と命名されたのですが、それが元禄6年(1693)のことですから、隅田川でも古参ですね。
1912年にカーネギー社の鉄材を使った橋が、木橋時代よりもやや上流の現在位置に架けられました。間もなく市電も開通。
1923年の関東大震災の折に避難の道として多数の人命を救ったこの橋も、1977年に現在の斜張橋に架けかえられ、旧橋の一部は、博物館明治村に保存されています。
溜池は池だった
溜池は江戸時代が始まって間もない1606年に浅野幸長が江戸城外堀として築造したとも伝えられますが、もともと四谷方面から流れていた川の水が自然に滞留する沼地だったのでしょう。
自然のままでは汐が逆流する可能性もあったことから、堰を造って溜池とし、上水の確保にも利用しました。ダムから勢いよく溢れ出る水が流れる下流は汐留川と呼ばれるようになり、汐留は現在は かつて河口があった付近の地名になっています。
明治8年(1875)の東京第二大区小区分絵図ではしっかり水を湛えた池が描かれています。池の下手にある工学寮が1877年に工部大学校に改称されたのですから、工部大学校を建設するために溜池が埋め立てられたわけではありません。
余談ですが、工部大学校址碑は会計検査院の横にあります。その敷地は、ここから文部科学省、霞が関ビル、更には現在の外堀通りの向う側に及んでいた日向延岡藩内藤家の上屋敷跡です。溜池から外堀に落ちた水は延岡藩邸に沿って左折し、虎の御門の前で右折し新橋に向いました。商船三井ビルと虎の門三井ビルのL字形配列は、この左折した外堀の跡です。現在の道路は鍵の手を避けて特許庁前(溜池の跡)から虎ノ門交差点へとカーブしているので、千代田区霞が関三丁目の一部が外堀通りの右側(港区側)に取り残されています。(実は、ここにかつてhmtの職場があったのです。)
それはさておき、
人文社の「明治の東京」(1996)p.60には、明治10年に堰の石を60cmほど除いたら、あれよあれよという間に干上がって、池が小川になってしまったと記されています。
というわけで、明治16年参謀本部測量の5千分一図ではここは湿地になっています。明治20年に埋め立てられました。
昭和になってからここに地下鉄が通りましたが、やはり溜池の跡は地盤が悪かったようで、営団は溜池山王駅開設の前に、地下構造物を造り直す大規模改良工事を行なったようです。
弁天島は陸続き…東側からの参道…19世紀の時点ですでに「池中参道」があったようにうかがえます。
[32193]hmtでリンクした不忍池の最後の項目には「寛文の末(1670)に陸道が築かれ、木橋が架けられ」と記されています。
ア! [33170]KMKZさんが既にレスしておられましたね。
東側からの参道は17世紀から存在したのですが、架橋なので陸続きではないと考えています。
[32231]は西側からの長い「池中参道」についての疑惑に答えたものですが、短い東側についても同様である旨、言葉を添えておくべきだったかもしれません。
この地図が表現する「江戸」の範囲
[33164] ryoさんが「朱引内」のソースとしてリンクされた東京都公文書館のHPには 江戸朱引図 があります。この図には 朱引線(御府内外境)と 町奉行支配境墨筋 とが記載されています。
この「墨引」範囲をたどってみると、東は猿江村のあたり [都営新宿線住吉駅付近] が張り出しているが、その他はほぼ大横川 [三ツ目通りの東の運河] の線です。北は駒込村、西は柏木村・千駄ヶ谷村までが墨引内。そして南は 下高輪町と北品川村の間に墨筋が引かれています。
太白さんの記述はこの「墨引」範囲を指しているようです。
リンク画像は「文政元寅年八月に江戸の範囲確定を評定所で評議し、十二月に老中決済を受けた」という趣旨のことが書いてある右端が切れているのですが、それでも「別紙絵図朱引ノ内ヲ御府内ト相心得」という勘定奉行の公式見解を読み取ることができます。
江戸東京博物館の図録「大江戸八百八町」に収録されている「旧江戸朱引内図」(上記リンク画像と同じ)から、朱引の内側に記入されている村の名を読みとってみました。
南品川町、下大崎村、上大崎村、白金村、中豊沢村、上豊沢村、上渋谷村、隠田村、代々木村、角筈村、鳴子宿、戸塚村、上落合村、長崎村、上板橋村、下板橋村、瀧川村、堀ノ内村、上尾久村、下尾久村、町屋村、三河島村、小塚原町、千住町組中川町、木下村、木下川村、葛西川村、亀戸村、小名木村、萩・又兵衛新田、中里新田村、八郎衛門新田、太郎兵衛新田
ryoさんもご指摘になっていますが、朱引の外にある中目黒村と下目黒村だけが町奉行支配の「墨引内」として突出しています。
ところで、[14798] Issieさんが紹介された
1989年に東京都が発行した「江戸復元図」によれば,1869(明治2)年の「朱引き線」は,以下の点を通過しています
の範囲は、文政元年の朱引の範囲より明らかに縮小されています。「御一新」による見直しがあったのでしょうか?
西が上になります。この描き方は、江戸時代の江戸の地図に共通しています。
上記の江戸朱引図は、東が上になっていますね。
もっとも、同じく東京都公文書館の「江戸府内朱引図」 (乾と坤)は、西が上です。こちらは墨引線がありません。
江戸切絵図は、御城の方角が上になっているものが多いように思いますが、そうでない図もあります。
石川島に人足寄場が設置された18世紀末
鬼平で知られる長谷川平蔵宣以が、1790年に開設した石川島の人足寄場は、技術習得、精神教育、資金提供を通じて収容者の社会復帰を図る施設でした。
新大橋は歴史がある
両国橋の「大橋」に対して「新大橋」と命名されたのですが、それが元禄6年(1693)のことですから、隅田川でも古参ですね。
1912年にカーネギー社の鉄材を使った橋が、木橋時代よりもやや上流の現在位置に架けられました。間もなく市電も開通。
1923年の関東大震災の折に避難の道として多数の人命を救ったこの橋も、1977年に現在の斜張橋に架けかえられ、旧橋の一部は、博物館明治村に保存されています。
溜池は池だった
溜池は江戸時代が始まって間もない1606年に浅野幸長が江戸城外堀として築造したとも伝えられますが、もともと四谷方面から流れていた川の水が自然に滞留する沼地だったのでしょう。
自然のままでは汐が逆流する可能性もあったことから、堰を造って溜池とし、上水の確保にも利用しました。ダムから勢いよく溢れ出る水が流れる下流は汐留川と呼ばれるようになり、汐留は現在は かつて河口があった付近の地名になっています。
明治8年(1875)の東京第二大区小区分絵図ではしっかり水を湛えた池が描かれています。池の下手にある工学寮が1877年に工部大学校に改称されたのですから、工部大学校を建設するために溜池が埋め立てられたわけではありません。
余談ですが、工部大学校址碑は会計検査院の横にあります。その敷地は、ここから文部科学省、霞が関ビル、更には現在の外堀通りの向う側に及んでいた日向延岡藩内藤家の上屋敷跡です。溜池から外堀に落ちた水は延岡藩邸に沿って左折し、虎の御門の前で右折し新橋に向いました。商船三井ビルと虎の門三井ビルのL字形配列は、この左折した外堀の跡です。現在の道路は鍵の手を避けて特許庁前(溜池の跡)から虎ノ門交差点へとカーブしているので、千代田区霞が関三丁目の一部が外堀通りの右側(港区側)に取り残されています。(実は、ここにかつてhmtの職場があったのです。)
それはさておき、
人文社の「明治の東京」(1996)p.60には、明治10年に堰の石を60cmほど除いたら、あれよあれよという間に干上がって、池が小川になってしまったと記されています。
というわけで、明治16年参謀本部測量の5千分一図ではここは湿地になっています。明治20年に埋め立てられました。
昭和になってからここに地下鉄が通りましたが、やはり溜池の跡は地盤が悪かったようで、営団は溜池山王駅開設の前に、地下構造物を造り直す大規模改良工事を行なったようです。
弁天島は陸続き…東側からの参道…19世紀の時点ですでに「池中参道」があったようにうかがえます。
[32193]hmtでリンクした不忍池の最後の項目には「寛文の末(1670)に陸道が築かれ、木橋が架けられ」と記されています。
ア! [33170]KMKZさんが既にレスしておられましたね。
東側からの参道は17世紀から存在したのですが、架橋なので陸続きではないと考えています。
[32231]は西側からの長い「池中参道」についての疑惑に答えたものですが、短い東側についても同様である旨、言葉を添えておくべきだったかもしれません。
… スポンサーリンク …