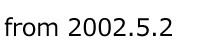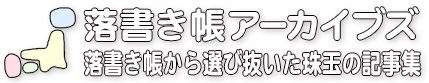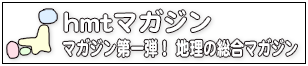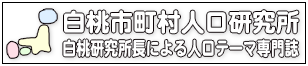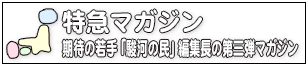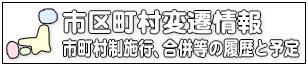明治大正期の都市人口とその後の変遷
トップ > 落書き帳アーカイブズ > 明治大正期の都市人口とその後の変遷
記事数=16件/更新日:2005年4月20日/編集者:YSK
記事数=16件/更新日:2005年4月20日/編集者:YSK
明治大正期の都市人口は、現在のそれとちょっと違った分布となっていました。明治大正期以降の都市の人口とその後の変遷について、まとめてみました。
… スポンサーリンク …
| 記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
|---|---|---|
| [3293] | 2002年9月23日 | 横ちゃん |
| [3295] | 2002年9月23日 | YSK |
| [3296] | 2002年9月23日 | 夜鳴き寿司屋 |
| [3399] | 2002年9月28日 | ニジェガロージェッツ |
| [6150] | 2002年12月8日 | ふぁいん |
| [6165] | 2002年12月8日 | YSK |
| [6167] | 2002年12月9日 | ふぁいん |
| [6169] | 2002年12月9日 | YSK |
| [6170] | 2002年12月9日 | ふぁいん |
| [6184] | 2002年12月9日 | ken |
| [6204] | 2002年12月9日 | YSK |
| [39658] | 2005年4月11日 | ふぁいん |
| [39685] | 2005年4月12日 | ふぁいん |
| [39686] | 2005年4月12日 | ふぁいん |
| [39936] | 2005年4月17日 | ふぁいん |
| [39973] | 2005年4月18日 | ken |
| [3293] 2002年 9月 23日(月)20:46:43 | 横ちゃん さん |
| 昔はどうだった | |
昨今の大都市圏への人口集中・過密化、それに伴う地方の人口減少・過疎化を見るにつけ、田舎出身の私としては将来の地方のあり方を心配しております。
ところで、現在でこそ東京都が人口が一番多いですが、明治時代は新潟県が一番だというデータを見たことがあります。明治時代、大正時代、昭和初期等の古い時代の都道府県人口ランキング及び都市別人口ランキングはないでしょうか。
あまり過去のことにさかのぼるのは、このHPの趣旨から外れるかもしれませんが、現在のような大都市、地方の格差の無い、地方はなやかりし時代のことが知りたかったものですから。
ところで、現在でこそ東京都が人口が一番多いですが、明治時代は新潟県が一番だというデータを見たことがあります。明治時代、大正時代、昭和初期等の古い時代の都道府県人口ランキング及び都市別人口ランキングはないでしょうか。
あまり過去のことにさかのぼるのは、このHPの趣旨から外れるかもしれませんが、現在のような大都市、地方の格差の無い、地方はなやかりし時代のことが知りたかったものですから。
| [3295] 2002年 9月 23日(月)23:33:50 | YSK さん |
| 明治・大正期の都市人口 | |
[3293]
明治・大正期の都市人口のランキングデータが手元にあるので、ご紹介します。
1876(明治9) 1920(大正9)
1 東京 1,121,883 1 東京 2,173,201
2 大阪 361,694 2 大阪 1,252,983
3 京都 245,675 3 神戸 608,644
4 名古屋 131,492 4 京都 591,323
5 金沢 97,654 5 名古屋 429,997
6 横浜 89,554 6 横浜 422,938
7 広島 81,954 7 長崎 176,534
8 神戸 80,446 8 広島 160,510
9 仙台 61,709 9 函館 144,749
10 徳島 57,456 10 呉 130,362
11 和歌山 54,868 11 金沢 129,265
12 富山 53,556 12 仙台 118,984
13 函館 45,477 13 小樽 108,113
14 鹿児島 45,097 14 鹿児島 103,180
15 熊本 44,384 15 札幌 102,580
16 堺 44,015 16 八幡 100,235
17 福岡 42,617 17 福岡 95,381
18 新潟 40,776 18 岡山 94,845
19 長崎 38,229 19 新潟 92,130
20 高松 37,698 20 横須賀 89,879
21 福井 37,376 21 佐世保 87,022
22 静岡 36,838 22 堺 84,999
23 松江 33,381 23 和歌山 83,500
24 岡山 32,989 24 渋谷 80,799
25 前橋 32,981 25 静岡 74,093
26 下関 30,825 26 下関 72,300
27 八幡 29,487 27 門司 72,111
28 秋田 29,225 28 熊本 70,388
29 米沢 29,203 29 徳島 68,457
30 鳥取 28,275 30 豊橋 65,163
出典 古厩忠夫(1997)『裏日本-近代日本を問いなおす-』岩波新書
なお、このデータの原典である『明治大正国勢要覧』について詳細を知らないので断言できませんが、「門司」などが見えることから、統計年次時点での地方自治制度に基づく区域内の人口をまとめたものと思われます。なお、「八幡」は現在の北九州市八幡です。「渋谷」は旧東京市合併直前の旧渋谷町のことだと思われますが、はっきりとは分かりません。
また、最新の市のランキングはこのホームページのデータを参照してくださいね。
明治期のデータを見ると、初代政令市の6市が既に上位に見えます。また、上位30位以内に秋田、新潟、富山、金沢、福井、鳥取、松江と日本海側の諸都市が名を連ねています。特に、金沢は東京、大阪、京都、名古屋に次ぐ大都市だったのです。米沢の名前も見えますね。
しかし、太平洋側に偏った近代化の影響もあって、上記の年のうち金沢と新潟を除く都市はランキングの圏外に消え、替わって呉、横須賀、佐世保などの軍需関連の諸都市を代表とした工業都市が急成長を見せます。
また、第二次世界大戦後は東京・大阪・名古屋の3大都市圏への人口集中が進み、相模原、船橋、松戸、東大阪などの住宅都市が上位30位にランキングされることとなります。
とはいえ、住宅都市の成長などの若干の動きはあるものの、現在でも多くの人口を抱える主要地方都市の多くは、明治期からすでに力のある都市であったことも見て取れますね。
話は変わりますが、出典に利用させていただいた上記文献は、近代日本の成長過程を『裏日本』の視点により見つめなおしたものです。
一部日本海側の地域におけるイデオロギーの変化等思想的な記述の部分等、地理的な観点とは少し離れた部分もありますが、日本近代化の光と影を知るには興味深い文献だと思います。
それによると、『裏日本』という用語は現在でこそ、日本海側と太平洋側との経済的な較差を含む語として忌避されますが、この言葉が造語された明治中期においては、もともとは単純に「日本海側の地域」といった自然地理学的な語意だったようです。
その後政府は地方の均衡的な発展でなく、あくまで効率的な資本投下による富国強兵・殖産興業を優先させる政策をとり、戦後の「所得倍増計画」を受けた「全国総合開発計画」においても、その基本的な構想は変わりませんでした。
その結果、上に見た年のランキングの変化に垣間見られるように、日本海側は相対的に停滞を余儀なくされます。
最近東京電力による原子力発電所にかかる不祥事が明るみになりましたが、原子力発電所の多くが立地しているのも日本海側です。
>昨今の大都市圏への人口集中・過密化、それに伴う地方の人口減少・過疎化を見るにつけ、
>田舎出身の私としては将来の地方のあり方を心配しております。
私も同感です。
私たちは、こういった歴史に学び、地方のあり方について考えていく必要があるように思います。
明治・大正期の都市人口のランキングデータが手元にあるので、ご紹介します。
1876(明治9) 1920(大正9)
1 東京 1,121,883 1 東京 2,173,201
2 大阪 361,694 2 大阪 1,252,983
3 京都 245,675 3 神戸 608,644
4 名古屋 131,492 4 京都 591,323
5 金沢 97,654 5 名古屋 429,997
6 横浜 89,554 6 横浜 422,938
7 広島 81,954 7 長崎 176,534
8 神戸 80,446 8 広島 160,510
9 仙台 61,709 9 函館 144,749
10 徳島 57,456 10 呉 130,362
11 和歌山 54,868 11 金沢 129,265
12 富山 53,556 12 仙台 118,984
13 函館 45,477 13 小樽 108,113
14 鹿児島 45,097 14 鹿児島 103,180
15 熊本 44,384 15 札幌 102,580
16 堺 44,015 16 八幡 100,235
17 福岡 42,617 17 福岡 95,381
18 新潟 40,776 18 岡山 94,845
19 長崎 38,229 19 新潟 92,130
20 高松 37,698 20 横須賀 89,879
21 福井 37,376 21 佐世保 87,022
22 静岡 36,838 22 堺 84,999
23 松江 33,381 23 和歌山 83,500
24 岡山 32,989 24 渋谷 80,799
25 前橋 32,981 25 静岡 74,093
26 下関 30,825 26 下関 72,300
27 八幡 29,487 27 門司 72,111
28 秋田 29,225 28 熊本 70,388
29 米沢 29,203 29 徳島 68,457
30 鳥取 28,275 30 豊橋 65,163
出典 古厩忠夫(1997)『裏日本-近代日本を問いなおす-』岩波新書
なお、このデータの原典である『明治大正国勢要覧』について詳細を知らないので断言できませんが、「門司」などが見えることから、統計年次時点での地方自治制度に基づく区域内の人口をまとめたものと思われます。なお、「八幡」は現在の北九州市八幡です。「渋谷」は旧東京市合併直前の旧渋谷町のことだと思われますが、はっきりとは分かりません。
また、最新の市のランキングはこのホームページのデータを参照してくださいね。
明治期のデータを見ると、初代政令市の6市が既に上位に見えます。また、上位30位以内に秋田、新潟、富山、金沢、福井、鳥取、松江と日本海側の諸都市が名を連ねています。特に、金沢は東京、大阪、京都、名古屋に次ぐ大都市だったのです。米沢の名前も見えますね。
しかし、太平洋側に偏った近代化の影響もあって、上記の年のうち金沢と新潟を除く都市はランキングの圏外に消え、替わって呉、横須賀、佐世保などの軍需関連の諸都市を代表とした工業都市が急成長を見せます。
また、第二次世界大戦後は東京・大阪・名古屋の3大都市圏への人口集中が進み、相模原、船橋、松戸、東大阪などの住宅都市が上位30位にランキングされることとなります。
とはいえ、住宅都市の成長などの若干の動きはあるものの、現在でも多くの人口を抱える主要地方都市の多くは、明治期からすでに力のある都市であったことも見て取れますね。
話は変わりますが、出典に利用させていただいた上記文献は、近代日本の成長過程を『裏日本』の視点により見つめなおしたものです。
一部日本海側の地域におけるイデオロギーの変化等思想的な記述の部分等、地理的な観点とは少し離れた部分もありますが、日本近代化の光と影を知るには興味深い文献だと思います。
それによると、『裏日本』という用語は現在でこそ、日本海側と太平洋側との経済的な較差を含む語として忌避されますが、この言葉が造語された明治中期においては、もともとは単純に「日本海側の地域」といった自然地理学的な語意だったようです。
その後政府は地方の均衡的な発展でなく、あくまで効率的な資本投下による富国強兵・殖産興業を優先させる政策をとり、戦後の「所得倍増計画」を受けた「全国総合開発計画」においても、その基本的な構想は変わりませんでした。
その結果、上に見た年のランキングの変化に垣間見られるように、日本海側は相対的に停滞を余儀なくされます。
最近東京電力による原子力発電所にかかる不祥事が明るみになりましたが、原子力発電所の多くが立地しているのも日本海側です。
>昨今の大都市圏への人口集中・過密化、それに伴う地方の人口減少・過疎化を見るにつけ、
>田舎出身の私としては将来の地方のあり方を心配しております。
私も同感です。
私たちは、こういった歴史に学び、地方のあり方について考えていく必要があるように思います。
| [3296] 2002年 9月 23日(月)23:39:47 | 夜鳴き寿司屋 さん |
| Re:昔はどうだった | |
[3293]横ちゃんさん
総務省統計局統計センターのホームページにエクセル形式ですが
「第2章 人口・世帯人口,世帯,人口動態,人口移動」で日本の明治5年(1872年)から
2000年までの人口の推移と、第一回国勢調査が行われた1920年以降5年ごとの都道府県の人口の推移の資料などが閲覧できます。下記がアドレスです。
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/02.htm
少し見にくい表ですが、何らかの参考になると思います。エクセルファイルですのでダウンロード
して自分のランキングに並び替えたりする事も可能ですが、暇がおありでしたら出来ると思います。(ちなみに私は暇潰しにやってしまいました)
総務省統計局統計センターのホームページにエクセル形式ですが
「第2章 人口・世帯人口,世帯,人口動態,人口移動」で日本の明治5年(1872年)から
2000年までの人口の推移と、第一回国勢調査が行われた1920年以降5年ごとの都道府県の人口の推移の資料などが閲覧できます。下記がアドレスです。
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/02.htm
少し見にくい表ですが、何らかの参考になると思います。エクセルファイルですのでダウンロード
して自分のランキングに並び替えたりする事も可能ですが、暇がおありでしたら出来ると思います。(ちなみに私は暇潰しにやってしまいました)
| [3399] 2002年 9月 28日(土)22:21:07 | ニジェガロージェッツ さん |
| 東京市35区の区別人口 | |
遅れレスですみません。
[3293]で横ちゃんさんから昔の人口についての書き込みがあり、またYSKさんからも[3295]に興味深いデータと詳しいご解説があり、大変勉強になりました。
私も以前に戦前の「六大都市」(私が中学生の頃までは良く聞いた表現ですが、現在では死語?、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸をひとまとめにして言う)の人口を20年ぐらい前に調べていました。とりあえず昭和10年(1935年)、昭和15年(1940年)の東京市の区別人口の統計データが出てきましたのでご紹介致します。
横ちゃんさんのご趣旨からは逸れるかもしれませんが、何かのご参考にしてください。
昭和10年(1935年)人口 昭和15年(1940年)人口 昭和10年 面積 k㎡
【東京市】 5,875,667 【東京市】 6,778,804 【東京市】 550.85
(35区) (35区) (35区)
荒 川 326,210 荒 川 351,281 板 橋 80.68
本 所 278,194 豊 島 312,209 足 立 53.52
浅 草 273,693 世田谷 281,804 江戸川 46.81
豊 島 268,015 大 森 278,985 世田谷 38.80
渋 谷 234,850 本 所 △273,407 葛 飾 35.78
深 川 214,175 浅 草 △271,063 杉 並 34.10
品 川 204,262 渋 谷 256,706 大 森 23.40
大 森 201,425 蒲 田 252,799 蒲 田 22.15
芝 190,776 杉 並 245,435 王 子 15.98
下 谷 190,524 板 橋 233,115 中 野 15.41
世田谷 190,486 品 川 231,303 渋 谷 15.24
杉 並 190,217 足 立 231,246 目 黒 14.73
向 島 186,698 深 川 226,754 豊 島 13.26
中 野 178,383 王 子 220,304 荒 川 10.57
足 立 174,612 中 野 214,117 城 東 10.18
王 子 171,047 向 島 206,402 品 川 10.16
城 東 171,047 目 黒 198,795 淀 橋 10.06
淀 橋 169,187 城 東 192,400 芝 8.61
荏 原 161,863 芝 191,445 麹 町 8.28
目 黒 152,187 下 谷 △189,191 深 川 8.24
板 橋 150,868 淀 橋 189,152 向 島 7.79
蒲 田 147,516 荏 原 188,100 本 所 6.49
京 橋 147,334 江戸川 177,304 小石川 6.06
小石川 147,135 小石川 154,655 荏 原 5.80
本 郷 141,215 葛 飾 153,041 浅 草 5.27
神 田 136,906 本 郷 146,146 牛 込 5.21
牛 込 130,340 京 橋 △142,269 滝野川 5.20
江戸川 129,230 滝野川 130,705 京 橋 5.11
滝野川 114,514 牛 込 △128,888 下 谷 5.04
日本橋 113,871 神 田 △128,178 本 郷 4.87
葛 飾 105,682 日本橋 △101,777 赤 坂 4.30
麻 布 87,857 麻 布 89,163 麻 布 4.29
四 谷 76,321 四 谷 76,440 四 谷 3.24
麹 町 60,327 麹 町 △58,521 日本橋 3.12
赤 坂 58,700 赤 坂 △55,704 神 田 3.10
この間、世田谷区は昭和11年(1936年)10月1日、北多摩郡砧村、千歳村を編入し区域が拡大(現在の区域が確定)しています。
[3293]で横ちゃんさんから昔の人口についての書き込みがあり、またYSKさんからも[3295]に興味深いデータと詳しいご解説があり、大変勉強になりました。
私も以前に戦前の「六大都市」(私が中学生の頃までは良く聞いた表現ですが、現在では死語?、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸をひとまとめにして言う)の人口を20年ぐらい前に調べていました。とりあえず昭和10年(1935年)、昭和15年(1940年)の東京市の区別人口の統計データが出てきましたのでご紹介致します。
横ちゃんさんのご趣旨からは逸れるかもしれませんが、何かのご参考にしてください。
昭和10年(1935年)人口 昭和15年(1940年)人口 昭和10年 面積 k㎡
【東京市】 5,875,667 【東京市】 6,778,804 【東京市】 550.85
(35区) (35区) (35区)
荒 川 326,210 荒 川 351,281 板 橋 80.68
本 所 278,194 豊 島 312,209 足 立 53.52
浅 草 273,693 世田谷 281,804 江戸川 46.81
豊 島 268,015 大 森 278,985 世田谷 38.80
渋 谷 234,850 本 所 △273,407 葛 飾 35.78
深 川 214,175 浅 草 △271,063 杉 並 34.10
品 川 204,262 渋 谷 256,706 大 森 23.40
大 森 201,425 蒲 田 252,799 蒲 田 22.15
芝 190,776 杉 並 245,435 王 子 15.98
下 谷 190,524 板 橋 233,115 中 野 15.41
世田谷 190,486 品 川 231,303 渋 谷 15.24
杉 並 190,217 足 立 231,246 目 黒 14.73
向 島 186,698 深 川 226,754 豊 島 13.26
中 野 178,383 王 子 220,304 荒 川 10.57
足 立 174,612 中 野 214,117 城 東 10.18
王 子 171,047 向 島 206,402 品 川 10.16
城 東 171,047 目 黒 198,795 淀 橋 10.06
淀 橋 169,187 城 東 192,400 芝 8.61
荏 原 161,863 芝 191,445 麹 町 8.28
目 黒 152,187 下 谷 △189,191 深 川 8.24
板 橋 150,868 淀 橋 189,152 向 島 7.79
蒲 田 147,516 荏 原 188,100 本 所 6.49
京 橋 147,334 江戸川 177,304 小石川 6.06
小石川 147,135 小石川 154,655 荏 原 5.80
本 郷 141,215 葛 飾 153,041 浅 草 5.27
神 田 136,906 本 郷 146,146 牛 込 5.21
牛 込 130,340 京 橋 △142,269 滝野川 5.20
江戸川 129,230 滝野川 130,705 京 橋 5.11
滝野川 114,514 牛 込 △128,888 下 谷 5.04
日本橋 113,871 神 田 △128,178 本 郷 4.87
葛 飾 105,682 日本橋 △101,777 赤 坂 4.30
麻 布 87,857 麻 布 89,163 麻 布 4.29
四 谷 76,321 四 谷 76,440 四 谷 3.24
麹 町 60,327 麹 町 △58,521 日本橋 3.12
赤 坂 58,700 赤 坂 △55,704 神 田 3.10
この間、世田谷区は昭和11年(1936年)10月1日、北多摩郡砧村、千歳村を編入し区域が拡大(現在の区域が確定)しています。
| [6150] 2002年 12月 8日(日)18:54:44 | ふぁいん さん |
| 明治期の都市人口 | |
[6133] YSKさん
[3295]の方を見ました。
私も『裏日本-近代日本を問いなおす-』を拝見したことがありますが、
以前、実際にその原典である『明治大正国勢要覧』も見たことがあります。
そしてその『明治大正国勢要覧』には、確かM19年末、M26年末、M31年末、M36年末、M41年末、T2年末、
T7年末、T9国勢調査、T14国勢調査
の各主要都市の人口が記されていたと記憶しています。
そのうち、『明治大正国勢要覧』で私がみたM19年末(1886)の都市の人口を抜粋しますと、
函館 45,477
東京 1,121,883
大阪 361,694
堺 44,015
京都 245,675
青森 14,920
弘前 28,170
盛岡 30,166
仙台 61,709
秋田 29,225
山形 26,971
米沢 29,203
鶴岡 19,666
酒田 21,004
水戸 19,010
宇都宮 20,475
前橋 32,531
横浜 89,545
新潟 40,776
高田 24,571
富山 53,556
金沢 97,653
福井 37,376
岐阜 23,377
静岡 36,838
名古屋 131,492
宇治山田 21,223
大津 23,167
神戸 80,446
姫路 22,677
奈良 22,666
和歌山 54,868
鳥取 28,275
松江 33,381
岡山 32,989
広島 81,914
下関 30,825
徳島 57,456
高松 37,698
八幡 29,487
福岡 42,617
久留米 20,907
佐賀 24,657
長崎 38,229
熊本 44,384
鹿児島 45,097
首里 25,581
このことから、
『裏日本-近代日本を問いなおす-』岩波新書
と比べ、調査年度、および都市人口が少し違うことがわかりました。
また、盛岡の人口もベスト30から抜けております。
原典自体が『明治大正国勢要覧』なので、やはり実際はこちらが正しかったのでは???と思っております。
どうなんでしょうね。
また、この人口はT14年頃当時の市域にあてはめたものだと思います。
[3295]の方を見ました。
私も『裏日本-近代日本を問いなおす-』を拝見したことがありますが、
以前、実際にその原典である『明治大正国勢要覧』も見たことがあります。
そしてその『明治大正国勢要覧』には、確かM19年末、M26年末、M31年末、M36年末、M41年末、T2年末、
T7年末、T9国勢調査、T14国勢調査
の各主要都市の人口が記されていたと記憶しています。
そのうち、『明治大正国勢要覧』で私がみたM19年末(1886)の都市の人口を抜粋しますと、
函館 45,477
東京 1,121,883
大阪 361,694
堺 44,015
京都 245,675
青森 14,920
弘前 28,170
盛岡 30,166
仙台 61,709
秋田 29,225
山形 26,971
米沢 29,203
鶴岡 19,666
酒田 21,004
水戸 19,010
宇都宮 20,475
前橋 32,531
横浜 89,545
新潟 40,776
高田 24,571
富山 53,556
金沢 97,653
福井 37,376
岐阜 23,377
静岡 36,838
名古屋 131,492
宇治山田 21,223
大津 23,167
神戸 80,446
姫路 22,677
奈良 22,666
和歌山 54,868
鳥取 28,275
松江 33,381
岡山 32,989
広島 81,914
下関 30,825
徳島 57,456
高松 37,698
八幡 29,487
福岡 42,617
久留米 20,907
佐賀 24,657
長崎 38,229
熊本 44,384
鹿児島 45,097
首里 25,581
このことから、
『裏日本-近代日本を問いなおす-』岩波新書
と比べ、調査年度、および都市人口が少し違うことがわかりました。
また、盛岡の人口もベスト30から抜けております。
原典自体が『明治大正国勢要覧』なので、やはり実際はこちらが正しかったのでは???と思っております。
どうなんでしょうね。
また、この人口はT14年頃当時の市域にあてはめたものだと思います。
| [6165] 2002年 12月 8日(日)23:12:48 | YSK さん |
| 明治大正国勢要覧 | |
[6150]ふぁいんさん
『明治大正国勢要覧』につきまして、貴重なご解説をいただきまして、ありがとうございました。
私も、[3295]を投稿するにあたり、『明治大正国勢要覧』についていろいろ調べたのですが、結局原典の内容に行き着くことができず、本の内容のまま引用させていただいたのです。
ご提示いただいたデータ(明治19年時の都市人口)を、人口の多い順に再構成してみました。
確かに、ご指摘のとおり、[3295]のデータと比較すると、(1)盛岡が抜けていることと、(2)統計年次が10年ずれていること、(3)金沢と横浜の数字が微妙に違うこと、の3点を除けば、数字が全く同じですね。仮に、原典に明治9年時のデータがあったとしても、こうまで数字が一致しているのはやはり不自然に思えます。
この本の内容を見ていて感じたのは、「裏日本」についての史実の検証などの考察に関しては誠に的を射た鋭い議論が展開されているのですが、数字の取り扱いや、データの考察などの一部に、やや雑な点があるということでした。
私も、ふぁいんさんのおっしゃるとおり、このデータに関しては、ふぁいんさんのご提示いただいた内容の方が正しいのではないのかな・・・、という気持ちです。
もちろん、『裏日本・・・』自体については、総論的にはまったく問題のない、筋の通った内容であると思います。
追伸:30位以下の都市人口データも、酒田や宇治山田(伊勢の前身)などが見え、非常に興味深いですね。確認ですが、データの「抜粋」とのお話でしたが、上位47都市をそのままご記入いただいたと判断してよろしいのですよね?
『明治大正国勢要覧』につきまして、貴重なご解説をいただきまして、ありがとうございました。
私も、[3295]を投稿するにあたり、『明治大正国勢要覧』についていろいろ調べたのですが、結局原典の内容に行き着くことができず、本の内容のまま引用させていただいたのです。
ご提示いただいたデータ(明治19年時の都市人口)を、人口の多い順に再構成してみました。
| 順位 | 都市名 | 人口 |
| 1 | 東京 | 1,121,883 |
| 2 | 大阪 | 361,694 |
| 3 | 京都 | 245,675 |
| 4 | 名古屋 | 131,492 |
| 5 | 金沢 | 97,653 |
| 6 | 横浜 | 89,545 |
| 7 | 広島 | 81,914 |
| 8 | 神戸 | 80,446 |
| 9 | 仙台 | 61,709 |
| 10 | 徳島 | 57,456 |
| 11 | 和歌山 | 54,868 |
| 12 | 富山 | 53,556 |
| 13 | 函館 | 45,477 |
| 14 | 鹿児島 | 45,097 |
| 15 | 熊本 | 44,384 |
| 16 | 堺 | 44,015 |
| 17 | 福岡 | 42,617 |
| 18 | 新潟 | 40,776 |
| 19 | 長崎 | 38,229 |
| 20 | 高松 | 37,698 |
| 21 | 福井 | 37,376 |
| 22 | 静岡 | 36,838 |
| 23 | 松江 | 33,381 |
| 24 | 岡山 | 32,989 |
| 25 | 前橋 | 32,531 |
| 26 | 下関 | 30,825 |
| 27 | 盛岡 | 30,166 |
| 28 | 八幡 | 29,487 |
| 29 | 秋田 | 29,225 |
| 30 | 米沢 | 29,203 |
| 31 | 鳥取 | 28,275 |
| 32 | 弘前 | 28,170 |
| 33 | 山形 | 26,971 |
| 34 | 首里 | 25,581 |
| 35 | 佐賀 | 24,657 |
| 36 | 高田 | 24,571 |
| 37 | 岐阜 | 23,377 |
| 38 | 大津 | 23,167 |
| 39 | 姫路 | 22,677 |
| 40 | 奈良 | 22,666 |
| 41 | 宇治山田 | 21,223 |
| 42 | 酒田 | 21,004 |
| 43 | 久留米 | 20,907 |
| 44 | 宇都宮 | 20,475 |
| 45 | 鶴岡 | 19,666 |
| 46 | 水戸 | 19,010 |
| 47 | 青森 | 14,920 |
確かに、ご指摘のとおり、[3295]のデータと比較すると、(1)盛岡が抜けていることと、(2)統計年次が10年ずれていること、(3)金沢と横浜の数字が微妙に違うこと、の3点を除けば、数字が全く同じですね。仮に、原典に明治9年時のデータがあったとしても、こうまで数字が一致しているのはやはり不自然に思えます。
この本の内容を見ていて感じたのは、「裏日本」についての史実の検証などの考察に関しては誠に的を射た鋭い議論が展開されているのですが、数字の取り扱いや、データの考察などの一部に、やや雑な点があるということでした。
私も、ふぁいんさんのおっしゃるとおり、このデータに関しては、ふぁいんさんのご提示いただいた内容の方が正しいのではないのかな・・・、という気持ちです。
もちろん、『裏日本・・・』自体については、総論的にはまったく問題のない、筋の通った内容であると思います。
追伸:30位以下の都市人口データも、酒田や宇治山田(伊勢の前身)などが見え、非常に興味深いですね。確認ですが、データの「抜粋」とのお話でしたが、上位47都市をそのままご記入いただいたと判断してよろしいのですよね?
| [6167] 2002年 12月 9日(月)00:08:03 | ふぁいん さん |
| 明治大正国勢要覧 | |
[6165] YSKさん
金沢、横浜の他に広島、前橋の人口も違ってましたね。
30位以下に関しての都市ですが、46位の水戸までは人口順で問題ないであろうと
考えています。ただ、青森に関しては、水戸と差があるため、かなり怪しいところです。
1886年に関しましてはその47都市しか記されていませんでした。なので全都市載せておきました。
それと『明治大正国勢要覧』ですが、基本的にはM19、M26、M31、M36、M41、T2、T7、T9、T14の各年度において、2万人以上の都市に関してのみ記されていました。
金沢、横浜の他に広島、前橋の人口も違ってましたね。
30位以下に関しての都市ですが、46位の水戸までは人口順で問題ないであろうと
考えています。ただ、青森に関しては、水戸と差があるため、かなり怪しいところです。
1886年に関しましてはその47都市しか記されていませんでした。なので全都市載せておきました。
それと『明治大正国勢要覧』ですが、基本的にはM19、M26、M31、M36、M41、T2、T7、T9、T14の各年度において、2万人以上の都市に関してのみ記されていました。
| [6169] 2002年 12月 9日(月)00:13:09【1】 | YSK さん |
| ふぁいんさんへ | |
| [6170] 2002年 12月 9日(月)00:31:52 | ふぁいん さん |
| 追伸:『明治大正国勢要覧』 | |
[6169] YSKさんへ
ちなみに私は、都立図書館にて『明治大正国勢要覧』を発見し、データを手に入れました。
もしYSKさんも近ければ、行って見られてはいかがでしょうか??
都立にあれば、県立図書館でもあるとこはあるかもしれません。
ちなみに『明治大正国勢要覧』は、すっごい分厚い本でして、
該当する都市人口推移のデータに関しましては、ほんの2,3ページのみでした(爆)
ちなみに私は、都立図書館にて『明治大正国勢要覧』を発見し、データを手に入れました。
もしYSKさんも近ければ、行って見られてはいかがでしょうか??
都立にあれば、県立図書館でもあるとこはあるかもしれません。
ちなみに『明治大正国勢要覧』は、すっごい分厚い本でして、
該当する都市人口推移のデータに関しましては、ほんの2,3ページのみでした(爆)
| [6184] 2002年 12月 9日(月)11:41:43 | ken さん |
| re:明治初年の都市人口 | |
[6165] YSK さん
に
> 人口の多い順に再構成してみ
ていただきましたが、遠い昔大学時代、これを調べたことがあったのを思い出しました。
一見して現在の人口とはずいぶん違った印象があります。
これ[6165]を見ていただくと2つの傾向が見て取れると思います。(人の褌で偉そうに)
一つは、江戸時代の石高の大小です。
もう一つは、開港場です。
金沢が5位であること、あるいはもっと言えば富山も合わせて位置づけるべきかも。
鹿児島の方が福岡よりも人口が多いですよね。
九州の石高は鹿児島、熊本、福岡、佐賀、久留米の順です。小倉はその次。
徳島が四国最大の都市だったりするのも、四国最大の藩だったこととは無縁ではないでしょう。
小藩並立だった福島県や、愛媛県、大分県、などの都市は登場しない。
弘前、久留米なんて、今では地方都市という感じですが、国主級の大名の城下町でしたから。
江戸末期の正確なものがわかれば、もっとはっきりするのだと思いますが、徒歩と船が主要な交通で、米の集散量が、都市機能の器=都市人口=商工業従事者人口と言ってもいいかもしれませんが、に色濃く反映しますよね。商工だけでなく、旧士族の数も馬鹿にならないと思いますが、これも石高に比例しますからね。
開港場については、説明不要と思いますが。
たった数十年で、一介の漁村だった、横浜、神戸がここまで来ているのは、驚きますね。
青森も新開地ですね。
埼玉県が一つも登場しない中で、山形県からは4つが入っているあたり、日本の中央集権化の凄まじさを感じますね。
昔は地方にも力があった。
交通が便利になればなるほど、地方都市の存在意義は薄れていくんですよね。
に
> 人口の多い順に再構成してみ
ていただきましたが、遠い昔大学時代、これを調べたことがあったのを思い出しました。
一見して現在の人口とはずいぶん違った印象があります。
これ[6165]を見ていただくと2つの傾向が見て取れると思います。(人の褌で偉そうに)
一つは、江戸時代の石高の大小です。
もう一つは、開港場です。
金沢が5位であること、あるいはもっと言えば富山も合わせて位置づけるべきかも。
鹿児島の方が福岡よりも人口が多いですよね。
九州の石高は鹿児島、熊本、福岡、佐賀、久留米の順です。小倉はその次。
徳島が四国最大の都市だったりするのも、四国最大の藩だったこととは無縁ではないでしょう。
小藩並立だった福島県や、愛媛県、大分県、などの都市は登場しない。
弘前、久留米なんて、今では地方都市という感じですが、国主級の大名の城下町でしたから。
江戸末期の正確なものがわかれば、もっとはっきりするのだと思いますが、徒歩と船が主要な交通で、米の集散量が、都市機能の器=都市人口=商工業従事者人口と言ってもいいかもしれませんが、に色濃く反映しますよね。商工だけでなく、旧士族の数も馬鹿にならないと思いますが、これも石高に比例しますからね。
開港場については、説明不要と思いますが。
たった数十年で、一介の漁村だった、横浜、神戸がここまで来ているのは、驚きますね。
青森も新開地ですね。
埼玉県が一つも登場しない中で、山形県からは4つが入っているあたり、日本の中央集権化の凄まじさを感じますね。
昔は地方にも力があった。
交通が便利になればなるほど、地方都市の存在意義は薄れていくんですよね。
| [6204] 2002年 12月 9日(月)21:03:16 | YSK さん |
| 都市人口の変遷についての一考察。 | |
[6184]kenさん
>一見して現在の人口とはずいぶん違った印象があります。
>これ[6165]を見ていただくと2つの傾向が見て取れると思います
>一つは、江戸時代の石高の大小です。
>もう一つは、開港場です。
レスありがとうございます。お話を拝見して、私も、同じ感想を持ちました。さすが、江戸期の藩にお詳しいkenさんならではのご指摘ですね。
#いつも、ホームページ、興味深く拝見しております。
>埼玉県が一つも登場しない中で、山形県からは4つが入っているあたり、
>日本の中央集権化の凄まじさを感じますね。昔は地方にも力があった。
本当に、そのとおりですね。
戦後の住宅都市の成長等によって、人口の多い都市のランキングは大きく変わってきましたが、日本の中央集権化の前に、都市の人口増加に拍車をかけた要因があります。[3295]の1920年のデータでの分析でちょっと書きましたが、それは、工業都市への人口集中です。横須賀、呉、佐世保は軍需関連。長崎や八幡、門司も工業の成長と関連がありそうです。
城下町起源の大都市に、開港場、工業都市という都市の顔ぶれに、第二次大戦後の三大都市圏を中心とした大都市地域への人口集中が加わって、現在のラインナップが作られてきてといえます。一方、戦前から工業都市として発達した都市(あるいは戦後初期までに発達した都市)の多くは、重厚長大型の産業を基盤としており、高度成長の終焉に伴い、海外との競争などで産業が相対的に停滞するに及び、その影響を受けているところも少なくないようです。
※ [6165]の話に戻りますが、北前船による物流の拠点として繁栄した酒田や、伊勢神宮の門前町宇治山田の名前が見えるところも、江戸時代の名残が感じられて、興味深いですね。
また、本当に、昔は地方もその土地ならではの特色を生かした力があった、という感慨を持たずにはいられないデータですよね。
>一見して現在の人口とはずいぶん違った印象があります。
>これ[6165]を見ていただくと2つの傾向が見て取れると思います
>一つは、江戸時代の石高の大小です。
>もう一つは、開港場です。
レスありがとうございます。お話を拝見して、私も、同じ感想を持ちました。さすが、江戸期の藩にお詳しいkenさんならではのご指摘ですね。
#いつも、ホームページ、興味深く拝見しております。
>埼玉県が一つも登場しない中で、山形県からは4つが入っているあたり、
>日本の中央集権化の凄まじさを感じますね。昔は地方にも力があった。
本当に、そのとおりですね。
戦後の住宅都市の成長等によって、人口の多い都市のランキングは大きく変わってきましたが、日本の中央集権化の前に、都市の人口増加に拍車をかけた要因があります。[3295]の1920年のデータでの分析でちょっと書きましたが、それは、工業都市への人口集中です。横須賀、呉、佐世保は軍需関連。長崎や八幡、門司も工業の成長と関連がありそうです。
城下町起源の大都市に、開港場、工業都市という都市の顔ぶれに、第二次大戦後の三大都市圏を中心とした大都市地域への人口集中が加わって、現在のラインナップが作られてきてといえます。一方、戦前から工業都市として発達した都市(あるいは戦後初期までに発達した都市)の多くは、重厚長大型の産業を基盤としており、高度成長の終焉に伴い、海外との競争などで産業が相対的に停滞するに及び、その影響を受けているところも少なくないようです。
※ [6165]の話に戻りますが、北前船による物流の拠点として繁栄した酒田や、伊勢神宮の門前町宇治山田の名前が見えるところも、江戸時代の名残が感じられて、興味深いですね。
また、本当に、昔は地方もその土地ならではの特色を生かした力があった、という感慨を持たずにはいられないデータですよね。
| [39658] 2005年 4月 11日(月)21:16:12 | ふぁいん さん |
| 明治初期まで日本で4番目に大きかった都市は、一体どこでしょう? | |
[39641] 229さん
私も229さんと同じく、昔は国勢調査の人口だけ調査すればいいやって思っていました(笑)
しかし、一旦全部知ってしまうと、さらに昔はどうなっていたんだろうか?
この都市は昔はどうだったんだろうか?って更なる欲望が延々と駆り立てられるのです。
現在私は、明治中期・明治初期・江戸後期の詳しい都市人口が一番知りたいのです・・・・
そういう資料・本がなかなか無くて困ってます。
ところで、みなさん幕末期・明治維新頃の国内第4の都市は、どこだと思いますか?
いきなり答えを言ってしまうと、それは金沢なんです。当時の金沢の人口は約12万人。
江戸~明治初期までは、江戸・京都・大阪に次ぐ大都市でした。
ちなみに、当時日本第5の都市は、名古屋でした。
しかし版籍奉還により、武士に依存していた加賀百万石の経済力は急激に衰退し、
明治30(1897)年まで人口が激減することになります。
名古屋が金沢の人口を抜くのは、明治8(1875)~明治10(1877)年頃だと思われます。
明治12(1879)年の名古屋の人口は111,783人、金沢は107,876人です。
その後、明治20(1887)年には、横浜・神戸の両都市に抜かれ、
明治27(1894)年には、ついに広島にも抜かれ、国内第8の都市に転落していきます。
さらに追い討ちをかけるように、明治30(1897)年・明治31(1898)年には、仙台・長崎両都市に抜かれます。
幕末期・明治維新頃に約12万人だった人口が明治30(1897)年には人口82,378人まで
減り続けましたが、「軍都」となってようやく活力を取り戻していったのです。
再び金沢が10万都市に復帰するのは、明治37(1904)年のことです。当時国内10位。
ちなみに明治維新以後、国内の都市で人口ベスト10入りしたことのある都市は
以下のとおりです。
北から順に・・・
札幌
函館
仙台
さいたま
東京
川崎
横浜
横須賀
金沢
名古屋
京都
大阪
神戸
和歌山
広島
呉
徳島
北九州
八幡(現・北九州)
福岡
長崎
熊本
私も229さんと同じく、昔は国勢調査の人口だけ調査すればいいやって思っていました(笑)
しかし、一旦全部知ってしまうと、さらに昔はどうなっていたんだろうか?
この都市は昔はどうだったんだろうか?って更なる欲望が延々と駆り立てられるのです。
現在私は、明治中期・明治初期・江戸後期の詳しい都市人口が一番知りたいのです・・・・
そういう資料・本がなかなか無くて困ってます。
ところで、みなさん幕末期・明治維新頃の国内第4の都市は、どこだと思いますか?
いきなり答えを言ってしまうと、それは金沢なんです。当時の金沢の人口は約12万人。
江戸~明治初期までは、江戸・京都・大阪に次ぐ大都市でした。
ちなみに、当時日本第5の都市は、名古屋でした。
しかし版籍奉還により、武士に依存していた加賀百万石の経済力は急激に衰退し、
明治30(1897)年まで人口が激減することになります。
名古屋が金沢の人口を抜くのは、明治8(1875)~明治10(1877)年頃だと思われます。
明治12(1879)年の名古屋の人口は111,783人、金沢は107,876人です。
その後、明治20(1887)年には、横浜・神戸の両都市に抜かれ、
明治27(1894)年には、ついに広島にも抜かれ、国内第8の都市に転落していきます。
さらに追い討ちをかけるように、明治30(1897)年・明治31(1898)年には、仙台・長崎両都市に抜かれます。
幕末期・明治維新頃に約12万人だった人口が明治30(1897)年には人口82,378人まで
減り続けましたが、「軍都」となってようやく活力を取り戻していったのです。
再び金沢が10万都市に復帰するのは、明治37(1904)年のことです。当時国内10位。
ちなみに明治維新以後、国内の都市で人口ベスト10入りしたことのある都市は
以下のとおりです。
北から順に・・・
札幌
函館
仙台
さいたま
東京
川崎
横浜
横須賀
金沢
名古屋
京都
大阪
神戸
和歌山
広島
呉
徳島
北九州
八幡(現・北九州)
福岡
長崎
熊本
| [39685] 2005年 4月 12日(火)00:44:02 | ふぁいん さん |
| 1886(明治19)年 都市人口ベスト100 | |
| 順位 | 都市名 | 都道府県名 | 人口 |
| 1 | 東京 | 東京府 | 1,121,883 |
| 2 | 大阪 | 大阪府 | 361,694 |
| 3 | 京都 | 京都府 | 245,675 |
| 4 | 名古屋 | 愛知県 | 131,492 |
| 5 | 金沢 | 石川県 | 97,653 |
| 6 | 横浜 | 神奈川県 | 89,545 |
| 7 | 広島 | 広島県 | 81,914 |
| 8 | 神戸 | 兵庫県 | 80,446 |
| 9 | 仙台 | 宮城県 | 61,709 |
| 10 | 徳島 | 徳島県 | 57,456 |
| 11 | 和歌山 | 和歌山県 | 54,868 |
| 12 | 富山 | 富山県 | 53,556 |
| 13 | 函館 | 北海道 | 45,477 |
| 14 | 鹿児島 | 鹿児島県 | 45,097 |
| 15 | 熊本 | 熊本県 | 44,384 |
| 16 | 堺 | 大阪府 | 44,015 |
| 17 | 福岡 | 福岡県 | 42,617 |
| 18 | 新潟 | 新潟県 | 40,778 |
| 19 | 長崎 | 長崎県 | 38,229 |
| 20 | 高松 | 愛媛県 | 37,698 |
| 21 | 福井 | 福井県 | 37,376 |
| 22 | 静岡 | 静岡県 | 36,838 |
| 23 | 松江 | 島根県 | 33,381 |
| 24 | 岡山 | 岡山県 | 32,989 |
| 25 | 高知 | 高知県 | 30,987 |
| 26 | 赤間関 | 山口県 | 30,825 |
| 27 | 盛岡 | 岩手県 | 30,166 |
| 28 | 松山 | 愛媛県 | 29,487 |
| 29 | 秋田 | 秋田県 | 29,225 |
| 30 | 米沢 | 山形県 | 29,203 |
| 31 | 鳥取 | 鳥取県 | 28,275 |
| 32 | 弘前 | 青森県 | 28,170 |
| 33 | 那覇 | 沖縄県 | 27,193 |
| 34 | 山形 | 山形県 | 26,971 |
| 35 | 銚子 | 千葉県 | 25,766 |
| 36 | 首里 | 沖縄県 | 25,587 |
| 37 | 佐賀 | 佐賀県 | 24,657 |
| 38 | 高田 | 新潟県 | 24,571 |
| 39 | 岐阜 | 岐阜県 | 23,377 |
| 40 | 大津 | 滋賀県 | 23,167 |
| 41 | 姫路 | 兵庫県 | 22,677 |
| 42 | 奈良 | 大阪府 | 22,666 |
| 43 | 山田 | 三重県 | 21,223 |
| 44 | 萩 | 山口県 | 21,206 |
| 45 | 酒田 | 山形県 | 21,004 |
| 46 | 久留米 | 福岡県 | 20,907 |
| 47 | 宇都宮 | 栃木県 | 20,475 |
| 48 | 高崎 | 群馬県 | 20,312 |
| 49 | 伏見 | 京都府 | 19,831 |
| 50 | 鶴岡 | 山形県 | 19,666 |
| 51 | 水戸 | 茨城県 | 19,010 |
| 52 | 明石 | 兵庫県 | 18,587 |
| 53 | 彦根 | 滋賀県 | 18,577 |
| 54 | 甲府 | 山梨県 | 18,411 |
| 55 | 長野 | 長野県 | 18,222 |
| 56 | 千葉 | 千葉県 | 18,204 |
| 57 | 若松 | 福島県 | 18,004 |
| 58 | 高岡 | 富山県 | 17,974 |
| 59 | 島原 | 長崎県 | 17,593 |
| 60 | 松本 | 長野県 | 17,478 |
| 61 | 尾道 | 広島県 | 17,307 |
| 62 | 撫養 | 徳島県 | 17,075 |
| 63 | 石巻 | 宮城県 | 16,618 |
| 64 | 前橋 | 群馬県 | 16,585 |
| 65 | 熱田 | 愛知県 | 16,390 |
| 66 | 大垣 | 岐阜県 | 16,339 |
| 67 | 長岡 | 新潟県 | 16,152 |
| 68 | 丸亀 | 愛媛県 | 16,149 |
| 69 | 津 | 三重県 | 15,884 |
| 70 | 小樽 | 北海道 | 15,882 |
| 71 | 品川 | 東京府 | 15,874 |
| 72 | 八王子 | 神奈川県 | 15,775 |
| 73 | 新湊 | 富山県 | 15,762 |
| 74 | 中津 | 大分県 | 15,518 |
| 75 | 高山 | 岐阜県 | 15,267 |
| 76 | 桑名 | 三重県 | 15,204 |
| 77 | 上田 | 長野県 | 15,172 |
| 78 | 札幌 | 北海道 | 15,041 |
| 79 | 青森 | 青森県 | 14,920 |
| 80 | 福山 | 広島県 | 14,663 |
| 81 | 足利 | 栃木県 | 14,632 |
| 82 | 津山 | 岡山県 | 14,582 |
| 83 | 大分 | 大分県 | 14,315 |
| 84 | 川越 | 埼玉県 | 14,184 |
| 85 | 小田原 | 神奈川県 | 14,009 |
| 86 | 横須賀 | 神奈川県 | 13,251 |
| 87 | 今治 | 愛媛県 | 13,101 |
| 88 | 武生 | 福井県 | 13,074 |
| 89 | 郡山 | 大阪府 | 12,834 |
| 90 | 上野 | 三重県 | 12,785 |
| 91 | 岡崎 | 愛知県 | 12,742 |
| 91 | 尼ヶ崎 | 兵庫県 | 12,742 |
| 93 | 千住 | 東京府 | 12,506 |
| 94 | 岸和田 | 大阪府 | 12,366 |
| 95 | 柳川 | 福岡県 | 12,350 |
| 96 | 浜松 | 静岡県 | 12,141 |
| 97 | 松阪 | 三重県 | 11,958 |
| 98 | 西宮 | 兵庫県 | 11,932 |
| 99 | 敦賀 | 福井県 | 11,878 |
| 100 | 米子 | 鳥取県 | 11,860 |
| [39686] 2005年 4月 12日(火)00:51:03 | ふぁいん さん |
| 1889(明治22)年 都市人口ベスト100 | |
| 順位 | 都市名 | 都道府県名 | 人口 |
| 1 | 東京市 | 東京府 | 1,389,684 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 476,271 |
| 3 | 京都市 | 京都府 | 279,792 |
| 4 | 名古屋市 | 愛知県 | 162,767 |
| 5 | 神戸市 | 兵庫県 | 135,639 |
| 6 | 横浜市 | 神奈川県 | 121,985 |
| 7 | 金沢市 | 石川県 | 94,257 |
| 8 | 仙台市 | 宮城県 | 90,231 |
| 9 | 広島市 | 広島県 | 88,820 |
| 10 | 徳島市 | 徳島県 | 61,107 |
| 11 | 富山市 | 富山県 | 58,159 |
| 12 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 57,465 |
| 13 | 和歌山市 | 和歌山県 | 56,713 |
| 14 | 長崎市 | 長崎県 | 55,063 |
| 15 | 福岡市 | 福岡県 | 53,014 |
| 16 | 函館区 | 北海道 | 52,909 |
| 17 | 熊本市 | 熊本県 | 52,833 |
| 18 | 岡山市 | 岡山県 | 48,333 |
| 19 | 堺市 | 大阪府 | 48,165 |
| 20 | 新潟市 | 新潟県 | 46,353 |
| 21 | 福井市 | 福井県 | 40,849 |
| -- | 那覇 | 沖縄県 | 40,212 |
| 22 | 静岡市 | 静岡県 | 37,664 |
| 23 | 松江市 | 島根県 | 35,934 |
| 24 | 松山市 | 愛媛県 | 32,738 |
| 25 | 高知市 | 高知県 | 32,241 |
| -- | 高松 | 香川県 | 32,081 |
| 26 | 盛岡市 | 岩手県 | 31,153 |
| 27 | 甲府市 | 山梨県 | 31,135 |
| 28 | 宇都宮町 | 栃木県 | 30,698 |
| 29 | 弘前市 | 青森県 | 30,487 |
| 30 | 大津町 | 滋賀県 | 29,941 |
| 31 | 赤間関市 | 山口県 | 29,919 |
| 32 | 米沢市 | 山形県 | 29,591 |
| 33 | 秋田市 | 秋田県 | 29,568 |
| 34 | 松本町 | 長野県 | 29,319 |
| 35 | 山形市 | 山形県 | 29,019 |
| 36 | 長野町 | 長野県 | 28,980 |
| 37 | 高岡市 | 富山県 | 28,928 |
| 38 | 鳥取市 | 鳥取県 | 28,396 |
| 39 | 津市 | 三重県 | 28,156 |
| 40 | 前橋町 | 群馬県 | 28,115 |
| 41 | 宇治山田町 | 三重県 | 27,365 |
| 42 | 岐阜市 | 岐阜県 | 27,089 |
| 43 | 姫路市 | 兵庫県 | 27,055 |
| 44 | 佐賀市 | 佐賀県 | 26,401 |
| -- | 首里 | 沖縄県 | 26,205 |
| 45 | 難波村 | 大阪府 | 25,617 |
| 46 | 水戸市 | 茨城県 | 25,591 |
| 47 | 久留米市 | 福岡県 | 24,859 |
| 48 | 奈良町 | 奈良県 | 24,459 |
| 49 | 横須賀町 | 神奈川県 | 24,366 |
| 50 | 谷山村 | 鹿児島県 | 24,248 |
| 51 | 高崎町 | 群馬県 | 24,182 |
| 52 | 千葉町 | 千葉県 | 22,259 |
| 53 | 大垣町 | 岐阜県 | 21,640 |
| 54 | 若松町 | 福島県 | 21,584 |
| 55 | 八王子町 | 神奈川県 | 21,555 |
| 56 | 酒田町 | 山形県 | 20,918 |
| 57 | 高田町 | 新潟県 | 20,191 |
| 58 | 明石町 | 兵庫県 | 19,819 |
| 59 | 萩町 | 山口県 | 19,804 |
| 60 | 鶴岡町 | 山形県 | 19,562 |
| 61 | 頴娃村 | 鹿児島県 | 19,500 |
| 62 | 青森町 | 青森県 | 19,484 |
| 63 | 栃木町 | 栃木県 | 19,055 |
| 64 | 東南方村 | 鹿児島県 | 19,007 |
| 65 | 尾道町 | 広島県 | 18,473 |
| -- | 丸亀 | 香川県 | 18,295 |
| 66 | 熱田町 | 愛知県 | 18,276 |
| 67 | 撫養町 | 徳島県 | 18,259 |
| 68 | 川越町 | 埼玉県 | 17,988 |
| 69 | 串木野村 | 鹿児島県 | 17,940 |
| 70 | 桑名町 | 三重県 | 17,890 |
| 71 | 彦根町 | 滋賀県 | 17,568 |
| 72 | 四日市町 | 三重県 | 17,531 |
| 73 | 桐生町 | 群馬県 | 17,504 |
| 74 | 伏見町 | 京都府 | 17,503 |
| 75 | 上田町 | 長野県 | 17,242 |
| 76 | 品川町 | 東京府 | 17,108 |
| 77 | 新湊町 | 富山県 | 17,034 |
| 78 | 石巻町 | 宮城県 | 16,974 |
| 79 | 札幌区 | 北海道 | 16,876 |
| 80 | 志布志村 | 鹿児島県 | 16,764 |
| 81 | 福島町 | 福島県 | 16,629 |
| 82 | 小倉町 | 福岡県 | 16,099 |
| 83 | 岡崎町 | 愛知県 | 16,034 |
| 84 | 本銚子町 | 千葉県 | 15,556 |
| 85 | 神奈川町 | 神奈川県 | 15,382 |
| 86 | 戸太村 | 神奈川県 | 15,253 |
| 87 | 福山町 | 広島県 | 14,900 |
| -- | 中城 | 沖縄県 | 14,857 |
| 88 | 阿久根村 | 鹿児島県 | 14,814 |
| 89 | 知覧村 | 鹿児島県 | 14,793 |
| 90 | 高山町 | 岐阜県 | 14,775 |
| 91 | 天王寺村 | 大阪府 | 14,699 |
| 92 | 敦賀町 | 福井県 | 14,606 |
| 93 | 指宿村 | 鹿児島県 | 14,517 |
| 94 | 伊敷村 | 鹿児島県 | 14,512 |
| 95 | 伊作村 | 鹿児島県 | 14,507 |
| 96 | 二保島村 | 広島県 | 14,283 |
| 97 | 武生町 | 福井県 | 14,175 |
| 98 | 千住町 | 東京府 | 14,010 |
| 99 | 足利町 | 栃木県 | 13,924 |
| 100 | 豊橋町 | 愛知県 | 13,911 |
※1889(明治22)年当時、香川県・沖縄県には、まだ市町村制が施行されていません。
※1886(明治19)年・1889(明治22)年共に、12月31日現在の人口です。
| [39936] 2005年 4月 17日(日)14:36:41【2】 | ふぁいん さん |
| 昭和25(1950)年沖縄県人口の謎&明治12(1879)年主要都市人口について | |
[39935] 白桃 さん
沖縄県がHPで発表している市町村別の国勢調査人口を齟齬が生じないように慎重に入力しております。
ただし、1947年はありません。
ただ、占領時下に沖縄でも国勢調査は行われていたのですかね?
記録があるから、間違いではないと思いますが・・・
やはりそうですか。私も沖縄県のHPを参考にしてデータを作成しています。
しかし、沖縄県発表の昭和25(1950)年のデータがどうもしっくりいかないのです。
各年代・国勢調査報告第1巻の付表2 都道府県の市区町村の推移によれば、
昭和25年の沖縄県
市区町村数:86
市数:6
町数:12
村数:68
県人口:914,907人
となっています。
沖縄県発表の場合は、66市町村・698,827人です。
残りの20市町村・216,080人はどこに行ってしまったのかなぁと・・・・
そのため全国の合計人口も合わないし。
戦後の一時期のみ、他にも沖縄県を名乗っていた地域があったのだろうか。
とても不思議に感じております。
白桃さんは、このことにお気づきだったでしょうか?
[39897] 両毛人 さん
これは私からもリクエストいたします!
[39896] ken さん
またそれは、金沢が4位だった時のデータについても、可能でしょうか?
残念ながらありません。おおよその人口位しかわかりません。
金沢の人口を「約」12万人としたのもそのためです。
少なくとも明治4(1871)年の調査までは、金沢には約12万人いたそうです。
その他、富山が当時全国9位。
注:[39658] では、明治維新以後、国内の都市で人口ベスト10入りしたことのある都市として、
22都市あげておりますが、富山が抜けておりました・・・
この年代についても、可能な限り調査したのですが、詳細なデータらしきデータが全くなかったのです。
私が明治中期・明治初期・江戸後期の詳しい都市人口を知りたいのは、このためなんです。。。
明治12(1879)年の主要都市の人口のデータなら持っていますので記載します。
(私が現在所有する最古の人口データとなります)
その他、
富山 約55,000~60,000
堺 約40,000
福井 約40,000
松江 約35,000
鳥取 約32,000
位となります。
上記5都市は様々な資料を参考・調査した結果の推測人口です
[39882] 愛比売命 さん
一番くびれている立科町なんて,ほとんど道路一本でつながっているような状況。
へぇ~~~~これはすごい。ホントに見事なまでに道路一本でかろうじてつながっていますね
最も細いところで、東西約100mといったところでしょうか・・・・
どのようにして、このような町域になったのか経緯が気になりますね・・・
ということで、少し調べてみました。
長野県北佐久郡立科町(全国市町村名変遷総覧・日本加除出版より)
S30.4.1 北佐久郡芦田村・横島村・三都和村の3村が合併し、北佐久郡立科村となる
S33.10.1 町制施行
S35.4.15 北佐久郡望月町(大字茂田井の一部)を編入
芦田という地名が立科町北側にある(町役場も立科町芦田ですし・・・)ので、そこらへんが旧芦田村かな?と思ったら、
なんと南側の白樺湖付近も「芦田」八ヶ野という地名が・・・・
横島、三都和という地名も既に現存しておらず、ここでギブアップ。
旧3村はどんな形をしていたのでしょうかね・・・
おそらく、北側が旧芦田村域で間違いないと思うが。
沖縄県がHPで発表している市町村別の国勢調査人口を齟齬が生じないように慎重に入力しております。
ただし、1947年はありません。
ただ、占領時下に沖縄でも国勢調査は行われていたのですかね?
記録があるから、間違いではないと思いますが・・・
やはりそうですか。私も沖縄県のHPを参考にしてデータを作成しています。
しかし、沖縄県発表の昭和25(1950)年のデータがどうもしっくりいかないのです。
各年代・国勢調査報告第1巻の付表2 都道府県の市区町村の推移によれば、
昭和25年の沖縄県
市区町村数:86
市数:6
町数:12
村数:68
県人口:914,907人
となっています。
沖縄県発表の場合は、66市町村・698,827人です。
残りの20市町村・216,080人はどこに行ってしまったのかなぁと・・・・
そのため全国の合計人口も合わないし。
戦後の一時期のみ、他にも沖縄県を名乗っていた地域があったのだろうか。
とても不思議に感じております。
白桃さんは、このことにお気づきだったでしょうか?
[39897] 両毛人 さん
これは私からもリクエストいたします!
[39896] ken さん
またそれは、金沢が4位だった時のデータについても、可能でしょうか?
残念ながらありません。おおよその人口位しかわかりません。
金沢の人口を「約」12万人としたのもそのためです。
少なくとも明治4(1871)年の調査までは、金沢には約12万人いたそうです。
その他、富山が当時全国9位。
注:[39658] では、明治維新以後、国内の都市で人口ベスト10入りしたことのある都市として、
22都市あげておりますが、富山が抜けておりました・・・
この年代についても、可能な限り調査したのですが、詳細なデータらしきデータが全くなかったのです。
私が明治中期・明治初期・江戸後期の詳しい都市人口を知りたいのは、このためなんです。。。
明治12(1879)年の主要都市の人口のデータなら持っていますので記載します。
(私が現在所有する最古の人口データとなります)
| 東京 | 761,335 |
| 大阪 | 291,565 |
| 京都 | 232,683 |
| 名古屋 | 111,783 |
| 金沢 | 107,876 |
| 広島 | 76,589 |
| 和歌山 | 62,080 |
| 仙台 | 55,035 |
| 横浜 | 46,187 |
| 福岡 | 45,480 |
| 熊本 | 45,032 |
| 神戸 | 44,368 |
| 新潟 | 36,591 |
| 岡山 | 33,028 |
| 長崎 | 32,815 |
| 赤間関 | 26,502 |
| 函館 | 22,088 |
| 伏見 | 22,011 |
| 札幌 | 8,782 |
その他、
富山 約55,000~60,000
堺 約40,000
福井 約40,000
松江 約35,000
鳥取 約32,000
位となります。
上記5都市は様々な資料を参考・調査した結果の推測人口です
[39882] 愛比売命 さん
一番くびれている立科町なんて,ほとんど道路一本でつながっているような状況。
へぇ~~~~これはすごい。ホントに見事なまでに道路一本でかろうじてつながっていますね
最も細いところで、東西約100mといったところでしょうか・・・・
どのようにして、このような町域になったのか経緯が気になりますね・・・
ということで、少し調べてみました。
長野県北佐久郡立科町(全国市町村名変遷総覧・日本加除出版より)
S30.4.1 北佐久郡芦田村・横島村・三都和村の3村が合併し、北佐久郡立科村となる
S33.10.1 町制施行
S35.4.15 北佐久郡望月町(大字茂田井の一部)を編入
芦田という地名が立科町北側にある(町役場も立科町芦田ですし・・・)ので、そこらへんが旧芦田村かな?と思ったら、
なんと南側の白樺湖付近も「芦田」八ヶ野という地名が・・・・
横島、三都和という地名も既に現存しておらず、ここでギブアップ。
旧3村はどんな形をしていたのでしょうかね・・・
おそらく、北側が旧芦田村域で間違いないと思うが。
| [39973] 2005年 4月 18日(月)00:46:41 | ken さん |
| 大変失礼いたしました | |
[39897] 両毛人 さん
[39896]kenさん
既に、ふぁいんさん[39685][39686]にてご投稿いただいています。
大変、失礼いたしました。
ふぁいんさん、両毛人さん、お騒がせしました。
[39936] ふぁいん さん
明治12(1879)年の主要都市の人口のデータなら持っていますので記載します。
(私が現在所有する最古の人口データとなります)
どうもありがとうございます。m(_ _)m
私の個人的興味は、江戸時代の藩の石高と、人口の相関なのですが。
12年でも、ずいぶん開港地の勢いが凄いですね。
19年よりも、和歌山が上位に来ているあたり、ちょっと、石高相関の絡みでは、興味深いです。
ここにない、鹿児島は、4万人台の後半~5万人なんでしょうかね。
私の持論としては、鹿児島は、福岡、熊本より、上位にいて欲しいのですが。
1万石=1000人、というあたり、証明できると面白いのですが。
結構、金沢を筆頭に、岡山、松江、福井、熊本、福岡、福山、津山、川越、大垣、長岡あたり、良い感じのところも多いのですが、
徳島は石高で考えると、四国最大の藩であったとはいえ、常にちょっと多い印象ですね。何か、維新後の要素で、徳島にプラスで出る事象はありましたかね?
赤間関を考慮に入れても、明治19年の萩のBest50入りは、現在の萩市を考えると、やはり凄いですね。
水戸藩は、常府でしたので、殿様は参勤交代がなく、ずっと江戸在住ですので、家臣団もそれに連関して、国許が少ない影響が出ているかもしれません。
どうもありがとうございました。
P.S.
名古屋から、転勤して来る時には、挨拶状に「在名中は一方ならぬお世話になり」と書きましたね。「在命中」じゃないですよ。「在名」
「来葉」も文章語としては使うと思います。
海外観光客の来葉促進になど
「来津」は大津と津と両方で使いますね。
「来岡」も洛陽市政府友好訪日団の来岡などに見えますね。
これも、リストアップしたいですね。
[39896]kenさん
既に、ふぁいんさん[39685][39686]にてご投稿いただいています。
大変、失礼いたしました。
ふぁいんさん、両毛人さん、お騒がせしました。
[39936] ふぁいん さん
明治12(1879)年の主要都市の人口のデータなら持っていますので記載します。
(私が現在所有する最古の人口データとなります)
どうもありがとうございます。m(_ _)m
私の個人的興味は、江戸時代の藩の石高と、人口の相関なのですが。
12年でも、ずいぶん開港地の勢いが凄いですね。
19年よりも、和歌山が上位に来ているあたり、ちょっと、石高相関の絡みでは、興味深いです。
ここにない、鹿児島は、4万人台の後半~5万人なんでしょうかね。
私の持論としては、鹿児島は、福岡、熊本より、上位にいて欲しいのですが。
1万石=1000人、というあたり、証明できると面白いのですが。
結構、金沢を筆頭に、岡山、松江、福井、熊本、福岡、福山、津山、川越、大垣、長岡あたり、良い感じのところも多いのですが、
徳島は石高で考えると、四国最大の藩であったとはいえ、常にちょっと多い印象ですね。何か、維新後の要素で、徳島にプラスで出る事象はありましたかね?
赤間関を考慮に入れても、明治19年の萩のBest50入りは、現在の萩市を考えると、やはり凄いですね。
水戸藩は、常府でしたので、殿様は参勤交代がなく、ずっと江戸在住ですので、家臣団もそれに連関して、国許が少ない影響が出ているかもしれません。
どうもありがとうございました。
P.S.
名古屋から、転勤して来る時には、挨拶状に「在名中は一方ならぬお世話になり」と書きましたね。「在命中」じゃないですよ。「在名」
「来葉」も文章語としては使うと思います。
海外観光客の来葉促進になど
「来津」は大津と津と両方で使いますね。
「来岡」も洛陽市政府友好訪日団の来岡などに見えますね。
これも、リストアップしたいですね。
この特集記事はあなたのお気に召しましたか。よろしければ推奨してください。→ ★推奨します★(元祖いいね)
推奨するためには、メンバー登録が必要です。→ メンバー登録のご案内
… スポンサーリンク …