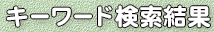… スポンサーリンク …
| [79242] 2011年 8月 24日(水)21:48:52 | 88 さん |
| 市区町村変遷情報(市制町村制施行時) 小レス(石川県) +α | |
レスを溜めないように、少しずつでも処理していきます。
M22.4.1付け石川県市制町村制施行時の件について
この件については、[78864] むっくん さん で、解説をしていただきました。
M22.3.8付け石川県令第28号をご紹介いただきましたが、今回の議論に関する重要なものですので、全文を転記します(旧字体は新字体に置換え)。
石川県令第二十八号 二十二年三月八日
本年四月一日ヨリ本県下ニ於テ市町村制施行ニ付各町ノ内従来小町名ヲ公称シタルモノハ其全市街ヲ一団体トナシ金沢市街ハ従来ノ通小町ヲ公称セシメ其他各町及分合ニ係ル旧町村ノ名称ハ大字トシテ之ヲ存置ス
つまり、M22.3.8付け石川県令第23号中の51コマ参照(従来ノ町村中分合セサルモノ左ノ如シ)と組み合わせて読み、「各町ノ内従来小町名ヲ公称シタルモノ」とあわせて、M22.4.1付けの廃置分合を考える必要がある、とのご教示でした。まったくそのとおりであると思います。
言い換えれば、M22.4.1付けの市制町村制施行は、M22.3.8付け石川県令第28号を優先して考え、小町名(金沢、小松、松任、七尾、輪島)を公称していたものは、その全市街を一団体、つまり、一つの市町村とする、ということです。
これらを踏まえ、個別に見ていきます。
■金沢市
これについては、結果的に、既にM22.3.8付け石川県令第23号に従い対応済みで、そのままとしました。
■江沼郡 大聖寺町
江沼郡 大聖寺荒町, 大聖寺鉄砲町, ・・・の60町が合併した、と修正しました。
■能美郡 小松町
[78861] EMM さん
一方、「小松新大工町」が「小松本大工町」では?については、元の書き込みの1行目に「小松新大工町」、3行目に「小松本大工町」が書いてあるんですけれども、新大工町も本大工町に含まれるような記載であったと言う事でしょうか?
地名辞典の「[近世]小松町」の項によると新大工町は天明5年にはその名が文献に出て来るとの事なので、明治に入ってからもそのまま存続しているのではないかと思われるのですが。
失礼しました。これは私の単なる転記誤りです。「幕末以降総覧」では、「小松○○町」28町(小松新大工町、小松本大工町を共に含む)と、中町地方、浜田地方、向野地方によりM22.4.1付けで能美郡小松町が発足した、とあります。
なお、この件につきましては、[78864] むっくん さん でも追加情報をいただきました。再度、以下に記します。
能美郡 小松龍助町, 小松八日市町, 小松三日市町, 小松東町, 小松八日市町地方, 小松三日市町地方, 小松本折町, 小松上本折町, 小松西町, 小松大文字町, 小松寺町, 小松本鍛冶町, 小松塗師屋町, 小松本大工町, 小松土居原町, 小松京町, 小松地子町, 小松新大工町, 中町地方, 小松浜田町, 浜田地方, 向野地方, 小松小馬出町, 小松松任町, 小松細工町, 小松新町, 小松茶屋町, 小松泥町, 小松中町, 小松材木町, 小松新鍛冶町
なお、むっくんさんは「石川縣史第四巻(著・出版:石川県、S6.3.31)153頁」の記述ということで「小松龍松町」と書いていらっしゃいますが、「幕末以降総覧」「日本地名大辞典」(EMMさん)ではは「小松龍助町」です。新旧対照市町村一覧、大日本市町村名鑑でも、町村の順序は一部異なりますが、名称はすべて一致します。誤りの連鎖さえなければ、小松龍助町 で間違いないでしょう。
なお、現在の小松市龍助町付近に当たると思われます。
ちなみに、「幕末以降総覧」によると、これら31町村はM22.4.1までの間に
との変遷を経た旨の記述もありますので、あわせて参考までにお知らせしておきます。
という訳で、M22.4.1付けで31町村により 能美郡 小松町 が発足した、と修正しました。
■石川郡 松任町
石川郡 松任茶屋町, 松任安田町, ・・・の22町が合併した、と修正しました
■鹿島郡 七尾町
鹿島郡 七尾府中町, 七尾湊町一丁目, ・・・の24町及び4村のそれぞれ(微)が合併した、とそのままとしました
■鳳至郡 輪島町
鳳至郡 輪島河井町, 輪島海士町, ・・・の4町が合併した、と修正しました
――――――――――
■河北郡 小金村となった従前の町村名の一部について 河北郡 伝灯寺村 or 河北郡 伝燈寺村
これも、石川郡 倉ヶ嶽村と同様、現在の表記を重視し、河北郡 伝燈寺村 と修正しました。
(金沢市のHP内で検索してみると見事にふらふらでした)
例えば、条例だけ見てもこんな感じですね。
伝灯寺町・・・金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
伝燈寺町・・・金沢市消防団条例
もっとも、条例はweb上のものよりは、条例制定時に公報に掲載されたものが正式なものですので、web上だけの誤りの可能性もあり、何とも言えません(本当の条例が誤っている可能性もあります)。
何よりも、町名・字名を正式に規定するのは、あくまで地方自治法第260条第2項です。
第二百六十条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
これにより、知事が告示したもの(市長に委任されている場合は市長)があくまで本当の正式なものですが。
なお、[67802] 拙稿の「市町村の名称の書き表わし方について」(昭和33年4月21日自丙行発第7号自治庁行政局長通知)も参照してみてください。
――――――――――
以下別件。
[79169] 播磨坂 さん
■S30(1955).1.1付けで新潟県西鎌原郡巻町となる従前の町村名の一部について 西蒲原郡 峰岡町 or 西蒲原郡 峰岡村
S29.12.27付け総理府告示第1119号を確認しました。単なる入力誤りでした。西蒲原郡 峰岡村 と修正しました。
M22.4.1付け石川県市制町村制施行時の件について
この件については、[78864] むっくん さん で、解説をしていただきました。
M22.3.8付け石川県令第28号をご紹介いただきましたが、今回の議論に関する重要なものですので、全文を転記します(旧字体は新字体に置換え)。
石川県令第二十八号 二十二年三月八日
本年四月一日ヨリ本県下ニ於テ市町村制施行ニ付各町ノ内従来小町名ヲ公称シタルモノハ其全市街ヲ一団体トナシ金沢市街ハ従来ノ通小町ヲ公称セシメ其他各町及分合ニ係ル旧町村ノ名称ハ大字トシテ之ヲ存置ス
つまり、M22.3.8付け石川県令第23号中の51コマ参照(従来ノ町村中分合セサルモノ左ノ如シ)と組み合わせて読み、「各町ノ内従来小町名ヲ公称シタルモノ」とあわせて、M22.4.1付けの廃置分合を考える必要がある、とのご教示でした。まったくそのとおりであると思います。
言い換えれば、M22.4.1付けの市制町村制施行は、M22.3.8付け石川県令第28号を優先して考え、小町名(金沢、小松、松任、七尾、輪島)を公称していたものは、その全市街を一団体、つまり、一つの市町村とする、ということです。
これらを踏まえ、個別に見ていきます。
■金沢市
これについては、結果的に、既にM22.3.8付け石川県令第23号に従い対応済みで、そのままとしました。
■江沼郡 大聖寺町
江沼郡 大聖寺荒町, 大聖寺鉄砲町, ・・・の60町が合併した、と修正しました。
■能美郡 小松町
[78861] EMM さん
一方、「小松新大工町」が「小松本大工町」では?については、元の書き込みの1行目に「小松新大工町」、3行目に「小松本大工町」が書いてあるんですけれども、新大工町も本大工町に含まれるような記載であったと言う事でしょうか?
地名辞典の「[近世]小松町」の項によると新大工町は天明5年にはその名が文献に出て来るとの事なので、明治に入ってからもそのまま存続しているのではないかと思われるのですが。
失礼しました。これは私の単なる転記誤りです。「幕末以降総覧」では、「小松○○町」28町(小松新大工町、小松本大工町を共に含む)と、中町地方、浜田地方、向野地方によりM22.4.1付けで能美郡小松町が発足した、とあります。
なお、この件につきましては、[78864] むっくん さん でも追加情報をいただきました。再度、以下に記します。
能美郡 小松龍助町, 小松八日市町, 小松三日市町, 小松東町, 小松八日市町地方, 小松三日市町地方, 小松本折町, 小松上本折町, 小松西町, 小松大文字町, 小松寺町, 小松本鍛冶町, 小松塗師屋町, 小松本大工町, 小松土居原町, 小松京町, 小松地子町, 小松新大工町, 中町地方, 小松浜田町, 浜田地方, 向野地方, 小松小馬出町, 小松松任町, 小松細工町, 小松新町, 小松茶屋町, 小松泥町, 小松中町, 小松材木町, 小松新鍛冶町
なお、むっくんさんは「石川縣史第四巻(著・出版:石川県、S6.3.31)153頁」の記述ということで「小松龍松町」と書いていらっしゃいますが、「幕末以降総覧」「日本地名大辞典」(EMMさん)ではは「小松龍助町」です。新旧対照市町村一覧、大日本市町村名鑑でも、町村の順序は一部異なりますが、名称はすべて一致します。誤りの連鎖さえなければ、小松龍助町 で間違いないでしょう。
なお、現在の小松市龍助町付近に当たると思われます。
ちなみに、「幕末以降総覧」によると、これら31町村はM22.4.1までの間に
| 年 | 変更後 | 変更種別 | 変更前 |
| M17 | 小松松任町 | 編入 | 小松松任町, 松任町地方 |
| M8 | 小松茶屋町 | 改称 | 梯出村 |
| M8 | 浜田地方 | 改称 | 浜田村 |
| M8 | 向野地方 | 改称 | 向野村 |
という訳で、M22.4.1付けで31町村により 能美郡 小松町 が発足した、と修正しました。
■石川郡 松任町
石川郡 松任茶屋町, 松任安田町, ・・・の22町が合併した、と修正しました
■鹿島郡 七尾町
鹿島郡 七尾府中町, 七尾湊町一丁目, ・・・の24町及び4村のそれぞれ(微)が合併した、とそのままとしました
■鳳至郡 輪島町
鳳至郡 輪島河井町, 輪島海士町, ・・・の4町が合併した、と修正しました
――――――――――
■河北郡 小金村となった従前の町村名の一部について 河北郡 伝灯寺村 or 河北郡 伝燈寺村
これも、石川郡 倉ヶ嶽村と同様、現在の表記を重視し、河北郡 伝燈寺村 と修正しました。
(金沢市のHP内で検索してみると見事にふらふらでした)
例えば、条例だけ見てもこんな感じですね。
伝灯寺町・・・金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
伝燈寺町・・・金沢市消防団条例
もっとも、条例はweb上のものよりは、条例制定時に公報に掲載されたものが正式なものですので、web上だけの誤りの可能性もあり、何とも言えません(本当の条例が誤っている可能性もあります)。
何よりも、町名・字名を正式に規定するのは、あくまで地方自治法第260条第2項です。
第二百六十条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。
3 第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
これにより、知事が告示したもの(市長に委任されている場合は市長)があくまで本当の正式なものですが。
なお、[67802] 拙稿の「市町村の名称の書き表わし方について」(昭和33年4月21日自丙行発第7号自治庁行政局長通知)も参照してみてください。
――――――――――
以下別件。
[79169] 播磨坂 さん
■S30(1955).1.1付けで新潟県西鎌原郡巻町となる従前の町村名の一部について 西蒲原郡 峰岡町 or 西蒲原郡 峰岡村
S29.12.27付け総理府告示第1119号を確認しました。単なる入力誤りでした。西蒲原郡 峰岡村 と修正しました。
| [79282] 2011年 8月 30日(火)06:43:52 | 千本桜 さん |
| 仙台区町名 | |
明治41年発行「仙台市史」を引用しながら仙台区の町について書き込みます。仙台市史は「行政組織及び区画の沿革」について
明治11年7月22日布告第17号を以て郡区町村編成法を発布せられ、庁下を仙台区と称し、区長一員を置かる、是に於いて仙台は一の独立行政区となれり、此年11月区内を5部に分ち毎部町場持4人乃至6人を置き、部内を4分又は6分して布告布達等の事務を取扱はしむ、之を区行政の区画とする
として、5部(5つの地域ブロック)と253の町名を記載しています。この数字は要注意です。東西に長く延びた北一番丁などは町域が2つのブロックに跨がっていて、各々のブロックに北一番丁が載っいています。つまり重複記載です。このような町名が25ありますから、253-25=228で実際は228町になります。なお、仙台市史は町数の合計を記載していないので、私が町名を追いながら算出しました。検算していますが2、3の漏れがある可能性も考えられます。
明治14年4月15日、仙台区と宮城郡南目、荒巻、小田原各村の内、地所交換、(中略)同年10月24日、1名称にして数町に亘る市街区分を左の如く定めらる
として、町名と各々の町を細分した丁目を記載しています。町の延長が短い南町などは1丁目から2丁目まで。延長が長い北二番丁などは1丁目から14丁目まであります。これに記載された町の名称は140。丁目の合計は402です。この場合、町数を140とするか402とするか迷いますが、私は140町とするのが自然だと思います。
明治15年10月行政区画を改めて、各町組合を設け組毎に組長1人を置き、
明治18年4月1日之を更正して140組とし、(中略)
明治18年10月15日追廻組を中ノ町組に合併、
明治19年2月13日更に改めて56組とし、
明治19年3月29日北七番丁(堤通東)を北二、三、四、五、六番丁東組に、北七、八、九番丁(通町東 堤通西)を通町組に変更せり、其の名称及区画は左の如し
として、56組207町の名称を記載しています。207町の名称は次のとおりです。
河原町, 新河原町, 新河原町東丁, 南石切町, 新弓ノ町, 八軒小路, 南染師町, 南鍛冶町, 南材木町, 穀町, 三百人町, 五十人町, 六十人町, 畳屋丁, 保春院前丁, 成田町, 表柴田町, 裏柴田町, 元茶畑, 椌木通, 木ノ下, 西新丁, 東新丁, 荒町, 連坊小路, 清水小路, 北目町, 上染師町, 田町, 南町, 柳町, 大町一丁目頭, 大町一丁目, 大町二丁目, 大町三丁目, 大町四丁目, 大町五丁目, 大町五丁目新丁, 新伝馬町, 名掛丁, 二十人町, 榴ヶ岡, 舟丁, 堰場, 石名坂, 弓ノ町, 土樋, 猿牽丁, 姉歯横丁, 石垣町, 米ヶ袋上丁, 米ヶ袋中丁, 米ヶ袋下丁, 米ヶ袋十二軒丁, 米ヶ袋広丁, 米ヶ袋鍛冶屋前丁, 七軒丁, 鉄砲横丁, 桜小路, 道場小路, 伊勢屋横丁, 六軒丁, 片平丁, 本荒町, 良覚院丁, 狐小路, 袋町, 中ノ町, 琵琶首丁, 琵琶首新丁, 花壇, 花壇川前丁, 霊屋下, 越路, 越路六軒丁, 越路路地町, 宮沢, 川内大橋通, 川内柳丁, 川内中ノ瀬町, 川内大工町, 川内川前丁, 川内明神横丁, 川内元支倉, 川内澱橋通, 川内元支倉通, 川内新横丁, 川内数寄屋丁, 川内亀岡町, 川内亀岡北裏丁, 川内三十人町, 川内山屋敷, 肴町, 立町, 立町新丁, 本柳町,元櫓丁, 定禅寺通櫓丁, 元鍛冶町, 常盤町, 北材木町, 本材木町, 跡付町, 木町末無, 立町通, 定禅寺通, 南町通, 南光院丁, 教楽院丁, 薬鑵小路, 裏五番丁, 柳町通, 北目町通, 新寺小路, 国分町, 二日町, 北鍛冶町, 通町, 北田町, 堤町, 支倉町, 木町通, 新坂通, 土橋通, 支倉通, 半子町, 伊勢堂下, 神子町, 北山町, 八幡町, 坊主町, 江戸町, 覚性院丁, 石切町, 中島丁, 切通, 十二軒丁, 北五十人町, 滝前丁, 角五郎丁, 角五郎新丁, 澱町, 勾当台通, 表小路, 外記丁, 堤通, 外記丁通, 同心町通, 中杉山通, 光禅寺通, 二本杉通, 杉山通, 元寺小路, 茂市ヶ坂, 掃部丁, 末無掃部丁, 大仏前, 同心町中丁, 元貞坂, 空堀丁, 新名懸丁, 新小路, 花京院通, 長丁, 長刀丁, 北六軒丁, 鉄砲町, 車町, 小田原山本丁, 小田原裏山本丁, 小田原車通, 小田原宮町東裏丁, 小田原東丁, 小田原袖振丁, 小田原遣水丁, 小田原長丁通, 小田原高松通, 小田原金剛院丁, 小田原広丁, 小田原大行院丁, 小田原牛小屋丁, 小田原清水沼通, 小田原弓ノ町, 小田原北一番丁通, 小田原北二番丁通, 小田原北三番丁通, 宮町, 東一番丁, 東二番丁, 東三番丁, 東四番丁, 東五番丁, 東六番丁, 東七番丁, 東八番丁, 東九番丁, 東十番丁, 北一番丁, 北二番丁, 北三番丁, 北四番丁, 北五番丁, 北六番丁, 北七番丁, 北八番丁, 北九番丁, 北十番丁
而して区は22年3月31日更に区域を変更すること左の如し
として、下記の5村から各々土地の一部を編入したとしています。
宮城郡荒巻村の一部(字山上清水, 字滝前, 字宮裏, 字上郡山, 字中丿沢)
宮城郡小田原村の一部(字小野田, 字杉山)
宮城郡南目村の一部(字柳沢, 字二軒茶屋)
宮城郡南小泉村の一部(字八軒小路, 字行人塚, 字五ツ谷, 字桃源院東, 字鍛冶屋敷, 字広瀬川橋下)
名取郡長町村の一部(字窪谷地の一部)
また、
仙台区宮沢の一部を名取郡茂ヶ崎村に編入
仙台区北六番丁の一部を宮城郡原町に編入
とあります。
以上のことから、仙台区の町村として市区町村変遷情報に乗せるべきは、掲載した207の町名および明治22年3月31日に行われた区画変更の情報だと思います。
(注):207町について。原文のまま書き出せれば良いのですが、
1・誤字脱字が見受けられること。
2・複数の組に跨がる町は重複して町名が記載されていること。
3・同名の町名があり、それを区別表記をしなければならないこと。
そのような理由があり、私が手を加えています。
88さん
明治22年(1889年) 3月31日 宮城県 市制町村制施行直前の廃置分合等ですが、この表組を普通に読めば、「明治22年(1889年) 3月31日に仙台区, 仙台区新河原町, 新弓ノ町,(以下省略)が合併して仙台区が新設された。」になります。表組作成にもう一工夫必要かなと思いました。
明治11年7月22日布告第17号を以て郡区町村編成法を発布せられ、庁下を仙台区と称し、区長一員を置かる、是に於いて仙台は一の独立行政区となれり、此年11月区内を5部に分ち毎部町場持4人乃至6人を置き、部内を4分又は6分して布告布達等の事務を取扱はしむ、之を区行政の区画とする
として、5部(5つの地域ブロック)と253の町名を記載しています。この数字は要注意です。東西に長く延びた北一番丁などは町域が2つのブロックに跨がっていて、各々のブロックに北一番丁が載っいています。つまり重複記載です。このような町名が25ありますから、253-25=228で実際は228町になります。なお、仙台市史は町数の合計を記載していないので、私が町名を追いながら算出しました。検算していますが2、3の漏れがある可能性も考えられます。
明治14年4月15日、仙台区と宮城郡南目、荒巻、小田原各村の内、地所交換、(中略)同年10月24日、1名称にして数町に亘る市街区分を左の如く定めらる
として、町名と各々の町を細分した丁目を記載しています。町の延長が短い南町などは1丁目から2丁目まで。延長が長い北二番丁などは1丁目から14丁目まであります。これに記載された町の名称は140。丁目の合計は402です。この場合、町数を140とするか402とするか迷いますが、私は140町とするのが自然だと思います。
明治15年10月行政区画を改めて、各町組合を設け組毎に組長1人を置き、
明治18年4月1日之を更正して140組とし、(中略)
明治18年10月15日追廻組を中ノ町組に合併、
明治19年2月13日更に改めて56組とし、
明治19年3月29日北七番丁(堤通東)を北二、三、四、五、六番丁東組に、北七、八、九番丁(通町東 堤通西)を通町組に変更せり、其の名称及区画は左の如し
として、56組207町の名称を記載しています。207町の名称は次のとおりです。
河原町, 新河原町, 新河原町東丁, 南石切町, 新弓ノ町, 八軒小路, 南染師町, 南鍛冶町, 南材木町, 穀町, 三百人町, 五十人町, 六十人町, 畳屋丁, 保春院前丁, 成田町, 表柴田町, 裏柴田町, 元茶畑, 椌木通, 木ノ下, 西新丁, 東新丁, 荒町, 連坊小路, 清水小路, 北目町, 上染師町, 田町, 南町, 柳町, 大町一丁目頭, 大町一丁目, 大町二丁目, 大町三丁目, 大町四丁目, 大町五丁目, 大町五丁目新丁, 新伝馬町, 名掛丁, 二十人町, 榴ヶ岡, 舟丁, 堰場, 石名坂, 弓ノ町, 土樋, 猿牽丁, 姉歯横丁, 石垣町, 米ヶ袋上丁, 米ヶ袋中丁, 米ヶ袋下丁, 米ヶ袋十二軒丁, 米ヶ袋広丁, 米ヶ袋鍛冶屋前丁, 七軒丁, 鉄砲横丁, 桜小路, 道場小路, 伊勢屋横丁, 六軒丁, 片平丁, 本荒町, 良覚院丁, 狐小路, 袋町, 中ノ町, 琵琶首丁, 琵琶首新丁, 花壇, 花壇川前丁, 霊屋下, 越路, 越路六軒丁, 越路路地町, 宮沢, 川内大橋通, 川内柳丁, 川内中ノ瀬町, 川内大工町, 川内川前丁, 川内明神横丁, 川内元支倉, 川内澱橋通, 川内元支倉通, 川内新横丁, 川内数寄屋丁, 川内亀岡町, 川内亀岡北裏丁, 川内三十人町, 川内山屋敷, 肴町, 立町, 立町新丁, 本柳町,元櫓丁, 定禅寺通櫓丁, 元鍛冶町, 常盤町, 北材木町, 本材木町, 跡付町, 木町末無, 立町通, 定禅寺通, 南町通, 南光院丁, 教楽院丁, 薬鑵小路, 裏五番丁, 柳町通, 北目町通, 新寺小路, 国分町, 二日町, 北鍛冶町, 通町, 北田町, 堤町, 支倉町, 木町通, 新坂通, 土橋通, 支倉通, 半子町, 伊勢堂下, 神子町, 北山町, 八幡町, 坊主町, 江戸町, 覚性院丁, 石切町, 中島丁, 切通, 十二軒丁, 北五十人町, 滝前丁, 角五郎丁, 角五郎新丁, 澱町, 勾当台通, 表小路, 外記丁, 堤通, 外記丁通, 同心町通, 中杉山通, 光禅寺通, 二本杉通, 杉山通, 元寺小路, 茂市ヶ坂, 掃部丁, 末無掃部丁, 大仏前, 同心町中丁, 元貞坂, 空堀丁, 新名懸丁, 新小路, 花京院通, 長丁, 長刀丁, 北六軒丁, 鉄砲町, 車町, 小田原山本丁, 小田原裏山本丁, 小田原車通, 小田原宮町東裏丁, 小田原東丁, 小田原袖振丁, 小田原遣水丁, 小田原長丁通, 小田原高松通, 小田原金剛院丁, 小田原広丁, 小田原大行院丁, 小田原牛小屋丁, 小田原清水沼通, 小田原弓ノ町, 小田原北一番丁通, 小田原北二番丁通, 小田原北三番丁通, 宮町, 東一番丁, 東二番丁, 東三番丁, 東四番丁, 東五番丁, 東六番丁, 東七番丁, 東八番丁, 東九番丁, 東十番丁, 北一番丁, 北二番丁, 北三番丁, 北四番丁, 北五番丁, 北六番丁, 北七番丁, 北八番丁, 北九番丁, 北十番丁
而して区は22年3月31日更に区域を変更すること左の如し
として、下記の5村から各々土地の一部を編入したとしています。
宮城郡荒巻村の一部(字山上清水, 字滝前, 字宮裏, 字上郡山, 字中丿沢)
宮城郡小田原村の一部(字小野田, 字杉山)
宮城郡南目村の一部(字柳沢, 字二軒茶屋)
宮城郡南小泉村の一部(字八軒小路, 字行人塚, 字五ツ谷, 字桃源院東, 字鍛冶屋敷, 字広瀬川橋下)
名取郡長町村の一部(字窪谷地の一部)
また、
仙台区宮沢の一部を名取郡茂ヶ崎村に編入
仙台区北六番丁の一部を宮城郡原町に編入
とあります。
以上のことから、仙台区の町村として市区町村変遷情報に乗せるべきは、掲載した207の町名および明治22年3月31日に行われた区画変更の情報だと思います。
(注):207町について。原文のまま書き出せれば良いのですが、
1・誤字脱字が見受けられること。
2・複数の組に跨がる町は重複して町名が記載されていること。
3・同名の町名があり、それを区別表記をしなければならないこと。
そのような理由があり、私が手を加えています。
88さん
明治22年(1889年) 3月31日 宮城県 市制町村制施行直前の廃置分合等ですが、この表組を普通に読めば、「明治22年(1889年) 3月31日に仙台区, 仙台区新河原町, 新弓ノ町,(以下省略)が合併して仙台区が新設された。」になります。表組作成にもう一工夫必要かなと思いました。
| [79658] 2011年 11月 21日(月)08:23:17 | 千本桜 さん |
| 仙台区から仙台市に移行する時点での町名・まとめ2 | |
88さんへ。[79657] の続きです
[79282] でも書きましたが、もう一度、明治41年発行「仙台市史」を引用しながら仙台区の町について書きます。なお、仙台市史は町数を載せていないので、私が町名を追いながら計算しています。
【ステップ1】郡区町村編成法が発布された明治11年から始めます。仙台市史は次のように書いています。
明治11年7月22日布告第17号を以て郡区町村編成法を発布せられ、庁下を仙台区と称し、区長一員を置かる、是に於いて仙台は一の独立行政区となれり、此年11月区内を5部に分ち毎部町場持4人乃至6人を置き、部内を4分又は6分して布告布達等の事務を取扱はしむ、之を区行政の区画とする
と記述して、第1部(河原町など31町)、第2部(片平丁など74町)、第3部(南町など50町)、第4部(国分町など59町)、第5部(八幡町など39町)を挙げ、計253町を掲出しています。しかし、この町数は要注意です。延長の長い町は2つの部に分割され、双方の部に町名が載っているからです。つまり重複記載です。このような重複記載が25ありますから、253-25=228で実際は228町になります。
【ステップ2】次に、市史は明治14年に行われた区画変更の記述に進みます。
明治14年4月15日、仙台区と宮城郡南目、荒巻、小田原各村の内、地所交換、区は差引6町1反7畝15歩余を増せり、同年10月24日、1名称にして数町に亘る市街区分を左の如く定めらる
と記述して、140の町名を掲出し、各町を幾つかの丁目に細分しています。具体的には、国分町(1丁目より5丁目まで)、北二番丁(1丁目より14丁目まで)のように書いてあり、丁目の合計数は402になります。この丁目区分は、本当に明治14年に定められたのかは疑わしい。なぜなら、明治13年出版の宮城県仙台区全図に既に丁目が表示されているからです。この区分は、市制直前の町名解決に繋がらないようなので思いきって無視します。
【ステップ3】次に、市史は明治15、18、19年に行われた行政組織と区画更正の記述に進みます。その全文を引用します。
同15年10月行政区画を改めて、各町組合を設け組毎に組長1人を置き、18年4月1日之を更正して140組とし、同時に組長設置規則を改め、組長は満25歳以上にして組内に不動産を所有するものより選挙し、任期を3ヶ年として専ら組内の布告回達、納税注意、戸籍方並に篤行者、極貧者の取調を司り兼ねて共同の事件に関係せり、其筆紙墨料は1ヶ年1戸に付拾銭を徴せり、明治18年10月15日追廻組を中ノ町組に合併、19年2月13日更に改めて56組とし、翌月29日北七番丁(堤通東)を北二、三、四、五、六番丁東組に、北七、八、九番丁(通町東 堤通西)を通町組に変更せり、其名称及区画は左の如し
として、八幡町組(八幡町、坊主町ほか3町)、花京院通組(花京院通、空堀丁ほか6町)など56組207町の名称を掲出しています。207町の名称は下記のとおりです。207町を原文のまま書き出せれば良いのですが、誤字脱字があったり、複数の組に跨がる町については重複記載の調整が必要なことから、私が手を加えています。[79282] に記載した207町をもう一度掲載します
河原町, 新河原町, 新河原町東丁, 南石切町, 新弓ノ町, 八軒小路, 南染師町, 南鍛冶町, 南材木町, 穀町, 三百人町, 五十人町, 六十人町, 畳屋丁, 保春院前丁, 成田町, 表柴田町, 裏柴田町, 元茶畑, 椌木通, 木ノ下, 西新丁, 東新丁, 荒町, 連坊小路, 清水小路, 北目町, 上染師町, 田町, 南町, 柳町, 大町一丁目頭, 大町一丁目, 大町二丁目, 大町三丁目, 大町四丁目, 大町五丁目, 大町五丁目新丁, 新伝馬町, 名掛丁, 二十人町, 榴ヶ岡, 舟丁, 堰場, 石名坂, 弓ノ町, 土樋, 猿牽丁, 姉歯横丁, 石垣町, 米ヶ袋上丁, 米ヶ袋中丁, 米ヶ袋下丁, 米ヶ袋十二軒丁, 米ヶ袋広丁, 米ヶ袋鍛冶屋前丁, 七軒丁, 鉄砲横丁, 桜小路, 道場小路, 伊勢屋横丁, 六軒丁, 片平丁, 本荒町, 良覚院丁, 狐小路, 袋町, 中ノ町, 琵琶首丁, 琵琶首新丁, 花壇, 花壇川前丁, 霊屋下, 越路, 越路六軒丁, 越路路地町, 宮沢, 川内大橋通, 川内柳丁, 川内中ノ瀬町, 川内大工町, 川内川前丁, 川内明神横丁, 川内元支倉, 川内澱橋通, 川内元支倉通, 川内新横丁, 川内数寄屋丁, 川内亀岡町, 川内亀岡北裏丁, 川内三十人町, 川内山屋敷, 肴町, 立町, 立町新丁, 本柳町,元櫓丁, 定禅寺通櫓丁, 元鍛冶町, 常盤町, 北材木町, 本材木町, 跡付町, 木町末無, 立町通, 定禅寺通, 南町通, 南光院丁, 教楽院丁, 薬鑵小路, 裏五番丁, 柳町通, 北目町通, 新寺小路, 国分町, 二日町, 北鍛冶町, 通町, 北田町, 堤町, 支倉町, 木町通, 新坂通, 土橋通, 支倉通, 半子町, 伊勢堂下, 神子町, 北山町, 八幡町, 坊主町, 江戸町, 覚性院丁, 石切町, 中島丁, 切通, 十二軒丁, 北五十人町, 滝前丁, 角五郎丁, 角五郎新丁, 澱町, 勾当台通, 表小路, 外記丁, 堤通, 外記丁通, 同心町通, 中杉山通, 光禅寺通, 二本杉通, 杉山通, 元寺小路, 茂市ヶ坂, 掃部丁, 末無掃部丁, 大仏前, 同心町中丁, 元貞坂, 空堀丁, 新名懸丁, 新小路, 花京院通, 長丁, 長刀丁, 北六軒丁, 鉄砲町, 車町, 小田原山本丁, 小田原裏山本丁, 小田原車通, 小田原宮町東裏丁, 小田原東丁, 小田原袖振丁, 小田原遣水丁, 小田原長丁通, 小田原高松通, 小田原金剛院丁, 小田原広丁, 小田原大行院丁, 小田原牛小屋丁, 小田原清水沼通, 小田原弓ノ町, 小田原北一番丁通, 小田原北二番丁通, 小田原北三番丁通, 宮町, 東一番丁, 東二番丁, 東三番丁, 東四番丁, 東五番丁, 東六番丁, 東七番丁, 東八番丁, 東九番丁, 東十番丁, 北一番丁, 北二番丁, 北三番丁, 北四番丁, 北五番丁, 北六番丁, 北七番丁, 北八番丁, 北九番丁, 北十番丁
【ステップ4】次に、市史は明治22年3月に行われた区域変更の記述へ進みます。仙台区消滅直前の区域変更です。
而して区は22年3月31日更に区域を変更すること左の如し
と述べて、宮城郡荒巻村の一部(字山上清水, 字滝前, 字宮裏, 字上郡山, 字中丿沢)、宮城郡小田原村の一部(字小野田, 字杉山)、宮城郡南目村の一部(字柳沢, 字二軒茶屋)、宮城郡南小泉村の一部(字八軒小路, 字行人塚, 字五ツ谷, 字桃源院東, 字鍛冶屋敷, 字広瀬川橋下)、名取郡長町村の一部(字窪谷地の一部)を仙台区に編入。また、仙台区宮沢の一部を名取郡茂ヶ崎村に編入し、仙台区北六番丁の一部を宮城郡原町に編入したと記しています。
以上のことから、88さんが纏めておられる市区町村変遷情報に載せるべき仙台の町は、【ステップ3】で掲載した207町および【ステップ4】で掲載した周辺村との区画変更だと思いました。しかしその後、市史に町名書き漏れの疑念をいだき、各種資料を突き合わせてチェックしました。チェックの方法は[79312]に書いたとおりです。その結果、上杉山通、米ヶ袋中ノ坂、米ヶ袋鹿子清水通、大聖寺裏門通の4町が書き漏れとして浮上しました。
しかし、大聖寺裏門通(現在の青葉区本町二丁目錦町公園付近)で頭を抱えてしまいました。地籍があっても家屋が消滅して無人になっていた可能性が見え隠れするからです。大聖寺裏門通という地籍があったとする根拠は歴史的町名復活検討委員会の29ページ「旧城下の町名(住居表示実施直前の町名)一覧」と36ページ右側の地図に大聖寺裏門通の表記があるからです。また、明治22年当時は無人になっていたかも知れないという根拠は、36ページ右側の地図に線引きされた大聖寺裏門通の区域が非常に狭いことに加え、明治後期の地図には家屋のない更地ふうに描かれているからです。
大聖寺裏門通が無人か有人かで引っ掛かり、前進できないでおりましたが、これ以上考えるのは止めましょう。仙台区から仙台市に移行する時点で、上杉山通、米ヶ袋中ノ坂、米ヶ袋鹿子清水通、大聖寺裏門通の4町は存在していたと決着をつけます。そうしないと埒があきません。
上記を踏まえ、明治22年仙台区消滅直前の町数は、【ステップ3】に掲げた207町に上杉山通、米ヶ袋中ノ坂、米ヶ袋鹿子清水通、大聖寺裏門通の4町を加え、211町に訂正したいと思います。【ステップ3】に掲げた207町のうち、六軒丁を南六軒丁に修正し、宮沢と北六番丁に(微)を付し、新たに加える上杉山通、米ヶ袋中ノ坂、米ヶ袋鹿子清水通、大聖寺裏門通は、それぞれ適宜な位置に挿入しました。はたして判断が正しいのか否か自信はありませんが、自分なりに出した結論に従い仙台211町5村を掲出しますので、市区町村変遷情報を下記のように修正してください。
河原町, 新河原町, 新河原町東丁, 南石切町, 新弓ノ町, 八軒小路, 南染師町, 南鍛冶町, 南材木町, 穀町, 三百人町, 五十人町, 六十人町, 畳屋丁, 保春院前丁, 成田町, 表柴田町, 裏柴田町, 元茶畑, 椌木通, 木ノ下, 西新丁, 東新丁, 荒町, 連坊小路, 清水小路, 北目町, 上染師町, 田町, 南町, 柳町, 大町一丁目頭, 大町一丁目, 大町二丁目, 大町三丁目, 大町四丁目, 大町五丁目, 大町五丁目新丁, 新伝馬町, 名掛丁, 二十人町, 榴ヶ岡, 舟丁, 堰場, 石名坂, 弓ノ町, 土樋, 猿牽丁, 姉歯横丁, 石垣町, 米ヶ袋上丁, 米ヶ袋中丁, 米ヶ袋下丁, 米ヶ袋十二軒丁, 米ヶ袋広丁, 米ヶ袋鍛冶屋前丁, 米ヶ袋中ノ坂, 米ヶ袋鹿子清水通, 七軒丁, 鉄砲横丁, 桜小路, 道場小路, 伊勢屋横丁, 南六軒丁, 片平丁, 本荒町, 良覚院丁, 狐小路, 袋町, 中ノ町, 琵琶首丁, 琵琶首新丁, 花壇, 花壇川前丁, 霊屋下, 越路, 越路六軒丁, 越路路地町, 宮沢(微), 川内大橋通, 川内柳丁, 川内中ノ瀬町, 川内大工町, 川内川前丁, 川内明神横丁, 川内元支倉, 川内澱橋通, 川内元支倉通, 川内新横丁, 川内数寄屋丁, 川内亀岡町, 川内亀岡北裏丁, 川内三十人町, 川内山屋敷, 肴町, 立町, 立町新丁, 本柳町,元櫓丁, 定禅寺通櫓丁, 元鍛冶町, 常盤町, 北材木町, 本材木町, 跡付町, 木町末無, 立町通, 定禅寺通, 南町通, 南光院丁, 教楽院丁, 薬鑵小路, 裏五番丁, 柳町通, 北目町通, 新寺小路, 国分町, 二日町, 北鍛冶町, 通町, 北田町, 堤町, 支倉町, 木町通, 新坂通, 土橋通, 支倉通, 半子町, 伊勢堂下, 神子町, 北山町, 八幡町, 坊主町, 江戸町, 覚性院丁, 石切町, 中島丁, 切通, 十二軒丁, 北五十人町, 滝前丁, 角五郎丁, 角五郎新丁, 澱町, 勾当台通, 表小路, 外記丁, 堤通, 外記丁通, 上杉山通, 同心町通, 中杉山通, 光禅寺通, 二本杉通, 杉山通, 元寺小路, 茂市ヶ坂, 掃部丁, 末無掃部丁, 大仏前, 同心町中丁, 元貞坂, 大聖寺裏門通, 空堀丁, 新名懸丁, 新小路, 花京院通, 長丁, 長刀丁, 北六軒丁, 鉄砲町, 車町, 小田原山本丁, 小田原裏山本丁, 小田原車通, 小田原宮町東裏丁, 小田原東丁, 小田原袖振丁, 小田原遣水丁, 小田原長丁通, 小田原高松通, 小田原金剛院丁, 小田原広丁, 小田原大行院丁, 小田原牛小屋丁, 小田原清水沼通, 小田原弓ノ町, 小田原北一番丁通, 小田原北二番丁通, 小田原北三番丁通, 宮町, 東一番丁, 東二番丁, 東三番丁, 東四番丁, 東五番丁, 東六番丁, 東七番丁, 東八番丁, 東九番丁, 東十番丁, 北一番丁, 北二番丁, 北三番丁, 北四番丁, 北五番丁, 北六番丁(微),, 北七番丁, 北八番丁, 北九番丁, 北十番丁, 宮城郡 荒巻村(微), 小田原村(微), 南目村(微), 南小泉村(微), 名取郡 長町村(微)
[79282] でも書きましたが、もう一度、明治41年発行「仙台市史」を引用しながら仙台区の町について書きます。なお、仙台市史は町数を載せていないので、私が町名を追いながら計算しています。
【ステップ1】郡区町村編成法が発布された明治11年から始めます。仙台市史は次のように書いています。
明治11年7月22日布告第17号を以て郡区町村編成法を発布せられ、庁下を仙台区と称し、区長一員を置かる、是に於いて仙台は一の独立行政区となれり、此年11月区内を5部に分ち毎部町場持4人乃至6人を置き、部内を4分又は6分して布告布達等の事務を取扱はしむ、之を区行政の区画とする
と記述して、第1部(河原町など31町)、第2部(片平丁など74町)、第3部(南町など50町)、第4部(国分町など59町)、第5部(八幡町など39町)を挙げ、計253町を掲出しています。しかし、この町数は要注意です。延長の長い町は2つの部に分割され、双方の部に町名が載っているからです。つまり重複記載です。このような重複記載が25ありますから、253-25=228で実際は228町になります。
【ステップ2】次に、市史は明治14年に行われた区画変更の記述に進みます。
明治14年4月15日、仙台区と宮城郡南目、荒巻、小田原各村の内、地所交換、区は差引6町1反7畝15歩余を増せり、同年10月24日、1名称にして数町に亘る市街区分を左の如く定めらる
と記述して、140の町名を掲出し、各町を幾つかの丁目に細分しています。具体的には、国分町(1丁目より5丁目まで)、北二番丁(1丁目より14丁目まで)のように書いてあり、丁目の合計数は402になります。この丁目区分は、本当に明治14年に定められたのかは疑わしい。なぜなら、明治13年出版の宮城県仙台区全図に既に丁目が表示されているからです。この区分は、市制直前の町名解決に繋がらないようなので思いきって無視します。
【ステップ3】次に、市史は明治15、18、19年に行われた行政組織と区画更正の記述に進みます。その全文を引用します。
同15年10月行政区画を改めて、各町組合を設け組毎に組長1人を置き、18年4月1日之を更正して140組とし、同時に組長設置規則を改め、組長は満25歳以上にして組内に不動産を所有するものより選挙し、任期を3ヶ年として専ら組内の布告回達、納税注意、戸籍方並に篤行者、極貧者の取調を司り兼ねて共同の事件に関係せり、其筆紙墨料は1ヶ年1戸に付拾銭を徴せり、明治18年10月15日追廻組を中ノ町組に合併、19年2月13日更に改めて56組とし、翌月29日北七番丁(堤通東)を北二、三、四、五、六番丁東組に、北七、八、九番丁(通町東 堤通西)を通町組に変更せり、其名称及区画は左の如し
として、八幡町組(八幡町、坊主町ほか3町)、花京院通組(花京院通、空堀丁ほか6町)など56組207町の名称を掲出しています。207町の名称は下記のとおりです。207町を原文のまま書き出せれば良いのですが、誤字脱字があったり、複数の組に跨がる町については重複記載の調整が必要なことから、私が手を加えています。[79282] に記載した207町をもう一度掲載します
河原町, 新河原町, 新河原町東丁, 南石切町, 新弓ノ町, 八軒小路, 南染師町, 南鍛冶町, 南材木町, 穀町, 三百人町, 五十人町, 六十人町, 畳屋丁, 保春院前丁, 成田町, 表柴田町, 裏柴田町, 元茶畑, 椌木通, 木ノ下, 西新丁, 東新丁, 荒町, 連坊小路, 清水小路, 北目町, 上染師町, 田町, 南町, 柳町, 大町一丁目頭, 大町一丁目, 大町二丁目, 大町三丁目, 大町四丁目, 大町五丁目, 大町五丁目新丁, 新伝馬町, 名掛丁, 二十人町, 榴ヶ岡, 舟丁, 堰場, 石名坂, 弓ノ町, 土樋, 猿牽丁, 姉歯横丁, 石垣町, 米ヶ袋上丁, 米ヶ袋中丁, 米ヶ袋下丁, 米ヶ袋十二軒丁, 米ヶ袋広丁, 米ヶ袋鍛冶屋前丁, 七軒丁, 鉄砲横丁, 桜小路, 道場小路, 伊勢屋横丁, 六軒丁, 片平丁, 本荒町, 良覚院丁, 狐小路, 袋町, 中ノ町, 琵琶首丁, 琵琶首新丁, 花壇, 花壇川前丁, 霊屋下, 越路, 越路六軒丁, 越路路地町, 宮沢, 川内大橋通, 川内柳丁, 川内中ノ瀬町, 川内大工町, 川内川前丁, 川内明神横丁, 川内元支倉, 川内澱橋通, 川内元支倉通, 川内新横丁, 川内数寄屋丁, 川内亀岡町, 川内亀岡北裏丁, 川内三十人町, 川内山屋敷, 肴町, 立町, 立町新丁, 本柳町,元櫓丁, 定禅寺通櫓丁, 元鍛冶町, 常盤町, 北材木町, 本材木町, 跡付町, 木町末無, 立町通, 定禅寺通, 南町通, 南光院丁, 教楽院丁, 薬鑵小路, 裏五番丁, 柳町通, 北目町通, 新寺小路, 国分町, 二日町, 北鍛冶町, 通町, 北田町, 堤町, 支倉町, 木町通, 新坂通, 土橋通, 支倉通, 半子町, 伊勢堂下, 神子町, 北山町, 八幡町, 坊主町, 江戸町, 覚性院丁, 石切町, 中島丁, 切通, 十二軒丁, 北五十人町, 滝前丁, 角五郎丁, 角五郎新丁, 澱町, 勾当台通, 表小路, 外記丁, 堤通, 外記丁通, 同心町通, 中杉山通, 光禅寺通, 二本杉通, 杉山通, 元寺小路, 茂市ヶ坂, 掃部丁, 末無掃部丁, 大仏前, 同心町中丁, 元貞坂, 空堀丁, 新名懸丁, 新小路, 花京院通, 長丁, 長刀丁, 北六軒丁, 鉄砲町, 車町, 小田原山本丁, 小田原裏山本丁, 小田原車通, 小田原宮町東裏丁, 小田原東丁, 小田原袖振丁, 小田原遣水丁, 小田原長丁通, 小田原高松通, 小田原金剛院丁, 小田原広丁, 小田原大行院丁, 小田原牛小屋丁, 小田原清水沼通, 小田原弓ノ町, 小田原北一番丁通, 小田原北二番丁通, 小田原北三番丁通, 宮町, 東一番丁, 東二番丁, 東三番丁, 東四番丁, 東五番丁, 東六番丁, 東七番丁, 東八番丁, 東九番丁, 東十番丁, 北一番丁, 北二番丁, 北三番丁, 北四番丁, 北五番丁, 北六番丁, 北七番丁, 北八番丁, 北九番丁, 北十番丁
【ステップ4】次に、市史は明治22年3月に行われた区域変更の記述へ進みます。仙台区消滅直前の区域変更です。
而して区は22年3月31日更に区域を変更すること左の如し
と述べて、宮城郡荒巻村の一部(字山上清水, 字滝前, 字宮裏, 字上郡山, 字中丿沢)、宮城郡小田原村の一部(字小野田, 字杉山)、宮城郡南目村の一部(字柳沢, 字二軒茶屋)、宮城郡南小泉村の一部(字八軒小路, 字行人塚, 字五ツ谷, 字桃源院東, 字鍛冶屋敷, 字広瀬川橋下)、名取郡長町村の一部(字窪谷地の一部)を仙台区に編入。また、仙台区宮沢の一部を名取郡茂ヶ崎村に編入し、仙台区北六番丁の一部を宮城郡原町に編入したと記しています。
以上のことから、88さんが纏めておられる市区町村変遷情報に載せるべき仙台の町は、【ステップ3】で掲載した207町および【ステップ4】で掲載した周辺村との区画変更だと思いました。しかしその後、市史に町名書き漏れの疑念をいだき、各種資料を突き合わせてチェックしました。チェックの方法は[79312]に書いたとおりです。その結果、上杉山通、米ヶ袋中ノ坂、米ヶ袋鹿子清水通、大聖寺裏門通の4町が書き漏れとして浮上しました。
しかし、大聖寺裏門通(現在の青葉区本町二丁目錦町公園付近)で頭を抱えてしまいました。地籍があっても家屋が消滅して無人になっていた可能性が見え隠れするからです。大聖寺裏門通という地籍があったとする根拠は歴史的町名復活検討委員会の29ページ「旧城下の町名(住居表示実施直前の町名)一覧」と36ページ右側の地図に大聖寺裏門通の表記があるからです。また、明治22年当時は無人になっていたかも知れないという根拠は、36ページ右側の地図に線引きされた大聖寺裏門通の区域が非常に狭いことに加え、明治後期の地図には家屋のない更地ふうに描かれているからです。
大聖寺裏門通が無人か有人かで引っ掛かり、前進できないでおりましたが、これ以上考えるのは止めましょう。仙台区から仙台市に移行する時点で、上杉山通、米ヶ袋中ノ坂、米ヶ袋鹿子清水通、大聖寺裏門通の4町は存在していたと決着をつけます。そうしないと埒があきません。
上記を踏まえ、明治22年仙台区消滅直前の町数は、【ステップ3】に掲げた207町に上杉山通、米ヶ袋中ノ坂、米ヶ袋鹿子清水通、大聖寺裏門通の4町を加え、211町に訂正したいと思います。【ステップ3】に掲げた207町のうち、六軒丁を南六軒丁に修正し、宮沢と北六番丁に(微)を付し、新たに加える上杉山通、米ヶ袋中ノ坂、米ヶ袋鹿子清水通、大聖寺裏門通は、それぞれ適宜な位置に挿入しました。はたして判断が正しいのか否か自信はありませんが、自分なりに出した結論に従い仙台211町5村を掲出しますので、市区町村変遷情報を下記のように修正してください。
河原町, 新河原町, 新河原町東丁, 南石切町, 新弓ノ町, 八軒小路, 南染師町, 南鍛冶町, 南材木町, 穀町, 三百人町, 五十人町, 六十人町, 畳屋丁, 保春院前丁, 成田町, 表柴田町, 裏柴田町, 元茶畑, 椌木通, 木ノ下, 西新丁, 東新丁, 荒町, 連坊小路, 清水小路, 北目町, 上染師町, 田町, 南町, 柳町, 大町一丁目頭, 大町一丁目, 大町二丁目, 大町三丁目, 大町四丁目, 大町五丁目, 大町五丁目新丁, 新伝馬町, 名掛丁, 二十人町, 榴ヶ岡, 舟丁, 堰場, 石名坂, 弓ノ町, 土樋, 猿牽丁, 姉歯横丁, 石垣町, 米ヶ袋上丁, 米ヶ袋中丁, 米ヶ袋下丁, 米ヶ袋十二軒丁, 米ヶ袋広丁, 米ヶ袋鍛冶屋前丁, 米ヶ袋中ノ坂, 米ヶ袋鹿子清水通, 七軒丁, 鉄砲横丁, 桜小路, 道場小路, 伊勢屋横丁, 南六軒丁, 片平丁, 本荒町, 良覚院丁, 狐小路, 袋町, 中ノ町, 琵琶首丁, 琵琶首新丁, 花壇, 花壇川前丁, 霊屋下, 越路, 越路六軒丁, 越路路地町, 宮沢(微), 川内大橋通, 川内柳丁, 川内中ノ瀬町, 川内大工町, 川内川前丁, 川内明神横丁, 川内元支倉, 川内澱橋通, 川内元支倉通, 川内新横丁, 川内数寄屋丁, 川内亀岡町, 川内亀岡北裏丁, 川内三十人町, 川内山屋敷, 肴町, 立町, 立町新丁, 本柳町,元櫓丁, 定禅寺通櫓丁, 元鍛冶町, 常盤町, 北材木町, 本材木町, 跡付町, 木町末無, 立町通, 定禅寺通, 南町通, 南光院丁, 教楽院丁, 薬鑵小路, 裏五番丁, 柳町通, 北目町通, 新寺小路, 国分町, 二日町, 北鍛冶町, 通町, 北田町, 堤町, 支倉町, 木町通, 新坂通, 土橋通, 支倉通, 半子町, 伊勢堂下, 神子町, 北山町, 八幡町, 坊主町, 江戸町, 覚性院丁, 石切町, 中島丁, 切通, 十二軒丁, 北五十人町, 滝前丁, 角五郎丁, 角五郎新丁, 澱町, 勾当台通, 表小路, 外記丁, 堤通, 外記丁通, 上杉山通, 同心町通, 中杉山通, 光禅寺通, 二本杉通, 杉山通, 元寺小路, 茂市ヶ坂, 掃部丁, 末無掃部丁, 大仏前, 同心町中丁, 元貞坂, 大聖寺裏門通, 空堀丁, 新名懸丁, 新小路, 花京院通, 長丁, 長刀丁, 北六軒丁, 鉄砲町, 車町, 小田原山本丁, 小田原裏山本丁, 小田原車通, 小田原宮町東裏丁, 小田原東丁, 小田原袖振丁, 小田原遣水丁, 小田原長丁通, 小田原高松通, 小田原金剛院丁, 小田原広丁, 小田原大行院丁, 小田原牛小屋丁, 小田原清水沼通, 小田原弓ノ町, 小田原北一番丁通, 小田原北二番丁通, 小田原北三番丁通, 宮町, 東一番丁, 東二番丁, 東三番丁, 東四番丁, 東五番丁, 東六番丁, 東七番丁, 東八番丁, 東九番丁, 東十番丁, 北一番丁, 北二番丁, 北三番丁, 北四番丁, 北五番丁, 北六番丁(微),, 北七番丁, 北八番丁, 北九番丁, 北十番丁, 宮城郡 荒巻村(微), 小田原村(微), 南目村(微), 南小泉村(微), 名取郡 長町村(微)
| [90671] 2016年 7月 3日(日)13:59:51【1】 | 伊豆之国 さん |
| ものの名前(地名関連) | |
今日の日経新聞の最終面「文化」面に、作曲家の池辺晋一郎氏が「ものの名前」と題した記事を載せており、その中で「地名」に関するくだりがいくつか書かれていました。
たとえば地名。長野県松本市に「渚」という地名がある。私鉄の駅名にもなっている(→[89119])。紛れもない山地だ。波が打ち寄せる光景とは縁がない。が、実はその辺りは古代には湖だった。その名残の地名なのだ
この続きに、大阪の地名「難波」は「なんば」か「なにわ」か、浅草にあるお寺がなぜ「浅草寺(せんそうじ)」と読みが違うのか、目黒区「洗足」と大田区「千束」が隣接する([76006])のは奇妙じゃないか、世田谷区と多摩川を挟んだ川崎市に同じ「等々力」がある([75335])のはなぜか、その「多摩川」に近い世田谷区の地名が「玉川」なのは奇妙だ、といったことが書かれており、また京都と札幌の「○条」の意味の違いなどにも触れていました。
そして、終わりのほうで再び地名の話に戻り、
合併ばやりだが、最近多いのが新生の市の奇妙な名前だ。また、由緒ある地名が合併ゆえに消滅してがっかりしたことも、何度もある。しかし理由があるのは、まだいい。江戸期の住人の職種が具体的にわかる大工町・鉄砲町・博労町(馬喰町、馬口労町とも)などがどんどん消え、何でもない地名に取って代わったりしているのは許せない。○○市中央、とか駅前町などという安直な地名に出会うと腹が立ってくる
と「個人的感想」を述べています。
…私自身が投稿していた「せんぞく」も出てきた「自治体越え地名」とか、「平成の大合併」でできた新自治体名批判など、「落書き帳」の常連から見れば「見飽きた、聞き飽きた」ような話題も出てきて、この方面が本業ではない人の話なのに実によくできていて大いに感心したのでした。信州の「渚」の地名の由来、これは飛騨のここも同じ意味だったのでしょうか?(こちらには「猪」の誤記説もあるようですが。)
▲[90669]のクイズの「第四ヒント」ですが…。「G2B」ランクの松本市も、【Group A】に入っています。
【1】書き込みの途中で誤動作を起こしたため、書き込み訂正の形によって加筆修正しました。
たとえば地名。長野県松本市に「渚」という地名がある。私鉄の駅名にもなっている(→[89119])。紛れもない山地だ。波が打ち寄せる光景とは縁がない。が、実はその辺りは古代には湖だった。その名残の地名なのだ
この続きに、大阪の地名「難波」は「なんば」か「なにわ」か、浅草にあるお寺がなぜ「浅草寺(せんそうじ)」と読みが違うのか、目黒区「洗足」と大田区「千束」が隣接する([76006])のは奇妙じゃないか、世田谷区と多摩川を挟んだ川崎市に同じ「等々力」がある([75335])のはなぜか、その「多摩川」に近い世田谷区の地名が「玉川」なのは奇妙だ、といったことが書かれており、また京都と札幌の「○条」の意味の違いなどにも触れていました。
そして、終わりのほうで再び地名の話に戻り、
合併ばやりだが、最近多いのが新生の市の奇妙な名前だ。また、由緒ある地名が合併ゆえに消滅してがっかりしたことも、何度もある。しかし理由があるのは、まだいい。江戸期の住人の職種が具体的にわかる大工町・鉄砲町・博労町(馬喰町、馬口労町とも)などがどんどん消え、何でもない地名に取って代わったりしているのは許せない。○○市中央、とか駅前町などという安直な地名に出会うと腹が立ってくる
と「個人的感想」を述べています。
…私自身が投稿していた「せんぞく」も出てきた「自治体越え地名」とか、「平成の大合併」でできた新自治体名批判など、「落書き帳」の常連から見れば「見飽きた、聞き飽きた」ような話題も出てきて、この方面が本業ではない人の話なのに実によくできていて大いに感心したのでした。信州の「渚」の地名の由来、これは飛騨のここも同じ意味だったのでしょうか?(こちらには「猪」の誤記説もあるようですが。)
▲[90669]のクイズの「第四ヒント」ですが…。「G2B」ランクの松本市も、【Group A】に入っています。
【1】書き込みの途中で誤動作を起こしたため、書き込み訂正の形によって加筆修正しました。
| [95735] 2018年 4月 30日(月)16:58:03 | むっくん さん |
| 市区町村変遷情報(その2) | |
>グリグリさん
[95557]拙稿に引き続いての第2弾です。
市区町村変遷情報で以下の所の訂正をお願いします。
埼玉県
#122 1889(M22).4.1 新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 古池村
は
#122 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 「比企郡」 古池村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#123 1889(M22).4.1 新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 麦原村
は
#123 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 「比企郡」 麦原村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#132 1889(M22).4.1 新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 森戸新田, 駒寺野新田
は
#132 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 「入間郡」 森戸新田, 駒寺野新田
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#155 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村
は
#155 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 「男衾郡」 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#160 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 小用村
は
#160 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 「入間郡」 小用村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#210 1889(M22).4.1 新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村
は
#210 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 「榛沢郡」 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#217 1889(M22).4.1 村制 児玉郡共和村 児玉郡 「共和村」
は
#217 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡共和村 児玉郡 「今井村, 蛭川村, 高関村, 入浅見村, 下浅見村, 下真下村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)
#220 1889(M22).4.1 村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村
は
#220 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村「, 長沖村, 高柳村, 飯倉村, 塩谷村, 宮内村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)
#227 1889(M22).4.1 新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 熊野堂村
は
#227 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 「児玉郡」 熊野堂村
参考:埼玉県令甲第10号(M22.3.26)[69697]
#232 1889(M22).4.1 新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 戸出村, 平戸村
は
#232 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 「北埼玉郡」 戸出村, 平戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#238 1889(M22).4.1 村制 大里郡大幡村 大里郡 「大幡村」
は
#238 1889(M22).4.1 「郡変更/新設/」村制 大里郡大幡村 大里郡 「原島村, 代村, 幡羅郡 柿沼村, 新島村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#240 1889(M22).4.1 村制 大里郡吉岡村 大里郡 「吉岡村」
は
#240 1889(M22).4.1 「新設/」村制 大里郡吉岡村 大里郡 「万吉村, 村岡村, 平塚新田」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)
#264 1889(M22).4.1 新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 藤田村
は
#264 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 「男衾郡」 藤田村
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#321 1889(M22).4.1 村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「太田村」
は
#321 1889(M22).4.1 「新設/」村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「小針村, 下須戸村, 若小玉村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)
富山県
#160 1889(M22).4.1 新設/町制 射水郡伏木町 射水郡 伏木本町, 伏木中道町, 伏木湊町, 伏木臥浦町, 伏木石坂町, 伏木玉川町, 伏木新町, 「伏木古国府町」, 「伏木新島町」, 「伏木串岡町」, 一ノ宮村, 古府村, 矢田村, 国分村
「」を追加。
参考:富山県令第38号(M22.3.19)、地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)
静岡県
# 1 1889(M22).4.1 新設/市制 静岡市 安倍郡 静岡追手町, 「有渡郡」静岡鷹匠町一丁目, 静岡鷹匠町二丁目, 静岡鷹匠町三丁目, 静岡東鷹匠町, 「安倍郡/有渡郡」静岡横内町, 「安倍郡」静岡水落町一丁目, 静岡水落町二丁目, 静岡水落町三丁目, 静岡東草深町一丁目, 静岡東草深町二丁目, 静岡東草深町三丁目, 静岡西草深町, 「安倍郡」静岡通研屋町, 静岡草深町代地, 静岡屋形町, 静岡裏一番町, 静岡一番町, 静岡二番町, 静岡三番町, 静岡四番町, 静岡五番町, 静岡六番町, 静岡七番町, 静岡八番町, 静岡通車町, 静岡本通裏町, 静岡北番町, 「有渡郡」静岡誉田町, 静岡静岡宿, 静岡台所町, 静岡鋳物師町, 静岡下八幡町, 静岡下横田町, 静岡院内町, 静岡上横田町, 「有渡郡」静岡栄町, 静岡上八幡町, 静岡猿屋町, 静岡中八幡町, 「安倍郡」静岡材木町, 静岡片羽町, 静岡安倍町, 静岡御器屋町, 静岡宮ヶ崎町, 静岡馬場町, 静岡車町, 静岡四ツ足町, 「安倍郡/有渡郡」静岡本通一丁目, 静岡本通二丁目, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通三丁目, 静岡本通四丁目, 静岡本通五丁目, 静岡本通六丁目, 静岡本通七丁目, 静岡本通八丁目, 静岡本通九丁目,「安倍郡」静岡研屋町, 静岡上魚町, 静岡茶町一丁目, 静岡茶町二丁目, 静岡上桶屋町, 静岡土太夫町, 静岡柚木町, 静岡安西一丁目, 静岡安西二丁目, 静岡安西三丁目, 静岡安西四丁目, 静岡安西五丁目, 静岡安西一丁目南裏町, 「安倍郡/有渡郡」静岡呉服町一丁目, 静岡呉服町二丁目, 静岡呉服町三丁目, 静岡呉服町四丁目, 静岡呉服町五丁目, 静岡呉服町六丁目, 静岡江川町, 静岡新谷町, 「有渡郡」静岡札ノ辻町, 静岡七間町一丁目, 静岡七間町二丁目, 静岡七間町三丁目, 静岡両替町一丁目, 静岡両替町二丁目, 静岡両替町三丁目, 静岡両替町四丁目, 静岡両替町五丁目, 静岡両替町六丁目, 静岡紺屋町, 静岡上石町一丁目, 静岡上石町二丁目, 静岡梅屋町, 静岡人宿町一丁目, 静岡人宿町二丁目, 静岡人宿町三丁目, 静岡寺町一丁目, 静岡寺町二丁目, 静岡寺町三丁目, 静岡寺町四丁目, 静岡下石町一丁目, 静岡下石町二丁目, 静岡下石町三丁目, 静岡常慶町, 「静岡藤右衛門町」, 静岡下魚町, 静岡江尻町, 静岡平屋町, 静岡下桶屋町, 静岡鍛冶町, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通川越町, 静岡堤添川越町, 「安倍郡」静岡西寺町, 静岡大鋸町, 静岡上大工町, 「有渡郡」静岡新通一丁目, 静岡新通大工町, 静岡新通三丁目, 静岡新通四丁目, 静岡新通五丁目, 静岡新通六丁目, 静岡新通七丁目, 静岡新通川越町, 静岡安倍川町, 静岡白山町, 川辺村(微)
へと変更。
#郡名を追加、静岡藤右衛門町を追加。
#静岡栄町は元々、有渡郡南安東村の一部でM22.3.1の有渡郡南安東村消滅時に出来た町と考えられることより、有渡郡としました。
参考:静岡県令第18号(M22.2.26)、地方行政区画便覧257コマ258コマ(編・発行:内務省地理局, 1887)
#127 1889(M22).3.1 郡変更/新設 志太郡藤枝町 志太郡 藤枝宿若王子町, 「益津郡/志太郡」 藤枝宿本町, 志太郡 藤枝宿五十海町, 藤枝宿市部町, 藤枝宿鬼岩寺町, 「益津郡」藤枝宿益津町, 「志太郡」原村, 益津郡 郡村(微)
へと変更。
参考:地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)
三重県
#1 1889(M22).4.1 新設/市制 津市 安濃郡 津京口町, 津立町, 津大門町, 津中ノ番町, 津宿屋町, 津蔵町, 津千歳町, 津堀川町, 津沢「ノ」上町, 津新中町, 津魚町, 津北浜町, 津地頭領町, 津分部町, 津新魚町, 津築地町, 津極楽町, 津山「ノ」世古町, 津大世古町, 津南「ノ」世古町, 津南浜町, 津片浜町, 津贄崎町, 西ノ口出屋敷, 津鷹匠町, 津西町, 津釜屋町, 津塔世町, 津門前町, 津万町, 津北町, 津東町, 津西来寺町, 津宝禄町, 津新立町, 津「新東」町, 津入江町,津西検校町, 津東検校町, 津新道, 津玉置町, 津西堀端, 津北堀端, 津南堀端, 津一番町, 津二番町, 津三番町, 津五軒町, 津枕町, 津松「ノ」下, 津西新「町」, 津中新町, 津丸ノ内, 津伊予町, 「津伊予町ノ内 的場」 , 「岩田村ノ内 岩田町」, 「岩田村ノ内 宮之前」, 「岩田村ノ内 佐伯町」, 「岩田村ノ内 弓屋敷」, 「岩田村ノ内 立合町」, 「岩田村ノ内 西裏」, 「岩田村ノ内 久留島」, 「岩田村ノ内 野崎垣内」, 「岩田村ノ内 元築造」, 「岩田村ノ内 出口」, 「岩田村ノ内 弓ノ町」, 「岩田村ノ内 山中」, 「岩田村ノ内 綿打」, 「津興村ノ内 船頭町」, 「津興村ノ内 上弁財町」, 「津興村ノ内 柳山」, 「津興村ノ内 阿漕町」, 「津興村ノ内 下弁財町」, 八幡町, 藤枝町, 栄町, 下部田村(本), 「下部田村ノ内 余慶町」, 乙部村(微), 塔世村(微), 古河村(微), 藤方村(微), 奄芸郡 大部田村
へと変更。
#当時の町名順に並び替えて記載しています。
三重県では、岩田村は13町村もの自治体に分かれて存在しており、岩田村というものはありませんでした。同じく津興村というものもなく、5町村に分かれて存在していました。又、津伊予町もこれとは別途に津伊予町ノ内 的場が存在していました。
江戸時代の最後の郷帳である天保郷帳によく見られた「○○村ノ内△△」、「□□村枝郷 ××」として記載される近世村(自治体)が明治22年まで唯一残ったのが三重県です。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県統計書(明治21年)(著・発行:三重県庁, M22.12.2130コマ251コマ、三重県令第12号(PDF)(M22.3.1)1-2コマ
#113 1889(M22).4.1 新設/町制 安濃郡新町 安濃郡 古賀村, 刑部村, 「古賀村刑部村ノ内 八町 」, 神納村, 南河路村
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)9コマ
#古賀村刑部村ノ内 八町 も古賀村や刑部村とは別の自治体です。
#246 1889(M22).4.1 新設/町制 阿拝郡上野町 阿拝郡 上野西ノ丸, 上野丸之内, 上野幸坂町, 上野馬苦労町, 上野西町, 上野向島町, 上野中町, 上野東町, 上野清水町, 上野福居町, 上野徳居町, 上野小玉町, 上野魚町, 上野三ノ西町, 上野紺屋町, 上野相生町, 上野忍町, 上野愛宕町, 上野万町(本), 上野鉄砲町, 上野池町, 上野西日南町, 上野東日南町, 上野桑町, 上野恵美須町, 上野農人町, 上野赤坂町, 上野玄蕃町, 上野車坂町, 上野田端町, 上野裏町, 上野寺町, 上野新町, 上野片原町, 上野鍛冶町, 上野町(微), 上野村(本), 木興村(微), 小田村(微)
#247 1889(M22).4.1 新設/村制 阿拝郡小田村 阿拝郡 木興村(本), 久米村, 浅宇田村, 四十九村, 小田村(本), 上野町(微), 上野万町(微), 上野村(微)
#246,247の両方とも
上野町(微)→上野町の一部
へと変更することになります。
M22.3.1三重県令第13号では上野市街地、三重県統計書(明治19年)では上野町と書かれている所です。これは恐らくM3の大水害の後に当時の人が移り住んだ上野城の堀の埋立地などに地籍が与えられいまま、おそらく所属未定地のままM22まで来たところではないかと推定します。ゆえに、適切な名称をつけるとするのと、三重県統計書(明治19年)での上野町を借用して共に
「上野町の一部」と記載するしかないと思います。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)16コマ
鳥取県
#3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡勝田村 八橋郡 豊定村
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
M31鳥取県告示第183号(豊定村保永村合併ノ件)(PDF)132コマで1898年に合併が行われましたので、正しくは
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
です。
#77 1935(S10).2.20 編入 八頭郡智頭町 八頭郡 智頭町, 山形村, 那岐村, 土師村
鳥取県告示第80号(PDF)(S10.2.14)によりますと、合併方式は新設。
愛媛県
#15 1898(M31).11.22 町制 周桑郡小松町 周桑郡小松村
#16 1898(M31).11.28 町制 温泉郡北条町 温泉郡北条村
#17 1898(M31).12.21 町制 宇摩郡川之江町 宇摩郡川之江村
これら3村の町制は愛媛県告示第187号(M31.11.21)で
#14 1898(M31).11.21 町制 宇摩郡三島町 宇摩郡三島村
と同じくすべて1898(M31).11.21
#21 1900(M33).__.__ 境界変更 温泉郡道後村 温泉郡 道後村, 御幸村の一部
この境界変更は1900(M33).6.1
#23 1901(M34).8.20 町制/改称 上浮穴郡久万町 上浮穴郡久万町村
この町制/改称は1900(M34).8.15
#38 1916(T5).10.1 境界変更 温泉郡浅海村 温泉郡 浅海村, 立岩村の一部
この境界変更は1916(T5).4.1
参考:えひめの記憶
長崎県
#10 1912(M45).4.1 分立 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 境界変更/改称 下県郡久田村 下県郡 与良村, 厳原町の一部
長崎県令第14号(M45.3.5)で、
#10 1912(M45).4.1 分割 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 新設 下県郡久田村 下県郡 与良村の一部, 厳原町の一部
に。
#23 1925(T14).4.1 町制 壱岐郡武生水町 壱岐郡 武生水村
長崎県告示第91号(T14.3.6)で
1925(T14).4.1→1925(T14).3.10
#29 1927(S2).4.1 編入 東彼杵郡早岐町 東彼杵郡 早岐町, 広田村
長崎県告示第141号1コマ2コマ(S2.4.1)で
編入→新設
[95557]拙稿に引き続いての第2弾です。
市区町村変遷情報で以下の所の訂正をお願いします。
埼玉県
#122 1889(M22).4.1 新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 古池村
は
#122 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 入間郡越生町 入間郡 上野村, 越生村, 如意村, 黒岩村, 西和田村, 大谷村, 鹿ノ下村, 成瀬村, 「比企郡」 古池村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#123 1889(M22).4.1 新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 麦原村
は
#123 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 入間郡梅園村 入間郡 津久根村, 大満村, 黒山村, 龍ヶ谷村, 小杉村, 堂山村, 上谷村, 「比企郡」 麦原村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#132 1889(M22).4.1 新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 森戸新田, 駒寺野新田
は
#132 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 高麗郡高萩村 高麗郡 高萩村, 下高萩新田, 下大谷沢村, 女影村, 女影新田, 馬引沢村, 田木村, 大谷沢村, 中沢村, 「入間郡」 森戸新田, 駒寺野新田
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#155 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村
は
#155 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡竹沢村 比企郡 笠原村, 原川村, 「男衾郡」 勝呂村, 木部村, 靱負村, 木呂子村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#160 1889(M22).4.1 新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 小用村
は
#160 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 比企郡今宿村 比企郡 石坂村, 今宿村, 赤沼村, 大豆戸村, 「入間郡」 小用村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#210 1889(M22).4.1 新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村
は
#210 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 児玉郡藤田村 児玉郡 傍示堂村, 鵜森村, 「榛沢郡」 牧西村, 小和瀬村, 滝瀬村, 宮戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#217 1889(M22).4.1 村制 児玉郡共和村 児玉郡 「共和村」
は
#217 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡共和村 児玉郡 「今井村, 蛭川村, 高関村, 入浅見村, 下浅見村, 下真下村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)
#220 1889(M22).4.1 村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村
は
#220 1889(M22).4.1 「新設/」村制 児玉郡金屋村 児玉郡 金屋村「, 長沖村, 高柳村, 飯倉村, 塩谷村, 宮内村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)
#227 1889(M22).4.1 新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 熊野堂村
は
#227 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 賀美郡丹荘村 賀美郡 植竹村, 元阿保村, 原新田村, 八日市村, 関口村, 肥土村, 貫井村, 小浜村, 四軒在家村, 「児玉郡」 熊野堂村
参考:埼玉県令甲第10号(M22.3.26)[69697]
#232 1889(M22).4.1 新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 戸出村, 平戸村
は
#232 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/村制 大里郡佐谷田村 大里郡 佐谷田村, 「北埼玉郡」 戸出村, 平戸村
参考:埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#238 1889(M22).4.1 村制 大里郡大幡村 大里郡 「大幡村」
は
#238 1889(M22).4.1 「郡変更/新設/」村制 大里郡大幡村 大里郡 「原島村, 代村, 幡羅郡 柿沼村, 新島村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#240 1889(M22).4.1 村制 大里郡吉岡村 大里郡 「吉岡村」
は
#240 1889(M22).4.1 「新設/」村制 大里郡吉岡村 大里郡 「万吉村, 村岡村, 平塚新田」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)
#264 1889(M22).4.1 新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 藤田村
は
#264 1889(M22).4.1 「郡変更/」新設/町制 榛沢郡寄居町 榛沢郡 寄居町, 末野村, 「男衾郡」 藤田村
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)、埼玉県令甲第6号(M22.3.23)[69697]
#321 1889(M22).4.1 村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「太田村」
は
#321 1889(M22).4.1 「新設/」村制 北埼玉郡太田村 北埼玉郡 「小針村, 下須戸村, 若小玉村」
参考:埼玉県市町村合併史上巻(編:埼玉県地方課、出版:埼玉県、1960)に収録の埼玉県令甲第7号(M22.3.23)
富山県
#160 1889(M22).4.1 新設/町制 射水郡伏木町 射水郡 伏木本町, 伏木中道町, 伏木湊町, 伏木臥浦町, 伏木石坂町, 伏木玉川町, 伏木新町, 「伏木古国府町」, 「伏木新島町」, 「伏木串岡町」, 一ノ宮村, 古府村, 矢田村, 国分村
「」を追加。
参考:富山県令第38号(M22.3.19)、地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)
静岡県
# 1 1889(M22).4.1 新設/市制 静岡市 安倍郡 静岡追手町, 「有渡郡」静岡鷹匠町一丁目, 静岡鷹匠町二丁目, 静岡鷹匠町三丁目, 静岡東鷹匠町, 「安倍郡/有渡郡」静岡横内町, 「安倍郡」静岡水落町一丁目, 静岡水落町二丁目, 静岡水落町三丁目, 静岡東草深町一丁目, 静岡東草深町二丁目, 静岡東草深町三丁目, 静岡西草深町, 「安倍郡」静岡通研屋町, 静岡草深町代地, 静岡屋形町, 静岡裏一番町, 静岡一番町, 静岡二番町, 静岡三番町, 静岡四番町, 静岡五番町, 静岡六番町, 静岡七番町, 静岡八番町, 静岡通車町, 静岡本通裏町, 静岡北番町, 「有渡郡」静岡誉田町, 静岡静岡宿, 静岡台所町, 静岡鋳物師町, 静岡下八幡町, 静岡下横田町, 静岡院内町, 静岡上横田町, 「有渡郡」静岡栄町, 静岡上八幡町, 静岡猿屋町, 静岡中八幡町, 「安倍郡」静岡材木町, 静岡片羽町, 静岡安倍町, 静岡御器屋町, 静岡宮ヶ崎町, 静岡馬場町, 静岡車町, 静岡四ツ足町, 「安倍郡/有渡郡」静岡本通一丁目, 静岡本通二丁目, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通三丁目, 静岡本通四丁目, 静岡本通五丁目, 静岡本通六丁目, 静岡本通七丁目, 静岡本通八丁目, 静岡本通九丁目,「安倍郡」静岡研屋町, 静岡上魚町, 静岡茶町一丁目, 静岡茶町二丁目, 静岡上桶屋町, 静岡土太夫町, 静岡柚木町, 静岡安西一丁目, 静岡安西二丁目, 静岡安西三丁目, 静岡安西四丁目, 静岡安西五丁目, 静岡安西一丁目南裏町, 「安倍郡/有渡郡」静岡呉服町一丁目, 静岡呉服町二丁目, 静岡呉服町三丁目, 静岡呉服町四丁目, 静岡呉服町五丁目, 静岡呉服町六丁目, 静岡江川町, 静岡新谷町, 「有渡郡」静岡札ノ辻町, 静岡七間町一丁目, 静岡七間町二丁目, 静岡七間町三丁目, 静岡両替町一丁目, 静岡両替町二丁目, 静岡両替町三丁目, 静岡両替町四丁目, 静岡両替町五丁目, 静岡両替町六丁目, 静岡紺屋町, 静岡上石町一丁目, 静岡上石町二丁目, 静岡梅屋町, 静岡人宿町一丁目, 静岡人宿町二丁目, 静岡人宿町三丁目, 静岡寺町一丁目, 静岡寺町二丁目, 静岡寺町三丁目, 静岡寺町四丁目, 静岡下石町一丁目, 静岡下石町二丁目, 静岡下石町三丁目, 静岡常慶町, 「静岡藤右衛門町」, 静岡下魚町, 静岡江尻町, 静岡平屋町, 静岡下桶屋町, 静岡鍛冶町, 「安倍郡/有渡郡」 静岡本通川越町, 静岡堤添川越町, 「安倍郡」静岡西寺町, 静岡大鋸町, 静岡上大工町, 「有渡郡」静岡新通一丁目, 静岡新通大工町, 静岡新通三丁目, 静岡新通四丁目, 静岡新通五丁目, 静岡新通六丁目, 静岡新通七丁目, 静岡新通川越町, 静岡安倍川町, 静岡白山町, 川辺村(微)
へと変更。
#郡名を追加、静岡藤右衛門町を追加。
#静岡栄町は元々、有渡郡南安東村の一部でM22.3.1の有渡郡南安東村消滅時に出来た町と考えられることより、有渡郡としました。
参考:静岡県令第18号(M22.2.26)、地方行政区画便覧257コマ258コマ(編・発行:内務省地理局, 1887)
#127 1889(M22).3.1 郡変更/新設 志太郡藤枝町 志太郡 藤枝宿若王子町, 「益津郡/志太郡」 藤枝宿本町, 志太郡 藤枝宿五十海町, 藤枝宿市部町, 藤枝宿鬼岩寺町, 「益津郡」藤枝宿益津町, 「志太郡」原村, 益津郡 郡村(微)
へと変更。
参考:地方行政区画便覧(編・発行:内務省地理局, 1887)
三重県
#1 1889(M22).4.1 新設/市制 津市 安濃郡 津京口町, 津立町, 津大門町, 津中ノ番町, 津宿屋町, 津蔵町, 津千歳町, 津堀川町, 津沢「ノ」上町, 津新中町, 津魚町, 津北浜町, 津地頭領町, 津分部町, 津新魚町, 津築地町, 津極楽町, 津山「ノ」世古町, 津大世古町, 津南「ノ」世古町, 津南浜町, 津片浜町, 津贄崎町, 西ノ口出屋敷, 津鷹匠町, 津西町, 津釜屋町, 津塔世町, 津門前町, 津万町, 津北町, 津東町, 津西来寺町, 津宝禄町, 津新立町, 津「新東」町, 津入江町,津西検校町, 津東検校町, 津新道, 津玉置町, 津西堀端, 津北堀端, 津南堀端, 津一番町, 津二番町, 津三番町, 津五軒町, 津枕町, 津松「ノ」下, 津西新「町」, 津中新町, 津丸ノ内, 津伊予町, 「津伊予町ノ内 的場」 , 「岩田村ノ内 岩田町」, 「岩田村ノ内 宮之前」, 「岩田村ノ内 佐伯町」, 「岩田村ノ内 弓屋敷」, 「岩田村ノ内 立合町」, 「岩田村ノ内 西裏」, 「岩田村ノ内 久留島」, 「岩田村ノ内 野崎垣内」, 「岩田村ノ内 元築造」, 「岩田村ノ内 出口」, 「岩田村ノ内 弓ノ町」, 「岩田村ノ内 山中」, 「岩田村ノ内 綿打」, 「津興村ノ内 船頭町」, 「津興村ノ内 上弁財町」, 「津興村ノ内 柳山」, 「津興村ノ内 阿漕町」, 「津興村ノ内 下弁財町」, 八幡町, 藤枝町, 栄町, 下部田村(本), 「下部田村ノ内 余慶町」, 乙部村(微), 塔世村(微), 古河村(微), 藤方村(微), 奄芸郡 大部田村
へと変更。
#当時の町名順に並び替えて記載しています。
三重県では、岩田村は13町村もの自治体に分かれて存在しており、岩田村というものはありませんでした。同じく津興村というものもなく、5町村に分かれて存在していました。又、津伊予町もこれとは別途に津伊予町ノ内 的場が存在していました。
江戸時代の最後の郷帳である天保郷帳によく見られた「○○村ノ内△△」、「□□村枝郷 ××」として記載される近世村(自治体)が明治22年まで唯一残ったのが三重県です。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県統計書(明治21年)(著・発行:三重県庁, M22.12.2130コマ251コマ、三重県令第12号(PDF)(M22.3.1)1-2コマ
#113 1889(M22).4.1 新設/町制 安濃郡新町 安濃郡 古賀村, 刑部村, 「古賀村刑部村ノ内 八町 」, 神納村, 南河路村
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)9コマ
#古賀村刑部村ノ内 八町 も古賀村や刑部村とは別の自治体です。
#246 1889(M22).4.1 新設/町制 阿拝郡上野町 阿拝郡 上野西ノ丸, 上野丸之内, 上野幸坂町, 上野馬苦労町, 上野西町, 上野向島町, 上野中町, 上野東町, 上野清水町, 上野福居町, 上野徳居町, 上野小玉町, 上野魚町, 上野三ノ西町, 上野紺屋町, 上野相生町, 上野忍町, 上野愛宕町, 上野万町(本), 上野鉄砲町, 上野池町, 上野西日南町, 上野東日南町, 上野桑町, 上野恵美須町, 上野農人町, 上野赤坂町, 上野玄蕃町, 上野車坂町, 上野田端町, 上野裏町, 上野寺町, 上野新町, 上野片原町, 上野鍛冶町, 上野町(微), 上野村(本), 木興村(微), 小田村(微)
#247 1889(M22).4.1 新設/村制 阿拝郡小田村 阿拝郡 木興村(本), 久米村, 浅宇田村, 四十九村, 小田村(本), 上野町(微), 上野万町(微), 上野村(微)
#246,247の両方とも
上野町(微)→上野町の一部
へと変更することになります。
M22.3.1三重県令第13号では上野市街地、三重県統計書(明治19年)では上野町と書かれている所です。これは恐らくM3の大水害の後に当時の人が移り住んだ上野城の堀の埋立地などに地籍が与えられいまま、おそらく所属未定地のままM22まで来たところではないかと推定します。ゆえに、適切な名称をつけるとするのと、三重県統計書(明治19年)での上野町を借用して共に
「上野町の一部」と記載するしかないと思います。
参考:三重県統計書(明治19年)(著・発行:三重県庁, M20.11.15)、三重県令第13号(PDF)(M22.3.1)16コマ
鳥取県
#3 1894(M27).3.30 改称 八橋郡勝田村 八橋郡 豊定村
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 勝田村, 保永村
M31鳥取県告示第183号(豊定村保永村合併ノ件)(PDF)132コマで1898年に合併が行われましたので、正しくは
#14 1898(M31).7.22 新設 東伯郡成美村 東伯郡 豊定村, 保永村
です。
#77 1935(S10).2.20 編入 八頭郡智頭町 八頭郡 智頭町, 山形村, 那岐村, 土師村
鳥取県告示第80号(PDF)(S10.2.14)によりますと、合併方式は新設。
愛媛県
#15 1898(M31).11.22 町制 周桑郡小松町 周桑郡小松村
#16 1898(M31).11.28 町制 温泉郡北条町 温泉郡北条村
#17 1898(M31).12.21 町制 宇摩郡川之江町 宇摩郡川之江村
これら3村の町制は愛媛県告示第187号(M31.11.21)で
#14 1898(M31).11.21 町制 宇摩郡三島町 宇摩郡三島村
と同じくすべて1898(M31).11.21
#21 1900(M33).__.__ 境界変更 温泉郡道後村 温泉郡 道後村, 御幸村の一部
この境界変更は1900(M33).6.1
#23 1901(M34).8.20 町制/改称 上浮穴郡久万町 上浮穴郡久万町村
この町制/改称は1900(M34).8.15
#38 1916(T5).10.1 境界変更 温泉郡浅海村 温泉郡 浅海村, 立岩村の一部
この境界変更は1916(T5).4.1
参考:えひめの記憶
長崎県
#10 1912(M45).4.1 分立 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 境界変更/改称 下県郡久田村 下県郡 与良村, 厳原町の一部
長崎県令第14号(M45.3.5)で、
#10 1912(M45).4.1 分割 下県郡豆酘村 下県郡 与良村の一部
#11 1912(M45).4.1 新設 下県郡久田村 下県郡 与良村の一部, 厳原町の一部
に。
#23 1925(T14).4.1 町制 壱岐郡武生水町 壱岐郡 武生水村
長崎県告示第91号(T14.3.6)で
1925(T14).4.1→1925(T14).3.10
#29 1927(S2).4.1 編入 東彼杵郡早岐町 東彼杵郡 早岐町, 広田村
長崎県告示第141号1コマ2コマ(S2.4.1)で
編入→新設
… スポンサーリンク …