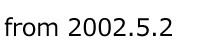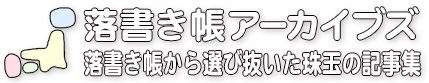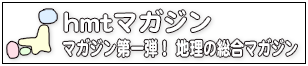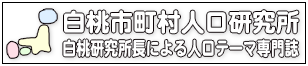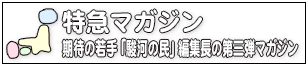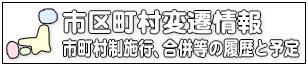北海道の「○条〜丁目」
トップ > 落書き帳アーカイブズ > 北海道の「○条〜丁目」
記事数=13件/更新日:2005年4月24日/編集者:YSK
記事数=13件/更新日:2005年4月24日/編集者:YSK
北海道の市街地では、しばしば「○条〜丁目」というパターンの住所表示を見かけます。これは碁盤目状の街路をナンバリングし、その座標を示すことができるよう工夫されたものです。関連する書き込みを集めました。
… スポンサーリンク …
| [1715] 2002年 6月 2日(日)18:55:06 | Issie さん |
| 条 | |
>札幌や旭川の街区で「条」を使うのも、その発想の延長でしょうか?
むしろ,これは律令時代の条里制に近い発想なのではないかと思います。
対象区域を東西・南北軸の碁盤の目に区切って,南北軸の座標を「条」,東西軸の座標を「里」というシステム。東西座標の方は後の時代に呼称が変わってしまいますが,南北座標の「条」の方は京都(平安京)や奈良(平城京)で健在ですね。
条里制は都の区域だけでなく各地で実施されていますから,これによる「一条」「二条」…という地名は各地に残っています。この区画に基づいて班田収受が行われる決まりになっていたのです。
そして,条里制に基づく耕地の最小の区画の呼称が「坪」。これも「一ノ坪」(「市野坪」と表記されることも)などの形で残っています。
明治期に建設された札幌や旭川のような北海道の開拓都市の場合,古代の条里制に直結するわけではないけれど(恐らく,碁盤の目の地割は,条里制よりもアメリカ合衆国の制度をお手本にしたものだと思います),基本的な発想は同じですね。
ここでは「条・丁目制」。南北座標が「条」なのは同じだけど,東西座標は「丁目」になっていますね。
「条・丁目」で座標表示するのは市街地。農業開拓地については「号・線」という呼称で座標表示をするという習慣になっています。
蛇足:
もともと日本語には疑問符(?)や感嘆符(!)を使う習慣はありません。正式な文章では使用しないものです。新聞も本文では基本的に使っていないでしょ。
使うか使わないかは,その人の好みによるものです。要は,疑問文であるかどうかが伝わりさえすればいいのだから。
ちなみに私は「基本的に使わない派」です。
むしろ,これは律令時代の条里制に近い発想なのではないかと思います。
対象区域を東西・南北軸の碁盤の目に区切って,南北軸の座標を「条」,東西軸の座標を「里」というシステム。東西座標の方は後の時代に呼称が変わってしまいますが,南北座標の「条」の方は京都(平安京)や奈良(平城京)で健在ですね。
条里制は都の区域だけでなく各地で実施されていますから,これによる「一条」「二条」…という地名は各地に残っています。この区画に基づいて班田収受が行われる決まりになっていたのです。
そして,条里制に基づく耕地の最小の区画の呼称が「坪」。これも「一ノ坪」(「市野坪」と表記されることも)などの形で残っています。
明治期に建設された札幌や旭川のような北海道の開拓都市の場合,古代の条里制に直結するわけではないけれど(恐らく,碁盤の目の地割は,条里制よりもアメリカ合衆国の制度をお手本にしたものだと思います),基本的な発想は同じですね。
ここでは「条・丁目制」。南北座標が「条」なのは同じだけど,東西座標は「丁目」になっていますね。
「条・丁目」で座標表示するのは市街地。農業開拓地については「号・線」という呼称で座標表示をするという習慣になっています。
蛇足:
もともと日本語には疑問符(?)や感嘆符(!)を使う習慣はありません。正式な文章では使用しないものです。新聞も本文では基本的に使っていないでしょ。
使うか使わないかは,その人の好みによるものです。要は,疑問文であるかどうかが伝わりさえすればいいのだから。
ちなみに私は「基本的に使わない派」です。
| [1731] 2002年 6月 3日(月)18:40:33 | 紅葉橋律乃介[もみじばし銀治助] さん |
| 条丁目 | |
だいぶ前ですが、「松浦武四郎」の件にお答えをいただきまして、ありがとうございました。
北海道の都市では、市街地は「○条○丁目」という場合が多いですね。
かくいう我が岩見沢市も1~13条まであります。
これが当たり前だと思っていましたが、実際は違うんですね。
と言うことは、北海道の人間は「内地」では迷いやすいのでは?
北海道の都市では、市街地は「○条○丁目」という場合が多いですね。
かくいう我が岩見沢市も1~13条まであります。
これが当たり前だと思っていましたが、実際は違うんですね。
と言うことは、北海道の人間は「内地」では迷いやすいのでは?
| [10350] 2003年 3月 4日(火)09:02:14【1】 | YSK さん |
| Re:細長い地名 | |
仕事が始まりましたので、取り急ぎレスです。
[10349]uttさん
札幌市の「北~条東×丁目」などは、「北~条東」という町名としたら、
東西に細長い町がいっぱいあって札幌市の市街地を形成していることになります。
しかも、30丁目とか平気であったりします
以前、札幌市の町名ごとに色分けされた地図で、横縞になっていたのを見た覚えがあります。
こういう例は、あまり認めたくなく、ただの座標に過ぎないと思うのですけど。。。
やはり札幌市は「北~条東」という町名なのでしょうか?
私も、北海道のこのパターンの地名を連想しました。
また、ここの特徴は、ご指摘のとおり座標軸的な発想ですので、20丁目まであって、21~24丁目が抜けて、25丁目からまたあるなど、途中が抜けたりもします。
ただ、「北~条東」単位で郵便番号は割り振られているようですし、どうやら住居表示にもなっているように思われます。まあ、きわめて北海道らしい、町名といえるのかもしれませんね。
北海道でも、釧路市や紋別市などはこういった座標軸的な町丁設定はされていなくて、本州で一般的に見られるような、ブロックごとの住居表示ですね。紋別市は住居表示の法律の実施に伴い整理したのだと、オホーツク流氷科学館を訪れたときの企画展(たまたま、北海道関連の地図の展示をやってて、ラッキー☆でした)でみましたね。
[10349]uttさん
札幌市の「北~条東×丁目」などは、「北~条東」という町名としたら、
東西に細長い町がいっぱいあって札幌市の市街地を形成していることになります。
しかも、30丁目とか平気であったりします
以前、札幌市の町名ごとに色分けされた地図で、横縞になっていたのを見た覚えがあります。
こういう例は、あまり認めたくなく、ただの座標に過ぎないと思うのですけど。。。
やはり札幌市は「北~条東」という町名なのでしょうか?
私も、北海道のこのパターンの地名を連想しました。
また、ここの特徴は、ご指摘のとおり座標軸的な発想ですので、20丁目まであって、21~24丁目が抜けて、25丁目からまたあるなど、途中が抜けたりもします。
ただ、「北~条東」単位で郵便番号は割り振られているようですし、どうやら住居表示にもなっているように思われます。まあ、きわめて北海道らしい、町名といえるのかもしれませんね。
北海道でも、釧路市や紋別市などはこういった座標軸的な町丁設定はされていなくて、本州で一般的に見られるような、ブロックごとの住居表示ですね。紋別市は住居表示の法律の実施に伴い整理したのだと、オホーツク流氷科学館を訪れたときの企画展(たまたま、北海道関連の地図の展示をやってて、ラッキー☆でした)でみましたね。
| [10363] 2003年 3月 4日(火)12:00:43 | ken さん |
| Re:細長い地名 | |
[10350]YSK さん
[10349]uttさん
札幌市の「北~条東×丁目」などは、「北~条東」という町名としたら
北海道の「条」・「丁目」って、なかなか「面としての住居表示」に馴染まないですよね。
以前の職場の先輩で、生まれてから北大まで札幌で過ごした人物ですが、
郵便の宛名書きなどでは、南4条西14丁目は、略す場合は、南4-西14-と書き、
内地の人が「丁目」まで書くような丁寧な書き方であれば、条と丁目は両方書き、
下目黒5-3-17のように丁目を省略する書き方の場合は、条も丁目もセットで省略して、北3-東12-、と書くんだそうです。
普通、手で書く場合は、後者のように、北3-東12-と書く方が多いそうです。
条と丁目は、まさに緯線経線と同様のもので、「北3条」とかが内地で言う「町丁名」にあたるわけではなく、「丁目」は、内地のように「町丁名」の下位に来る概念ではない、言っていました。
ですから、単に西22丁目と言う概念も存在し、南北に縦長の帯状の西22丁目通り沿いを意識し、円山公園に近い方だなあ、と思う、と言うんです。
南(北)条、東(西)丁目は、たまたま、便宜上その条→丁目の順番に書いてますが、頭の中の位置把握では、条と丁目は同列の緯線経線で、意識としては「丁目は条に所属していない」し、必ずしも条を先に規定してから丁目を意識するということでもなく、話の展開としてはその逆も有り得る、ということでした。
北海道民の方、フォローあれば、お願いします。
[10349]uttさん
札幌市の「北~条東×丁目」などは、「北~条東」という町名としたら
北海道の「条」・「丁目」って、なかなか「面としての住居表示」に馴染まないですよね。
以前の職場の先輩で、生まれてから北大まで札幌で過ごした人物ですが、
郵便の宛名書きなどでは、南4条西14丁目は、略す場合は、南4-西14-と書き、
内地の人が「丁目」まで書くような丁寧な書き方であれば、条と丁目は両方書き、
下目黒5-3-17のように丁目を省略する書き方の場合は、条も丁目もセットで省略して、北3-東12-、と書くんだそうです。
普通、手で書く場合は、後者のように、北3-東12-と書く方が多いそうです。
条と丁目は、まさに緯線経線と同様のもので、「北3条」とかが内地で言う「町丁名」にあたるわけではなく、「丁目」は、内地のように「町丁名」の下位に来る概念ではない、言っていました。
ですから、単に西22丁目と言う概念も存在し、南北に縦長の帯状の西22丁目通り沿いを意識し、円山公園に近い方だなあ、と思う、と言うんです。
南(北)条、東(西)丁目は、たまたま、便宜上その条→丁目の順番に書いてますが、頭の中の位置把握では、条と丁目は同列の緯線経線で、意識としては「丁目は条に所属していない」し、必ずしも条を先に規定してから丁目を意識するということでもなく、話の展開としてはその逆も有り得る、ということでした。
北海道民の方、フォローあれば、お願いします。
| [10368] 2003年 3月 4日(火)12:58:50 | ペーロケ[utt] さん |
| 北海道の地名 | |
[10363]kenさま
郵便の宛名書きなどでは、南4条西14丁目は、略す場合は、南4-西14-と書き、・・・
そうですね。実は私もほんの一時期ながら元北海道民なのですが、
住所表記には北4西3のような書き方をよく見かけます。
そういう意味では、札幌の場合は、面的な町名とも言えるのですよね。
それは郊外においても同じで、例えば「発寒2-3」(発寒2条3丁目)などのような書き方をします。
ということは、逆に言えば中心部の「北〇東×」は、「大字なし」にあたるのでしょうか(え、まさか??)
[10350]YSKさま
北海道でも、釧路市や紋別市などはこういった座標軸的な町丁設定はされていなくて、本州で一般的に見られるような、ブロックごとの住居表示ですね。
私が思うに、函館、小樽、釧路などの港町として発展してきた街は丁目表記が多くて、
帯広、旭川、中標津などの内陸の農業で発展してきた街は~条~丁目表記が多いのかなって思います。
港町のほうが歴史があるのか、それとも内陸の街は計画都市が多いのか。。。
(まあ一概にそう言えず、例外も多いですけどね。白糠町とか北見市など)
郵便の宛名書きなどでは、南4条西14丁目は、略す場合は、南4-西14-と書き、・・・
そうですね。実は私もほんの一時期ながら元北海道民なのですが、
住所表記には北4西3のような書き方をよく見かけます。
そういう意味では、札幌の場合は、面的な町名とも言えるのですよね。
それは郊外においても同じで、例えば「発寒2-3」(発寒2条3丁目)などのような書き方をします。
ということは、逆に言えば中心部の「北〇東×」は、「大字なし」にあたるのでしょうか(え、まさか??)
[10350]YSKさま
北海道でも、釧路市や紋別市などはこういった座標軸的な町丁設定はされていなくて、本州で一般的に見られるような、ブロックごとの住居表示ですね。
私が思うに、函館、小樽、釧路などの港町として発展してきた街は丁目表記が多くて、
帯広、旭川、中標津などの内陸の農業で発展してきた街は~条~丁目表記が多いのかなって思います。
港町のほうが歴史があるのか、それとも内陸の街は計画都市が多いのか。。。
(まあ一概にそう言えず、例外も多いですけどね。白糠町とか北見市など)
| [10379] 2003年 3月 4日(火)16:19:26 | まがみ さん |
| Re: 北海道の地名 | |
| [10387] 2003年 3月 4日(火)18:04:33 | 三丁目[YJ3] さん |
| 札幌での居住経験から | |
[10363]kenさん
条と丁目は両方書き、下目黒5-3-17のように丁目を省略する書き方の場合は、条も丁目もセットで省略して、北3-東12-、と書く(以下略)
頭の中の位置把握では、条と丁目は同列の緯線経線で、意識としては「丁目は条に所属していない」し、必ずしも条を先に規定してから丁目を意識するということでもなく、話の展開としてはその逆も有り得る、ということでした。
[10368]uttさん
中心部の「北〇東×」は、「大字なし」にあたるのでしょうか(え、まさか??)
[10379]まがみさん
同じ一つの交差点でも、例えば、
北東側は「北7西3」
北西側は「北7西4」
南西側は「北6西4」
南東側は「北6西3」
という標示が取りつけられていて、「同じ交差点なのに」と興味深く思ったことがあります。
皆様方のお話を私が勘違いしているのかもしれませんが、○条×丁目という住所を聞けば、○と×で囲まれた平行線同士の四辺形の中を、連想していましたよ。私が住んでいた住所を明らかにすると、札幌市中央区南5条西16丁目でしたから、南5という東西を既定する平行線と、西16丁目という南北を既定する平行線で囲まれた四辺形の中で、さらに1-1などの地番(?)がふられてましたから、それで細かく特定できるわけです。
そのことは、同じ一つの交差点なのに、四辺形のどの角と接しているかで、○条×丁目が変わりますから、まがみさんが表示を興味深く思われたのも、無理もないことだと思います。
最後に、言い訳を少々。私は、大学受験科目で世界史を選択したと、かつてご紹介したことがありますが、点をとれる科目と好きな科目は違う、と、言わせてください。ちょっと、受験生の皆さんへのアドバイス(?になるかどうか)も含めて。小学校では地図帳遊びをしてたなど、小中学校での地理は好きでしたが、高校での地理は、私が覚えられない各国の特産物や気候などがたくさんでてきて、どうにも苦手でした。興味を持っていれば覚えられる、という単純なものではありません。
かたや、数字や人名は意識しないでも記憶に残る方なので、歴史系の方がテストの点はよかったのです。そうすれば、ペーパーテストというのは点数勝負ですから、点数をとれる方で挑戦するのはいたしかたないこと、ではないでしょうか。とは言いつつも、私が書き込める内容というのは、地理ネタというより、経験からくる地域ネタなんだな、と気づいたこの頃なのでした。だから書き込めることがあまりないのです。
条と丁目は両方書き、下目黒5-3-17のように丁目を省略する書き方の場合は、条も丁目もセットで省略して、北3-東12-、と書く(以下略)
頭の中の位置把握では、条と丁目は同列の緯線経線で、意識としては「丁目は条に所属していない」し、必ずしも条を先に規定してから丁目を意識するということでもなく、話の展開としてはその逆も有り得る、ということでした。
[10368]uttさん
中心部の「北〇東×」は、「大字なし」にあたるのでしょうか(え、まさか??)
[10379]まがみさん
同じ一つの交差点でも、例えば、
北東側は「北7西3」
北西側は「北7西4」
南西側は「北6西4」
南東側は「北6西3」
という標示が取りつけられていて、「同じ交差点なのに」と興味深く思ったことがあります。
皆様方のお話を私が勘違いしているのかもしれませんが、○条×丁目という住所を聞けば、○と×で囲まれた平行線同士の四辺形の中を、連想していましたよ。私が住んでいた住所を明らかにすると、札幌市中央区南5条西16丁目でしたから、南5という東西を既定する平行線と、西16丁目という南北を既定する平行線で囲まれた四辺形の中で、さらに1-1などの地番(?)がふられてましたから、それで細かく特定できるわけです。
そのことは、同じ一つの交差点なのに、四辺形のどの角と接しているかで、○条×丁目が変わりますから、まがみさんが表示を興味深く思われたのも、無理もないことだと思います。
最後に、言い訳を少々。私は、大学受験科目で世界史を選択したと、かつてご紹介したことがありますが、点をとれる科目と好きな科目は違う、と、言わせてください。ちょっと、受験生の皆さんへのアドバイス(?になるかどうか)も含めて。小学校では地図帳遊びをしてたなど、小中学校での地理は好きでしたが、高校での地理は、私が覚えられない各国の特産物や気候などがたくさんでてきて、どうにも苦手でした。興味を持っていれば覚えられる、という単純なものではありません。
かたや、数字や人名は意識しないでも記憶に残る方なので、歴史系の方がテストの点はよかったのです。そうすれば、ペーパーテストというのは点数勝負ですから、点数をとれる方で挑戦するのはいたしかたないこと、ではないでしょうか。とは言いつつも、私が書き込める内容というのは、地理ネタというより、経験からくる地域ネタなんだな、と気づいたこの頃なのでした。だから書き込めることがあまりないのです。
| [11968] 2003年 3月 27日(木)20:06:24 | 三丁目 さん |
| 北海道「都市部」での条・丁目 | |
[11851]uttさん
北海道では、都市部では東西を条、南北を丁目といった地名を付けますが
つまらない反応をして、スイマセン。揚足を取るつもりではないので、ご容赦下さい。[11907]で、太白さんが引用されているのを見て(引用の白抜きに目がとまりました)「都市部」に引っかかったものですから。
道内の市で、条・丁目が使われているのは、私の記憶では(細かい地図が手元にないので確認せず申し訳ありません)札幌、旭川、帯広、北見、岩見沢くらいでしょうか。以前、拙稿[11539]で最古参6市という言い方をしましたが、札幌、旭川、函館、釧路、小樽、室蘭(現在の人口順)のうち、上位2市だけが、条・丁目を採用しています。
たしか、札幌市史で読んだと思うのですが、もともと、新しい入植地として北海道を開拓するに当たり、条里制を導入しようとした、そうです。が、それなりの平坦地があったのが、先述の5市だったと思われます。小樽、室蘭は、かねてから港町であったように、傾斜の急な土地が多かったため、条里制を採用できなかったのではないかと、思っていました。釧路は、よくわかりません。
函館は、歴史的に既に土地の名が定着しており、それが函館旧市でも、採用されたと考えていますが、確認はしておりません。スイマセン。
uttさんも、北海道にお住まいになってたと記憶してますから、他意がないのはわかるのですが、「都市部」と言われてしまうと、その他大勢の方が多いのに、とつい、反応してしまいました。
なお、太白さんへ。私の平行線で囲まれた四辺形という表現よりは、[10398]kenさんの帯と帯が交差したところ、の方がわかりやすいと、反省してました。
北海道では、都市部では東西を条、南北を丁目といった地名を付けますが
つまらない反応をして、スイマセン。揚足を取るつもりではないので、ご容赦下さい。[11907]で、太白さんが引用されているのを見て(引用の白抜きに目がとまりました)「都市部」に引っかかったものですから。
道内の市で、条・丁目が使われているのは、私の記憶では(細かい地図が手元にないので確認せず申し訳ありません)札幌、旭川、帯広、北見、岩見沢くらいでしょうか。以前、拙稿[11539]で最古参6市という言い方をしましたが、札幌、旭川、函館、釧路、小樽、室蘭(現在の人口順)のうち、上位2市だけが、条・丁目を採用しています。
たしか、札幌市史で読んだと思うのですが、もともと、新しい入植地として北海道を開拓するに当たり、条里制を導入しようとした、そうです。が、それなりの平坦地があったのが、先述の5市だったと思われます。小樽、室蘭は、かねてから港町であったように、傾斜の急な土地が多かったため、条里制を採用できなかったのではないかと、思っていました。釧路は、よくわかりません。
函館は、歴史的に既に土地の名が定着しており、それが函館旧市でも、採用されたと考えていますが、確認はしておりません。スイマセン。
uttさんも、北海道にお住まいになってたと記憶してますから、他意がないのはわかるのですが、「都市部」と言われてしまうと、その他大勢の方が多いのに、とつい、反応してしまいました。
なお、太白さんへ。私の平行線で囲まれた四辺形という表現よりは、[10398]kenさんの帯と帯が交差したところ、の方がわかりやすいと、反省してました。
| [11974] 2003年 3月 27日(木)21:38:14【1】 | ペーロケ[utt] さん |
| ~条~丁目の不適用条件 | |
[11968]三丁目さま
つまらない反応をして、スイマセン。
いえいえ、こちらこそ、書き方まずかったですね。
「北海道では、多くの都市の都市部では・・・」とすべきでした。
もちろん、北海道の全ての都市が「~条~丁目」表記をするとは限らないことは存じております。
でも、三丁目さまの意見を見て、改めて気づかされました。
傾斜の急な土地が多かったため、条里制を採用できなかったのではないかと、
言われて見れば。。。確かにそうですね。
[10368]では、港町のほうが歴史があるから~って安易な考察をしてましたが(^^;;
あと、北見市って中心部の狭い範囲だけ「~条~丁目」表記なのですね。
比較的駅に近いものの、その範囲外に住む友人がいるので、
北見市は内陸の農業都市なのに、そのような表記をしない都市かと思っていました。
しかし、北見市っていろんな謎が多いですね。
なぜ北見市中心部は斜めに作られたのだろうでしょうか??
石北線の市街地アンダーパスが地下鉄(?)っぽいですね。
あと、北見市は網走支庁の中心に位置しており、圧倒的に人口も多いのに、
なぜ網走に支庁が設置されたのでしょうか??
おかげで、網走監獄のイメージが強すぎ、相対的に北見市の知名度はかなり低くなっていますね。
釧路は、よくわかりません。
釧路市は、明治時代、釧路川(ちょっと前まで旧釧路川と言われていたほう)
の南側の丘陵地付近に街(というか町?)があり、
釧路川の北側は湿原の泥炭地帯が広がっていたそうで、住むのには適さなかったようです。
鉄道開通をきっかけに、ようやく北側も区画整理され、人が住むようになったらしいですが、
それでも今よりもっと港寄りに駅があり、今の釧路駅周辺は何もない原野だったそうで、
漁業と炭鉱のおかげか、相変わらず南側の丘陵地帯が街の中心だったようです。
今でこそ、市街地も北側の平地の方に拡大し、
炭鉱・漁業の衰退によって南大通りが寂れて、相対的に北側が中心街になっていますが。。。
そのような事情がある釧路市も、三丁目さまの「傾斜地条里制不適用説」は見事に当てはまります。
uttさんも、北海道にお住まいになってたと記憶してますから、
はい、1年間だけ、札幌に住んでました。
つまらない反応をして、スイマセン。
いえいえ、こちらこそ、書き方まずかったですね。
「北海道では、多くの都市の都市部では・・・」とすべきでした。
もちろん、北海道の全ての都市が「~条~丁目」表記をするとは限らないことは存じております。
でも、三丁目さまの意見を見て、改めて気づかされました。
傾斜の急な土地が多かったため、条里制を採用できなかったのではないかと、
言われて見れば。。。確かにそうですね。
[10368]では、港町のほうが歴史があるから~って安易な考察をしてましたが(^^;;
あと、北見市って中心部の狭い範囲だけ「~条~丁目」表記なのですね。
比較的駅に近いものの、その範囲外に住む友人がいるので、
北見市は内陸の農業都市なのに、そのような表記をしない都市かと思っていました。
しかし、北見市っていろんな謎が多いですね。
なぜ北見市中心部は斜めに作られたのだろうでしょうか??
石北線の市街地アンダーパスが地下鉄(?)っぽいですね。
あと、北見市は網走支庁の中心に位置しており、圧倒的に人口も多いのに、
なぜ網走に支庁が設置されたのでしょうか??
おかげで、網走監獄のイメージが強すぎ、相対的に北見市の知名度はかなり低くなっていますね。
釧路は、よくわかりません。
釧路市は、明治時代、釧路川(ちょっと前まで旧釧路川と言われていたほう)
の南側の丘陵地付近に街(というか町?)があり、
釧路川の北側は湿原の泥炭地帯が広がっていたそうで、住むのには適さなかったようです。
鉄道開通をきっかけに、ようやく北側も区画整理され、人が住むようになったらしいですが、
それでも今よりもっと港寄りに駅があり、今の釧路駅周辺は何もない原野だったそうで、
漁業と炭鉱のおかげか、相変わらず南側の丘陵地帯が街の中心だったようです。
今でこそ、市街地も北側の平地の方に拡大し、
炭鉱・漁業の衰退によって南大通りが寂れて、相対的に北側が中心街になっていますが。。。
そのような事情がある釧路市も、三丁目さまの「傾斜地条里制不適用説」は見事に当てはまります。
uttさんも、北海道にお住まいになってたと記憶してますから、
はい、1年間だけ、札幌に住んでました。
| [11977] 2003年 3月 27日(木)22:03:18 | 地理好きのケン さん |
| 条・丁目 | |
北海道で条・丁目を使用している市は札幌市、石狩市、江別市、岩見沢市、美唄市、旭川市、深川市、砂川市、芦別市、帯広市、名寄市、士別市、北見市、網走市です。
| [11997] 2003年 3月 28日(金)02:40:20 | 紅葉橋律乃介[紅葉橋瑤知朗] さん |
| 条丁目 | |
「都市部」(?)北海道岩見沢市民です。
実際に住んでいる身としては、バイト先は「4条西3丁目」であり、非常に分かりやすいと思うのですが。
このような地名の場合、たとえば線路と平行に道路を作り、近いほうから1条2条…とふり、垂直にも道を作って、1本目と2本目の間を「1丁目」などとしていますね。
「○条通り」という通りの名前だと、たしかに裏側だと分かりにくいです。
ただ、岩見沢市の場合、市街地のみ原則から離れまして、「4条通り」は旧国道12号線なのですが、通りの両側を「4条」としています。ややこしいなあ。
ちなみに、「市」だけてはなくて、「町」にも条丁目制があります。というか、例に上がった市も、市制施行は昭和になってからのところもありますから。
「全て」
何の疑問も持ちませんでした(漢字検定2級保持)。「新明解」第4版(1997年)にも載っています。
相撲ファンとしては、「軍配をあげて」が疑問符。
「軍配」は戦で総大将が持っているやつで、行司さんが持っているのは「団扇(うちわ)」。まあ、どっちでもいいですが。
だいぶ離れますが、[11963]基ずく、[11974]北海道フェチも気になります。
特に、後者(これに関する苦情は受け付けません)は、深い意味は無いにせよ、小学生も来ているのですから、大人として配慮願います。
実際に住んでいる身としては、バイト先は「4条西3丁目」であり、非常に分かりやすいと思うのですが。
このような地名の場合、たとえば線路と平行に道路を作り、近いほうから1条2条…とふり、垂直にも道を作って、1本目と2本目の間を「1丁目」などとしていますね。
「○条通り」という通りの名前だと、たしかに裏側だと分かりにくいです。
ただ、岩見沢市の場合、市街地のみ原則から離れまして、「4条通り」は旧国道12号線なのですが、通りの両側を「4条」としています。ややこしいなあ。
ちなみに、「市」だけてはなくて、「町」にも条丁目制があります。というか、例に上がった市も、市制施行は昭和になってからのところもありますから。
「全て」
何の疑問も持ちませんでした(漢字検定2級保持)。「新明解」第4版(1997年)にも載っています。
相撲ファンとしては、「軍配をあげて」が疑問符。
「軍配」は戦で総大将が持っているやつで、行司さんが持っているのは「団扇(うちわ)」。まあ、どっちでもいいですが。
だいぶ離れますが、[11963]基ずく、[11974]北海道フェチも気になります。
特に、後者(これに関する苦情は受け付けません)は、深い意味は無いにせよ、小学生も来ているのですから、大人として配慮願います。
| [12087] 2003年 3月 29日(土)23:40:29 | てへへ さん |
| re:条・丁目 | |
[11977]地理好きのケン さん
北海道で条・丁目を使用している市は札幌市、石狩市、江別市、岩見沢市、美唄市、旭川市、深川市、砂川市、芦別市、帯広市、名寄市、士別市、北見市、網走市です。
確認してみました。北海道で条を使用している市は地理好きのケンさんの挙げている14市です。このうち深川市は○条はありますが○条○丁目のように丁目と一緒に使用する地域が見つかりませんでした。実例があればご教示ください。
[11997]紅葉橋瑤知朗 さん
ちなみに、「市」だけてはなくて、「町」にも条丁目制があります。
ということで北海道の町村でも調べてみました。市と合わせて支庁別にまとめてみました。なお丁目部分は算用数字にしています。
支庁により偏りがあります。全14支庁のうち、北海道南部の渡島、桧山、胆振、日高の各支庁には条・丁目の例が見つかりませんでした。推測ですが条・丁目が無い函館の影響があったのかもしれません。
北海道は条・丁目という住居表示のイメージが強いのですが、札幌市を区ごとに数えた場合の市区町村の数で見る限り、46/221で約20%となり、てへへが思っていたよりも少なかったです。
なお条の最大値51、丁目の最大値41についてこれよりも大きな値を見つけた場合はご教示ください。あくまでも目視チェックですので。
北海道で条・丁目を使用している市は札幌市、石狩市、江別市、岩見沢市、美唄市、旭川市、深川市、砂川市、芦別市、帯広市、名寄市、士別市、北見市、網走市です。
確認してみました。北海道で条を使用している市は地理好きのケンさんの挙げている14市です。このうち深川市は○条はありますが○条○丁目のように丁目と一緒に使用する地域が見つかりませんでした。実例があればご教示ください。
[11997]紅葉橋瑤知朗 さん
ちなみに、「市」だけてはなくて、「町」にも条丁目制があります。
ということで北海道の町村でも調べてみました。市と合わせて支庁別にまとめてみました。なお丁目部分は算用数字にしています。
| 支庁・町村名 | 条・丁目の例 | 備考 |
| 石狩支庁 | - | |
| 札幌市 | 東区北五十一条東15丁目 | 条の最大値。全10区で条・丁目使用。 |
| 江別市 | 八条8丁目 | |
| 石狩市 | 花川南十条4丁目 | |
| 空知支庁 | - | |
| 岩見沢市 | 十三条西5丁目 | |
| 美唄市 | 東六条南6丁目 | |
| 砂川市 | 東六条北11丁目 | |
| 芦別市 | 北六条東1丁目 | |
| 後志支庁 | - | |
| 虻田郡倶知安町 | 南十一条東1丁目 | |
| 上川支庁 | - | |
| 旭川市 | 流通団地四条5丁目 | |
| 名寄市 | 西十六条南9丁目 | |
| 士別市 | 東十条13丁目 | |
| 上川郡鷹栖町 | 北野東五条1丁目 | |
| 上川郡東神楽町 | 南三条東1丁目 | |
| 上川郡当麻町 | 六条東3丁目 | |
| 中川郡美深町 | 東六条南1丁目 | |
| 留萌支庁 | - | |
| 苫前郡羽幌町 | 北六条1丁目 | |
| 天塩郡幌延町 | 六条南1丁目 | |
| 宗谷支庁 | - | |
| 天塩郡豊富町 | 東六条1丁目 | |
| 網走支庁 | - | |
| 北見市 | 北十一条東4丁目 | |
| 網走市 | 南十四条西3丁目 | |
| 網走郡女満別町 | 西七条5丁目 | |
| 網走郡美幌町 | 東四条南2丁目 | |
| 紋別郡遠軽町 | 二条通北1丁目 | |
| 十勝支庁 | - | |
| 帯広市 | 西十五条南41丁目 | 丁目の最大値。 |
| 河東郡音更町 | 駒場北1条通1丁目 | |
| 上川郡新得町 | 一条北1丁目 | |
| 上川郡清水町 | 御影西二条1丁目 | |
| 河西郡芽室町 | 西一条1丁目 | |
| 河西郡中札内村 | 東一条北1丁目 | |
| 広尾郡広尾町 | 東一条14丁目 | |
| 中川郡池田町 | 西一条1丁目 | |
| 足寄郡足寄町 | 北二条1丁目 | |
| 十勝郡浦幌町 | 厚内一条通2丁目 | |
| 釧路支庁 | - | |
| 厚岸郡浜中町 | 霧多布西一条1丁目 | |
| 白糠郡白糠町 | 西庶路西一条北1丁目 | |
| 根室支庁 | - | |
| 標津郡中標津町 | 西十条北1丁目 | |
| 標津郡標津町 | 北一条東1丁目 |
支庁により偏りがあります。全14支庁のうち、北海道南部の渡島、桧山、胆振、日高の各支庁には条・丁目の例が見つかりませんでした。推測ですが条・丁目が無い函館の影響があったのかもしれません。
北海道は条・丁目という住居表示のイメージが強いのですが、札幌市を区ごとに数えた場合の市区町村の数で見る限り、46/221で約20%となり、てへへが思っていたよりも少なかったです。
なお条の最大値51、丁目の最大値41についてこれよりも大きな値を見つけた場合はご教示ください。あくまでも目視チェックですので。
| [12313] 2003年 4月 2日(水)20:54:00 | 三丁目 さん |
| しつこく条・丁目 | |
[11997]地理好きのケンさん
北海道で条・丁目を使用している市は札幌市、石狩市、江別市、岩見沢市、美唄市、旭川市、深川市、砂川市、芦別市、帯広市、名寄市、士別市、北見市、網走市です。
[12087]てへへさん
地理好きのケンさんの挙げている14市です。北海道の町村でも調べてみました。
条・丁目について、引き続き考察しましたので、ご紹介いたします。
まず、現在、条・丁目を住居表示に採用している市町村のうち、せっかくてへへさんが全て挙げてくださったのですが、とりあえず市だけで考えました。住居表示は古くからあることを鑑みて、石狩市が新しい市制施行(と言っても7年前ですが)ということで除くと、それ以外は基本的に海に面していない市です。このうち、網走市だけが、例外です。ちょっと話はそれますが、町村まで範囲を広げると、海に面しているところが増えるので、考察対象を絞り込むために、市だけにしたものです。
それで、私の疑問は、海に面した網走市が、なぜ条・丁目を採用しているのか、でした。海に面した人口の多い市は、函館市、小樽市、室蘭市、苫小牧市、釧路市を思い浮かべましたが、それらの市では採用していません。結論を先に申し上げてしまうと、明解なこれだという理由はわかりませんでした。
網走市の古くからの集落は北見町と言い、現在、条・丁目が採用されている地区にあたります。簡単に述べると、平坦地だから、につきるのかな、と思いました。
では逆に、平坦地なのに、苫小牧市は、なぜ条・丁目制を採用していないのだろう、とも思いました。この疑問は、苫小牧市役所に聞いてしまいました。回答としては、住居表示は2通りあり、道路方式(条・丁目)と街区方式(町名を付けていく)なのだそうです。それで、どちらを採用するかはそれぞれの市町村の判断となり、苫小牧市では街区方式を採用した、とのことでした。なんか、あまりあっさり言われると、拍子抜けしました。
実際のところ、苫小牧市は、一部は碁盤の目ですが、あちこち斜めに曲っていたり、T字路が多かったりして、広い範囲には条里制を適用できなさそうに思われます。逆に、都市計画の観点から言うと、もっと計画的にできたはずで、網走市のように条・丁目を採用できたのでは?と思わずにはいられませんでした。
以上ですが、こねくりまわした割りには、たいした結論を導けなくて、申し訳ありません。
北海道で条・丁目を使用している市は札幌市、石狩市、江別市、岩見沢市、美唄市、旭川市、深川市、砂川市、芦別市、帯広市、名寄市、士別市、北見市、網走市です。
[12087]てへへさん
地理好きのケンさんの挙げている14市です。北海道の町村でも調べてみました。
条・丁目について、引き続き考察しましたので、ご紹介いたします。
まず、現在、条・丁目を住居表示に採用している市町村のうち、せっかくてへへさんが全て挙げてくださったのですが、とりあえず市だけで考えました。住居表示は古くからあることを鑑みて、石狩市が新しい市制施行(と言っても7年前ですが)ということで除くと、それ以外は基本的に海に面していない市です。このうち、網走市だけが、例外です。ちょっと話はそれますが、町村まで範囲を広げると、海に面しているところが増えるので、考察対象を絞り込むために、市だけにしたものです。
それで、私の疑問は、海に面した網走市が、なぜ条・丁目を採用しているのか、でした。海に面した人口の多い市は、函館市、小樽市、室蘭市、苫小牧市、釧路市を思い浮かべましたが、それらの市では採用していません。結論を先に申し上げてしまうと、明解なこれだという理由はわかりませんでした。
網走市の古くからの集落は北見町と言い、現在、条・丁目が採用されている地区にあたります。簡単に述べると、平坦地だから、につきるのかな、と思いました。
では逆に、平坦地なのに、苫小牧市は、なぜ条・丁目制を採用していないのだろう、とも思いました。この疑問は、苫小牧市役所に聞いてしまいました。回答としては、住居表示は2通りあり、道路方式(条・丁目)と街区方式(町名を付けていく)なのだそうです。それで、どちらを採用するかはそれぞれの市町村の判断となり、苫小牧市では街区方式を採用した、とのことでした。なんか、あまりあっさり言われると、拍子抜けしました。
実際のところ、苫小牧市は、一部は碁盤の目ですが、あちこち斜めに曲っていたり、T字路が多かったりして、広い範囲には条里制を適用できなさそうに思われます。逆に、都市計画の観点から言うと、もっと計画的にできたはずで、網走市のように条・丁目を採用できたのでは?と思わずにはいられませんでした。
以上ですが、こねくりまわした割りには、たいした結論を導けなくて、申し訳ありません。
この特集記事はあなたのお気に召しましたか。よろしければ推奨してください。→ ★推奨します★(元祖いいね)
推奨するためには、メンバー登録が必要です。→ メンバー登録のご案内
… スポンサーリンク …