… スポンサーリンク …
| [114799] 2025年 7月 18日(金)22:07:21【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 18日(金)22:16:16 | オーナー グリグリ |
| 御礼(十番勝負の前に) | |
[114774] ピーくんさん
台風上陸ランキング更新よろしくお願いします。
台風上陸回数を更新しました。先日北海道に上陸した台風5号のデータを追加しました。また、説明文を次のように更新しました。
「2025年7月15日(火)2時頃、台風5号(ナーリー)は北海道襟裳岬付近に上陸しました。北海道に台風が上陸するのは2016年の台風11号以来、9年ぶりです。2025年初めての上陸です。2024年は、8月29日、台風10号が鹿児島県に上陸しました。また、8月13日、台風5号が岩手県に上陸しました。岩手県への上陸は2016年の台風10号以来2度目です(1951年以降)。」
[114776] にまんさん
情報公開の根拠として、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が挙げられていますが、この法律は「国の行政機関」を対象としたものですので、地方自治体は対象外となっています。(ちなみに、行政機関でない国会や裁判所も対象外)
ですので、自治体の情報公開の根拠は各自治体の「情報公開条例」となります。(東京都の場合東京都情報公開条例)
基本的には、法律と各自治体の条例で大きな差はないと思われ、「個人に関する情報」は不開示情報とされていると思います。
ただ、例外として「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報)は不開示情報ではないとされていて、これに該当するかどうかの判断は、自治体によって取り扱いに差がでそうです。
丁寧がご説明をありがとうございました。このご説明を受け、生年月日をすべて確認することはできないだろうということから、[114781]で年齢不詳者の表記を検討した次第です。ありがとうございました。
[114783] 下総みなとさん
先のグリグリさんの投稿([114779])で、切手のページから誕生日登録ができることを初めて知りました。
まだまだこのサイトの探索が足りない感じがしてなりません。
ありがとうございます。私の誕生日の切手は、当初1997年に独立で立ち上げたサイトです(都道府県市区町村は1996年に立ち上げ)。昨年、リニューアルして都道府県市区町村のスピンオフ企画として統合しました。
早速誕生日を登録してみましたが、切手の掲載範囲と誕生日が重なってないために、切手が見られるのは暫く先になりそうですね。
リニューアルしましたが、誕生日切手そのものの収集と整理は進んでいません。また、今後も進捗をお約束することができません。申し訳ありませんが、気長にというか忘れない程度にお待ちいただければ幸いです。
Amandaさんにも登録していただきました。同じくよろしくお願いいたします。
[114794] あきごんさん
ところで、今回は十番勝負開始までのカウントダウンタイマーはされていないのですね。
すっかり失念していました。ご指摘を受け、急ぎ設定しました。今後ともよろしくお願いいたします。
[114795] ピーくんさん
高浜町 欠員となりました。
氏名に注記を付け更新しました。加えて、高知県田野町から回答があり、坂本町長の生年月日は 1964.9.23 と確認でき更新しました。また、愛媛県愛南町については、ピーくんさん[114718]と同様の回答でした。
台風上陸ランキング更新よろしくお願いします。
台風上陸回数を更新しました。先日北海道に上陸した台風5号のデータを追加しました。また、説明文を次のように更新しました。
「2025年7月15日(火)2時頃、台風5号(ナーリー)は北海道襟裳岬付近に上陸しました。北海道に台風が上陸するのは2016年の台風11号以来、9年ぶりです。2025年初めての上陸です。2024年は、8月29日、台風10号が鹿児島県に上陸しました。また、8月13日、台風5号が岩手県に上陸しました。岩手県への上陸は2016年の台風10号以来2度目です(1951年以降)。」
[114776] にまんさん
情報公開の根拠として、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が挙げられていますが、この法律は「国の行政機関」を対象としたものですので、地方自治体は対象外となっています。(ちなみに、行政機関でない国会や裁判所も対象外)
ですので、自治体の情報公開の根拠は各自治体の「情報公開条例」となります。(東京都の場合東京都情報公開条例)
基本的には、法律と各自治体の条例で大きな差はないと思われ、「個人に関する情報」は不開示情報とされていると思います。
ただ、例外として「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報)は不開示情報ではないとされていて、これに該当するかどうかの判断は、自治体によって取り扱いに差がでそうです。
丁寧がご説明をありがとうございました。このご説明を受け、生年月日をすべて確認することはできないだろうということから、[114781]で年齢不詳者の表記を検討した次第です。ありがとうございました。
[114783] 下総みなとさん
先のグリグリさんの投稿([114779])で、切手のページから誕生日登録ができることを初めて知りました。
まだまだこのサイトの探索が足りない感じがしてなりません。
ありがとうございます。私の誕生日の切手は、当初1997年に独立で立ち上げたサイトです(都道府県市区町村は1996年に立ち上げ)。昨年、リニューアルして都道府県市区町村のスピンオフ企画として統合しました。
早速誕生日を登録してみましたが、切手の掲載範囲と誕生日が重なってないために、切手が見られるのは暫く先になりそうですね。
リニューアルしましたが、誕生日切手そのものの収集と整理は進んでいません。また、今後も進捗をお約束することができません。申し訳ありませんが、気長にというか忘れない程度にお待ちいただければ幸いです。
Amandaさんにも登録していただきました。同じくよろしくお願いいたします。
[114794] あきごんさん
ところで、今回は十番勝負開始までのカウントダウンタイマーはされていないのですね。
すっかり失念していました。ご指摘を受け、急ぎ設定しました。今後ともよろしくお願いいたします。
[114795] ピーくんさん
高浜町 欠員となりました。
氏名に注記を付け更新しました。加えて、高知県田野町から回答があり、坂本町長の生年月日は 1964.9.23 と確認でき更新しました。また、愛媛県愛南町については、ピーくんさん[114718]と同様の回答でした。
| [114798] 2025年 7月 18日(金)19:44:23 | BANDALGOM さん |
| 高校野球千葉大会決勝戦 | |
[114768]白桃 さん
千葉大会の決勝会場はZOZOマリンスタジアムですね。
昔は県総合運動場(天台球場)でした。千葉市天台の県総合運動場には、高校時代弓道部(3年の初めまでは同好会)に所属していた私もしょっちゅう行ったものです。
中学では1年の時だけバスケ部でしたが、2年になって顧問が代わり、トレーニングがキツくなったため退部。その失敗から、高校では文化系に入ろうと考え、写真部を念頭に入れていましたが、部室に行っても扉は固く閉ざされていました。そこで、運動部ではあるけれど、キツいトレーニングはない、ってことで、弓道部を選んだのでした。
しかし、下手ではあったので大会にはなかなか出られず、親にも文句を言われるので、顧問にせがんで、2年の夏休みの遠的大会(三十三間堂の通し矢と同じ射程)に出させてもらいました。
ただ、大会や段級審査のたびに天台にはよく行っていたので、野球場の場所も分かりますし、稲毛駅からのバスの車内放送が独特だったのを覚えています。
千葉大会の決勝会場はZOZOマリンスタジアムですね。
昔は県総合運動場(天台球場)でした。千葉市天台の県総合運動場には、高校時代弓道部(3年の初めまでは同好会)に所属していた私もしょっちゅう行ったものです。
中学では1年の時だけバスケ部でしたが、2年になって顧問が代わり、トレーニングがキツくなったため退部。その失敗から、高校では文化系に入ろうと考え、写真部を念頭に入れていましたが、部室に行っても扉は固く閉ざされていました。そこで、運動部ではあるけれど、キツいトレーニングはない、ってことで、弓道部を選んだのでした。
しかし、下手ではあったので大会にはなかなか出られず、親にも文句を言われるので、顧問にせがんで、2年の夏休みの遠的大会(三十三間堂の通し矢と同じ射程)に出させてもらいました。
ただ、大会や段級審査のたびに天台にはよく行っていたので、野球場の場所も分かりますし、稲毛駅からのバスの車内放送が独特だったのを覚えています。
| [114797] 2025年 7月 18日(金)18:49:09 | N さん |
| Re2:要確認情報など2 | |
[114793]グリグリさん
ご対応ありがとうございます。
>大郷町
連続無投票は任期連続が前提と考えていますので、注記不要と考えます。
承知です。
>野沢温泉村
そうすると任期満了日も「2029.3.29」となるはずですが、長野県の市町村長の任期満了一覧では「2029.3.28」となっています。1期就任日を前倒ししていると考えるのか、任期満了日は前任と同じになるのか、それとも単なる更新漏れなのか、どうなんでしょう。
その資料は見落としていました。理屈の上では仰る通り2029.3.29になるはずですが、とりあえず長野県選管に問合せ投げてみました。
#イレギュラーが無ければ前回の任期満了日に4年足すだけの日付なので、資料の更新ミスだとは思いますが…
ご対応ありがとうございます。
>大郷町
連続無投票は任期連続が前提と考えていますので、注記不要と考えます。
承知です。
>野沢温泉村
そうすると任期満了日も「2029.3.29」となるはずですが、長野県の市町村長の任期満了一覧では「2029.3.28」となっています。1期就任日を前倒ししていると考えるのか、任期満了日は前任と同じになるのか、それとも単なる更新漏れなのか、どうなんでしょう。
その資料は見落としていました。理屈の上では仰る通り2029.3.29になるはずですが、とりあえず長野県選管に問合せ投げてみました。
#イレギュラーが無ければ前回の任期満了日に4年足すだけの日付なので、資料の更新ミスだとは思いますが…
| [114796] 2025年 7月 18日(金)16:36:12 | ピーくん さん |
| 東筑敗退 | |
白桃さん
文武両道の東筑負けてしまいました。広島県は広島商と広陵ですかね。迫田兄弟があちこちで監督した頃は広島商と広陵以外もチャンスがありましたが迫田兄弟は亡くなられたり高齢になられました。野球関係のYouTubeの監督が上下高校に来ました。楽しみです。
北海道の予選はエスコンフィールド羨ましいです。暑苦しい甲子園より良いです。三本松頑張ってください。
十番勝負は不参加で寂しいです。
文武両道の東筑負けてしまいました。広島県は広島商と広陵ですかね。迫田兄弟があちこちで監督した頃は広島商と広陵以外もチャンスがありましたが迫田兄弟は亡くなられたり高齢になられました。野球関係のYouTubeの監督が上下高校に来ました。楽しみです。
北海道の予選はエスコンフィールド羨ましいです。暑苦しい甲子園より良いです。三本松頑張ってください。
十番勝負は不参加で寂しいです。
| [114795] 2025年 7月 18日(金)13:38:38【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 18日(金)16:21:50 | ピーくん さん |
| 訃報 | |
関西電力高浜原発が立地する福井県高浜町長の野瀬豊(のせ・ゆたか)さんが17日午後7時46分、虫垂がん治療のため入院中、京都市の医療機関で死去した。65歳。高浜町出身。自宅は高浜町鐘寄13の6。葬儀・告別式は近親者で執り行う。
御冥福をお祈りします。
高浜町 欠員となりました。
グリグリさま
更新よろしくお願いします。
御冥福をお祈りします。
高浜町 欠員となりました。
グリグリさま
更新よろしくお願いします。
| [114794] 2025年 7月 18日(金)12:59:42【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 18日(金)13:07:21 | あきごん さん |
| 平年並みなのにやっと梅雨明け? | |
気象庁が「関東甲信・北陸・東北南部が梅雨明けしたとみられる」と発表したようです。関東甲信では平年より1日早い梅雨明けだそうですが、近畿地方では6月27日に早々に梅雨明けしているので、「やっと?」という感覚になってしまいます。
先月の梅雨明け以降、私の住む奈良県でも連日、最高気温は35度を超えるのが当たり前。32~33度だったら「今日は涼しい」と感じてしまうのは、自分でも感覚がおかしくなってしまっていると感じます。小学生の頃(昭和50年頃のお話しです)、夏休みの宿題の絵日記では、毎日、天気と気温の欄だけはしっかりと記録していたので記憶に残っていますが、最高気温は大体30度ちょっとで33度を超えたら、「今日はめちゃくちゃ暑い」と言っていました。35度を超える日などほとんどなく、最高気温が36度になったら全国ニュースになっていたのに…、ホントにどうなってしまったんだと思います。
梅雨明けして、もう3週間、毎日のように酷暑と夕立の心配をしているので、もうすっかり8月の気分なのですが、まだ7月の半ば過ぎでした。これから夏が本番と考えるとぐったりしてしまいます。
[114792] グリグリさん
いよいよ、あと1日後の明日午前9時スタートです。
上記のように日時感覚がすこしおかしくなっているので実感がなかったのですが、もう明日の朝、十陣勝負スタートなのですね。どうぞ、よろしくお願いします。
ところで、今回は十番勝負開始までのカウントダウンタイマーはされていないのですね。明日から十番勝負だといわれて、そういえば今回はないなあと気付きました。
先月の梅雨明け以降、私の住む奈良県でも連日、最高気温は35度を超えるのが当たり前。32~33度だったら「今日は涼しい」と感じてしまうのは、自分でも感覚がおかしくなってしまっていると感じます。小学生の頃(昭和50年頃のお話しです)、夏休みの宿題の絵日記では、毎日、天気と気温の欄だけはしっかりと記録していたので記憶に残っていますが、最高気温は大体30度ちょっとで33度を超えたら、「今日はめちゃくちゃ暑い」と言っていました。35度を超える日などほとんどなく、最高気温が36度になったら全国ニュースになっていたのに…、ホントにどうなってしまったんだと思います。
梅雨明けして、もう3週間、毎日のように酷暑と夕立の心配をしているので、もうすっかり8月の気分なのですが、まだ7月の半ば過ぎでした。これから夏が本番と考えるとぐったりしてしまいます。
[114792] グリグリさん
いよいよ、あと1日後の明日午前9時スタートです。
上記のように日時感覚がすこしおかしくなっているので実感がなかったのですが、もう明日の朝、十陣勝負スタートなのですね。どうぞ、よろしくお願いします。
ところで、今回は十番勝負開始までのカウントダウンタイマーはされていないのですね。明日から十番勝負だといわれて、そういえば今回はないなあと気付きました。
| [114793] 2025年 7月 18日(金)12:12:33 | オーナー グリグリ |
| Re:要確認情報など2 | |
[114780] Nさん
2007年以前の軽米町長選挙の結果がどうだったのか把握されていますでしょうか。
・・・
2009年以前の大郷町長選挙の結果がどうだったのか把握されていますでしょうか。
すみません、どちらも把握しておりません。
■黒川郡大郷町
少なくとも2005年は無投票のようですが、1-3期(1997-2005)連続無投票にならない根拠はありますでしょうか。またさらに遡って自治体レベルで5期以上無投票の可能性もないでしょうか。
こちらも把握できていません。
#ところで、もし仮に2017年も無投票だったら田中氏は2005,2017,2021で3回連続無投票になっていましたが、この場合は任期連続していなくても3期連続無投票の注記をする理解であっていますか?
連続無投票は任期連続が前提と考えていますので、注記不要と考えます。
■下伊那郡阿智村
2002年は無投票かつ1998年が選挙戦なので、自治体レベルで2002-2018の5期連続無投票です。
更新しました。
■北安曇郡松川村
■下高井郡野沢温泉村
どちらも現村長が1期目で直近無投票ではないので注記対象ではないと思いますが、
松川村は2008年の無投票が16年ぶり、野沢温泉村は2005年が選挙戦なので、いずれも連続4期止まりです。
#近所で5期以上可能性ありそうな生坂村も2003年が8年ぶり無投票なので3期連続止まり。
了解しました。ありがとうございます。
なお、野沢温泉村について上野氏の1期就任日は選挙日の「2025.3.30」が正のようです。
確認しました。こちらも更新しました。ただ、そうすると任期満了日も「2029.3.29」となるはずですが、長野県の市町村長の任期満了一覧では「2029.3.28」となっています。1期就任日を前倒ししていると考えるのか、任期満了日は前任と同じになるのか、それとも単なる更新漏れなのか、どうなんでしょう。とりあえあず、「2025.3.30」「2029.3.28」としていますが。
2007年以前の軽米町長選挙の結果がどうだったのか把握されていますでしょうか。
・・・
2009年以前の大郷町長選挙の結果がどうだったのか把握されていますでしょうか。
すみません、どちらも把握しておりません。
■黒川郡大郷町
少なくとも2005年は無投票のようですが、1-3期(1997-2005)連続無投票にならない根拠はありますでしょうか。またさらに遡って自治体レベルで5期以上無投票の可能性もないでしょうか。
こちらも把握できていません。
#ところで、もし仮に2017年も無投票だったら田中氏は2005,2017,2021で3回連続無投票になっていましたが、この場合は任期連続していなくても3期連続無投票の注記をする理解であっていますか?
連続無投票は任期連続が前提と考えていますので、注記不要と考えます。
■下伊那郡阿智村
2002年は無投票かつ1998年が選挙戦なので、自治体レベルで2002-2018の5期連続無投票です。
更新しました。
■北安曇郡松川村
■下高井郡野沢温泉村
どちらも現村長が1期目で直近無投票ではないので注記対象ではないと思いますが、
松川村は2008年の無投票が16年ぶり、野沢温泉村は2005年が選挙戦なので、いずれも連続4期止まりです。
#近所で5期以上可能性ありそうな生坂村も2003年が8年ぶり無投票なので3期連続止まり。
了解しました。ありがとうございます。
なお、野沢温泉村について上野氏の1期就任日は選挙日の「2025.3.30」が正のようです。
確認しました。こちらも更新しました。ただ、そうすると任期満了日も「2029.3.29」となるはずですが、長野県の市町村長の任期満了一覧では「2029.3.28」となっています。1期就任日を前倒ししていると考えるのか、任期満了日は前任と同じになるのか、それとも単なる更新漏れなのか、どうなんでしょう。とりあえあず、「2025.3.30」「2029.3.28」としていますが。
| [114792] 2025年 7月 18日(金)09:00:00 | オーナー グリグリ |
| 第七十二回 全国の現役首長リリース記念 全国の市十番勝負 明日午前9時開始! | |
いよいよ、あと1日後の明日午前9時スタートです。「全国の現役首長リリース」を記念して、第七十二回 全国の市十番勝負です。
多くの方のご参加をお待ちしています。初めての方もお気軽に。みなさん、どうぞお楽しみに。私も楽しみにしています。
多くの方のご参加をお待ちしています。初めての方もお気軽に。みなさん、どうぞお楽しみに。私も楽しみにしています。
| [114790] 2025年 7月 18日(金)00:28:32 | しまなみ さん |
| 返信 > 出身地 | |
[114789] 下総みなと さん
1.隣接市区町村数 2
2.人口密度 9,782.80
3.財政力指数 0.80
これは恐らく、1967年に市となった後2011年にもう片方の問題の市に編入された「あの市」ですね。
その対象である、
1.隣接市区町村数 7
2.人口密度 9,598.85
3.財政力指数 0.932(令和5年度時点)
の市は、実は政令指定都市を除けば人口が2番目に多い市らしいです。
ちなみにこの市はオハイオ州の某市と姉妹都市提携をしていたりしています。
私はこの市に行ったことすらありません。その隣の市でちょっと降りたりはしていますが...
1.隣接市区町村数 2
2.人口密度 9,782.80
3.財政力指数 0.80
これは恐らく、1967年に市となった後2011年にもう片方の問題の市に編入された「あの市」ですね。
その対象である、
1.隣接市区町村数 7
2.人口密度 9,598.85
3.財政力指数 0.932(令和5年度時点)
の市は、実は政令指定都市を除けば人口が2番目に多い市らしいです。
ちなみにこの市はオハイオ州の某市と姉妹都市提携をしていたりしています。
私はこの市に行ったことすらありません。その隣の市でちょっと降りたりはしていますが...
| [114788] 2025年 7月 17日(木)23:20:14 | Amanda さん |
| 返信 | |
[114786]
しまなみさん、流石です。正解は大阪府高槻市です。
新快速で一本で京都にも大阪にも出れるのはとても便利でよく重宝しています。
高槻市はイメージの通りベッドタウンの側面が強いですが、没個性的ではなく歴史の息づく魅力的な街です。
継体天皇陵(非公式)など上代のものや、高槻城や富田の伝統的な酒造りなどの近世のもののように見るべき点はたくさんあります。
ぜひ皆さんも高槻市に足を運んでください。
しまなみさん、流石です。正解は大阪府高槻市です。
新快速で一本で京都にも大阪にも出れるのはとても便利でよく重宝しています。
高槻市はイメージの通りベッドタウンの側面が強いですが、没個性的ではなく歴史の息づく魅力的な街です。
継体天皇陵(非公式)など上代のものや、高槻城や富田の伝統的な酒造りなどの近世のもののように見るべき点はたくさんあります。
ぜひ皆さんも高槻市に足を運んでください。
| [114787] 2025年 7月 17日(木)21:46:14 | ピーくん さん |
| お誕生日 | |
今日は北海道の日でした。おがちゃんさんお誕生日おめでとうございます。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1165143/
こちらの記事に稚内市の新庁舎の開庁日が2025年10月14日を目指しているとの事でした。まあ大体予想出来ます。三連休明けが多いです。まあ梅雨明けも山口県を除く中国地方や四国地方もしれっと訂正されそうです。関東甲信と同じになりそうです。東西で一ヶ月違うと将来気象関係者が疑問になりそうです。梅雨の中休みという。四国地方の早明浦ダムも恵みの雨が降りました。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1165143/
こちらの記事に稚内市の新庁舎の開庁日が2025年10月14日を目指しているとの事でした。まあ大体予想出来ます。三連休明けが多いです。まあ梅雨明けも山口県を除く中国地方や四国地方もしれっと訂正されそうです。関東甲信と同じになりそうです。東西で一ヶ月違うと将来気象関係者が疑問になりそうです。梅雨の中休みという。四国地方の早明浦ダムも恵みの雨が降りました。
| [114786] 2025年 7月 17日(木)19:52:09 | しまなみ さん |
| 返信 > 私の出身地 | |
[114785] Amanda さん
1.人口密度 3301.23
2.財政力指数 0.78(2022)
3.市の木 けやき 市の花 うのはな
なるほど、その市ですか。
ということは、直近2年間に書き込みのある方の内、ここを出身とする方は二人目ですね。
そういえば私自身も今週の日曜日にこの市へ行きましたね。まあ、降りたのはその市名を冠している駅ではないのですが(笑)
また、その駅に行っても結局行ったのは市立図書館でした。(この「駅到着→図書館直行」の流れは結構な場所でやってます)
1.人口密度 3301.23
2.財政力指数 0.78(2022)
3.市の木 けやき 市の花 うのはな
なるほど、その市ですか。
ということは、直近2年間に書き込みのある方の内、ここを出身とする方は二人目ですね。
そういえば私自身も今週の日曜日にこの市へ行きましたね。まあ、降りたのはその市名を冠している駅ではないのですが(笑)
また、その駅に行っても結局行ったのは市立図書館でした。(この「駅到着→図書館直行」の流れは結構な場所でやってます)
(開く)ネタバレになる発言
| [114785] 2025年 7月 17日(木)19:20:57 | Amanda さん |
| 私の出身地 | |
こんばんは、Amandaです。
そういえば[114761]で私の出身地を申し上げていなかったのですが、普通に言うのもつまらないので皆様に当てていただけるとありがたいです。
十番勝負とは形式が違いますが皆様の地理的な推察の勘(?)を磨いてくださると嬉しいです。
1.人口密度 3301.23
2.財政力指数 0.78(2022)
3.市の木 けやき 市の花 うのはな
そういえば[114761]で私の出身地を申し上げていなかったのですが、普通に言うのもつまらないので皆様に当てていただけるとありがたいです。
十番勝負とは形式が違いますが皆様の地理的な推察の勘(?)を磨いてくださると嬉しいです。
1.人口密度 3301.23
2.財政力指数 0.78(2022)
3.市の木 けやき 市の花 うのはな
| [114784] 2025年 7月 17日(木)18:36:43【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 17日(木)20:26:13 | かぱぷう さん |
| メンバー紹介編集担当のお仕事とは | |
拙稿[114701]にて書き込みましたメンバー紹介編集担当者募集の件、立候補いただける方はいらっしゃいますでしょうか?
十番勝負が始まると落書き帳も賑やかになりますので、その前にご検討の一助として、そもそもメンバー紹介編集担当とは果たしてどのような“お仕事”なのか?を少しばかりご案内いたします。
【業務内容】
主に(というかほとんど100%)、落書き帳に投稿を寄せて縁あってメンバー登録された方を紹介するメンバー紹介ページにおいて、メンバーさんの紹介記事(いわゆる紹介文)をしたためるお仕事です。
【歴史】
2002年10月:新規メニューとしてメンバー紹介ページがスタート。この時の紹介文執筆者はオーナーご自身でした。
2002年12月:オーナーからメンバー紹介記事の編集長募集のアナウンス
→流れで初代編集者に深海魚さんが就任。
2003年8月:2代目編集者にまがみさんが就任
2003年10月頃:メンバー登録や紹介記事の在り方について、論議が交わされる
2003年11月:まがみさんに加え、太白さんも編集者に就任
2004年5月:「メンバー紹介編集画面」をリリース。紹介文以外のところをメンバー各々が編集できるようになる
(蛇足… 2005年4月 かぱぷう初書き込み)
2008年8月:オーナーより後任のメンバー紹介記事編集者募集のアナウンス
→これを受け、2008年9月よりおがちゃんさんと私が編集者に就任。(2018年4月より私単独に移行)
【編集ポリシー】
メンバー紹介ページにて
紹介記事は、書き込みからの想像もありますので、内容については、疑義、誇張などがあることをあらかじめご承知おきください。
とありますように、メンバーさんの書き込みを手掛かりに文章を作っていきます。
私が落書き帳を訪問するようになったのは自身の結婚(2003年10月)前後でしたので、最初期のメンバー紹介がどのようなものだったのかは見ておりません。メンバー紹介ページをリリースした際の[4187]オーナー グリグリさんの記事
多少、人物像を独断と偏見で誇張したり想像したりしています。誹謗、中傷に取られ兼ねないちょっと危険な企画ですが、広い心で受け入れていただければ幸いです。
から察すると、オーナーが作ったベースをこれまでの編集者が引き継いで育ててきたものだと思われます。
#このあたり、古参のメンバーさんいかがでしょう??
【効能】
お会いしたことのない方の紹介をするというなんとも不思議な作業ですが、それゆえに想像力が必要で、作成を重ねることで自らの想像力を研鑽できます。それに付随して、空想力(?)や妄想力(??)が深まります。
また、悪いことは書きませんし書けませんので、相手をおもんばかるスキルが身に付きます。
【副反応】
どなたかが自己紹介やエピソードを書き込んだ際に、ついつい「これを紹介文でどのように料理しようかいな」と考えてしまいます。(そして、考えるだけで更新しないのが私の悪い癖…)
[114731]白桃さん
身に余るお言葉をありがとうございます。ただ、私も50代が目前で半年前には五十肩を患い(それは関係ナッシング)、どうも若かりし頃のエネルギーがなくなっているなと感じています。また、当職を引き受けて17年、ちょっと長くなったかなという気もしており、新たな着眼から執筆いただける方がいらっしゃればバトンタッチもありかな…と思った次第です。
みなさま、何卒よろしくお願いいたします。
十番勝負が始まると落書き帳も賑やかになりますので、その前にご検討の一助として、そもそもメンバー紹介編集担当とは果たしてどのような“お仕事”なのか?を少しばかりご案内いたします。
【業務内容】
主に(というかほとんど100%)、落書き帳に投稿を寄せて縁あってメンバー登録された方を紹介するメンバー紹介ページにおいて、メンバーさんの紹介記事(いわゆる紹介文)をしたためるお仕事です。
【歴史】
2002年10月:新規メニューとしてメンバー紹介ページがスタート。この時の紹介文執筆者はオーナーご自身でした。
2002年12月:オーナーからメンバー紹介記事の編集長募集のアナウンス
→流れで初代編集者に深海魚さんが就任。
2003年8月:2代目編集者にまがみさんが就任
2003年10月頃:メンバー登録や紹介記事の在り方について、論議が交わされる
2003年11月:まがみさんに加え、太白さんも編集者に就任
2004年5月:「メンバー紹介編集画面」をリリース。紹介文以外のところをメンバー各々が編集できるようになる
(蛇足… 2005年4月 かぱぷう初書き込み)
2008年8月:オーナーより後任のメンバー紹介記事編集者募集のアナウンス
→これを受け、2008年9月よりおがちゃんさんと私が編集者に就任。(2018年4月より私単独に移行)
【編集ポリシー】
メンバー紹介ページにて
紹介記事は、書き込みからの想像もありますので、内容については、疑義、誇張などがあることをあらかじめご承知おきください。
とありますように、メンバーさんの書き込みを手掛かりに文章を作っていきます。
私が落書き帳を訪問するようになったのは自身の結婚(2003年10月)前後でしたので、最初期のメンバー紹介がどのようなものだったのかは見ておりません。メンバー紹介ページをリリースした際の[4187]オーナー グリグリさんの記事
多少、人物像を独断と偏見で誇張したり想像したりしています。誹謗、中傷に取られ兼ねないちょっと危険な企画ですが、広い心で受け入れていただければ幸いです。
から察すると、オーナーが作ったベースをこれまでの編集者が引き継いで育ててきたものだと思われます。
#このあたり、古参のメンバーさんいかがでしょう??
【効能】
お会いしたことのない方の紹介をするというなんとも不思議な作業ですが、それゆえに想像力が必要で、作成を重ねることで自らの想像力を研鑽できます。それに付随して、空想力(?)や妄想力(??)が深まります。
また、悪いことは書きませんし書けませんので、相手をおもんばかるスキルが身に付きます。
【副反応】
どなたかが自己紹介やエピソードを書き込んだ際に、ついつい「これを紹介文でどのように料理しようかいな」と考えてしまいます。(そして、考えるだけで更新しないのが私の悪い癖…)
[114731]白桃さん
身に余るお言葉をありがとうございます。ただ、私も50代が目前で半年前には五十肩を患い(それは関係ナッシング)、どうも若かりし頃のエネルギーがなくなっているなと感じています。また、当職を引き受けて17年、ちょっと長くなったかなという気もしており、新たな着眼から執筆いただける方がいらっしゃればバトンタッチもありかな…と思った次第です。
みなさま、何卒よろしくお願いいたします。
| [114783] 2025年 7月 17日(木)15:51:58 | 下総みなと さん |
| 誕生日の登録 | |
おがちゃんさん、はじめまして。お誕生日おめでとうございます。
先のグリグリさんの投稿([114779])で、切手のページから誕生日登録ができることを初めて知りました。
まだまだこのサイトの探索が足りない感じがしてなりません。
早速誕生日を登録してみましたが、切手の掲載範囲と誕生日が重なってないために、切手が見られるのは暫く先になりそうですね。
私の母は昔切手集めにハマっていたようで、見せてもらったことがありますが、海外のものが多く日本のものはあまりなかった記憶。
私の誕生日の切手も残しておいて欲しかったです。
先のグリグリさんの投稿([114779])で、切手のページから誕生日登録ができることを初めて知りました。
まだまだこのサイトの探索が足りない感じがしてなりません。
早速誕生日を登録してみましたが、切手の掲載範囲と誕生日が重なってないために、切手が見られるのは暫く先になりそうですね。
私の母は昔切手集めにハマっていたようで、見せてもらったことがありますが、海外のものが多く日本のものはあまりなかった記憶。
私の誕生日の切手も残しておいて欲しかったです。
| [114782] 2025年 7月 17日(木)14:48:26【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 17日(木)15:55:23 | おがちゃん さん |
| 28歳のはじまり | |
[114779] グリグリさん
お祝いありがとうございます。
折角なので「都道府県市区町村」っぽい話をしますと、この1年は都道府県版経県値の上昇がすさまじく、34点加算できました。
全県宿泊まで先は長いですが、既に手元に旅行計画はいくつもありますし、次の1年で全県宿泊にどこまで近づけるか楽しみです。
また今年で28歳になりました。
[107709]にて芦屋市の髙島市長を指して
ついに同年生まれが市長になる"お年頃"になったのか
と書き込みましたが、リリースされたばかりの全国の現役首長一覧【現在年齢順】によれば、27歳だったこの1年間で同学年の大館市の石田市長が就任してました。
ついに同学年市長が誕生するお年頃になりましたが、石田市長は6月生まれなので、まだかろうじて792市全ての市長より若いようです。まあ誇ることでもないのですが!笑
私も市長になる気は無いものの、きちんと参政権を行使しようと思いまして、28歳最初の外出として参院選の期日前投票をしてきました。
十番勝負もあって忙しいタイミングかもしれませんが、特に我々世代の皆さんはしっかり投票しましょうね。
#今回の十番勝負のタイトルにうってつけ...?
お祝いありがとうございます。
折角なので「都道府県市区町村」っぽい話をしますと、この1年は都道府県版経県値の上昇がすさまじく、34点加算できました。
全県宿泊まで先は長いですが、既に手元に旅行計画はいくつもありますし、次の1年で全県宿泊にどこまで近づけるか楽しみです。
また今年で28歳になりました。
[107709]にて芦屋市の髙島市長を指して
ついに同年生まれが市長になる"お年頃"になったのか
と書き込みましたが、リリースされたばかりの全国の現役首長一覧【現在年齢順】によれば、27歳だったこの1年間で同学年の大館市の石田市長が就任してました。
ついに同学年市長が誕生するお年頃になりましたが、石田市長は6月生まれなので、まだかろうじて792市全ての市長より若いようです。まあ誇ることでもないのですが!笑
私も市長になる気は無いものの、きちんと参政権を行使しようと思いまして、28歳最初の外出として参院選の期日前投票をしてきました。
十番勝負もあって忙しいタイミングかもしれませんが、特に我々世代の皆さんはしっかり投票しましょうね。
#今回の十番勝負のタイトルにうってつけ...?
| [114781] 2025年 7月 17日(木)12:26:11【2】訂正年月日 【1】2025年 7月 17日(木)13:08:32 【2】2025年 7月 17日(木)17:49:00 | オーナー グリグリ |
| 年齢不詳情報の表記について | |
[114764]
一覧表については、生年月日が正確にわからなくても、誕生年や誕生年月までの情報や年齢情報などから「65歳?ヶ月」「55歳2-3ヶ月」などの不確定表記も今後検討したいと思います。
こちらについて検討し、年齢不詳者の現在の年齢と就任日年齢を次の表記に統一しました。[114773]の年齢不詳者です。
※年齢情報の注記は氏名欄から現在の年齢欄に変更しました。また、誕生日が年月まで判明している場合は年齢情報は削除しました。
※上記年齢不詳者は、現在の年齢順と就任日年齢順の一覧の対象とはしていません(追記)。
【現在の年齢・就任日年齢の算定方法(表記方法)】
1.リスト右端の推定生年月日 (推定より算定用と言った方が正しいですが) の決め方
(1) 誕生日が年月まで判明している場合 (表の#3#4):誕生日の日付を月末にする (15日案もありですが、次項との兼ね合いで)
(2) 誕生日が不明または年まで判明の場合:年齢情報の現在日付の月日を誕生日月日とし現在年と年齢から誕生年を計算する
2.現在の年齢・就任日年齢の算定
(1) 誕生日が年月まで判明している場合 (表の#3#4):推定生年月日から年齢 (◯年◯ヶ月) を計算し、末尾に "?" を付与
(2) 誕生日が不明または年まで判明の場合:推定生年月日から年齢とプラス1年の年齢幅で表示し、末尾に "?" を付与
[114765]
一覧表の関連項目に記事へのリンクを付与する仕組みを組み込む予定です。
こちらはまだ実現できていません。
対応が遅れましたが、[114775] Nさん、確認をありがとうございます。修正更新済みです。上記一覧表にも反映済みです。
追記:[114780]については別途あらためて対応します。
一覧表については、生年月日が正確にわからなくても、誕生年や誕生年月までの情報や年齢情報などから「65歳?ヶ月」「55歳2-3ヶ月」などの不確定表記も今後検討したいと思います。
こちらについて検討し、年齢不詳者の現在の年齢と就任日年齢を次の表記に統一しました。[114773]の年齢不詳者です。
| # | 都道府県 | 郡 | 市町村 | 首長 | 氏名 | 生年月日 | 現在の年齢 | 就任日年齢 | ※年齢情報 | 推定生年月日 | |
| 1 | 北海道 | 天塩郡 | 遠別町 | 町長 | 國部 雅人 | 53-54歳? | 53-54歳? | 2024.10.15現在 53歳 | 1971.10.15 | ||
| 2 | 北海道 | 礼文郡 | 礼文町 | 町長 | 渋谷 秀勝 | 60-61歳? | 60-61歳? | 2025.7.1現在 60歳 | 1965.7.1 | ||
| 3 | 神奈川県 | 三浦市 | 市長 | 出口 嘉一 | 1982.3.? | 43歳3ヶ月? | 43歳2ヶ月? | 1982.3.31 | |||
| 4 | 山梨県 | 南巨摩郡 | 早川町 | 町長 | 深沢 肇 | 1955.2.? | 70歳4ヶ月? | 69歳8ヶ月? | 1955.2.28 | ||
| 5 | 山梨県 | 南都留郡 | 西桂町 | 町長 | 堀内 達也 | 70-71歳? | 70-71歳? | 2024.11.11現在 70歳 | 1954.11.11 | ||
| 6 | 長野県 | 木曽郡 | 大桑村 | 村長 | 坂家 重吉 | 72-73歳? | 72-73歳? | 2024.9.24現在 72歳 | 1952.9.24 | ||
| 7 | 愛知県 | 西春日井郡 | 豊山町 | 町長 | 服部 正樹 | 1965.?.? | 59-60歳? | 51-52歳? | 2024.11.11現在 59歳 | 1965.11.11 | |
| 8 | 奈良県 | 吉野郡 | 十津川村 | 村長 | 玉置 広之 | 1985.?.? | 40-41歳? | 40-41歳? | 2025.4.20現在 40歳 | 1985.4.20 | |
| 9 | 愛媛県 | 南宇和郡 | 愛南町 | 町長 | 中村 維伯 | 1958.?.? | 65-66歳? | 65-66歳? | 2024.10.28現在 65歳 | 1959.10.28 | |
| 10 | 高知県 | 安芸郡 | 田野町 | 町長 | 坂本 正徳 | 60-61歳? | 60-61歳? | 2025.4.22現在 60歳 | 1965.4.22 | ||
| 11 | 高知県 | 安芸郡 | 芸西村 | 村長 | 松本 巧 | 56-57歳? | 56-57歳? | 2024.10.23現在 56歳 | 1968.10.23 | ||
| 12 | 高知県 | 長岡郡 | 大豊町 | 町長 | 下村 賢彦 | 56-57歳? | 56-57歳? | 2024.11.25現在 56歳 | 1968.11.25 | ||
| 13 | 福岡県 | 田川郡 | 赤村 | 村長 | 中村 孝 | 51-52歳? | 51-52歳? | 2025.6.29現在 51歳 | 1974.6.29 | ||
| 14 | 長崎県 | 北松浦郡 | 佐々町 | 町長 | 浜野 亘 | 1955.?.? | 69-70歳? | 68-69歳? | 2025.6.16現在 69歳 | 1956.6.16 | |
| 15 | 大分県 | 東国東郡 | 姫島村 | 村長 | 大海 靖治 | 60-61歳? | 60-61歳? | 2024.10.30現在 60歳 | 1964.10.30 |
※上記年齢不詳者は、現在の年齢順と就任日年齢順の一覧の対象とはしていません(追記)。
【現在の年齢・就任日年齢の算定方法(表記方法)】
1.リスト右端の推定生年月日 (推定より算定用と言った方が正しいですが) の決め方
(1) 誕生日が年月まで判明している場合 (表の#3#4):誕生日の日付を月末にする (15日案もありですが、次項との兼ね合いで)
(2) 誕生日が不明または年まで判明の場合:年齢情報の現在日付の月日を誕生日月日とし現在年と年齢から誕生年を計算する
2.現在の年齢・就任日年齢の算定
(1) 誕生日が年月まで判明している場合 (表の#3#4):推定生年月日から年齢 (◯年◯ヶ月) を計算し、末尾に "?" を付与
(2) 誕生日が不明または年まで判明の場合:推定生年月日から年齢とプラス1年の年齢幅で表示し、末尾に "?" を付与
[114765]
一覧表の関連項目に記事へのリンクを付与する仕組みを組み込む予定です。
こちらはまだ実現できていません。
対応が遅れましたが、[114775] Nさん、確認をありがとうございます。修正更新済みです。上記一覧表にも反映済みです。
追記:[114780]については別途あらためて対応します。
| [114780] 2025年 7月 17日(木)11:32:59【2】訂正年月日 【1】2025年 7月 17日(木)11:41:35 【2】2025年 7月 17日(木)11:43:41 | N さん |
| 要確認情報など2 | |
[114773]グリグリさん
十番勝負で間があきそうなので…[114775]の続きです。
まず、以下の2つは「要確認情報」に含めなくてよいかの確認です。
私の方で選挙ドットコムに載っていない過去選挙分で無投票か否かが調べきれませんでした。
■九戸郡軽米町
2007年以前の軽米町長選挙の結果がどうだったのか把握されていますでしょうか。
2007年は無投票だったようですが、2003年以前が無投票でない根拠はありますでしょうか。
#年表から、2003年、2000年、1996年、1992年…に選挙実施されていそうですが、無投票かどうかがわかりません。
■黒川郡大郷町
2009年以前の大郷町長選挙の結果がどうだったのか把握されていますでしょうか。
少なくとも2005年は無投票のようですが、1-3期(1997-2005)連続無投票にならない根拠はありますでしょうか。またさらに遡って自治体レベルで5期以上無投票の可能性もないでしょうか。
#1997年は前任の退職?に伴う選挙。順当に任期満了ならば1994年、1990年にも選挙実施されているはず。
#ところで、もし仮に2017年も無投票だったら田中氏は2005,2017,2021で3回連続無投票になっていましたが、この場合は任期連続していなくても3期連続無投票の注記をする理解であっていますか?
次に
5期以上無投票期間の可能性は?
の長野県3村について。
#東海三県+長野・滋賀・福井は中日新聞に2000年代の選挙データが概ね残ってます。
■下伊那郡阿智村
2002年は無投票かつ1998年が選挙戦なので、自治体レベルで2002-2018の5期連続無投票です。
■北安曇郡松川村
■下高井郡野沢温泉村
どちらも現村長が1期目で直近無投票ではないので注記対象ではないと思いますが、
松川村は2008年の無投票が16年ぶり、野沢温泉村は2005年が選挙戦なので、いずれも連続4期止まりです。
#近所で5期以上可能性ありそうな生坂村も2003年が8年ぶり無投票なので3期連続止まり。
なお、野沢温泉村について上野氏の1期就任日は選挙日の「2025.3.30」が正のようです。
野沢温泉村Facebookより、
令和7年3月28日に任期満了となる村長と、令和7年3月31日に任期満了となる村議会議員の選挙期日を、令和7年3月30日(日)と決定しました。
とありましたので、前任は2025.3.28までの任期でしたが議会議員選挙と選挙日を合わせた都合上、現任の任期が2025.3.30からになったようです。
十番勝負で間があきそうなので…[114775]の続きです。
まず、以下の2つは「要確認情報」に含めなくてよいかの確認です。
私の方で選挙ドットコムに載っていない過去選挙分で無投票か否かが調べきれませんでした。
■九戸郡軽米町
2007年以前の軽米町長選挙の結果がどうだったのか把握されていますでしょうか。
2007年は無投票だったようですが、2003年以前が無投票でない根拠はありますでしょうか。
#年表から、2003年、2000年、1996年、1992年…に選挙実施されていそうですが、無投票かどうかがわかりません。
■黒川郡大郷町
2009年以前の大郷町長選挙の結果がどうだったのか把握されていますでしょうか。
少なくとも2005年は無投票のようですが、1-3期(1997-2005)連続無投票にならない根拠はありますでしょうか。またさらに遡って自治体レベルで5期以上無投票の可能性もないでしょうか。
#1997年は前任の退職?に伴う選挙。順当に任期満了ならば1994年、1990年にも選挙実施されているはず。
#ところで、もし仮に2017年も無投票だったら田中氏は2005,2017,2021で3回連続無投票になっていましたが、この場合は任期連続していなくても3期連続無投票の注記をする理解であっていますか?
次に
5期以上無投票期間の可能性は?
の長野県3村について。
#東海三県+長野・滋賀・福井は中日新聞に2000年代の選挙データが概ね残ってます。
■下伊那郡阿智村
2002年は無投票かつ1998年が選挙戦なので、自治体レベルで2002-2018の5期連続無投票です。
■北安曇郡松川村
■下高井郡野沢温泉村
どちらも現村長が1期目で直近無投票ではないので注記対象ではないと思いますが、
松川村は2008年の無投票が16年ぶり、野沢温泉村は2005年が選挙戦なので、いずれも連続4期止まりです。
#近所で5期以上可能性ありそうな生坂村も2003年が8年ぶり無投票なので3期連続止まり。
なお、野沢温泉村について上野氏の1期就任日は選挙日の「2025.3.30」が正のようです。
野沢温泉村Facebookより、
令和7年3月28日に任期満了となる村長と、令和7年3月31日に任期満了となる村議会議員の選挙期日を、令和7年3月30日(日)と決定しました。
とありましたので、前任は2025.3.28までの任期でしたが議会議員選挙と選挙日を合わせた都合上、現任の任期が2025.3.30からになったようです。
| [114779] 2025年 7月 17日(木)07:33:49 | オーナー グリグリ |
| Happy Birthday Ogachan! | |
| [114778] 2025年 7月 17日(木)00:22:14 | YT さん |
| 明治の大合併直後の各酒井村の人口 | |
[114771] 白桃 さん
逆に「酒井」という自治体名は今までに存在していないのですね。
[114777] MIさん
これらの町村すべては町村制で合併などにより別名となり、その後も一つとして復活していないということになります。
以前[87941]でも紹介しましたが、『明治二十四年 徴発物件一覧表』の方に、明治23年(1890年)12月31日付の大字別人口がまとまっております。そこで今回MIさんによって紹介された酒井村の、明治の大合併直後の1890年の人口をまとめてみたところ、以下の通りとなりました。
残念ながら福井県の小浜町に関しては、大字別人口の記載がありませんでした・・・が、『新版 角川日本地名大辞典』の方に明治19年(1886年)の人口の情報が載っていたので、参考までに上に掲載します。なお「小浜酒井町」は歴史ある名前ではなく、『大正四年 福井県遠敷郡小浜町統計書』によると、明治7年(1873年)に区割整理の過程で、片原町と質屋町・松寺小路の各一部が合併して春日町となり、さらに明治13年(1880年)に春日町を酒井町に改名したとあります。この時作られた新地名はすべて全国の有名な神社に由来するとされ、どうも春日町の方は、奈良の春日大社に由来するらしいです。それが酒井町に改名されたのですが、こちらもどうも小浜藩主酒井家から取った名前のようです。つまり小浜の酒井町は廃藩置県前からの由緒ある地名ではありません。
というわけで、明治22年当時全国にあった酒井町の内、もっとも人口が少なかったのは現千葉県柏市の酒井根の27人、人口が一番多かったのは、現石川県羽咋市の酒井町826人。ただし現佐賀県鳥栖市の酒井西町・酒井東町の合計1635人は隣接しており、ここが藩政村時代の最大の酒井地区でしょう。
逆に「酒井」という自治体名は今までに存在していないのですね。
[114777] MIさん
これらの町村すべては町村制で合併などにより別名となり、その後も一つとして復活していないということになります。
以前[87941]でも紹介しましたが、『明治二十四年 徴発物件一覧表』の方に、明治23年(1890年)12月31日付の大字別人口がまとまっております。そこで今回MIさんによって紹介された酒井村の、明治の大合併直後の1890年の人口をまとめてみたところ、以下の通りとなりました。
| 府県 | 旧国 | 郡名 | 町村 | 大字(徴発物件一覧表での記載) | 戸数 | 男 | 女 | 合計 | 備考 |
| 山形県 | 羽後国 | 飽海郡 | 西荒瀬村 | 大字 酒井新田 | 93 | 386 | 382 | 768 | |
| 福島県 | 磐城国 | 菊多郡 | 窪田村 | 大字 酒井 | 79 | 242 | 216 | 458 | |
| 福島県 | 磐城国 | 標葉郡 | 大堀村 | 大字 酒井 | 45 | 188 | 213 | 401 | |
| 埼玉県 | 武蔵国 | 北葛飾郡 | 戸ヶ崎村 | 大字 酒井 | 27 | 119 | 92 | 211 | |
| 千葉県 | 下総国 | 東葛飾郡 | 土村 | 大字 酒井根 | 5 | 8 | 19 | 27 | |
| 神奈川県 | 相模国 | 大住郡 | 相川村 | 大字 酒井 | 92 | 276 | 259 | 535 | |
| 石川県 | 能登国 | 鹿島郡 | 余喜村 | 大字 酒井 | 145 | 435 | 391 | 826 | |
| 福井県 | 若狭国 | 遠敷郡 | 小浜町 | 【小浜酒井町】 | 75 | 182 | 174 | 356 | ※明治19年(1886年) |
| 愛知県 | 三河国 | 幡豆郡 | 荻原村 | 大字 酒井 | 48 | 110 | 114 | 224 | |
| 兵庫県 | 摂津国 | 川辺郡 | 神津村 | 口酒井村 | 40 | 106 | 110 | 216 | |
| 兵庫県 | 摂津国 | 川辺郡 | 高平村 | 酒井村 | 52 | 106 | 101 | 207 | |
| 福岡県 | 筑後国 | 上妻郡 | 三河村 | 大字 酒井田 | 103 | 277 | 254 | 531 | |
| 佐賀県 | 肥前国 | 基肄郡 | 基里村 | 大字 酒井西 | 142 | 424 | 399 | 823 | |
| 佐賀県 | 肥前国 | 基肄郡 | 基里村 | 大字 酒井東 | 136 | 389 | 423 | 812 | |
| 大分県 | 豊後国 | 大野郡 | 養老村 | 大字 酒井寺 | 65 | 136 | 141 | 277 |
残念ながら福井県の小浜町に関しては、大字別人口の記載がありませんでした・・・が、『新版 角川日本地名大辞典』の方に明治19年(1886年)の人口の情報が載っていたので、参考までに上に掲載します。なお「小浜酒井町」は歴史ある名前ではなく、『大正四年 福井県遠敷郡小浜町統計書』によると、明治7年(1873年)に区割整理の過程で、片原町と質屋町・松寺小路の各一部が合併して春日町となり、さらに明治13年(1880年)に春日町を酒井町に改名したとあります。この時作られた新地名はすべて全国の有名な神社に由来するとされ、どうも春日町の方は、奈良の春日大社に由来するらしいです。それが酒井町に改名されたのですが、こちらもどうも小浜藩主酒井家から取った名前のようです。つまり小浜の酒井町は廃藩置県前からの由緒ある地名ではありません。
というわけで、明治22年当時全国にあった酒井町の内、もっとも人口が少なかったのは現千葉県柏市の酒井根の27人、人口が一番多かったのは、現石川県羽咋市の酒井町826人。ただし現佐賀県鳥栖市の酒井西町・酒井東町の合計1635人は隣接しており、ここが藩政村時代の最大の酒井地区でしょう。
| [114777] 2025年 7月 16日(水)13:05:00 | MI さん |
| 酒井村 | |
[114771] 白桃 さん
逆に「酒井」という自治体名は今までに存在していないのですね。
意外な感じですが、たしかに変遷情報で検索しても「抽出件数:0 件」ですね。そこで1889年の市制町村制施行直前の自作データを調べたところ、「酒井」を含む町村がいくつか見つかったのでご紹介します。
これらの町村すべては町村制で合併などにより別名となり、その後も一つとして復活していないということになります。
#ずいぶんと久しぶりだなあと思いましたら、1年と5ヶ月ぶりの書き込みでした。
逆に「酒井」という自治体名は今までに存在していないのですね。
意外な感じですが、たしかに変遷情報で検索しても「抽出件数:0 件」ですね。そこで1889年の市制町村制施行直前の自作データを調べたところ、「酒井」を含む町村がいくつか見つかったのでご紹介します。
| 府県 | 郡 | 町村 | |
| 山形県 | 飽海郡 | 酒井新田村 | |
| 福島県 | 菊多郡 | 酒井村 | |
| 福島県 | 標葉郡 | 酒井村 | |
| 埼玉県 | 北葛飾郡 | 酒井村 | |
| 千葉県 | 東葛飾郡 | 酒井根村 | |
| 神奈川県 | 大住郡 | 酒井村 | |
| 石川県 | 鹿島郡 | 酒井村 | |
| 福井県 | 遠敷郡 | 小浜酒井町 | |
| 愛知県 | 幡豆郡 | 酒井村 | |
| 兵庫県 | 川辺郡 | 口酒井村 | 酒井村 |
| 福岡県 | 上妻郡 | 酒井田村 | |
| 佐賀県 | 基肄郡 | 酒井西村 | 酒井東村 |
| 大分県 | 大野郡 | 酒井寺村 |
#ずいぶんと久しぶりだなあと思いましたら、1年と5ヶ月ぶりの書き込みでした。
| [114776] 2025年 7月 15日(火)22:31:38 | にまん さん |
| 情報公開条例 | |
[114751] 未開人さん
[114764] オーナー グリグリさん
情報公開の根拠として、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が挙げられていますが、この法律は「国の行政機関」を対象としたものですので、地方自治体は対象外となっています。(ちなみに、行政機関でない国会や裁判所も対象外)
ですので、自治体の情報公開の根拠は各自治体の「情報公開条例」となります。(東京都の場合東京都情報公開条例)
基本的には、法律と各自治体の条例で大きな差はないと思われ、「個人に関する情報」は不開示情報とされていると思います。
ただ、例外として「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報)は不開示情報ではないとされていて、これに該当するかどうかの判断は、自治体によって取り扱いに差がでそうです。
[114764] オーナー グリグリさん
情報公開の根拠として、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が挙げられていますが、この法律は「国の行政機関」を対象としたものですので、地方自治体は対象外となっています。(ちなみに、行政機関でない国会や裁判所も対象外)
ですので、自治体の情報公開の根拠は各自治体の「情報公開条例」となります。(東京都の場合東京都情報公開条例)
基本的には、法律と各自治体の条例で大きな差はないと思われ、「個人に関する情報」は不開示情報とされていると思います。
ただ、例外として「慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報)は不開示情報ではないとされていて、これに該当するかどうかの判断は、自治体によって取り扱いに差がでそうです。
| [114775] 2025年 7月 15日(火)21:57:49 | N さん |
| 要確認情報など | |
[114773]グリグリさん
東松島市が「1-2期」のままですね。色麻町の注記をコピペでよいかと…
要確認情報のまとめです。
とりあえず把握している範囲で。
■雄勝郡東成瀬村
前村長の1期目(1998)および2期目(2002)は選挙戦のようなので連続5期で確定です。
■西村山郡朝日町
2004年は選挙戦なので連続5期で確定です。
■南巨摩郡早川町
1955年2月生まれまでは確定です。
■西春日井郡豊山町
1965年生まれは確定でよいと思います。
■丹波篠山市
選挙事由についてはWikipediaの記載を信頼してよいと思います。3期目が辞職→再選で任期が継続する形(辞職後選挙の3か月後に3期目の任期満了)ですので、
任期5期、当選6回
の理解で正しいと思います。
■南宇和郡愛南町
1958年生まれは確定です。
東松島市が「1-2期」のままですね。色麻町の注記をコピペでよいかと…
要確認情報のまとめです。
とりあえず把握している範囲で。
■雄勝郡東成瀬村
前村長の1期目(1998)および2期目(2002)は選挙戦のようなので連続5期で確定です。
■西村山郡朝日町
2004年は選挙戦なので連続5期で確定です。
■南巨摩郡早川町
1955年2月生まれまでは確定です。
■西春日井郡豊山町
1965年生まれは確定でよいと思います。
■丹波篠山市
選挙事由についてはWikipediaの記載を信頼してよいと思います。3期目が辞職→再選で任期が継続する形(辞職後選挙の3か月後に3期目の任期満了)ですので、
任期5期、当選6回
の理解で正しいと思います。
■南宇和郡愛南町
1958年生まれは確定です。
| [114774] 2025年 7月 15日(火)21:19:07 | ピーくん さん |
| 台風 | |
札幌管区気象台は15日、台風5号が同日午前2時ごろ、北海道襟裳岬付近に上陸したと発表した。道内への台風上陸は2016年以来。進路や発達の程度により、警報級の大雨になる恐れがあるといい、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に注意するよう呼び掛けている。
北海道に台風上陸は統計開始から7個目。徳島県と同じです。
グリグリさま
台風上陸ランキング更新よろしくお願いします。
北海道に台風上陸は統計開始から7個目。徳島県と同じです。
グリグリさま
台風上陸ランキング更新よろしくお願いします。
| [114773] 2025年 7月 15日(火)20:23:19【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 15日(火)20:28:12 | オーナー グリグリ |
| Re3:全国の現役首長一覧への指摘事項 | |
[114772] Nさん
対応内容確認しました。再訂正いただきたいポイントが何点か。
再確認、お手数おかけしてすみません。ありがとうございます。確認し修正しました。
[114765]
整理して不確定情報(要確認情報)として別途提示します。
要確認情報のまとめです。可能性があるものを広げています。
?:6期以上連続無投票の可能性は?
秋田県 東成瀬村、山形県 朝日町、島根県 西ノ島町、福岡県 宇美町
?:5期以上無投票期間の可能性は?
長野県 阿智村 松川村 野沢温泉村、奈良県 安堵町 御杖村、広島県 神石高原町、徳島県 上勝町、高知県 北川村 馬路村
?:丹波篠山市 酒井市長:任期5期、当選6回で正しいか?
?:和歌山県太地町 三軒町長:1-3期も無投票の可能性はないか?
次表は、[114699] で記載した生年月日不明者リストの更新版です。現時点で15名が不明になっています。
年齢情報は、一覧表の氏名に注記として付けました。
対応内容確認しました。再訂正いただきたいポイントが何点か。
再確認、お手数おかけしてすみません。ありがとうございます。確認し修正しました。
[114765]
整理して不確定情報(要確認情報)として別途提示します。
要確認情報のまとめです。可能性があるものを広げています。
?:6期以上連続無投票の可能性は?
秋田県 東成瀬村、山形県 朝日町、島根県 西ノ島町、福岡県 宇美町
?:5期以上無投票期間の可能性は?
長野県 阿智村 松川村 野沢温泉村、奈良県 安堵町 御杖村、広島県 神石高原町、徳島県 上勝町、高知県 北川村 馬路村
?:丹波篠山市 酒井市長:任期5期、当選6回で正しいか?
?:和歌山県太地町 三軒町長:1-3期も無投票の可能性はないか?
次表は、[114699] で記載した生年月日不明者リストの更新版です。現時点で15名が不明になっています。
| No. | 都道府県 | 郡 | 市町村 | 首長 | 氏名 | 氏名読み | 生年月日 | 年齢情報 |
| 1 | 北海道 | 天塩郡 | 遠別町 | 町長 | 國部 雅人 | くにべ まさひと | 2024.10.15現在 53歳 | |
| 2 | 北海道 | 礼文郡 | 礼文町 | 町長 | 渋谷 秀勝 | しぶや ひでかつ | 2025.7.1現在 60歳 | |
| 3 | 神奈川県 | 三浦市 | 市長 | 出口 嘉一 | でぐち かいち | 1982.3.? | 43歳?ヶ月 | |
| 4 | 山梨県 | 南巨摩郡 | 早川町 | 町長 | 深沢 肇 | ふかさわ はじめ | 2024.10.29現在 69歳 | |
| 5 | 山梨県 | 南都留郡 | 西桂町 | 町長 | 堀内 達也 | ほりうち たつや | 2024.11.11現在 70歳 | |
| 6 | 長野県 | 木曽郡 | 大桑村 | 村長 | 坂家 重吉 | さかや しげよし | 2024.9.24現在 72歳 | |
| 7 | 愛知県 | 西春日井郡 | 豊山町 | 町長 | 服部 正樹 | はっとり まさき | 2024.11.11現在 59歳 | |
| 8 | 奈良県 | 吉野郡 | 十津川村 | 村長 | 玉置 広之 | たまき ひろゆき | 1985.?.? | 2025.4.20現在 40歳 |
| 9 | 愛媛県 | 南宇和郡 | 愛南町 | 町長 | 中村 維伯 | なかむら まさのり | 2024.10.28現在 65歳 | |
| 10 | 高知県 | 安芸郡 | 田野町 | 町長 | 坂本 正徳 | さかもと まさのり | 2025.4.22現在 60歳 | |
| 11 | 高知県 | 安芸郡 | 芸西村 | 村長 | 松本 巧 | まつもと たくみ | 2024.10.23現在 56歳 | |
| 12 | 高知県 | 長岡郡 | 大豊町 | 町長 | 下村 賢彦 | しもむら やすひこ | 2024.11.25現在 56歳 | |
| 13 | 福岡県 | 田川郡 | 赤村 | 村長 | 中村 孝 | なかむら たかし | 2025.6.29現在 51歳 | |
| 14 | 長崎県 | 北松浦郡 | 佐々町 | 町長 | 浜野 亘 | はまの わたる | 1955.?.? | 2025.6.16現在 69歳 |
| 15 | 大分県 | 東国東郡 | 姫島村 | 村長 | 大海 靖治 | だいかい やすはる | 2024.10.30現在 60歳 |
| [114772] 2025年 7月 15日(火)14:31:23【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 15日(火)14:34:32 | N さん |
| Re2:全国の現役首長一覧への指摘事項 | |
[114765]グリグリさん
ご対応ありがとうございます。
対応内容確認しました。再訂正いただきたいポイントが何点か。
■東松島市
注記が消えています。現在まで2期連続なので注記は残す必要があります。(2-3期 現在まで2期連続無投票)
■香取郡東庄町
白糠町と若干書き方が違っていますね。「2-4期 "3期"連続無投票」とすべきでしょうか。
■安房郡鋸南町
[114755]の書き方が悪かったですが、7期目現在の任期満了日は「2027.4.26」のまま訂正いただく必要はありませんでした。
推測通り厚海氏の2期目以降がすべて統一地方選挙だとすると、イレギュラーが無い限り任期は以下の通りになります。
厚海氏・2期目:1979.4.22(1979年選挙日)-1983.4.21
厚海氏・3期目:1983.4.24(1983年選挙日)-1987.4.23
富永氏・1期目:1987.4.26(1987年選挙日)-1991.4.25
富永氏・2期目:1991.4.26-1995.4.25
富永氏・3期目:1995.4.26-1999.4.25
白石氏・1期目:1999.4.26-2003.4.25
白石氏・2期目:2003.4.27(2003年選挙日)-2007.4.26
白石氏・3期目:2007.4.27-2011.4.26
…
白石氏・7期目:2023.4.27-2027.4.26
となっていて、2003年を境に起算日の日付が変わっている可能性が高い、ということが指摘したかったポイントです。
統一地方選挙の年の4月が任期開始日・満了日になっているケースは単純に4年ごとに遡るのではなく、選挙日に合わせた補正が必要になってくるケースが多々です。
例えば今現在任期満了日が2027.4.22になっている自治体(2019年、2023年の統一地方選挙日が任期開始日になっている自治体)は、次回2027年の統一地方選挙は日の並び的に2027.4.25になると思いますので、この日程であれば次の首長の任期満了日は2031.4.22ではなく2031.4.24になるということです。
ついでに1件だけ新たな指摘も。
■今立郡池田町
現在8期連続の注記がありますが、前任の1996年も無投票です。そのため自治体レベルでは9期連続無投票になります。
※1997年の杉本氏新任時の選挙が逝去に伴う選挙のため前任の最終期は4年を満了していません。また1992年は選挙戦です。
ご対応ありがとうございます。
対応内容確認しました。再訂正いただきたいポイントが何点か。
■東松島市
注記が消えています。現在まで2期連続なので注記は残す必要があります。(2-3期 現在まで2期連続無投票)
■香取郡東庄町
白糠町と若干書き方が違っていますね。「2-4期 "3期"連続無投票」とすべきでしょうか。
■安房郡鋸南町
[114755]の書き方が悪かったですが、7期目現在の任期満了日は「2027.4.26」のまま訂正いただく必要はありませんでした。
推測通り厚海氏の2期目以降がすべて統一地方選挙だとすると、イレギュラーが無い限り任期は以下の通りになります。
厚海氏・2期目:1979.4.22(1979年選挙日)-1983.4.21
厚海氏・3期目:1983.4.24(1983年選挙日)-1987.4.23
富永氏・1期目:1987.4.26(1987年選挙日)-1991.4.25
富永氏・2期目:1991.4.26-1995.4.25
富永氏・3期目:1995.4.26-1999.4.25
白石氏・1期目:1999.4.26-2003.4.25
白石氏・2期目:2003.4.27(2003年選挙日)-2007.4.26
白石氏・3期目:2007.4.27-2011.4.26
…
白石氏・7期目:2023.4.27-2027.4.26
となっていて、2003年を境に起算日の日付が変わっている可能性が高い、ということが指摘したかったポイントです。
統一地方選挙の年の4月が任期開始日・満了日になっているケースは単純に4年ごとに遡るのではなく、選挙日に合わせた補正が必要になってくるケースが多々です。
例えば今現在任期満了日が2027.4.22になっている自治体(2019年、2023年の統一地方選挙日が任期開始日になっている自治体)は、次回2027年の統一地方選挙は日の並び的に2027.4.25になると思いますので、この日程であれば次の首長の任期満了日は2031.4.22ではなく2031.4.24になるということです。
ついでに1件だけ新たな指摘も。
■今立郡池田町
現在8期連続の注記がありますが、前任の1996年も無投票です。そのため自治体レベルでは9期連続無投票になります。
※1997年の杉本氏新任時の選挙が逝去に伴う選挙のため前任の最終期は4年を満了していません。また1992年は選挙戦です。
| [114771] 2025年 7月 15日(火)09:23:35 | 白桃 さん |
| フランキー堺 | |
[114769] YT さん
つまり秀吉時代以降、江戸時代、明治時代を通じて堺は大阪の郊外に組み込まれていると解釈されてしまっているのです。
堺が登場しない理由のほか、私の疑問に対して丁寧な説明をしていただき、有難うございます。
エラい昔に、海外に「大阪都」構想が漏れていたとは…(笑)。
ところで、バークレー(バークリー)と堺は姉妹都市なんですね。奇妙な縁ですね。
以下、脱線します。
「堺」と「坂井」は地名にも人名にも見かけますが、「境」という苗字の方に出会ったことがありません。逆に「酒井」という自治体名は今までに存在していないのですね。
[114761]Amanda さん
こんにちは、Amandaです。
経県値と白桃さんの都会度についての記事に惹かれて書き込みをするに至りました。
♪ようこそ ここへ クック クック…
50年前、私の下宿にはこの歌を歌った方のポスターが貼られていました。(;'∀')
私の「都会度」に惹かれて…、こんな嬉しい事・・・”淳子、カンゲキ!”
チャットGPTには「しろもも市町村人口研究所」となっていましたが、「ハクトウ市町村人口研究所所長」です。因みに、還暦を13年過ぎた男性です。が、精神年齢は♪美しい十代・・・ときどき、いや、頻繁に、しょうもない、わけのわからん事を発すると思いますが、今後とも宜しくお願いいたします。
つまり秀吉時代以降、江戸時代、明治時代を通じて堺は大阪の郊外に組み込まれていると解釈されてしまっているのです。
堺が登場しない理由のほか、私の疑問に対して丁寧な説明をしていただき、有難うございます。
エラい昔に、海外に「大阪都」構想が漏れていたとは…(笑)。
ところで、バークレー(バークリー)と堺は姉妹都市なんですね。奇妙な縁ですね。
以下、脱線します。
「堺」と「坂井」は地名にも人名にも見かけますが、「境」という苗字の方に出会ったことがありません。逆に「酒井」という自治体名は今までに存在していないのですね。
[114761]Amanda さん
こんにちは、Amandaです。
経県値と白桃さんの都会度についての記事に惹かれて書き込みをするに至りました。
♪ようこそ ここへ クック クック…
50年前、私の下宿にはこの歌を歌った方のポスターが貼られていました。(;'∀')
私の「都会度」に惹かれて…、こんな嬉しい事・・・”淳子、カンゲキ!”
チャットGPTには「しろもも市町村人口研究所」となっていましたが、「ハクトウ市町村人口研究所所長」です。因みに、還暦を13年過ぎた男性です。が、精神年齢は♪美しい十代・・・ときどき、いや、頻繁に、しょうもない、わけのわからん事を発すると思いますが、今後とも宜しくお願いいたします。
| [114770] 2025年 7月 15日(火)03:00:43 | 下総みなと さん |
| 自治体首長の更新など | |
時々、「どこの市区町村長選挙するのかな」と思い、地方選挙情報のページを見るのですが、毎週のように複数市町村が選挙をやっていて、同一候補が当選した場合は良いのですが、変わったときはまた生年月日の更新が大変ですね。。。
また、幾つかの市町村では問い合わせの結果、「個人情報保護の観点」から生年月日を非公開とする自治体がある一方で、年齢どころか市町村長の住所をHPに掲載する自治体があるなど、地域によって様々だなぁと思いました。
[114766] グリグリさん
それにしても地理に興味を持つのは男性が多い傾向があるようですが、何故でしょうね。
私自身、地理に関連するコミュニティに入っていますが、例に漏れず私含め皆男性で、逆に女性は今までに1人いたかどうか怪しいくらい希少ですね...
そのコミュニティに2、300人程度いると考えると、より少ないと思えます。
私自身マニアックな趣味には男性が多いという偏見があるのですが、地理もそういった感じなのでしょうかね?
鉄道や車好きにも、女性より男性の方が多いイメージがあります。
奥深い、所謂「ロマン」を求めているのでしょうか。
また、幾つかの市町村では問い合わせの結果、「個人情報保護の観点」から生年月日を非公開とする自治体がある一方で、年齢どころか市町村長の住所をHPに掲載する自治体があるなど、地域によって様々だなぁと思いました。
[114766] グリグリさん
それにしても地理に興味を持つのは男性が多い傾向があるようですが、何故でしょうね。
私自身、地理に関連するコミュニティに入っていますが、例に漏れず私含め皆男性で、逆に女性は今までに1人いたかどうか怪しいくらい希少ですね...
そのコミュニティに2、300人程度いると考えると、より少ないと思えます。
私自身マニアックな趣味には男性が多いという偏見があるのですが、地理もそういった感じなのでしょうかね?
鉄道や車好きにも、女性より男性の方が多いイメージがあります。
奥深い、所謂「ロマン」を求めているのでしょうか。
| [114769] 2025年 7月 15日(火)01:36:11【2】訂正年月日 【1】2025年 7月 15日(火)01:47:14 【2】2025年 7月 15日(火)01:51:44 | YT さん |
| Osaka-Sakai | |
[114763] 白桃 さん
③5万人をも超えていたと思われる堺が登場しないのは、どうしても腑に落ちません。
実は[114754]を投稿した際、堺に関する注意書きを足そうか悩みましたが、あっさり気付くとは…
"Four Thousand Years of Urban Growth"の"Osaka"の項目によると、
1590: Sakai was built in to Osaka (Wald. p. 56)
と書かれています。つまり秀吉時代以降、江戸時代、明治時代を通じて堺は大阪の郊外に組み込まれていると解釈されてしまっているのです。実際、江戸時代後半には大坂三郷の周辺の曽根崎、難波、天王寺、上下福島、南北平野などといった町続きが形成され、大坂の郊外が広がっていますが、多分堺まで市街地が接続するのは大正時代末期以降でしょう(ちゃんと検証していませんが)。
なおここに登場する文献は、Royal Wald著の "The Development of Osaka during the Sixteenth Century." University of California, Berkeley (1947年)なる博士論文?のようです。
②北海道の福山(松前)が明治期に北海道有数の「都会」?であったことは承知していますが、1898年に8,000人強の人口が35,000人になるとは信じがたい。
"Four Thousand Years of Urban Growth"の"Matsumaye (Fukuyama)"の項目によると、
c. 1840: 50,000 Sometime before 1857 (Gazetteer of World)
1850: 65,000
1864: 65,000 (Rosny. p. 79)
ここに登場する文献は、1850年~1856年に出版された"Gazetteer of the Worldと、1864年に出版されたLéon de Rosny著 "Etudes asiatiques de géographie et d'histoire"で、当時エディンバラやパリで出版された同時代的な本を引用しつつ、1840年頃のMatsumaye (Fukuyama)の人口を50,000人、1864年の人口を65,000人としています。この数字は明白に誤っており、5万人や6万5千人というのはどちらかというと松前藩支配下、あるいは蝦夷地全域の和人、アイヌ人の調査人口総数に匹敵するものです。松前藩の福山城下町のみのより正確な人口は、近世墓と人口史料による社会構造と人口変動に関する基礎的研究の報告書の方に詳しく纏められており、嘉永3年(1850年)の福山城下の人口は、武家・寺社人口を含めて14,133人、明治元年に本籍人口16,883人、現住人口17,722人で、明治時代に入ると人口はむしろ減少しております。ただ"Four Thousand Years of Urban Growth"の方では前提となる1850年の福山の人口を65,000人と、実際に記録に残っている福山の武家、寺社を含めた城下人口の5倍以上に過大評価しており、そこから1900年の人口を推定すると、35,000人と過大な推計値になるのでしょう。
①長府などが連担しているという判断で下関を68,000人にしたのは理解できますが、丸穂村や八幡村の一部が宇和島市街に連担していたとしても、宇和島の36,000人は多すぎるのではないでしょうか?
36,000人は"Uajima"の人口で、宇和島とも輪島とも、あるいはまったく日本とは関係のない地名とも解釈は可能です。とはいえUajimaで検索すると日本の地名ばかりで、特に能登地震以前は宇和島の方が主に引っかかります(逆に能登地震以降に輪島をUajimaと綴るような海外の報道機関は、珠洲 Suzuを蘇州 Suzhouと綴っていたりしています)。
まあこのように色々数字に問題はあるのですが、日本史の専門家でもない人がとにかく色々な文献から数字を集めている努力は認められます。
③5万人をも超えていたと思われる堺が登場しないのは、どうしても腑に落ちません。
実は[114754]を投稿した際、堺に関する注意書きを足そうか悩みましたが、あっさり気付くとは…
"Four Thousand Years of Urban Growth"の"Osaka"の項目によると、
1590: Sakai was built in to Osaka (Wald. p. 56)
と書かれています。つまり秀吉時代以降、江戸時代、明治時代を通じて堺は大阪の郊外に組み込まれていると解釈されてしまっているのです。実際、江戸時代後半には大坂三郷の周辺の曽根崎、難波、天王寺、上下福島、南北平野などといった町続きが形成され、大坂の郊外が広がっていますが、多分堺まで市街地が接続するのは大正時代末期以降でしょう(ちゃんと検証していませんが)。
なおここに登場する文献は、Royal Wald著の "The Development of Osaka during the Sixteenth Century." University of California, Berkeley (1947年)なる博士論文?のようです。
②北海道の福山(松前)が明治期に北海道有数の「都会」?であったことは承知していますが、1898年に8,000人強の人口が35,000人になるとは信じがたい。
"Four Thousand Years of Urban Growth"の"Matsumaye (Fukuyama)"の項目によると、
c. 1840: 50,000 Sometime before 1857 (Gazetteer of World)
1850: 65,000
1864: 65,000 (Rosny. p. 79)
ここに登場する文献は、1850年~1856年に出版された"Gazetteer of the Worldと、1864年に出版されたLéon de Rosny著 "Etudes asiatiques de géographie et d'histoire"で、当時エディンバラやパリで出版された同時代的な本を引用しつつ、1840年頃のMatsumaye (Fukuyama)の人口を50,000人、1864年の人口を65,000人としています。この数字は明白に誤っており、5万人や6万5千人というのはどちらかというと松前藩支配下、あるいは蝦夷地全域の和人、アイヌ人の調査人口総数に匹敵するものです。松前藩の福山城下町のみのより正確な人口は、近世墓と人口史料による社会構造と人口変動に関する基礎的研究の報告書の方に詳しく纏められており、嘉永3年(1850年)の福山城下の人口は、武家・寺社人口を含めて14,133人、明治元年に本籍人口16,883人、現住人口17,722人で、明治時代に入ると人口はむしろ減少しております。ただ"Four Thousand Years of Urban Growth"の方では前提となる1850年の福山の人口を65,000人と、実際に記録に残っている福山の武家、寺社を含めた城下人口の5倍以上に過大評価しており、そこから1900年の人口を推定すると、35,000人と過大な推計値になるのでしょう。
①長府などが連担しているという判断で下関を68,000人にしたのは理解できますが、丸穂村や八幡村の一部が宇和島市街に連担していたとしても、宇和島の36,000人は多すぎるのではないでしょうか?
36,000人は"Uajima"の人口で、宇和島とも輪島とも、あるいはまったく日本とは関係のない地名とも解釈は可能です。とはいえUajimaで検索すると日本の地名ばかりで、特に能登地震以前は宇和島の方が主に引っかかります(逆に能登地震以降に輪島をUajimaと綴るような海外の報道機関は、珠洲 Suzuを蘇州 Suzhouと綴っていたりしています)。
まあこのように色々数字に問題はあるのですが、日本史の専門家でもない人がとにかく色々な文献から数字を集めている努力は認められます。
| [114768] 2025年 7月 14日(月)23:42:00 | 白桃 さん |
| 今夏高校野球地方大会決勝戦が行われる球場がある都道府県庁所在地以外の市 | |
タイトルは、[114753]白桃
問:(重複解答アリ、想定解数11市+1市)
北広島市 いわき市 橿原市 倉敷市 久留米市
該当しない市:札幌市 京都市 大阪市 西宮市 高松市
町ヒント:山形県中山町
アナグラムヒント:石鹸急上昇(せっけんきゅうじょうしょう)
わかりやすいヒント:北海道は南北、東京は東西
の共通項です。・・・相変わらず共通項の文言のキレが悪い。(-_-;)
以下は想定解一覧です。北広島市は北北海道と南北海道の二つの決勝戦が行われますので、想定解数は11+1=12となります。
(注:決勝戦の予想は前評判を基に、あくまでも沈着冷静に行いましたので、とある一校をのぞき依怙贔屓はしておりません。)
既に敗れてしまって、依怙贔屓しようにもドモならん高校もありますね。(;'∀')
問:(重複解答アリ、想定解数11市+1市)
北広島市 いわき市 橿原市 倉敷市 久留米市
該当しない市:札幌市 京都市 大阪市 西宮市 高松市
町ヒント:山形県中山町
アナグラムヒント:石鹸急上昇(せっけんきゅうじょうしょう)
わかりやすいヒント:北海道は南北、東京は東西
の共通項です。・・・相変わらず共通項の文言のキレが悪い。(-_-;)
以下は想定解一覧です。北広島市は北北海道と南北海道の二つの決勝戦が行われますので、想定解数は11+1=12となります。
(注:決勝戦の予想は前評判を基に、あくまでも沈着冷静に行いましたので、とある一校をのぞき依怙贔屓はしておりません。)
既に敗れてしまって、依怙贔屓しようにもドモならん高校もありますね。(;'∀')
| 市名 | 球場名 | 大会名 | 決勝戦(大予想) |
| 北広島市 | エスコンフィールド北海道 | 北北海道 | クラーク国際vs旭川明成 |
| 北広島市 | エスコンフィールド北海道 | 南北海道 | 北海vs札幌日大 |
| 弘前市 | はるか夢球場 | 青森 | 青森山田vs八戸学院光星 |
| いわき市 | ヨークいわきスタジアアム | 福島 | 聖光学院vs学法石川 |
| 松本市 | セキスイハイム松本スタジアム | 長野 | 松本国際vs上田西 |
| 岡崎市 | 岡崎レッドダイヤモンドスタジアム | 愛知 | 豊川vs至学館 |
| 姫路市 | ウインク球場 | 兵庫 | 東洋大姫路vs報徳学園 |
| 橿原市 | 佐藤薬品スタジアム | 奈良 | 天理vs智辯学園 |
| 米子市 | どらドラ米子市民球場 | 鳥取 | 鳥取城北vs米子松蔭 |
| 倉敷市 | マスカットスタジアム | 岡山 | 創志学園vs岡山東商 |
| 三次市 | 電光石火きんさいスタジアム三次 | 広島 | 広島商vs広陵 |
| 久留米市 | 久留米市野球場 | 福岡 | 西日本短大付vs東筑 |
| (参考) | |||
| 中山町 | ヤマリョースタジアム山形 | 山形 | 酒田南vs山形中央 |
| [114767] 2025年 7月 14日(月)22:00:01 | _ さん |
| 生年月日情報は、ますます遠ざかる | |
総務省が5年前に発出した以下の行政文書をご確認ください。
「候補者の立候補の届出があった旨の告示事項等について(通知)」(PDFファイル)
公職選挙に際して立候補の届出があった場合に当該選挙の選挙長(たいていは選管の委員長が務める)が立候補者について告示することになっていますが、その告示内容についてプライバシーの観点から、性別の省略、住所記載の簡略化、生年月日記載を年齢記載への変更を図るものです。
この行政文書の性格は、各地の選管に対する技術的助言に過ぎず強制力はありませんが、こういう文書が出ると往々にして右へならえとなることが想定されます。
またこれは立候補者に関するものですが、公職就任者に関しても同様の受け止めが行われる可能性はあるでしょう。
「候補者の立候補の届出があった旨の告示事項等について(通知)」(PDFファイル)
公職選挙に際して立候補の届出があった場合に当該選挙の選挙長(たいていは選管の委員長が務める)が立候補者について告示することになっていますが、その告示内容についてプライバシーの観点から、性別の省略、住所記載の簡略化、生年月日記載を年齢記載への変更を図るものです。
この行政文書の性格は、各地の選管に対する技術的助言に過ぎず強制力はありませんが、こういう文書が出ると往々にして右へならえとなることが想定されます。
またこれは立候補者に関するものですが、公職就任者に関しても同様の受け止めが行われる可能性はあるでしょう。
| [114766] 2025年 7月 14日(月)21:27:33 | オーナー グリグリ |
| Re:よろしくお願いします | |
[114761] Amandaさん
こんにちは、Amandaです。
経県値と白桃さんの都会度についての記事に惹かれて書き込みをするに至りました。
はじめまして、Amandaさん、オーナーのグリグリです。ようこそ落書き帳へ。
高校地理を学習する高校生です。ちなみに女性です。地理はあんまり詳しくないですがお手柔らかにお願いします。
もちろん皆さんお手柔らかに対応する人たちばかりなので、気軽になんでも書き込んでみてください。オフ会にも毎回参加されるかすみさんという先輩もいらっしゃいます。それにしても地理に興味を持つのは男性が多い傾向があるようですが、何故でしょうね。それとも女性であることを敢えて言わずに書き込んでいる方も実は何人かいたりして^^;
趣味は野球観戦や旅行です。オリックスファンです。
私は以前はドラゴンズファンだったのですが、今はもっぱらMLBを観ています。大谷さん、スゴーイです。
こんにちは、Amandaです。
経県値と白桃さんの都会度についての記事に惹かれて書き込みをするに至りました。
はじめまして、Amandaさん、オーナーのグリグリです。ようこそ落書き帳へ。
高校地理を学習する高校生です。ちなみに女性です。地理はあんまり詳しくないですがお手柔らかにお願いします。
もちろん皆さんお手柔らかに対応する人たちばかりなので、気軽になんでも書き込んでみてください。オフ会にも毎回参加されるかすみさんという先輩もいらっしゃいます。それにしても地理に興味を持つのは男性が多い傾向があるようですが、何故でしょうね。それとも女性であることを敢えて言わずに書き込んでいる方も実は何人かいたりして^^;
趣味は野球観戦や旅行です。オリックスファンです。
私は以前はドラゴンズファンだったのですが、今はもっぱらMLBを観ています。大谷さん、スゴーイです。
| [114765] 2025年 7月 14日(月)21:18:30 | オーナー グリグリ |
| Re:全国の現役首長一覧への指摘事項 | |
[114755] Nさん
[114690]に引き続き石川県まで無投票などの確認進めましたので、一旦まとめてお伝えします。
ありがとうございます。すべてご説明通りに修正しました。三浦市の年齢表記に関しては、[114764]で述べた今後の表記の試行事例になります。なお、いただいた情報には推定や可能性としての情報もありますので、一覧表の関連項目に記事へのリンクを付与する仕組みを組み込む予定です。後からの確認を容易にするために。また、以前私が[114720]で、
なお、データ入力中に不確定な事項も見付かっており、具体的に情報提示して皆さんのご協力を得たいと考えています。
と書きましたが、今回のご指摘とも被っているところがありましたので、整理して不確定情報(要確認情報)として別途提示します。
[114758] Nさん
本題ですが、先程なんとなく検索してみたら生年月日不詳だった上牧町の阪本町長のプロフィールページが7.9付けで公開されていました。(お問い合わせ効果…?)1960.11.2です。
こちらもありがとうございます。問い合わせ効果だといいですね。^^
[114690]に引き続き石川県まで無投票などの確認進めましたので、一旦まとめてお伝えします。
ありがとうございます。すべてご説明通りに修正しました。三浦市の年齢表記に関しては、[114764]で述べた今後の表記の試行事例になります。なお、いただいた情報には推定や可能性としての情報もありますので、一覧表の関連項目に記事へのリンクを付与する仕組みを組み込む予定です。後からの確認を容易にするために。また、以前私が[114720]で、
なお、データ入力中に不確定な事項も見付かっており、具体的に情報提示して皆さんのご協力を得たいと考えています。
と書きましたが、今回のご指摘とも被っているところがありましたので、整理して不確定情報(要確認情報)として別途提示します。
[114758] Nさん
本題ですが、先程なんとなく検索してみたら生年月日不詳だった上牧町の阪本町長のプロフィールページが7.9付けで公開されていました。(お問い合わせ効果…?)1960.11.2です。
こちらもありがとうございます。問い合わせ効果だといいですね。^^
| [114764] 2025年 7月 14日(月)21:06:41 | オーナー グリグリ |
| 開示請求の法律 ほか | |
[114751] 未開人さん
法的には行政機関の保有する情報の公開に関する法律が根拠になっていると思われますが、自治体として公開しないことを決めている場合は拒否することができます。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」ですね。ご説明ありがとうございます。やはり拒否可能ということでしたか。全員の生年月日を明らかにするという目標設定は難しくなりました。ということで、一覧表については、生年月日が正確にわからなくても、誕生年や誕生年月までの情報や年齢情報などから「65歳?ヶ月」「55歳2-3ヶ月」などの不確定表記も今後検討したいと思います。
[114752] ばなしさん
ちょうど2015年10月から2016年4月でその並び順が変わっているので、これが2015年の外国人人口比が特におかしかった原因ということでしょうか。
多分そうだと思います。当時の作成手順など覚えていませんが、残っているエクセル表からはそんな感じです。
[114756] ピーくんさん
長崎県の市町課に電話しましたが生年月日は個人情報になるので市町名簿に載せていないとの事でした。ここのサイトが有名になったら生年月日の公開にうるさく言われそうですね。私は怪しまれたりしたくないので問い合わせは致しません。
[114715]の問合せの基本文章に書いた
私は全国の市区町村長の年齢を調査し平均年齢や地域差などを分析しています。
の調査分析の作業範囲にはサイトの一覧表作りも含まれていると勝手に解釈しています。いざという時の説明というか言い逃れ?
[114759] ピーくんさん
町の木 カツラ 町の花 ミツバツツジ
早川町のシンボル、更新しました。電話問い合わせをありがとうございました。
[114762] ピーくんさん
山梨県町村会に早川町町長の生年月日を問い合わせたらお答えできないとの事でした。
怪しまれない程度にお手柔らかにお願いします。
法的には行政機関の保有する情報の公開に関する法律が根拠になっていると思われますが、自治体として公開しないことを決めている場合は拒否することができます。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」ですね。ご説明ありがとうございます。やはり拒否可能ということでしたか。全員の生年月日を明らかにするという目標設定は難しくなりました。ということで、一覧表については、生年月日が正確にわからなくても、誕生年や誕生年月までの情報や年齢情報などから「65歳?ヶ月」「55歳2-3ヶ月」などの不確定表記も今後検討したいと思います。
[114752] ばなしさん
ちょうど2015年10月から2016年4月でその並び順が変わっているので、これが2015年の外国人人口比が特におかしかった原因ということでしょうか。
多分そうだと思います。当時の作成手順など覚えていませんが、残っているエクセル表からはそんな感じです。
[114756] ピーくんさん
長崎県の市町課に電話しましたが生年月日は個人情報になるので市町名簿に載せていないとの事でした。ここのサイトが有名になったら生年月日の公開にうるさく言われそうですね。私は怪しまれたりしたくないので問い合わせは致しません。
[114715]の問合せの基本文章に書いた
私は全国の市区町村長の年齢を調査し平均年齢や地域差などを分析しています。
の調査分析の作業範囲にはサイトの一覧表作りも含まれていると勝手に解釈しています。いざという時の説明というか言い逃れ?
[114759] ピーくんさん
町の木 カツラ 町の花 ミツバツツジ
早川町のシンボル、更新しました。電話問い合わせをありがとうございました。
[114762] ピーくんさん
山梨県町村会に早川町町長の生年月日を問い合わせたらお答えできないとの事でした。
怪しまれない程度にお手柔らかにお願いします。
| [114763] 2025年 7月 14日(月)17:51:51 | 白桃 さん |
| Re:1900年の世界の都市人口におけるランクサイズルールの実証 | |
[114754] YT さん
またまた興味深いデータを有難うございました。
自分がこの本に出合ったのもまさにそのバークリーで2002年のことでしたが、その出会いも本当に偶然で、自分の専門の仕事をサボって、地歴関係の本を図書館で漁って読んでいたら、たまたま見つけました。
正確には覚えていませんが、40年ほど昔、サンフランシスコ出張?(添乗?)の際に、プライベートでBARTに乗ってバークリー(校)に行ってきました。校内にはリスがいたり、なんとなく雰囲気のある所でした。それにしても、YTさんは専門以外に素晴らしい趣味?をお持ちですね。(笑)
上位100都市、およびリストに載っている日本の諸都市の推計人口を紹介すると、以下の通りです。
リストに載っている日本の都市の推計人口の両側に、1898年末現住人口(「日本帝国人口統計」)と1903年末現住人口(「日本帝国人口静態統計」)を並べてみたのが下の表です。(このデータもYTさんから送って頂いたものです。改めて御礼申し上げます。)
1900年の「推計人口」は、その推計方法は大いに疑問ではありますが、「都市的地域(urban area)」の推計人口であることを考慮すれば概ね「そんな、感じかな・・・」と納得いくものですが、以下の3点は???です。
①長府などが連担しているという判断で下関を68,000人にしたのは理解できますが、丸穂村や八幡村の一部が宇和島市街に連担していたとしても、宇和島の36,000人は多すぎるのではないでしょうか?
②北海道の福山(松前)が明治期に北海道有数の「都会」?であったことは承知していますが、1898年に8,000人強の人口が35,000人になるとは信じがたい。
③5万人をも超えていたと思われる堺が登場しないのは、どうしても腑に落ちません。
またまた興味深いデータを有難うございました。
自分がこの本に出合ったのもまさにそのバークリーで2002年のことでしたが、その出会いも本当に偶然で、自分の専門の仕事をサボって、地歴関係の本を図書館で漁って読んでいたら、たまたま見つけました。
正確には覚えていませんが、40年ほど昔、サンフランシスコ出張?(添乗?)の際に、プライベートでBARTに乗ってバークリー(校)に行ってきました。校内にはリスがいたり、なんとなく雰囲気のある所でした。それにしても、YTさんは専門以外に素晴らしい趣味?をお持ちですね。(笑)
上位100都市、およびリストに載っている日本の諸都市の推計人口を紹介すると、以下の通りです。
リストに載っている日本の都市の推計人口の両側に、1898年末現住人口(「日本帝国人口統計」)と1903年末現住人口(「日本帝国人口静態統計」)を並べてみたのが下の表です。(このデータもYTさんから送って頂いたものです。改めて御礼申し上げます。)
| 都市 | 1903年 | 1900年 | 1898年 | ----- | 都市 | 1903年 | 1900年 | 1898年 | 東京 | 1,818,655 | 1,497,000 | 1,440,121 | 松山 | 37,842 | 36,000 | 36,545 | 大阪 | 995,945 | 970,000 | 821,235 | 高松 | 37,430 | 34,000 | 34,416 | 京都 | 380,568 | 362,000 | 353,139 | 長野 | 37,202 | 36,000 | 31,319 | 横浜 | 326,035 | 245,000 | 193,762 | 横須賀(町) | 36,956 | 24,750 | 名古屋 | 288,639 | 260,000 | 244,145 | 水戸 | 36,928 | 33,778 | 神戸 | 285,002 | 242,000 | 215,780 | 小倉(市←町) | 36,825 | 27,504 | 長崎 | 153,293 | 115,000 | 107,422 | 姫路 | 36,509 | 35,000 | 35,282 | 広島 | 121,196 | 118,000 | 122,306 | 弘前 | 36,443 | 35,000 | 34,771 | 仙台 | 100,231 | 90,000 | 83,325 | 津 | 36,408 | 34,000 | 33,287 | 金沢 | 99,657 | 87,000 | 83,662 | 宇都宮 | 35,953 | 36,000 | 32,069 | 函館(区) | 85,313 | 80,000 | 78,040 | 高知 | 35,518 | 36,000 | 36,511 | 岡山 | 81,025 | 67,000 | 58,025 | 高崎(市←町) | 35,226 | 31,000 | 30,893 | 小樽(区) | 79,361 | 65,000 | 佐賀 | 35,083 | 32,753 | 福岡 | 71,047 | 67,000 | 66,190 | 松江 | 35,081 | 34,000 | 34,651 | 和歌山 | 68,527 | 65,000 | 63,667 | 青森 | 34,857 | 28,029 | 佐世保(市←村) | 68,344 | 49,000 | 37,485 | 秋田 | 34,350 | 29,477 | 呉 | 66,006 | 60,000 | 奈良 | 33,735 | 30,539 | 徳島 | 63,710 | 62,000 | 61,501 | 宇治山田(町) | 33,627 | 27,990 | 熊本 | 59,717 | 59,000 | 61,463 | 松本(町) | 33,493 | 31,324 | 新潟 | 59,576 | 55,000 | 53,366 | 久留米 | 33,273 | 29,008 | 鹿児島 | 59,001 | 55,000 | 53,481 | 米沢 | 33,063 | 31,000 | 30,719 | 富山 | 56,275 | 57,000 | 59,558 | 若松(市←町) | 32,534 | 29,200 | 札幌(区) | 55,304 | 44,000 | 37,482 | 盛岡 | 31,861 | 33,000 | 32,989 | 堺 | 54,040 | 50,203 | 長岡(町) | 31,310 | 9,780 | 福井 | 50,155 | 46,000 | 44,286 | 高岡 | 31,119 | 31,000 | 31,490 | 静岡 | 48,744 | 43,000 | 42,172 | 足尾(町) | 31,077 | 19,058 | 下関←赤間関 | 46,285 | 68,000 | 42,786 | 鳥取 | 31,023 | 28,496 | 甲府 | 44,188 | 38,000 | 37,561 | 尾道 | 30,529 | 22,312 | 那覇(区) | 43,132 | 38,000 | 35,453 | 大牟田(町) | 30,474 | 19,291 | 前橋 | 41,714 | 33,000 | 34,495 | 四日市 | 30,140 | 25,220 | 山形 | 40,248 | 36,000 | 35,300 | 桐生(町) | 30,022 | 23,991 | 岐阜 | 40,168 | 32,000 | 31,942 | 宇和島(町) | 12,798 | 36,000 | 13,366 | 大津 | 39,595 | 34,000 | 34,225 | 福山(町)(松前) | 7,863 | 35,000 | 門司(市←町) | 38,065 | 25,274 |
①長府などが連担しているという判断で下関を68,000人にしたのは理解できますが、丸穂村や八幡村の一部が宇和島市街に連担していたとしても、宇和島の36,000人は多すぎるのではないでしょうか?
②北海道の福山(松前)が明治期に北海道有数の「都会」?であったことは承知していますが、1898年に8,000人強の人口が35,000人になるとは信じがたい。
③5万人をも超えていたと思われる堺が登場しないのは、どうしても腑に落ちません。
| [114762] 2025年 7月 14日(月)17:21:27 | ピーくん さん |
| ひと休み | |
昨日13日までで、今年全国最長の16日連続の猛暑日となっていた大分県日田市、山口県岩国市広瀬、15日連続の猛暑日となっていた広島県府中市、福岡県朝倉市では、今日14日はいずれも35℃どころか30℃にも届かず、連続猛暑日がようやくストップしました。 日本気象協会 本社 日直主任 今日は涼しいです。強豪もひと休み。 Amandaさん
はじめまして、私も白桃さんの記事が好きです。 九里亜蓮さん 西川龍馬さん よろしくお願いします。西川龍馬さん怪我しています。 十番勝負があります。ヒントがたくさん出るので参加してください。
山梨県町村会に早川町町長の生年月日を問い合わせたらお答えできないとの事でした。
はじめまして、私も白桃さんの記事が好きです。 九里亜蓮さん 西川龍馬さん よろしくお願いします。西川龍馬さん怪我しています。 十番勝負があります。ヒントがたくさん出るので参加してください。
山梨県町村会に早川町町長の生年月日を問い合わせたらお答えできないとの事でした。
| [114761] 2025年 7月 14日(月)16:24:46 | Amanda さん |
| よろしくお願いします | |
こんにちは、Amandaです。
経県値と白桃さんの都会度についての記事に惹かれて書き込みをするに至りました。
高校地理を学習する高校生です。ちなみに女性です。地理はあんまり詳しくないですがお手柔らかにお願いします。
趣味は野球観戦や旅行です。オリックスファンです。
経県値と白桃さんの都会度についての記事に惹かれて書き込みをするに至りました。
高校地理を学習する高校生です。ちなみに女性です。地理はあんまり詳しくないですがお手柔らかにお願いします。
趣味は野球観戦や旅行です。オリックスファンです。
| [114760] 2025年 7月 14日(月)16:20:27【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 14日(月)16:21:28 | ピーくん さん |
| 手数料高い | |
貧乏人です。硬貨を引き出しました。ゆうちょ銀行は手数料がかかりました。110円しました。納得いかないです。
海辺を飛ぶ鳥さん
ベイスターズファンですか?優勝からは長らく経過していますが下剋上日本一がありました。谷繁元信さんは東城町で親しみがあります。野村投手 大門投手 石井琢朗さんはカープに来られました。明日からカープと三連戦カープ負けます。今年も下剋上日本一目指してください。十番勝負優勝目指して頑張ってください。
海辺を飛ぶ鳥さん
ベイスターズファンですか?優勝からは長らく経過していますが下剋上日本一がありました。谷繁元信さんは東城町で親しみがあります。野村投手 大門投手 石井琢朗さんはカープに来られました。明日からカープと三連戦カープ負けます。今年も下剋上日本一目指してください。十番勝負優勝目指して頑張ってください。
| [114759] 2025年 7月 14日(月)15:17:57 | ピーくん さん |
| 早川町について | |
電話しました。
町の木 カツラ 町の花 ミツバツツジ
でした。
グリグリさま
よろしくお願いします。
町の木 カツラ 町の花 ミツバツツジ
でした。
グリグリさま
よろしくお願いします。
| [114758] 2025年 7月 14日(月)15:11:44【2】訂正年月日 【1】2025年 7月 14日(月)15:14:54 【2】2025年 7月 14日(月)18:03:11 | N さん |
| 上牧町長の生年月日 | |
| [114757] 2025年 7月 14日(月)15:03:32 | オーナー グリグリ |
| 全国の現役首長関連 | |
[114752] ばなしさん
「全国の現役首長」正式公開おめでとうございます、そしてお疲れ様でした。
[114755] Nさん
正式公開おめでとうございます。
ばなしさん、Nさん、メッセージをありがとうございます。嬉しいです。
114755] Nさん
まず、今日現在の版が「2025年7月13日現在」になっていますが、現在年齢と辻褄合ってますでしょうか?
修正しました。私の手順ミスでした。現在年齢はエクセルで自動計算ですが、そちらを更新せずに最新日だけ更新していました。
#この土日の選挙結果分の更新で正しくなりそうではありますが、一応。
昨日は首長選挙がありませんでした。愛媛県議会補欠選挙のみです。今度の日曜は奈良市など17市町で首長選挙があります。
「全国の現役首長」正式公開おめでとうございます、そしてお疲れ様でした。
[114755] Nさん
正式公開おめでとうございます。
ばなしさん、Nさん、メッセージをありがとうございます。嬉しいです。
114755] Nさん
まず、今日現在の版が「2025年7月13日現在」になっていますが、現在年齢と辻褄合ってますでしょうか?
修正しました。私の手順ミスでした。現在年齢はエクセルで自動計算ですが、そちらを更新せずに最新日だけ更新していました。
#この土日の選挙結果分の更新で正しくなりそうではありますが、一応。
昨日は首長選挙がありませんでした。愛媛県議会補欠選挙のみです。今度の日曜は奈良市など17市町で首長選挙があります。
| [114756] 2025年 7月 14日(月)13:37:06 | ピーくん さん |
| 個人情報保護 | |
長崎県の市町課に電話しましたが生年月日は個人情報になるので市町名簿に載せていないとの事でした。ここのサイトが有名になったら生年月日の公開にうるさく言われそうですね。私は怪しまれたりしたくないので問い合わせは致しません。
| [114755] 2025年 7月 14日(月)13:06:09【2】訂正年月日 【1】2025年 7月 14日(月)13:06:36 【2】2025年 7月 14日(月)13:12:17 | N さん |
| 全国の現役首長一覧への指摘事項 | |
| [114754] 2025年 7月 14日(月)01:32:42【3】訂正年月日 【1】2025年 7月 14日(月)02:38:16 【2】2025年 7月 14日(月)12:35:45 【3】2025年 7月 14日(月)14:51:52 | YT さん |
| 1900年の世界の都市人口におけるランクサイズルールの実証 | |
[114741] 白桃さん
学生時に、お酒を呑んでる時間の半分ぐらいは地理の勉強に勤しんできた???白桃ですが、「ランクサイズルール」という言葉は知りませんでした。ご紹介いただき有難うございました。もっとも、私が地理を学んだところは、「理論地理学」「数理地理学」「計量地理学」などとも呼称される「新しい地理学」と縁遠いところで、数学的(計量的)手法を用いたり、モデル化を通じて法則化を追求することには批判的であったように思います。
すみません。てっきり大学での地理学の常識だとばっかり思っていました。私が大学生だったのは90年代に入ってからですが、理系向けの一般教養の地理学の授業で真っ先に習ったのがこの話でした。まあ大学の授業はある意味教員のやりたい放題で、その分野の代表面して講義をしていても、教養学部レベルですら全然その分野の主流ではない話をし放題であったりするんですよね。
ところで世界の過去の都市人口を推計した本として、ターシャス・チャンドラー著"Four Thousand Years of Urban Growth" (1987年)があります。その推計手法にははっきり言って問題だらけではあるのですが、自分が知る限り、時系列を踏まえた上で、この本を超える数の推計値を載せている文献は存在しません。ターシャス・チャンドラー自身はハーバード大学を卒業後、カリフォルニア州バークリーに居住を構え、2000年に交通事故で85歳で亡くなった歴史家とされていますが、大学での職は得られなかったアマチュア歴史家のようです。自分がこの本に出合ったのもまさにそのバークリーで2002年のことでしたが、その出会いも本当に偶然で、自分の専門の仕事をサボって、地歴関係の本を図書館で漁って読んでいたら、たまたま見つけました。
その本には1900年の都市人口として、人口3万人以上の世界中の1146の都市が列挙されています。ここでいう都市とは建物が連続して存在する(house-to-house)ような都市的地域(urban area)であり、つまり人口密集地帯が連続する限り、1個の都市としてカウントされています。1900年といえば、先進国で同時に国勢調査が実施されようとした年でしたが、残念ながら日本はそれに遅れ、1920年以降となってしまいました。それはともかくとして、それなりに信頼ある統計が残るようになった時代です。
以下、上位100都市、およびリストに載っている日本の諸都市の推計人口を紹介すると、以下の通りです。
さて、上の推計人口の是非は置いておいて、とりあえず1900年の上位100都市に関し、ランクサイズルールを適用すると、
log(人口) ≒ -0.684 log(順位) + 6.81 ※logは10を底とする常用対数
R2 = 0.995...
と、見事に高い相関係数で直線に乗ります。上位200位まで拡張しても
log(人口) ≒ -0.770 log(順位) + 6.94
R2 = 0.990...
と、少し相関は落ちますが、概ね直線に乗っています。つまり全世界に平均化すれば、ランクサイズルールはまあそれなりに成立するのです。
【「推定人口」を「推計人口」表記に統一、その他誤字修正、(台湾)追記、ブカレストの国名修正、ドイツとロシアは国境変更が多いので「帝国」表記に修正その他色々情報追加】
学生時に、お酒を呑んでる時間の半分ぐらいは地理の勉強に勤しんできた???白桃ですが、「ランクサイズルール」という言葉は知りませんでした。ご紹介いただき有難うございました。もっとも、私が地理を学んだところは、「理論地理学」「数理地理学」「計量地理学」などとも呼称される「新しい地理学」と縁遠いところで、数学的(計量的)手法を用いたり、モデル化を通じて法則化を追求することには批判的であったように思います。
すみません。てっきり大学での地理学の常識だとばっかり思っていました。私が大学生だったのは90年代に入ってからですが、理系向けの一般教養の地理学の授業で真っ先に習ったのがこの話でした。まあ大学の授業はある意味教員のやりたい放題で、その分野の代表面して講義をしていても、教養学部レベルですら全然その分野の主流ではない話をし放題であったりするんですよね。
ところで世界の過去の都市人口を推計した本として、ターシャス・チャンドラー著"Four Thousand Years of Urban Growth" (1987年)があります。その推計手法にははっきり言って問題だらけではあるのですが、自分が知る限り、時系列を踏まえた上で、この本を超える数の推計値を載せている文献は存在しません。ターシャス・チャンドラー自身はハーバード大学を卒業後、カリフォルニア州バークリーに居住を構え、2000年に交通事故で85歳で亡くなった歴史家とされていますが、大学での職は得られなかったアマチュア歴史家のようです。自分がこの本に出合ったのもまさにそのバークリーで2002年のことでしたが、その出会いも本当に偶然で、自分の専門の仕事をサボって、地歴関係の本を図書館で漁って読んでいたら、たまたま見つけました。
その本には1900年の都市人口として、人口3万人以上の世界中の1146の都市が列挙されています。ここでいう都市とは建物が連続して存在する(house-to-house)ような都市的地域(urban area)であり、つまり人口密集地帯が連続する限り、1個の都市としてカウントされています。1900年といえば、先進国で同時に国勢調査が実施されようとした年でしたが、残念ながら日本はそれに遅れ、1920年以降となってしまいました。それはともかくとして、それなりに信頼ある統計が残るようになった時代です。
以下、上位100都市、およびリストに載っている日本の諸都市の推計人口を紹介すると、以下の通りです。
(開く)1900年の世界/日本の主要都市(都市的地域)の推計都市人口
さて、上の推計人口の是非は置いておいて、とりあえず1900年の上位100都市に関し、ランクサイズルールを適用すると、
log(人口) ≒ -0.684 log(順位) + 6.81 ※logは10を底とする常用対数
R2 = 0.995...
と、見事に高い相関係数で直線に乗ります。上位200位まで拡張しても
log(人口) ≒ -0.770 log(順位) + 6.94
R2 = 0.990...
と、少し相関は落ちますが、概ね直線に乗っています。つまり全世界に平均化すれば、ランクサイズルールはまあそれなりに成立するのです。
【「推定人口」を「推計人口」表記に統一、その他誤字修正、(台湾)追記、ブカレストの国名修正、ドイツとロシアは国境変更が多いので「帝国」表記に修正その他色々情報追加】
| [114753] 2025年 7月 14日(月)00:17:50 | 白桃 さん |
| エスコンフィールド北海道 | |
[114749]海辺を飛ぶ鳥 さん
北海道日本ハムファイターズの本拠地は、札幌市ではなく北広島市ですね。と思いましたが、2020年時点では札幌ドームという事でしょうか。どちらにせよ注記があってもと思います。
アチャーァ!…エスコンフィールドって北広島にあるんですね。ご指摘有難うございました。
私の野球に関する関心順位は、
高校野球>MLB>日本のプロ野球>都市対抗野球>大学野球>草野球
なんて言い訳してイイワケありませんね。(^^;
お礼に代えて???十番勝負風問題を出させていただきます。
問:(重複解答アリ、想定解数11市+1市)
北広島市 いわき市 橿原市 倉敷市 久留米市
該当しない市:札幌市 京都市 大阪市 西宮市 高松市
町ヒント:山形県中山町
アナグラムヒント:石鹸急上昇(せっけんきゅうじょうしょう)
わかりやすいヒント:北海道は南北、東京は東西
共通項は、お付き合い頂く方があろうが/なかろうが、本日中に発表いたします。
北海道日本ハムファイターズの本拠地は、札幌市ではなく北広島市ですね。と思いましたが、2020年時点では札幌ドームという事でしょうか。どちらにせよ注記があってもと思います。
アチャーァ!…エスコンフィールドって北広島にあるんですね。ご指摘有難うございました。
私の野球に関する関心順位は、
高校野球>MLB>日本のプロ野球>都市対抗野球>大学野球>草野球
なんて言い訳してイイワケありませんね。(^^;
お礼に代えて???十番勝負風問題を出させていただきます。
問:(重複解答アリ、想定解数11市+1市)
北広島市 いわき市 橿原市 倉敷市 久留米市
該当しない市:札幌市 京都市 大阪市 西宮市 高松市
町ヒント:山形県中山町
アナグラムヒント:石鹸急上昇(せっけんきゅうじょうしょう)
わかりやすいヒント:北海道は南北、東京は東西
共通項は、お付き合い頂く方があろうが/なかろうが、本日中に発表いたします。
| [114752] 2025年 7月 13日(日)23:30:38 | ばなし さん |
| 諸々 | |
[114747]グリグリさん
「全国の現役首長」正式公開おめでとうございます、そしてお疲れ様でした。これまで一覧で表示するサイトがなかった(であろう)町長や村長は特に確認が大変だったので非常に助かります。就任日も流し見してみましたが、20世紀に就任された方が意外と多くてびっくりです。
[114742]グリグリさん
お忙しい中ご対応ありがとうございました。外国人人口比のエラーも[114750]でご修正いただいたので特に問題ないと思います。
[114740]グリグリさん
[98049]や[76346]などを参照してください。
こちら拝見しました。合併や移管絡みの3町の掲載位置ももちろんですが、そもそもデータベース検索における総合振興局・振興局の並び順自体が年によって違うのですね。ちょうど2015年10月から2016年4月でその並び順が変わっているので、これが2015年の外国人人口比が特におかしかった原因ということでしょうか。
[114739]海辺を飛ぶ鳥さん
フォローありがとうございました。十番勝負が始まる前に投稿しなければと思ってきちんと確認しないまま書き込んでしまったので、かなり抜けがありましたね…。
「全国の現役首長」正式公開おめでとうございます、そしてお疲れ様でした。これまで一覧で表示するサイトがなかった(であろう)町長や村長は特に確認が大変だったので非常に助かります。就任日も流し見してみましたが、20世紀に就任された方が意外と多くてびっくりです。
[114742]グリグリさん
お忙しい中ご対応ありがとうございました。外国人人口比のエラーも[114750]でご修正いただいたので特に問題ないと思います。
[114740]グリグリさん
[98049]や[76346]などを参照してください。
こちら拝見しました。合併や移管絡みの3町の掲載位置ももちろんですが、そもそもデータベース検索における総合振興局・振興局の並び順自体が年によって違うのですね。ちょうど2015年10月から2016年4月でその並び順が変わっているので、これが2015年の外国人人口比が特におかしかった原因ということでしょうか。
[114739]海辺を飛ぶ鳥さん
フォローありがとうございました。十番勝負が始まる前に投稿しなければと思ってきちんと確認しないまま書き込んでしまったので、かなり抜けがありましたね…。
| [114751] 2025年 7月 13日(日)22:41:55 | 未開人 さん |
| 開示請求 | |
十番勝負が来週に迫っていますね… 今週1週間でなんとか対策しましょう。
[114744]グリグリさん
開示請求すれば公開せざるを得ない何か法的根拠があるのでしょうか。やはりその辺りがはっきりしないと不安です。
僕はやらないですが、研究で開示請求を使用している人は身近にもいます。
法的には行政機関の保有する情報の公開に関する法律が根拠になっていると思われますが、自治体として公開しないことを決めている場合は拒否することができます。
手順はここに載せておきますが、割と労力がかかる一方で成果が得られないことも予想されます。
[114744]グリグリさん
開示請求すれば公開せざるを得ない何か法的根拠があるのでしょうか。やはりその辺りがはっきりしないと不安です。
僕はやらないですが、研究で開示請求を使用している人は身近にもいます。
法的には行政機関の保有する情報の公開に関する法律が根拠になっていると思われますが、自治体として公開しないことを決めている場合は拒否することができます。
手順はここに載せておきますが、割と労力がかかる一方で成果が得られないことも予想されます。
| [114750] 2025年 7月 13日(日)22:24:34 | オーナー グリグリ |
| Re:野球/現役首長/コード順 | |
[114749] 海辺を飛ぶ鳥さん
「全国の現役首長」の正式公開おめでとうございます。
ありがとうございます。
外国人人口比の一部データが「#VALUE!」になっています。ご修正お願いします。
こちらは修正しました。確認が甘かったです。_o_
「全国の現役首長」の正式公開おめでとうございます。
ありがとうございます。
外国人人口比の一部データが「#VALUE!」になっています。ご修正お願いします。
こちらは修正しました。確認が甘かったです。_o_
| [114749] 2025年 7月 13日(日)21:54:08【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 13日(日)22:30:14 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| 野球/現役首長/コード順 | |
[114741]白桃さん
人口と順位の対数はとっていませんが、両国の同順位の都市の人口を比較すると、実に似通っている(白桃的には「好勝負」している)ことがわかります。特に、2位の横浜VSロサンゼルス、3位の大阪VSシカゴ、4位の名古屋VSヒューストン、は、千秋楽の三役揃い踏み後の取組に持っていきたいです。
こんなに近いのはビックリしました。ベイスターズもドジャースに続いて、ジャイアンツに勝って連敗ストップとなりました!
(【1】ここでは言って無かった気もしますが、やっと巨人の2軍本拠地"は"出て行った事が嬉しいベイスターズファンの川崎市民です。)
北海道日本ハムファイターズの本拠地は、札幌市ではなく北広島市ですね。と思いましたが、2020年時点では札幌ドームという事でしょうか。どちらにせよ注記があってもと思います。
[114673]グリグリさん
ご対応ありがとうございます。仕様にについてもご説明ありがとうございます。了解しました。
[114747]グリグリさん
「全国の現役首長」の正式公開おめでとうございます。
[114740][114742]グリグリさん
ご対応、ご説明ありがとうございます。
面白データベース検索、「まち」「ちょう」、はデータは問題ないものも、コード順が間違っているならコード順に直したほうが良いのでは?と思っての書き込みでしたが、そういう経緯でしたら修正の必要は無いですね。失礼しました。
外国人人口比の一部データが「#VALUE!」になっています。ご修正お願いします。
人口と順位の対数はとっていませんが、両国の同順位の都市の人口を比較すると、実に似通っている(白桃的には「好勝負」している)ことがわかります。特に、2位の横浜VSロサンゼルス、3位の大阪VSシカゴ、4位の名古屋VSヒューストン、は、千秋楽の三役揃い踏み後の取組に持っていきたいです。
こんなに近いのはビックリしました。ベイスターズもドジャースに続いて、ジャイアンツに勝って連敗ストップとなりました!
(【1】ここでは言って無かった気もしますが、やっと巨人の2軍本拠地"は"出て行った事が嬉しいベイスターズファンの川崎市民です。)
北海道日本ハムファイターズの本拠地は、札幌市ではなく北広島市ですね。と思いましたが、2020年時点では札幌ドームという事でしょうか。どちらにせよ注記があってもと思います。
[114673]グリグリさん
ご対応ありがとうございます。仕様にについてもご説明ありがとうございます。了解しました。
[114747]グリグリさん
「全国の現役首長」の正式公開おめでとうございます。
[114740][114742]グリグリさん
ご対応、ご説明ありがとうございます。
面白データベース検索、「まち」「ちょう」、はデータは問題ないものも、コード順が間違っているならコード順に直したほうが良いのでは?と思っての書き込みでしたが、そういう経緯でしたら修正の必要は無いですね。失礼しました。
外国人人口比の一部データが「#VALUE!」になっています。ご修正お願いします。
| [114748] 2025年 7月 13日(日)20:52:44 | オーナー グリグリ |
| 公式メディア更新 | |
ピーくんさん、下総みなとさん、都道府県市区町村の公式メディアへの情報提供をありがとうございます。いただいた情報を確認し対象となる情報更新を行いました。ご確認いただければと思います。なお、いただいた情報の中にはすでに正式登録済みの情報も含まれていました。登録済みデータであるかどうかの確認は行なっていただいているかとは思いますが、再度ご確認いただければ確認の手間が省けますのでよろしくお願いいたします。
| [114747] 2025年 7月 13日(日)19:36:15 | オーナー グリグリ |
| New!「全国の現役首長」公開しました(新規リリース!) | |
少し時間が掛かってしまいましたが「全国の現役首長」を正式公開しました (新規リリース!)。トップメニューにしました。
URLは、 https://uub.jp/lce/ です。lceは、"local chief executive"の略です (地方自治体の首長)。
皆様にご覧(ご利用)いただければ幸いです。間違いの指摘、新規情報の提供など、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
URLは、 https://uub.jp/lce/ です。lceは、"local chief executive"の略です (地方自治体の首長)。
皆様にご覧(ご利用)いただければ幸いです。間違いの指摘、新規情報の提供など、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。
| [114746] 2025年 7月 13日(日)12:17:37 | 下総みなと さん |
| Re:難度は高い | |
[114735] ピーくんさん
下総みなと さん
はじめまして、メンバー登録されましたらグリグリさまから広報メディアの情報提供のサービスが受けられますのでそちらでは落書き帳より便利です。メンバー登録は10件の書き込みで可能です。
はじめまして。ご教授ありがとうございます。
メンバー登録によって何が変わるか、まだ把握しきれていないので参考にさせていただきます。
下総みなと さん
はじめまして、メンバー登録されましたらグリグリさまから広報メディアの情報提供のサービスが受けられますのでそちらでは落書き帳より便利です。メンバー登録は10件の書き込みで可能です。
はじめまして。ご教授ありがとうございます。
メンバー登録によって何が変わるか、まだ把握しきれていないので参考にさせていただきます。
| [114745] 2025年 7月 13日(日)07:08:55 | 白桃 さん |
| アメリカ及び日本の1960年国勢調査時人口トップ20都市 | |
[114741]は「ランクサイズルール」の検証の意味もあって投稿したのですが、書きながら、米国の都市の人口順位が昔というか、私が外国の人口にも関心をもち始めた頃とだいぶ違ってきているなぁ、と感じました。
下は、1960年(当時の私は、三度のごはんより、人口と地図とチャンバラと快傑ハリマオが好きな三本松小学校生徒だった)国勢調査の人口です。
当時の日本は「昭和の大合併」もほぼ終了し、高度経済成長まっしぐらの時代でありました。
日本の場合は、百万人を超える「六大都市」と福岡以下の市との間に結構な「段差」があり、10位の広島以下は50万人未満の都市が並ぶと言う状態ですが、特筆すべきは、合併によって北九州市となった八幡も含め、トップ20のすべての都市が2020年国調でもトップ50に入っている点であります。
それに対し、米国の場合は、ビッグ5の一つであった「自動車の街」デトロイトが2020年には27位まで沈下しているほか、クリーブランド、ピッツバーグ、バッファローの「重工業の街」として世界に名を馳せた都市や、セントルイス、ニューオーリンズの歴史ある街が2020年には50位から外れているのです。このように、米国の60年間の都市人口順位変動は日本と比べものにならないほど大きいものでした。
下は、1960年(当時の私は、三度のごはんより、人口と地図とチャンバラと快傑ハリマオが好きな三本松小学校生徒だった)国勢調査の人口です。
当時の日本は「昭和の大合併」もほぼ終了し、高度経済成長まっしぐらの時代でありました。
| 1960年順位 | 米国の都市(2020年順位) | 1960年人口 | ----- | 日本の都市(2020年順位) | 1960年人口 | 1位 | ニューヨーク(1) | 7,781,984 | 東京(1) | 8,310,027 | 2位 | シカゴ(3) | 3,550,404 | 大阪(3) | 3,011,563 | 3位 | ロサンゼルス(2) | 2,479,015 | 名古屋(4) | 1,591,935 | 4位 | フィラデルフィア(6) | 2,002,512 | 横浜(2) | 1,375,710 | 5位 | デトロイト(27) | 1,670,144 | 京都(9) | 1,284,818 | 6位 | ボルティモア(30) | 939,024 | 神戸(8) | 1,113,977 | 7位 | ヒューストン(4) | 938,219 | 福岡(6) | 647,122 | 8位 | クリーブランド(54) | 876,050 | 川崎(7) | 632,975 | 9位 | ワシントン(20) | 763,956 | 札幌(5) | 523,839 | 10位 | セントルイス(69) | 750,026 | 広島(11) | 431,336 | 11位 | ミルウォーキー(31) | 741,324 | 仙台(12) | 425,272 | 12位 | サンフランシスコ(17) | 740,316 | 尼崎(37) | 405,955 | 13位 | ボストン(24) | 697,197 | 熊本(18) | 373,922 | 14位 | ダラス(9) | 679,684 | 長崎(44) | 344,153 | 15位 | ニューオーリンズ(53) | 627,525 | 堺(15) | 339,863 | 16位 | ピッツバーグ(68) | 604,332 | 浜松(16) | 333,009 | 17位 | サンアントニオ(7) | 587,718 | 八幡(-) | 332,163 | 18位 | サンディエゴ(8) | 573,224 | 静岡(21) | 328,819 | 19位 | シアトル(18) | 557,087 | 姫路(26) | 328,689 | 20位 | バッファロー(76) | 532,759 | 新潟(17) | 314,528 |
それに対し、米国の場合は、ビッグ5の一つであった「自動車の街」デトロイトが2020年には27位まで沈下しているほか、クリーブランド、ピッツバーグ、バッファローの「重工業の街」として世界に名を馳せた都市や、セントルイス、ニューオーリンズの歴史ある街が2020年には50位から外れているのです。このように、米国の60年間の都市人口順位変動は日本と比べものにならないほど大きいものでした。
| [114744] 2025年 7月 12日(土)21:59:17 | オーナー グリグリ |
| 開示請求と法的根拠 | |
[114718] ピーくんさん
日頃から、愛南町政の推進に対しまして御理解と御協力を賜り、
誠にありがとうございます。
この度HPにお問合せいただいた件について、回答いたします。
お問い合わせいただいた内容につきましては、個人情報の保護に
関する法律により目的外での第三者への提供が制限されております。
つきましては、大変恐縮ですが、今回のお問い合わせには、回答
できかねますことを御了承いただきますようお願い申し上げます。
大桑村役場からも同様の回答でした。
大桑村役場の◯◯と申します。
ホームページにお問い合わせいただいた件についてですが、
当村では村長のプロフィールについては公開していません。
生年月日に関しては公表していないため個人情報保護の観点から回答は差し控えさせていただきます。
なお、メディア等で表記されている通り実年齢に関しては公表の対象として差支えありませんので、
7月現在73歳であることをもって回答とさせていただきます。
[114715]
と言うのも、市区町村長・知事というのは公人であり生年月日を問われた際には答える義務のようなものがあると思っているのですが、何らかの法的根拠があるのでしょうか。それとも慣例として公開しているのでしょうか。そのあたり少し不安というか曖昧な気分です。
[114719] 未開人さん
首長の年齢については必要なら開示請求もできると思いますので、ご検討ください。
未開人さん、開示請求すれば公開せざるを得ない何か法的根拠があるのでしょうか。やはりその辺りがはっきりしないと不安です。
日頃から、愛南町政の推進に対しまして御理解と御協力を賜り、
誠にありがとうございます。
この度HPにお問合せいただいた件について、回答いたします。
お問い合わせいただいた内容につきましては、個人情報の保護に
関する法律により目的外での第三者への提供が制限されております。
つきましては、大変恐縮ですが、今回のお問い合わせには、回答
できかねますことを御了承いただきますようお願い申し上げます。
大桑村役場からも同様の回答でした。
大桑村役場の◯◯と申します。
ホームページにお問い合わせいただいた件についてですが、
当村では村長のプロフィールについては公開していません。
生年月日に関しては公表していないため個人情報保護の観点から回答は差し控えさせていただきます。
なお、メディア等で表記されている通り実年齢に関しては公表の対象として差支えありませんので、
7月現在73歳であることをもって回答とさせていただきます。
[114715]
と言うのも、市区町村長・知事というのは公人であり生年月日を問われた際には答える義務のようなものがあると思っているのですが、何らかの法的根拠があるのでしょうか。それとも慣例として公開しているのでしょうか。そのあたり少し不安というか曖昧な気分です。
[114719] 未開人さん
首長の年齢については必要なら開示請求もできると思いますので、ご検討ください。
未開人さん、開示請求すれば公開せざるを得ない何か法的根拠があるのでしょうか。やはりその辺りがはっきりしないと不安です。
| [114743] 2025年 7月 12日(土)21:27:50 | EMM さん |
| 遅ればせながらオフ会2次会クイズ合戦(EMM出題分)の解答 | |
[114630]我がの
とにかく、当該の地名コレクションを見れば一発で分かるものばかりですが…答えは数日後に発表します。
翌週末には書き込みしようかな、と思っていたのに時間が取れずここまで引っ張ってしまいました。
遅ればせながらクイズの解答をご覧ください。
【「立神」コレクションには地図ではなくイオン公式HPに出てくる住所を根拠に登録してある地名があります。そのイオンは何県にある?】
答えは佐賀県、唐津市のイオン唐津ショッピングセンター。「立神」コレクション
Mapionでは小字が書かれていないエリアとなっているのですが、公式HPでは「佐賀県唐津市鏡字立神4671」。
これ、いろいろ調べているうちにある気付きがあり、それに関して書き込みしたい…と考えていたところでしたので出題してみました。
「書き込みしたい内容」は時間が取れましたら…
【「富士見坂」コレクションに登録されているものの中で、一番西にある富士見坂は何県にある?】
答えは香川県、丸亀市にある富士見坂。「富士見坂」コレクション
本家の富士山では無く、讃岐富士に対する「富士見」なのがミソ。
第五回クイ図の問四をもとに作成されたコレクションで、その解答をした方…MasAkaさんがいらっしゃったので瞬殺でした。
【地名コレクションの「同音異字系」カテゴリに含まれるコレクションは10件で、そのうち9件は担当者がグリグリさんですが、残り1件の担当者は誰?】
答えはスカンベルテクの鷹さん。「同音異字系」カテゴリ
新たなアイデアがありましたら落書き帳まで。
【「県境サイン」コレクションの「施設内にある県境サイン」カテゴリにはパーキングエリアが2つ登録されていますが、それはどこの都道府県境にある?】
答えは富山県|石川県の能越県境PAと福岡県|佐賀県の基山PA。「県境サイン」コレクション
能越県境PAは駐車スペースの路面にも印がありますし、実はPA外にもサインがあることを目視で確認しています。
【「百交差点」コレクションは交差点を通る国道の番号をいろいろな足し方で足した合計が百の倍数の交差点を集めたものですが、合計数字が一番大きい交差点の数字は?】
【その「数字が一番大きい百交差点」はどこの都道府県にある?】
答えは2400(パターン4)、大分県日田市の玉川交差点。「百交差点」コレクション
ちなみに次点は2300で愛知県設楽郡設楽町田峰にある三差路。
【地名コレクションで地名の収録数が一番少ないのは「高地」コレクション。では、2番目に少ないのは?】
答えは「橋立・天橋」コレクションで7件。
「高地」コレクションは5件。
増える余地は有るかもしれないので、もし情報ありましたら落書き帳まで。
【「漢字四字仮名四字」は漢字表記と読みがなの数が一致していれば5文字以上のものも登録してありますが、現時点で収録してるもので一番文字数の多いのは何文字?また、どこの都道府県にある?】
答えは秋田県秋田市の四ツ小屋小阿地で7文字。「漢字四字仮名四字」コレクション
あと3府県でコンプリートなのですが…がんばります。
とにかく、当該の地名コレクションを見れば一発で分かるものばかりですが…答えは数日後に発表します。
翌週末には書き込みしようかな、と思っていたのに時間が取れずここまで引っ張ってしまいました。
遅ればせながらクイズの解答をご覧ください。
【「立神」コレクションには地図ではなくイオン公式HPに出てくる住所を根拠に登録してある地名があります。そのイオンは何県にある?】
答えは佐賀県、唐津市のイオン唐津ショッピングセンター。「立神」コレクション
Mapionでは小字が書かれていないエリアとなっているのですが、公式HPでは「佐賀県唐津市鏡字立神4671」。
これ、いろいろ調べているうちにある気付きがあり、それに関して書き込みしたい…と考えていたところでしたので出題してみました。
「書き込みしたい内容」は時間が取れましたら…
【「富士見坂」コレクションに登録されているものの中で、一番西にある富士見坂は何県にある?】
答えは香川県、丸亀市にある富士見坂。「富士見坂」コレクション
本家の富士山では無く、讃岐富士に対する「富士見」なのがミソ。
第五回クイ図の問四をもとに作成されたコレクションで、その解答をした方…MasAkaさんがいらっしゃったので瞬殺でした。
【地名コレクションの「同音異字系」カテゴリに含まれるコレクションは10件で、そのうち9件は担当者がグリグリさんですが、残り1件の担当者は誰?】
答えはスカンベルテクの鷹さん。「同音異字系」カテゴリ
新たなアイデアがありましたら落書き帳まで。
【「県境サイン」コレクションの「施設内にある県境サイン」カテゴリにはパーキングエリアが2つ登録されていますが、それはどこの都道府県境にある?】
答えは富山県|石川県の能越県境PAと福岡県|佐賀県の基山PA。「県境サイン」コレクション
能越県境PAは駐車スペースの路面にも印がありますし、実はPA外にもサインがあることを目視で確認しています。
【「百交差点」コレクションは交差点を通る国道の番号をいろいろな足し方で足した合計が百の倍数の交差点を集めたものですが、合計数字が一番大きい交差点の数字は?】
【その「数字が一番大きい百交差点」はどこの都道府県にある?】
答えは2400(パターン4)、大分県日田市の玉川交差点。「百交差点」コレクション
ちなみに次点は2300で愛知県設楽郡設楽町田峰にある三差路。
【地名コレクションで地名の収録数が一番少ないのは「高地」コレクション。では、2番目に少ないのは?】
答えは「橋立・天橋」コレクションで7件。
「高地」コレクションは5件。
増える余地は有るかもしれないので、もし情報ありましたら落書き帳まで。
【「漢字四字仮名四字」は漢字表記と読みがなの数が一致していれば5文字以上のものも登録してありますが、現時点で収録してるもので一番文字数の多いのは何文字?また、どこの都道府県にある?】
答えは秋田県秋田市の四ツ小屋小阿地で7文字。「漢字四字仮名四字」コレクション
あと3府県でコンプリートなのですが…がんばります。
| [114742] 2025年 7月 12日(土)19:01:36 | オーナー グリグリ |
| Re:北海道の自治体並び順について | |
[114740]
ばなしさんご指摘の外国人人口のデータ誤りについては早急に対応します。
市区町村データランキングの外国人について、全体を確認し正しい人口データで修正しました。
[114739] 海辺を飛ぶ鳥さん
「外国人」以外の市区町村データランキング(人口増減や医師1人あたり人口など)、
人口増減、医師1人あたり人口、医師1人あたり人口(2020年)についても正しい人口データで修正しました。
面白データベース検索(人口の素因数分解などのソート順)、市区町村雑学(「まち」と読む町、「ちょう」と読む町)あたりも修正が必要ですよね。
こちらについてはデータの間違いはないと思います。
以上、ご確認いただけましたらありがたいです。ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。
ばなしさんご指摘の外国人人口のデータ誤りについては早急に対応します。
市区町村データランキングの外国人について、全体を確認し正しい人口データで修正しました。
[114739] 海辺を飛ぶ鳥さん
「外国人」以外の市区町村データランキング(人口増減や医師1人あたり人口など)、
人口増減、医師1人あたり人口、医師1人あたり人口(2020年)についても正しい人口データで修正しました。
面白データベース検索(人口の素因数分解などのソート順)、市区町村雑学(「まち」と読む町、「ちょう」と読む町)あたりも修正が必要ですよね。
こちらについてはデータの間違いはないと思います。
以上、ご確認いただけましたらありがたいです。ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。
| [114741] 2025年 7月 12日(土)12:01:14【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 12日(土)12:37:27 | 白桃 さん |
| 日米トップ50都市の人口比較 | |
[114714]YT さん
ところで人口の順位と人口に法則性を探るとなると、地理学には「順位・規模法則」または「ランクサイズルール/rank-size rule」というのがあります。
学生時に、お酒を呑んでる時間の半分ぐらいは地理の勉強に勤しんできた???白桃ですが、「ランクサイズルール」という言葉は知りませんでした。ご紹介いただき有難うございました。もっとも、私が地理を学んだところは、「理論地理学」「数理地理学」「計量地理学」などとも呼称される「新しい地理学」と縁遠いところで、数学的(計量的)手法を用いたり、モデル化を通じて法則化を追求することには批判的であったように思います。
「はじめから『他のすべての条件が同一と仮定して』と前置きする態度は、地理学には存在しないのである。」と「新しい地理学」を真っ向から批判した有名な「伝統的地理学者」がいたそうですが、白桃も、この「伝統的地理学者」に親近感を抱きます。もっとも、数Ⅲすら学んでいない白桃に「新しい地理学」に対して、どうのこうのと言う能力もなく、資格もありません。しかしながら、「ランクサイズルール」に関しては、都市の分布や人口順位に関心を持っている方の多くが感覚的に理解?している事象なので、格別に取り上げるほどの「法則」でもないと考えます。そういう意味でも、YTさんが仰っているように
ランクサイズルールが適用できる範囲は相当に限定的といえるでしょう。
は全く同感であり、かつまた、
このランクサイズルールは、それでいて直線に乗らなかった場合の説明の方が重要だったのです。
こそが「ランクサイズルール」の一番の「肝(キモ)」と考えて良いのでしょう。
・・・
矛盾するようですが、「ランクサイズルール」は日本やアメリカなどの先進国にはある程度あてはまる、という事は否定致しません。
下表は、日本とアメリカの市域人口トップ50です。
(いずれも2020年国勢調査人口)
人口と順位の対数はとっていませんが、両国の同順位の都市の人口を比較すると、実に似通っている(白桃的には「好勝負」している)ことがわかります。特に、2位の横浜VSロサンゼルス、3位の大阪VSシカゴ、4位の名古屋VSヒューストン、は、千秋楽の三役揃い踏み後の取組に持っていきたいです。因みに同順位の「対戦成績」は
(全体:日本17勝/米国33勝)(20位まで:日本16勝/米国4勝)(21位~50位:日本1勝/米国29勝)
アメリカの都市の実力の見るのには、市域人口より、都市圏人口や広域都市圏人口のほうが良いかもしれませんが、そうすると、「ランクサイズルール」が適合しなくような感じがします。
なお、余談ですが、都市名の後ろの〇印は、NPB/MLBの本拠地球場がある所(※2024年までオークランドを本拠地としていたアスレチックスは2028年にラスベガスに移転するまではウエストサクラメントに本拠地(球場)を置いている)
あっ! 大谷スプラッシュヒット!!!(サンフランシスコ湾に飛び込むホームラン!)
(参考)50位に入らない本拠地球場の有る市
ところで人口の順位と人口に法則性を探るとなると、地理学には「順位・規模法則」または「ランクサイズルール/rank-size rule」というのがあります。
学生時に、お酒を呑んでる時間の半分ぐらいは地理の勉強に勤しんできた???白桃ですが、「ランクサイズルール」という言葉は知りませんでした。ご紹介いただき有難うございました。もっとも、私が地理を学んだところは、「理論地理学」「数理地理学」「計量地理学」などとも呼称される「新しい地理学」と縁遠いところで、数学的(計量的)手法を用いたり、モデル化を通じて法則化を追求することには批判的であったように思います。
「はじめから『他のすべての条件が同一と仮定して』と前置きする態度は、地理学には存在しないのである。」と「新しい地理学」を真っ向から批判した有名な「伝統的地理学者」がいたそうですが、白桃も、この「伝統的地理学者」に親近感を抱きます。もっとも、数Ⅲすら学んでいない白桃に「新しい地理学」に対して、どうのこうのと言う能力もなく、資格もありません。しかしながら、「ランクサイズルール」に関しては、都市の分布や人口順位に関心を持っている方の多くが感覚的に理解?している事象なので、格別に取り上げるほどの「法則」でもないと考えます。そういう意味でも、YTさんが仰っているように
ランクサイズルールが適用できる範囲は相当に限定的といえるでしょう。
は全く同感であり、かつまた、
このランクサイズルールは、それでいて直線に乗らなかった場合の説明の方が重要だったのです。
こそが「ランクサイズルール」の一番の「肝(キモ)」と考えて良いのでしょう。
・・・
矛盾するようですが、「ランクサイズルール」は日本やアメリカなどの先進国にはある程度あてはまる、という事は否定致しません。
下表は、日本とアメリカの市域人口トップ50です。
(いずれも2020年国勢調査人口)
| 都市 | 人口 | 順位 | 人口 | 都市 | --- | 都市 | 人口 | 順位 | 人口 | 都市 |
| 東京〇〇 | 9,733,276 | 1 | 8,804,190 | ニューヨーク〇〇 | 姫路 | 530,495 | 26 | 641,903 | ラスベガス※ | |
| 横浜〇 | 3,777,491 | 2 | 3,898,747 | ロサンゼルス〇 | 宇都宮 | 518,757 | 27 | 639,111 | デトロイト〇 | |
| 大阪〇 | 2,752,412 | 3 | 2,746,388 | シカゴ〇〇 | 松山 | 511,192 | 28 | 633,104 | メンフィス | |
| 名古屋〇 | 2,332,176 | 4 | 2,304,580 | ヒューストン〇 | 松戸 | 498,232 | 29 | 633,045 | ルイビル | |
| 札幌〇 | 1,973,395 | 5 | 1,608,139 | フェニックス〇 | 市川 | 496,676 | 30 | 585,708 | ボルチモア〇 | |
| 福岡〇 | 1,612,392 | 6 | 1,603,797 | フィラデルフィア〇 | 東大阪 | 493,940 | 31 | 577,222 | ミルウォーキー〇 | |
| 川崎 | 1,538,262 | 7 | 1,434,625 | サンアントニオ | 西宮〇 | 485,587 | 32 | 564,559 | アルバカーキ | |
| 神戸 | 1,525,152 | 8 | 1,386,932 | サンディエゴ〇 | 大分 | 475,614 | 33 | 542,629 | ツーソン | |
| 京都 | 1,463,723 | 9 | 1,304,379 | ダラス | 倉敷 | 474,592 | 34 | 542,107 | フレズノ | |
| さいたま | 1,324,025 | 10 | 1,013,240 | サンノゼ | 金沢 | 463,254 | 35 | 524,943 | サクラメント | |
| 広島〇 | 1,200,754 | 11 | 961,855 | オースティン | 福山 | 460,930 | 36 | 508,090 | カンザスシティ〇 | |
| 仙台〇 | 1,096,704 | 12 | 949,611 | ジャクソンビル | 尼崎 | 459,593 | 37 | 504,258 | メサ | |
| 千葉〇 | 974,951 | 13 | 918,915 | フォートワース | 藤沢 | 436,905 | 38 | 498,715 | アトランタ〇 | |
| 北九州 | 939,029 | 14 | 905,748 | コロンバス | 町田 | 431,079 | 39 | 486,051 | オマハ | |
| 堺 | 826,161 | 151 | 887,642 | インディアナポリス | 柏 | 426,468 | 40 | 478,961 | コロラドスプリングス | |
| 浜松 | 790,718 | 16 | 874,579 | シャーロット | 豊田 | 422,330 | 41 | 467,665 | ローリー | |
| 新潟 | 789,275 | 17 | 873,965 | サンフランシスコ〇 | 高松 | 417,496 | 42 | 466,742 | ロングビーチ | |
| 熊本 | 738,865 | 18 | 737,015 | シアトル〇 | 富山 | 413,938 | 43 | 459,470 | バージニアビーチ | |
| 相模原 | 725,493 | 19 | 715,522 | デンバー〇 | 長崎 | 409,118 | 44 | 442,241 | マイアミ〇 | |
| 岡山 | 724,691 | 20 | 689,545 | ワシントン〇 | 岐阜 | 402,557 | 45 | 440,646 | オークランド※ | |
| 静岡 | 693,389 | 21 | 689,447 | ナッシュビル | 豊中 | 401,558 | 46 | 429,954 | ミネアポリス〇 | |
| 船橋 | 642,907 | 22 | 681,054 | オクラホマシティ | 宮崎 | 401,339 | 47 | 413,066 | タルサ | |
| 川口 | 594,274 | 23 | 678,815 | エルパソ | 枚方 | 397,289 | 48 | 403,455 | ベーカーズフィールド | |
| 鹿児島 | 593,128 | 24 | 675,647 | ボストン〇 | 横須賀 | 388,078 | 49 | 397,532 | ウィチタ | |
| 八王子 | 579,355 | 25 | 652,503 | ポートランド | 吹田 | 385,567 | 50 | 394,266 | アーリントン〇 |
(全体:日本17勝/米国33勝)(20位まで:日本16勝/米国4勝)(21位~50位:日本1勝/米国29勝)
アメリカの都市の実力の見るのには、市域人口より、都市圏人口や広域都市圏人口のほうが良いかもしれませんが、そうすると、「ランクサイズルール」が適合しなくような感じがします。
なお、余談ですが、都市名の後ろの〇印は、NPB/MLBの本拠地球場がある所(※2024年までオークランドを本拠地としていたアスレチックスは2028年にラスベガスに移転するまではウエストサクラメントに本拠地(球場)を置いている)
あっ! 大谷スプラッシュヒット!!!(サンフランシスコ湾に飛び込むホームラン!)
(参考)50位に入らない本拠地球場の有る市
| 順位 | 都市 | 国勢調査(2020年)人口 |
| 54 | クリーブランド | 372,624 |
| 56 | アナハイム | 346,824 |
| 61 | 所沢 | 342,464 |
| 65 | シンシナティ | 309,317 |
| 68 | ピッツバーグ | 302,971 |
| 69 | セントルイス | 301,578 |
| 85 | セントピーターズバーグ | 258,308 |
| [114740] 2025年 7月 12日(土)11:45:27 | オーナー グリグリ |
| 北海道の自治体並び順について | |
[114736] ばなしさん、[114739] 海辺を飛ぶ鳥さん、ご指摘有難うございます。取り急ぎ返信します。北海道の自治体並び順に関しては、過去に議論になっていますが悩ましいところがあります。サイトで統一できていません。[98049]や[76346]などを参照してください。私自身この件については現時点で記憶が不確かになっており、今現時点では正確に言えませんが、ばなしさんご指摘の外国人人口のデータ誤りについては早急に対応します。他にもデータに誤りがあるページがありましたらご指摘ください。自治体並び順の件については、コード順に統一するのが単純でスッキリするかもしれませんが、何か良いアイディアがある方はご提案ください。
| [114739] 2025年 7月 12日(土)11:29:22【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 12日(土)11:34:48 | 海辺を飛ぶ鳥 さん |
| データベース検索のコード順 | |
[114736]ばなしさん
次に、2015年と2020年いずれも、大空町の掲載位置にずれがあることによるものです。e-Statで確認した限りでは、国勢調査のデータは自治体コード順に並んでおり、大空町はオホーツク総合振興局で一番最後(雄武町のあと)にきています。一方このサイトのデータベース検索で「自治体コード順」に並べると、同じ網走郡に属する美幌町、津別町の直後に大空町がきています。
>グリグリさん
確認・修正中だと思うので、既に気づいかれているかもしれませんが、(全て確認した訳では無いので他にもあるかもしれませんが)データベース検索のコード順そのもの、「外国人」以外の市区町村データランキング(人口増減や医師1人あたり人口など)、面白データベース検索(人口の素因数分解などのソート順)、市区町村雑学(「まち」と読む町、「ちょう」と読む町)あたりも修正が必要ですよね。
【1】特に、データ自体は問題ないが、並び順だけは直さないといけないケースは他にありそうです。
それと、データベース検索のコード順なのですが、大空町以外にも幌延町と洞爺湖町の掲載位置もズレているようです。具体的には、
となっています。
次に、2015年と2020年いずれも、大空町の掲載位置にずれがあることによるものです。e-Statで確認した限りでは、国勢調査のデータは自治体コード順に並んでおり、大空町はオホーツク総合振興局で一番最後(雄武町のあと)にきています。一方このサイトのデータベース検索で「自治体コード順」に並べると、同じ網走郡に属する美幌町、津別町の直後に大空町がきています。
>グリグリさん
確認・修正中だと思うので、既に気づいかれているかもしれませんが、(全て確認した訳では無いので他にもあるかもしれませんが)データベース検索のコード順そのもの、「外国人」以外の市区町村データランキング(人口増減や医師1人あたり人口など)、面白データベース検索(人口の素因数分解などのソート順)、市区町村雑学(「まち」と読む町、「ちょう」と読む町)あたりも修正が必要ですよね。
【1】特に、データ自体は問題ないが、並び順だけは直さないといけないケースは他にありそうです。
それと、データベース検索のコード順なのですが、大空町以外にも幌延町と洞爺湖町の掲載位置もズレているようです。具体的には、
| e-Statや市区町村の役所・役場一覧 | データベース検索 |
| 礼文→利尻→利尻富士→幌延 | 幌延→礼文→利尻→利尻富士 |
| 壮瞥→白老→厚真→洞爺湖 | 洞爺湖→壮瞥→白老→厚真 |
| [114738] 2025年 7月 12日(土)11:28:09 | BANDALGOM さん |
| 島田市などの合併 | |
[114726] ゆうたに さん
川根町,中川根町,本川根町は三川根と呼ばれ交流も深く,協力し合っていたのになぜ平成の大合併で,川根本町と島田市川根地区に分かれてしまったのですか。後からでも川根町は川根本町に編入すればよかったのではないでしょうか。
「市区町村変遷情報」からの受け売りですが…。
2002年4月に、まず島田市と金谷町・中川根町・本川根町・川根町・吉田町の6市町で勉強会を設置しましたが、同年11月に島田市と金谷町・川根町が任意協議会設置で合意しました。しかし、島田市と金谷町は「中川根町・本川根町を含む5市町」の合併を主張した一方、川根町は「5市町以上」での合併を検討し、その結果、03年8月には川根町が合併協議からの離脱を表明しました。
その後、川根町は中川根町・本川根町に対し、4回にわたって合併協議を申し入れましたが、中川根町・本川根町は川根町の申し入れを拒否し、川根町は合併特例法期限内での合併を断念しました。
04年10月、川根町では合併を断念したことに関して、町長と町議会に対する解職・解散請求が起こされ、川根町議全員が辞職願を提出し、翌月の川根町長の解職の是非を問う住民投票でも「解職に賛成」が76.5%、「解職に反対」は23.5%という結果になりました。
05年5月に島田市と金谷町は合併しましたが、同年12月に川根町が島田市との合併を検討し始め、島田市に合併協議を申し入れて、2市町での合併を検討し、翌年に合併準備会を設置、12月には法定協議会を設置して、07年8月に合併協定に調印しました。
川根町,中川根町,本川根町は三川根と呼ばれ交流も深く,協力し合っていたのになぜ平成の大合併で,川根本町と島田市川根地区に分かれてしまったのですか。後からでも川根町は川根本町に編入すればよかったのではないでしょうか。
「市区町村変遷情報」からの受け売りですが…。
2002年4月に、まず島田市と金谷町・中川根町・本川根町・川根町・吉田町の6市町で勉強会を設置しましたが、同年11月に島田市と金谷町・川根町が任意協議会設置で合意しました。しかし、島田市と金谷町は「中川根町・本川根町を含む5市町」の合併を主張した一方、川根町は「5市町以上」での合併を検討し、その結果、03年8月には川根町が合併協議からの離脱を表明しました。
その後、川根町は中川根町・本川根町に対し、4回にわたって合併協議を申し入れましたが、中川根町・本川根町は川根町の申し入れを拒否し、川根町は合併特例法期限内での合併を断念しました。
04年10月、川根町では合併を断念したことに関して、町長と町議会に対する解職・解散請求が起こされ、川根町議全員が辞職願を提出し、翌月の川根町長の解職の是非を問う住民投票でも「解職に賛成」が76.5%、「解職に反対」は23.5%という結果になりました。
05年5月に島田市と金谷町は合併しましたが、同年12月に川根町が島田市との合併を検討し始め、島田市に合併協議を申し入れて、2市町での合併を検討し、翌年に合併準備会を設置、12月には法定協議会を設置して、07年8月に合併協定に調印しました。
| [114737] 2025年 7月 12日(土)11:12:11 | オーナー グリグリ |
| 7月19日 (土) 9:00 第七十二回全国の市十番勝負が始まります! | |
気が付けば一週間前です。今度の土曜日午前9時から全国の市十番勝負の開始です。今回も多くの皆さんのご参加をお待ちしています。ただいま問題を詰めているところです。皆さんにより楽しんでいただけるよう、開始まで問題のレベルアップを行います。お楽しみに。
| [114736] 2025年 7月 12日(土)00:37:57 | ばなし さん |
| 外国人人口について | |
市区町村データランキングの外国人を見ていて、雄武町の外国人比率がやけに高いなぁと前から不思議に思っていました。しかし数値をよくよく確認してみると、雄武町をはじめ北海道の一部町村で人口比がおかしくなっています。どうやら外国人人口は合っているのですが、人口比を算出するために使用している総人口が違う自治体のものになっているために発生しているようです。
まず、2015年の「十勝、釧路、根室管内を除く」北海道の各町村における総人口が合いません。これについては、本来であれば町村の部分が「石狩→渡島→檜山→後志→空知→上川→留萌→宗谷→オホーツク→胆振→日高(→十勝→釧路→根室)」の順番で並ぶはずが、なぜか総人口だけ「空知→石狩→後志→胆振→日高→渡島→檜山→上川→留萌→宗谷→オホーツク(→十勝→釧路→根室)」の順番で並んでしまっているのが原因です。
例えば2015年の当別町は外国人が35人、人口比で0.44%となっていますが、当別町の2015年の総人口は17,278人のため、正しくは人口比で0.20%です。これは南幌町の7,927人を参照しているために発生しているものです。
次に、2015年と2020年いずれも、大空町の掲載位置にずれがあることによるものです。e-Statで確認した限りでは、国勢調査のデータは自治体コード順に並んでおり、大空町はオホーツク総合振興局で一番最後(雄武町のあと)にきています。一方このサイトのデータベース検索で「自治体コード順」に並べると、同じ網走郡に属する美幌町、津別町の直後に大空町がきています。これが原因で、オホーツク総合振興局の大空町および斜里郡、常呂郡、紋別郡の町村の総人口がひとつずつずれてしまっていると思われます。2020年の雄武町の外国人比率がやけに高くなっていたのは、雄武町の外国人人口を、自治体コード順でひとつ前にあたる西興部村の総人口で割っていたことによるもの、ということです。
この文章で状況がちゃんと伝わっているか不安ですが、おそらくこの2点を修正すれば正しいデータになるかと思います。グリグリさん、お忙しいところ恐れ入りますが、こちら修正のほどよろしくお願いいたします。
まず、2015年の「十勝、釧路、根室管内を除く」北海道の各町村における総人口が合いません。これについては、本来であれば町村の部分が「石狩→渡島→檜山→後志→空知→上川→留萌→宗谷→オホーツク→胆振→日高(→十勝→釧路→根室)」の順番で並ぶはずが、なぜか総人口だけ「空知→石狩→後志→胆振→日高→渡島→檜山→上川→留萌→宗谷→オホーツク(→十勝→釧路→根室)」の順番で並んでしまっているのが原因です。
例えば2015年の当別町は外国人が35人、人口比で0.44%となっていますが、当別町の2015年の総人口は17,278人のため、正しくは人口比で0.20%です。これは南幌町の7,927人を参照しているために発生しているものです。
次に、2015年と2020年いずれも、大空町の掲載位置にずれがあることによるものです。e-Statで確認した限りでは、国勢調査のデータは自治体コード順に並んでおり、大空町はオホーツク総合振興局で一番最後(雄武町のあと)にきています。一方このサイトのデータベース検索で「自治体コード順」に並べると、同じ網走郡に属する美幌町、津別町の直後に大空町がきています。これが原因で、オホーツク総合振興局の大空町および斜里郡、常呂郡、紋別郡の町村の総人口がひとつずつずれてしまっていると思われます。2020年の雄武町の外国人比率がやけに高くなっていたのは、雄武町の外国人人口を、自治体コード順でひとつ前にあたる西興部村の総人口で割っていたことによるもの、ということです。
この文章で状況がちゃんと伝わっているか不安ですが、おそらくこの2点を修正すれば正しいデータになるかと思います。グリグリさん、お忙しいところ恐れ入りますが、こちら修正のほどよろしくお願いいたします。
| [114735] 2025年 7月 11日(金)23:02:46 | ピーくん さん |
| 難度は高い | |
下総みなと さん
はじめまして、メンバー登録されましたらグリグリさまから広報メディアの情報提供のサービスが受けられますのでそちらでは落書き帳より便利です。メンバー登録は10件の書き込みで可能です。
広島県なので珠洲市は読めませんでした。難度は高いです目くじらたてることではありません。
小豆島中央高校負けました。小豆島の方がいました。ジャイアンツファンが多いです。テレビたくさん見られるそうです。テレビせとうちがあって羨ましいです。2つの町どうしてもひとつになれないくらい仲が悪いです。
明日と明後日の沖縄の天気が悪いです。宜野座高校頑張ってほしいです。いつも沖縄県は早いが何かしら理由があるのかな?
はじめまして、メンバー登録されましたらグリグリさまから広報メディアの情報提供のサービスが受けられますのでそちらでは落書き帳より便利です。メンバー登録は10件の書き込みで可能です。
広島県なので珠洲市は読めませんでした。難度は高いです目くじらたてることではありません。
小豆島中央高校負けました。小豆島の方がいました。ジャイアンツファンが多いです。テレビたくさん見られるそうです。テレビせとうちがあって羨ましいです。2つの町どうしてもひとつになれないくらい仲が悪いです。
明日と明後日の沖縄の天気が悪いです。宜野座高校頑張ってほしいです。いつも沖縄県は早いが何かしら理由があるのかな?
| [114734] 2025年 7月 11日(金)15:53:10 | オーナー グリグリ |
| Re:3月26日 | |
[114733] 茨城県ニキさん
区町村などをご存知の方は、教えていただけると幸いです。
データベース検索 (詳細検索) で市区町村の施行日を検索表示させてページ内検索("3.26"で)するのが一番簡単でしょう。
施行日の新旧順の並び替えはできますが、月日順の並び替えはできませんので。
区町村などをご存知の方は、教えていただけると幸いです。
データベース検索 (詳細検索) で市区町村の施行日を検索表示させてページ内検索("3.26"で)するのが一番簡単でしょう。
施行日の新旧順の並び替えはできますが、月日順の並び替えはできませんので。
| [114733] 2025年 7月 11日(金)14:58:48 | 茨城県ニキ さん |
| 3月26日 | |
[114724] ピーくんさん
お問い合わせいただきました町長の生年月日についてですが、
昭和43年3月26日です。
邑南町の大屋町長、3/26生まれなのですね。僕も3/26生まれなので、勝手に親近感を抱いています。
3/26といえば、2016年に北海道新幹線が開業しましたね。ちなみに僕はそれよりは年上です。笑
他の有名な方は、俳優の柳楽優弥さん(1990年・平成2年)や作家の京極夏彦さん(1963年・昭和38年)などが3/26日生まれだそうです。
市町村では、(僕が調べられた範囲では)2006年(平成18年)に、飯塚市が市制施行したそうです。区町村などをご存知の方は、教えていただけると幸いです。
お問い合わせいただきました町長の生年月日についてですが、
昭和43年3月26日です。
邑南町の大屋町長、3/26生まれなのですね。僕も3/26生まれなので、勝手に親近感を抱いています。
3/26といえば、2016年に北海道新幹線が開業しましたね。ちなみに僕はそれよりは年上です。笑
他の有名な方は、俳優の柳楽優弥さん(1990年・平成2年)や作家の京極夏彦さん(1963年・昭和38年)などが3/26日生まれだそうです。
市町村では、(僕が調べられた範囲では)2006年(平成18年)に、飯塚市が市制施行したそうです。区町村などをご存知の方は、教えていただけると幸いです。
| [114732] 2025年 7月 11日(金)14:53:44 | 下総みなと さん |
| 市町村の公式Xの変更情報 ~青森・岩手・宮城編~ | |
公式Xの変更情報 青森・岩手・宮城編です。
今回はキャラクターや観光協会を含まず、公式のものを選定しました。
今回はキャラクターや観光協会を含まず、公式のものを選定しました。
| 都道府県名 | 自治体名 | 旧アカウントID | 新アカウントID | 備考 |
| 青森県 | 十和田市 | @TowadaCity | @towada_city | |
| 外ヶ浜町 | @Cg6BL4QFRSUqc5Y | @SotogahamaTown | ||
| 深浦町 | @Fukaura_town | - | 消滅 | |
| 大間町 | - | @ooma_town | 更新停止中 | |
| 風間浦村 | - | @kazamauramura | ソース:風間浦村HP | |
| 新郷村 | - | @villshingo | ||
| 岩手県 | 大船渡市 | @ofunaton | - | キャラクターのアカウントのため掲載非推奨 |
| 滝沢市 | @chagpon | - | 同上 | |
| 大槌町 | - | @otsuchi_PR | 観光PR特化だが、公式 | |
| 宮城県 | 多賀城市 | @webmaster003 | - | 消滅 |
| 涌谷町 | - | @WakuyaT |
| [114731] 2025年 7月 10日(木)07:04:53 | 白桃 さん |
| メンバー紹介編集&八王子と藤沢 | |
お蔭さまで昨日、退院できました。もう、同種目四度目の手術・入院ですからすっかり慣れてきました。医師から(退院後の生活について)「お酒は控えてください。」と今回もご忠告を受けていますが、「控え目に呑んでください。」と理解し、昨夜早速、新潟県村上市のお酒を頂きました。(^^;
入院中の記事で一番気になったのが、[114701]かぱぷう さんの
どなたか、メンバー紹介編集担当を引き受けていただける方はいらっしゃいませんでしょうか。
です。
多くの方も私と同じような思いだと推察しますが、かぱぷうさんの軽妙洒脱で温かみのある「メンバー紹介」は、一つの読みものとしても”読みごたえのある”「文芸作品」([103949]グリグリさん)と言って間違いありません。
最近は文章作成力と空想力が低下しており、
と書かれておりますが、あの空想力?想像力?創造力?は、余人をもって代えがたいものではないでしょうか。
ご多忙になり、メンバー紹介編集がどうしても負担になってきた、というのなら致し方ありませんが、出来うるならば今まで通りお願いしたい、と個人的には思っています。それと同時に、今後の新規登録者のメンバー紹介に関して、本人の希望によって「自己紹介もあり」という形をとれないものか?と勝手に考えています。
[114696]白桃
昭和40〜45年頃の話。
山形県米沢の女子大生をアリバイ工作に利用。夜のドライブで相模湖と称して相模湾に連れていく。その前に通過した都市X市を八王子とごまかす。
人口が同じぐらい、と作者は言うが、白桃の感覚とは少し違いますが都会度は確かに同じ。
果たしてX市とは?
上は、入院時に持ち込んだ文庫本(ミステリー短編集)からの出題なので、本当にネタバレになってしまいますので、著者(「本格推理」の旗頭)と短編のタイトルは伏せますが、犯行現場のX市は藤沢市です。
著者は作品の中で
東京からの走行距離もほぼ等しいし、八王子の人口は二十九万で藤沢は二十五万五千だから、都会としての規模もほぼ等しい。
と書いております。この短編の初出が1976年であることから、私は「昭和40〜45頃の話。」としましたが、下の両市の人口推移から見て、どうやら、昭和49年(1974年)頃の話だったようです。因みに、1974年1月1日の八王子市の住民基本台帳人口は287,869人(日本人のみ)となっています。
「都会度は確かに同じ。」と書きましたが、これは現在の話です。当時はどうだったのか…。なお、白桃の「人口段位」で言うと、現在、八王子が七段、藤沢が六段ですが、当時は両市とも六段でした。
「相模湖と相模湾」でふと思いだしたのが、「それまで日月潭しか知らなかった台湾の子供が、基隆(キールン)湾を見て『海は、日月潭の4倍ぐらいあった。』と作文に書いていた。」という父の言葉です。
入院中の記事で一番気になったのが、[114701]かぱぷう さんの
どなたか、メンバー紹介編集担当を引き受けていただける方はいらっしゃいませんでしょうか。
です。
多くの方も私と同じような思いだと推察しますが、かぱぷうさんの軽妙洒脱で温かみのある「メンバー紹介」は、一つの読みものとしても”読みごたえのある”「文芸作品」([103949]グリグリさん)と言って間違いありません。
最近は文章作成力と空想力が低下しており、
と書かれておりますが、あの空想力?想像力?創造力?は、余人をもって代えがたいものではないでしょうか。
ご多忙になり、メンバー紹介編集がどうしても負担になってきた、というのなら致し方ありませんが、出来うるならば今まで通りお願いしたい、と個人的には思っています。それと同時に、今後の新規登録者のメンバー紹介に関して、本人の希望によって「自己紹介もあり」という形をとれないものか?と勝手に考えています。
[114696]白桃
昭和40〜45年頃の話。
山形県米沢の女子大生をアリバイ工作に利用。夜のドライブで相模湖と称して相模湾に連れていく。その前に通過した都市X市を八王子とごまかす。
人口が同じぐらい、と作者は言うが、白桃の感覚とは少し違いますが都会度は確かに同じ。
果たしてX市とは?
上は、入院時に持ち込んだ文庫本(ミステリー短編集)からの出題なので、本当にネタバレになってしまいますので、著者(「本格推理」の旗頭)と短編のタイトルは伏せますが、犯行現場のX市は藤沢市です。
著者は作品の中で
東京からの走行距離もほぼ等しいし、八王子の人口は二十九万で藤沢は二十五万五千だから、都会としての規模もほぼ等しい。
と書いております。この短編の初出が1976年であることから、私は「昭和40〜45頃の話。」としましたが、下の両市の人口推移から見て、どうやら、昭和49年(1974年)頃の話だったようです。因みに、1974年1月1日の八王子市の住民基本台帳人口は287,869人(日本人のみ)となっています。
| 国勢調査年 | 八王子 | 藤沢 |
| 1965年 | 207,753 | 175,183 |
| 1970年 | 253,527 | 228,978 |
| 1975年 | 322,580 | 265,975 |
| 1980年 | 387,178 | 300,248 |
| 1985年 | 426,654 | 328,387 |
| 1990年 | 466,347 | 350,330 |
| 1995年 | 503,363 | 368,651 |
| 2000年 | 536,046 | 379,185 |
| 2005年 | 560,012 | 396,014 |
| 2010年 | 580,053 | 409,657 |
| 2015年 | 577,513 | 423,894 |
| 2020年 | 579,355 | 436,905 |
「相模湖と相模湾」でふと思いだしたのが、「それまで日月潭しか知らなかった台湾の子供が、基隆(キールン)湾を見て『海は、日月潭の4倍ぐらいあった。』と作文に書いていた。」という父の言葉です。
| [114730] 2025年 7月 9日(水)18:10:36 | 下総みなと さん |
| Re:公式メディアについて etc. | |
[114727] グリグリさん
回答ありがとうございます。
公式アカウントの掲載、よろしくお願いします。
ふるさと納税、キャラクター、観光協会など、サブテーマや関連施設のアカウントについては対象外としています。
わかりました。次回以降も記事にてメディアについて記事で情報提供することがあれば、総合的な公式アカウントのみ記載するようにします。
この基準についてはトップページの説明にはしっかり記述するようにします。
これについても、記述された基準に基づいて現行の掲載内容からの修正内容などを書いていけたらと思います。ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
公式アカウントの掲載、よろしくお願いします。
ふるさと納税、キャラクター、観光協会など、サブテーマや関連施設のアカウントについては対象外としています。
わかりました。次回以降も記事にてメディアについて記事で情報提供することがあれば、総合的な公式アカウントのみ記載するようにします。
この基準についてはトップページの説明にはしっかり記述するようにします。
これについても、記述された基準に基づいて現行の掲載内容からの修正内容などを書いていけたらと思います。ありがとうございました。
| [114729] 2025年 7月 9日(水)17:54:55【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 9日(水)18:56:46 | オーナー グリグリ |
| 全国の現役首長一覧リリース延期 | |
| [114728] 2025年 7月 9日(水)17:50:57 | ピーくん さん |
| 大崎上島町について | |
[94662]Nさん
ついに大崎上島町にローソンが出来ました。
広島県内にある唯一の離島の町=大崎上島町に、初めて24時間営業のコンビニエンスストアがオープンしました。中国放送
自治体に一応コンビニがあることになりました。
ついに大崎上島町にローソンが出来ました。
広島県内にある唯一の離島の町=大崎上島町に、初めて24時間営業のコンビニエンスストアがオープンしました。中国放送
自治体に一応コンビニがあることになりました。
| [114727] 2025年 7月 9日(水)17:50:50 | オーナー グリグリ |
| 公式メディアについて etc. | |
[114722][114723] 下総みなとさん、公式メディア情報を有難うございます。
掲載に値するか怪しいものもありますが、
とおっしゃっているように、ふるさと納税、キャラクター、観光協会など、サブテーマや関連施設のアカウントについては対象外としています。多少曖昧なものもありますが自治体の総合的な公式アカウントを対象とします。この基準についてはトップページの説明にはしっかり記述するようにします。
[114724] ピーくんさん、邑南町長の生年月日情報を有難うございます。私の方にも総務課から回答が来ました。
[114725] ピーくんさん、釜石市の新庁舎移転情報も有難うございます。情報更新済みです。
掲載に値するか怪しいものもありますが、
とおっしゃっているように、ふるさと納税、キャラクター、観光協会など、サブテーマや関連施設のアカウントについては対象外としています。多少曖昧なものもありますが自治体の総合的な公式アカウントを対象とします。この基準についてはトップページの説明にはしっかり記述するようにします。
[114724] ピーくんさん、邑南町長の生年月日情報を有難うございます。私の方にも総務課から回答が来ました。
[114725] ピーくんさん、釜石市の新庁舎移転情報も有難うございます。情報更新済みです。
| [114726] 2025年 7月 9日(水)16:10:47 | ゆうたに さん |
| 川根についての質問 | |
川根町,中川根町,本川根町は三川根と呼ばれ交流も深く,協力し合っていたのになぜ平成の大合併で,川根本町と島田市川根地区に分かれてしまったのですか。後からでも川根町は川根本町に編入すればよかったのではないでしょうか。
| [114725] 2025年 7月 9日(水)14:22:12 | ピーくん さん |
| 釜石市について | |
現時点で釜石市の公式YouTubeは開設しておりません。
新市庁舎は令和8年3月の完成、令和8年5月のゴールデンウイーク明けの5月中開庁予定です。
よろしくお願いいたします。
----------------------------------------------------
釜石市 総務企画部
オープンシティ・プロモーション室
釜石市の新庁舎の開庁日は令和8年5月になっています。
グリグリさまよろしくお願いします。
また、釜石市の公式YouTubeはありませんでした。
新市庁舎は令和8年3月の完成、令和8年5月のゴールデンウイーク明けの5月中開庁予定です。
よろしくお願いいたします。
----------------------------------------------------
釜石市 総務企画部
オープンシティ・プロモーション室
釜石市の新庁舎の開庁日は令和8年5月になっています。
グリグリさまよろしくお願いします。
また、釜石市の公式YouTubeはありませんでした。
| [114724] 2025年 7月 9日(水)14:13:58 | ピーくん さん |
| 生年月日判明 | |
お問い合わせいただきました町長の生年月日についてですが、
昭和43年3月26日です。
邑南町 総務課
大屋町長の生年月日が判明しました。
グリグリさま
よろしくお願いします。これで島根県はすべての首長の生年月日が判明しました。
昭和43年3月26日です。
邑南町 総務課
大屋町長の生年月日が判明しました。
グリグリさま
よろしくお願いします。これで島根県はすべての首長の生年月日が判明しました。
| [114723] 2025年 7月 9日(水)13:29:08 | 下総みなと さん |
| これまでの記事の訂正・補足 | |
連続の書き込みとなり失礼いたします。
これまでの書き込みで訂正・補足をさせて頂きます。
[114716] 訂正
こちらの記事のリンク、教員採用試験ではなく、職員採用試験でした。
[114722] 補足
こちらの記事の「旧アカウントID」というのは、当サイトの都道府県市区町村の公式メディア-北海道に記載されている、リンク切れとなっているアカウントのIDのこと。
仮に記載する際は、今回は浦河町の場所にあったXリンクを一度削除し、置き換えて頂きたいです。
他の記載されているアカウントは、上記ページに記載されていないアカウントの一覧で、仮に記載する際は新たに追加して頂きたいものです。
これまでの書き込みで訂正・補足をさせて頂きます。
[114716] 訂正
こちらの記事のリンク、教員採用試験ではなく、職員採用試験でした。
[114722] 補足
こちらの記事の「旧アカウントID」というのは、当サイトの都道府県市区町村の公式メディア-北海道に記載されている、リンク切れとなっているアカウントのIDのこと。
仮に記載する際は、今回は浦河町の場所にあったXリンクを一度削除し、置き換えて頂きたいです。
他の記載されているアカウントは、上記ページに記載されていないアカウントの一覧で、仮に記載する際は新たに追加して頂きたいものです。
| [114722] 2025年 7月 9日(水)13:15:10 | 下総みなと さん |
| 市町村の公式メディアの変更情報 ~北海道編~ | |
市町村長情報のほかに、市町村の公式メディア・SNSについての情報を収集してます。
現在は手始めにXについての情報を収集しています。
その中で、アカウントが消えていたり、変更されていたり、アカウントが見つかったり、色々あったので、掲載に値するか怪しいものもありますが、当記事では北海道のXアカウントに関する情報を挙げておきます。
現在は手始めにXについての情報を収集しています。
その中で、アカウントが消えていたり、変更されていたり、アカウントが見つかったり、色々あったので、掲載に値するか怪しいものもありますが、当記事では北海道のXアカウントに関する情報を挙げておきます。
| 自治体名 | 旧アカウントID | 新アカウントID | 備考 |
| 苫小牧市 | - | @kankotomakomai | 公式ではあるが、観光振興課 |
| 美唄市 | - | @HokkaidoBibai | 公式ではあるが、経済観光課 |
| 紋別市 | - | @mombetsu_ijyuu | ポスト停止中だが、サブスク登録中 |
| 砂川市 | - | @sunagawa_full | ふるさと納税のアカウント |
| 登別市 | - | @noboribetsu_fu | |
| 北斗市 | - | @hokutoinfo | 観光協会アカウント |
| - | @hokuto_chara | 北斗市のキャラクター(更新停止中) | |
| 木古内町 | - | @kikokikonai | 木古内町のキャラクター |
| 七飯町 | - | @nanaenow | |
| 奥尻町 | - | @okushiri_f | ふるさと納税のアカウント |
| せたな町 | - | @matasetana_0901 | 観光協会のアカウント |
| 寿都町 | - | @suttu3710 | 観光物産協会のアカウント |
| 留寿都村 | - | @rusutsu_fan | ふるさと納税アカウント、更新停止中 |
| 倶知安町 | - | @STUDIO_JAGATA | 倶知安町のキャラクター |
| 共和町 | - | @kyowa_official_ | 観光協会のアカウントではあるものの、IDにはofficialを使用 |
| 神恵内村 | - | @kamoenai_mura | |
| 仁木町 | - | @nikibo_dayo | 仁木町のキャラクター |
| 妹背牛町 | - | @JmAhDxodO6A7k0h | ふるさと納税のアカウント |
| 雨竜町 | - | @uryunuma_info | 観光協会のアカウント |
| 上川町 | - | @kamikawa_tyou | 既に記載されているものとは別のアカウント |
| 東川町 | - | @higashikawatown | |
| - | @higashikawa_kab | 株主制度・ふるさと納税のアカウント | |
| 美瑛町 | - | @bieitown | 試験運用、更新停止中 |
| - | @Okanomachi_biei | 観光協会のアカウント | |
| 剣淵町 | - | @N1sd1CGbP4EDC8f | 観光協会アカウント、更新停止中 |
| 下川町 | - | @shimokawanote | 更新停止中 |
| - | @shimokawalife | 移住サポートアカウント | |
| 中川町 | - | @nakagawatourism | 観光協会アカウント |
| 初山別村 | - | @Syosambetsu | 更新停止中 |
| 枝幸町 | - | @esashi_kankou | |
| - | @furusato_esashi | ふるさと納税のアカウント | |
| 豊富町 | - | @toyokan1728 | 観光協会のアカウント |
| 美幌町 | - | @bihorofurusato | ふるさと納税のアカウント |
| 津別町 | - | @ft_tsubetsu | 旧ふるさと納税アカウント |
| 興部町 | - | @okoppetown | |
| 厚真町 | - | @atsuma_tourism | 観光協会のアカウント |
| - | @atsumaru_kun | 厚真町のキャラクター | |
| 洞爺湖町 | - | @toyako_official | |
| - | @toyako_mankitsu | 観光発信アカウント | |
| 日高町 | - | @hidaka_furusato | ふるさと納税のアカウント |
| 浦河町 | @urakawa_bosai | @urakawa_town | |
| 鹿追町 | - | @ShikaoiFurusato | ふるさと納税のアカウント |
| 大樹町 | - | @taiki_furusato | ふるさと納税のアカウント |
| [114721] 2025年 7月 9日(水)06:27:08 | ワルイージ推し さん |
| Re:スウェーデンヒルズ行けませんでした | |
残念…(泣)
私の地元にある場所ですねー
17年ぶりですか、私はその時6歳ですね
また時間がある時に来られると嬉しいですね
私の地元にある場所ですねー
17年ぶりですか、私はその時6歳ですね
また時間がある時に来られると嬉しいですね
| [114720] 2025年 7月 8日(火)22:05:05【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 9日(水)06:56:59 | オーナー グリグリ |
| 全国の現役首長一覧 (評価版) 更新 | |
連続無投票の精査は全都道府県について完了しました。まだ見落としや間違いが含まれていると思いますが、そろそろ正式リリース(一般公開)したいと思っています。明日中にはリリースする予定です。リリース後も随時更新する予定なので、ご指摘についてはいつでも構いませんので、今後ともよろしくお願いいたします。なお、データ入力中に不確定な事項も見付かっており、具体的に情報提示して皆さんのご協力を得たいと考えています。→ 全国の現役首長一覧 (評価版)
【追記】[114711] Nさん「検索キーワードTips」、私とは技のレベルが違い過ぎますね。研鑽します。ありがとうございました。
【追記】[114711] Nさん「検索キーワードTips」、私とは技のレベルが違い過ぎますね。研鑽します。ありがとうございました。
| [114719] 2025年 7月 8日(火)17:50:56 | 未開人 さん |
| スウェーデンヒルズ行けませんでした | |
週末に17年ぶりに北海道に行ってきました。経県値についてはこれから更新します。
オフ会の際に教えていただいたスウェーデンヒルズですが、時間が足りなかったので残念ながら断念しました。
研究費で行っているのである程度の制約があるのは仕方がないです。
首長の年齢については必要なら開示請求もできると思いますので、ご検討ください。
オフ会の際に教えていただいたスウェーデンヒルズですが、時間が足りなかったので残念ながら断念しました。
研究費で行っているのである程度の制約があるのは仕方がないです。
首長の年齢については必要なら開示請求もできると思いますので、ご検討ください。
| [114718] 2025年 7月 8日(火)17:32:02 | ピーくん さん |
| 報告 | |
日頃から、愛南町政の推進に対しまして御理解と御協力を賜り、
誠にありがとうございます。
この度HPにお問合せいただいた件について、回答いたします。
お問い合わせいただいた内容につきましては、個人情報の保護に
関する法律により目的外での第三者への提供が制限されております。
つきましては、大変恐縮ですが、今回のお問い合わせには、回答
できかねますことを御了承いただきますようお願い申し上げます。
今後とも、町政運営に御理解と御協力を賜りますようお願い申し
上げます。
愛南町はダメでした。東洋大学卒業とかどうでも良いです。
誠にありがとうございます。
この度HPにお問合せいただいた件について、回答いたします。
お問い合わせいただいた内容につきましては、個人情報の保護に
関する法律により目的外での第三者への提供が制限されております。
つきましては、大変恐縮ですが、今回のお問い合わせには、回答
できかねますことを御了承いただきますようお願い申し上げます。
今後とも、町政運営に御理解と御協力を賜りますようお願い申し
上げます。
愛南町はダメでした。東洋大学卒業とかどうでも良いです。
| [114717] 2025年 7月 8日(火)16:40:42 | オーナー グリグリ |
| 早川町への問合せ | |
[114716] 下総みなとさん
数年前の教員採用試験申し込みページではありますが、こちらに総務課のメールアドレスが記載されているようです。
おっ、さすがですね。このアドレスに問合せメールを早速送りました。さて、結果はどうなるでしょうか。ありがとうございました。
数年前の教員採用試験申し込みページではありますが、こちらに総務課のメールアドレスが記載されているようです。
おっ、さすがですね。このアドレスに問合せメールを早速送りました。さて、結果はどうなるでしょうか。ありがとうございました。
| [114716] 2025年 7月 8日(火)16:15:44 | 下総みなと さん |
| Re:市区町村長・知事の生年月日 | |
[114715] グリグリさん
ただし、早川町だけはHPからの問い合わせフォームがなく、メルアドもないことから電話か手紙で問い合わせるしかなさそうです。
私の方で早川町の行政管理を行う総務課のメールアドレスを調べてみました。
数年前の教員採用試験申し込みページではありますが、こちらに総務課のメールアドレスが記載されているようです。
正しいのかは分かりませんが、問い合わせるならこのメールアドレスでしょうかね...?
あまりにも返信がないようでしたら、電話かはがきにて問い合わせるしかなさそうですけどね...
ただし、早川町だけはHPからの問い合わせフォームがなく、メルアドもないことから電話か手紙で問い合わせるしかなさそうです。
私の方で早川町の行政管理を行う総務課のメールアドレスを調べてみました。
数年前の教員採用試験申し込みページではありますが、こちらに総務課のメールアドレスが記載されているようです。
正しいのかは分かりませんが、問い合わせるならこのメールアドレスでしょうかね...?
あまりにも返信がないようでしたら、電話かはがきにて問い合わせるしかなさそうですけどね...
| [114715] 2025年 7月 8日(火)15:45:07【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 8日(火)15:49:12 | オーナー グリグリ |
| 市区町村長・知事の生年月日 | |
[114713] 下総みなとさん
やはり、直接自治体に問い合わせるのが手っ取り早いのでしょうかね...。
はい、そう思います。ということで、[114699]に書いた不明者リスト26名と[114707]の道志村について、昨日から本日にかけて市町村の公式HPのお問合せページから問い合わせを行いました(十津川村はメルアドから直接メール)。すでに大川市、下仁田町、道志村、能登町、宇治田原町の5市町村から回答がありました。ただし、早川町だけはHPからの問い合わせフォームがなく、メルアドもないことから電話か手紙で問い合わせるしかなさそうです。ちょっと戸惑っています^^;;。どなたか電話で問い合わせできますか?_^^;
早川町役場総務課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2513(直通)
以下は、私が問合せページから問い合わせる際の基本文章になります。
-------<<
タイトル:(市|町|村)長の生年月日について
私は全国の市区町村長の年齢を調査し平均年齢や地域差などを分析しています。
(昨年|今年)◯月に就任された◯◯町長の生年月日を教えていただけないでしょうか。
HPでは町長のプロフィールを見つけることができませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。
-------<<
個人HPで一覧として公開しているということは敢えて言っていません。→ [114534]参照
と言うのも、市区町村長・知事というのは公人であり生年月日を問われた際には答える義務のようなものがあると思っているのですが、何らかの法的根拠があるのでしょうか。それとも慣例として公開しているのでしょうか。そのあたり少し不安というか曖昧な気分です。
やはり、直接自治体に問い合わせるのが手っ取り早いのでしょうかね...。
はい、そう思います。ということで、[114699]に書いた不明者リスト26名と[114707]の道志村について、昨日から本日にかけて市町村の公式HPのお問合せページから問い合わせを行いました(十津川村はメルアドから直接メール)。すでに大川市、下仁田町、道志村、能登町、宇治田原町の5市町村から回答がありました。ただし、早川町だけはHPからの問い合わせフォームがなく、メルアドもないことから電話か手紙で問い合わせるしかなさそうです。ちょっと戸惑っています^^;;。どなたか電話で問い合わせできますか?_^^;
早川町役場総務課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2513(直通)
以下は、私が問合せページから問い合わせる際の基本文章になります。
-------<<
タイトル:(市|町|村)長の生年月日について
私は全国の市区町村長の年齢を調査し平均年齢や地域差などを分析しています。
(昨年|今年)◯月に就任された◯◯町長の生年月日を教えていただけないでしょうか。
HPでは町長のプロフィールを見つけることができませんでした。
何卒よろしくお願いいたします。
-------<<
個人HPで一覧として公開しているということは敢えて言っていません。→ [114534]参照
と言うのも、市区町村長・知事というのは公人であり生年月日を問われた際には答える義務のようなものがあると思っているのですが、何らかの法的根拠があるのでしょうか。それとも慣例として公開しているのでしょうか。そのあたり少し不安というか曖昧な気分です。
| [114714] 2025年 7月 8日(火)14:40:20【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 8日(火)16:10:34 | YT さん |
| ランクサイズルール | |
[114706] しまなみ さん
随分前に素数人口を出してネタ切れしていましたが、
「そう言えばこれがあるじゃん」と言うものを思いつきました。
題名の通り、フィボナッチ数です。
ここ最近は全く見なくなりましたが、自動車レースのF1では、1位が10ポイント、2位が6ポイント、3位が4ポイント、4位が3ポイント、5位が2ポイント、6位が1ポイントで、それ以下は完走してもポイント無しでした。1991年度当時高校生だった私は、これだと下位のレーサーの相対的な能力を比較できないと考え、ポイント制にフィボナッチ数列を見出し、強引に黄金比の逆数の等比級数で7位以下を含めてドライバーのポイントを計算し直し、誰それは高評価で、誰それは実際はもっと評価されるべきなどと閲に入っていました。
ところで人口の順位と人口に法則性を探るとなると、地理学には「順位・規模法則」または「ランクサイズルール/rank-size rule」というのがあります。多分過去にこの落書き帳でも誰か話題に出していると思って検索しましたが・・・誰も話題に出してないですね?
つまりある地域の都市の人口を、人口順に並べた際、順位の対数と人口の対数に相関がみられるという法則です。「対数」は高校以上で習う概念ですが、ある数(x)の別の数(a)を底とする対数(y = log_a (x))とは、ある数(x)が底となる数字(b)の指数(y)として表現可能な場合(x = b^y)の、指数(y)のことです。"_a"は下付き、"^y"は上付きで記述されるものです。まあ分かりやすく説明すると、
0.01は10の-2乗
0.1は10の-1乗
1は10の0乗
10は10の1乗
100は10の2乗
というふうに、指数で表現できます。さらに
√10 = 3.1622776...は10の0.5乗
10√10 = 31.622776...は10の1.5乗
というふうに、指数部分も整数以外に拡張できます。この時10を底とする対数である常用対数(log_10)を用いると、それぞれの数字の対数は以下のようになります。
log_10 (0.01) = -2
log_10 (0.1) = -1
log_10 (1) = 0
log_10 (√10)= 0.5
log_10 (10) = 1
log_10 (10√10)= 1.5
log_10 (100) = 2
身近なところでは、対数は地震のマグニチュード、星の等級なんかでも使われています。人間はものの大きさを感じる際、大きすぎたり小さすぎたりする場合には、対数に近い感覚になると言われており、実際には1等星は6等星の100倍明るいのですが、その間の明るさの違いは対数的に感知するというのです。
なお、数学の世界では、底の数字を省略して「log」 と書いてしまうと、ネイピア数を底とする自然対数に限定されてしまうのですが、物理や化学の世界では、ネイピア数を底とする自然対数を「ln」、底を10とする常用対数を「log」と表記するなど、自然科学の分野でも専門用語の「方言」が異なります。
さて、順位の対数を横軸、人口の対数を縦軸にプロットして、それが直線に乗る!という話を大学1年の時に私は一般教養の地理の講義で聞いて感動しましたが、実際に手元の日本や海外の都市人口の数字を使って、手書きでグラフにプロットしてみましたが、必ずしも直線には乗りません。なんというか、平成の大合併前であっても、人口が少ない方の自治体で末広がりになり、最小規模の方で再び急に下がります。当然ながら東京のように一局集中しているような都市が例外となるのは分かるのですが、直線に乗ったと断言できるような部分は一部を切り取った場合のみでした。高校生の時に人口集中地区を独自ルールで合算した数字が手元にあったので、これでプロットした場合、むしろ相関は悪くなりました。とはいえどうやっても相関係数はまあまあ良好で、概ね直線に乗るねと納得していました。
しかしながら身近にいた物理学の専門の人にこのルールを説明した時、
「両対数でプロットするの?そんなの相関が良くなって当たり前じゃん?」
と秒で指摘され、はっとしました。そうです、既に順位順に並べている時点で、人口の方も順位に対する縛りがあり、上下方向にずれるはずがないのです。しかも両対数グラフにプロットしている時点で、ある程度の直線性が保証されているのです。このランクサイズルールは、それでいて直線に乗らなかった場合の説明の方が重要だったのです。
順位と人口の対数をプロットして直線に乗る・・・と書きましたが、これは即ち、一番人口の多い都市に対し、2番目以降がその人口の半分、1/3、1/4、1/5・・・1/nと、順位nの逆数に比例する人口として記述できる状態を指します。で、1位~10位の上位の方で直線からずれるのは、一極集中だとか色々説明ができるのですが、人口が非常に少ない方でも直線からずれる理由としては、結局のところ「人口」というのは連続数ではないことを考慮するべきなのでしょう。人が0.5人存在する状態はありませんし、文化的には夫婦、家族や集落など、行政とは違うレベルで人口は縮退しています。ランクサイズルールの単純化したモデルではこの辺を無視しています。ランクサイズルールが適用できる範囲は相当に限定的といえるでしょう。とはいえこの話に量子化モデルを導入したとしても、まあ意味のあるモデル式ができるとも思えませんが。
とはいえ、統計データがないような過去の歴史上の都市の推定人口を算出する際なんかでは、このランクサイズルールを使っている事例がたくさんあるんですよね。その意味で過去の都市人口のデータはそのまま信用してはいけません(リンク先の数字をまとめたのは自分ですが)。
ところで、都市人口の順位がフィボナッチ数列に従った場合ですが、これは即ち等比数列なわけですので、横軸に順位、縦軸に人口の対数をプロットした「片対数」であれば見事に直線に乗りますが、両対数プロットしてしまうと、当然ながら順位が増えるほど落ち込んでいくグラフになってしまいます。とはいえ、例えば21位~100位と切り取ってくると、相関係数は0.96を超え、切り取り次第では直線に近づきます。
【リンク修正】
随分前に素数人口を出してネタ切れしていましたが、
「そう言えばこれがあるじゃん」と言うものを思いつきました。
題名の通り、フィボナッチ数です。
ここ最近は全く見なくなりましたが、自動車レースのF1では、1位が10ポイント、2位が6ポイント、3位が4ポイント、4位が3ポイント、5位が2ポイント、6位が1ポイントで、それ以下は完走してもポイント無しでした。1991年度当時高校生だった私は、これだと下位のレーサーの相対的な能力を比較できないと考え、ポイント制にフィボナッチ数列を見出し、強引に黄金比の逆数の等比級数で7位以下を含めてドライバーのポイントを計算し直し、誰それは高評価で、誰それは実際はもっと評価されるべきなどと閲に入っていました。
ところで人口の順位と人口に法則性を探るとなると、地理学には「順位・規模法則」または「ランクサイズルール/rank-size rule」というのがあります。多分過去にこの落書き帳でも誰か話題に出していると思って検索しましたが・・・誰も話題に出してないですね?
つまりある地域の都市の人口を、人口順に並べた際、順位の対数と人口の対数に相関がみられるという法則です。「対数」は高校以上で習う概念ですが、ある数(x)の別の数(a)を底とする対数(y = log_a (x))とは、ある数(x)が底となる数字(b)の指数(y)として表現可能な場合(x = b^y)の、指数(y)のことです。"_a"は下付き、"^y"は上付きで記述されるものです。まあ分かりやすく説明すると、
0.01は10の-2乗
0.1は10の-1乗
1は10の0乗
10は10の1乗
100は10の2乗
というふうに、指数で表現できます。さらに
√10 = 3.1622776...は10の0.5乗
10√10 = 31.622776...は10の1.5乗
というふうに、指数部分も整数以外に拡張できます。この時10を底とする対数である常用対数(log_10)を用いると、それぞれの数字の対数は以下のようになります。
log_10 (0.01) = -2
log_10 (0.1) = -1
log_10 (1) = 0
log_10 (√10)= 0.5
log_10 (10) = 1
log_10 (10√10)= 1.5
log_10 (100) = 2
身近なところでは、対数は地震のマグニチュード、星の等級なんかでも使われています。人間はものの大きさを感じる際、大きすぎたり小さすぎたりする場合には、対数に近い感覚になると言われており、実際には1等星は6等星の100倍明るいのですが、その間の明るさの違いは対数的に感知するというのです。
なお、数学の世界では、底の数字を省略して「log」 と書いてしまうと、ネイピア数を底とする自然対数に限定されてしまうのですが、物理や化学の世界では、ネイピア数を底とする自然対数を「ln」、底を10とする常用対数を「log」と表記するなど、自然科学の分野でも専門用語の「方言」が異なります。
さて、順位の対数を横軸、人口の対数を縦軸にプロットして、それが直線に乗る!という話を大学1年の時に私は一般教養の地理の講義で聞いて感動しましたが、実際に手元の日本や海外の都市人口の数字を使って、手書きでグラフにプロットしてみましたが、必ずしも直線には乗りません。なんというか、平成の大合併前であっても、人口が少ない方の自治体で末広がりになり、最小規模の方で再び急に下がります。当然ながら東京のように一局集中しているような都市が例外となるのは分かるのですが、直線に乗ったと断言できるような部分は一部を切り取った場合のみでした。高校生の時に人口集中地区を独自ルールで合算した数字が手元にあったので、これでプロットした場合、むしろ相関は悪くなりました。とはいえどうやっても相関係数はまあまあ良好で、概ね直線に乗るねと納得していました。
しかしながら身近にいた物理学の専門の人にこのルールを説明した時、
「両対数でプロットするの?そんなの相関が良くなって当たり前じゃん?」
と秒で指摘され、はっとしました。そうです、既に順位順に並べている時点で、人口の方も順位に対する縛りがあり、上下方向にずれるはずがないのです。しかも両対数グラフにプロットしている時点で、ある程度の直線性が保証されているのです。このランクサイズルールは、それでいて直線に乗らなかった場合の説明の方が重要だったのです。
順位と人口の対数をプロットして直線に乗る・・・と書きましたが、これは即ち、一番人口の多い都市に対し、2番目以降がその人口の半分、1/3、1/4、1/5・・・1/nと、順位nの逆数に比例する人口として記述できる状態を指します。で、1位~10位の上位の方で直線からずれるのは、一極集中だとか色々説明ができるのですが、人口が非常に少ない方でも直線からずれる理由としては、結局のところ「人口」というのは連続数ではないことを考慮するべきなのでしょう。人が0.5人存在する状態はありませんし、文化的には夫婦、家族や集落など、行政とは違うレベルで人口は縮退しています。ランクサイズルールの単純化したモデルではこの辺を無視しています。ランクサイズルールが適用できる範囲は相当に限定的といえるでしょう。とはいえこの話に量子化モデルを導入したとしても、まあ意味のあるモデル式ができるとも思えませんが。
とはいえ、統計データがないような過去の歴史上の都市の推定人口を算出する際なんかでは、このランクサイズルールを使っている事例がたくさんあるんですよね。その意味で過去の都市人口のデータはそのまま信用してはいけません(リンク先の数字をまとめたのは自分ですが)。
ところで、都市人口の順位がフィボナッチ数列に従った場合ですが、これは即ち等比数列なわけですので、横軸に順位、縦軸に人口の対数をプロットした「片対数」であれば見事に直線に乗りますが、両対数プロットしてしまうと、当然ながら順位が増えるほど落ち込んでいくグラフになってしまいます。とはいえ、例えば21位~100位と切り取ってくると、相関係数は0.96を超え、切り取り次第では直線に近づきます。
【リンク修正】
| [114713] 2025年 7月 8日(火)14:20:43 | 下総みなと さん |
| 市町村長の生年月日調査をする中での疑問 | |
最近、落書き帳の中で調査が進められている、市町村長の生年月日を調査する動き。
私自身も協力したいという思いで、不明者リストから色々探してみました(現状一人の生年月日の特定にすら至っていませんが...苦笑)。
幾つかの自治体ホームページには「市町村長のプロフィール」ページなどが設けられており、例えば、邑南町。
邑南町長のプロフィールの生年月日の欄に、「昭和43年3月生まれ」と書いてあって、思わず「生年月日じゃなくて生年月やないかい!」とツッコみたくなってしまいました。
やはり、直接自治体に問い合わせるのが手っ取り早いのでしょうかね...。
私自身も協力したいという思いで、不明者リストから色々探してみました(現状一人の生年月日の特定にすら至っていませんが...苦笑)。
幾つかの自治体ホームページには「市町村長のプロフィール」ページなどが設けられており、例えば、邑南町。
邑南町長のプロフィールの生年月日の欄に、「昭和43年3月生まれ」と書いてあって、思わず「生年月日じゃなくて生年月やないかい!」とツッコみたくなってしまいました。
やはり、直接自治体に問い合わせるのが手っ取り早いのでしょうかね...。
| [114712] 2025年 7月 7日(月)21:20:27 | 伊豆之国 さん |
| 湯の街の女城主、早くも絶体絶命 | |
[114664] ピーくんさん
学歴疑惑のかけられている女性市長がいました。東洋大学卒業
まぁ、私には縁のない事。多分図書館の建設に反対している市長なので建設したい人には嫌なので嫌がらせ
その昔、耳にタコができるほど聞かされたあの名CMで全国に名を轟かせた巨大ホテル「ハ○ヤ」、すり鉢状の火口がある美しい姿の「大○山」、その麓にある、近年は「カ○バラの入浴」でも人気の老舗テーマバーク「シャ〇テ〇公園」。昭和の面影も濃厚な、この「伊東の三大名所」を2年前、ようやくこの歳になってコンプリートすることができた伊東八万石領主伊豆守でございます。
さて、ここからが本題。
去る5月25日の市長選挙で初当選、29日より市長の職に就いた田久保真紀氏に、就任早々「学歴詐称」疑惑が発覚。東洋大を実際には卒業していなかった事実が明るみに出て、市議会は「辞職勧告」と「百条委員会」の設置を議決しました。
(SBS News)
追い詰められた田久保市長、いったんは「開き直り」ともとれる態度を見せていたとも言われていたそうですが、結局自ら辞職、出直し選挙に出馬ということになったようです。
(日刊スポーツ)
出直し市長選挙には、5月の選挙で田久保氏に惜敗した前市長も出馬の意向を示しているようです。
学歴疑惑のかけられている女性市長がいました。東洋大学卒業
まぁ、私には縁のない事。多分図書館の建設に反対している市長なので建設したい人には嫌なので嫌がらせ
その昔、耳にタコができるほど聞かされたあの名CMで全国に名を轟かせた巨大ホテル「ハ○ヤ」、すり鉢状の火口がある美しい姿の「大○山」、その麓にある、近年は「カ○バラの入浴」でも人気の老舗テーマバーク「シャ〇テ〇公園」。昭和の面影も濃厚な、この「伊東の三大名所」を2年前、ようやくこの歳になってコンプリートすることができた伊東八万石領主伊豆守でございます。
さて、ここからが本題。
去る5月25日の市長選挙で初当選、29日より市長の職に就いた田久保真紀氏に、就任早々「学歴詐称」疑惑が発覚。東洋大を実際には卒業していなかった事実が明るみに出て、市議会は「辞職勧告」と「百条委員会」の設置を議決しました。
(開く)学歴詐称疑惑で田久保真紀市長の辞職勧告決議案可決 全会一致で 百条委員会設置案も=静岡・伊東市議会
追い詰められた田久保市長、いったんは「開き直り」ともとれる態度を見せていたとも言われていたそうですが、結局自ら辞職、出直し選挙に出馬ということになったようです。
(開く)疑惑の伊東市長が辞任表明→出直し選へ 会見で学歴詐称疑惑をあらためて謝罪「市民の判断仰ぐ」
出直し市長選挙には、5月の選挙で田久保氏に惜敗した前市長も出馬の意向を示しているようです。
| [114711] 2025年 7月 7日(月)21:01:19【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 7日(月)21:02:21 | N さん |
| 検索キーワードTips | |
[114710]グリグリさん
ご対応ありがとうございました。
会議録を引っ掛ける検索KWの指定はどうされたのでしょうか?
今回の場合、まず単純に「出羽和平 道志村」で検索してみたら、議会議員名簿が簡単にヒットして生年の昭和23年はすぐわかりました。
その上で「出羽和平 "昭和23年" 生年 filetype:pdf」で検索したらトップに出てきましたね。
前職が町村議会議員ならば、当選当時の選挙人名簿や議会議事録がpdfファイルで残っているケース多いのでそういう観点で探すとヒットしやすいかもしれません。
あと普段よく使うのは完全一致ワードを元号ではなく西暦の"1948"に変えてみるとか、今回はたまたま生年が一発で分かったので使いませんでしたが、年齢しかわからない場合は1年ずらして"昭和22"や"1947"でも検索してみるとかはしてます。
ご対応ありがとうございました。
会議録を引っ掛ける検索KWの指定はどうされたのでしょうか?
今回の場合、まず単純に「出羽和平 道志村」で検索してみたら、議会議員名簿が簡単にヒットして生年の昭和23年はすぐわかりました。
その上で「出羽和平 "昭和23年" 生年 filetype:pdf」で検索したらトップに出てきましたね。
前職が町村議会議員ならば、当選当時の選挙人名簿や議会議事録がpdfファイルで残っているケース多いのでそういう観点で探すとヒットしやすいかもしれません。
あと普段よく使うのは完全一致ワードを元号ではなく西暦の"1948"に変えてみるとか、今回はたまたま生年が一発で分かったので使いませんでしたが、年齢しかわからない場合は1年ずらして"昭和22"や"1947"でも検索してみるとかはしてます。
| [114710] 2025年 7月 7日(月)19:52:58 | オーナー グリグリ |
| Re:道志村長生年月日他 | |
[114708] Nさん、いつも有難うございます。
1948.8.20です。
道志村村議会会議録
道志村新村長の生年月日情報を有難うございました。会議録を引っ掛ける検索KWの指定はどうされたのでしょうか?
道志村にも直接問い合わせていたのですが、つい先ほどメールで回答がありました。生年月日間違いありません。
■北群馬郡榛東村
本姓は「猿渡」で「南」は旧姓の可能性があります。
本人は「南」を使っているので氏名欄はそのままとし、注釈を追記しました。なお、女性首長一覧にも注記を付けました。
■千葉市
神谷氏の1期就任日が「2021.3.22」になっていますが、選挙日の「2021.3.21」とするのが適切かと思います。
前任の熊谷・現千葉県知事の知事選立候補に伴う辞職での選挙による就任のため「任期の起算日」は選挙日になります。「当選の告示日」が2021.3.22なので、媒体によってはこれを就任日としているものも多数ありますが。
ご指摘と解説を有難うございます。この辺り私もよく分かっていなかったので助かりました。同様のケースが他にもあったように思うので、後ほど見返して調べようと思います。
(■取手市)
※全国の現役首長一覧ではなく若年首長一覧に対する指摘です
海老原一雄氏の就任日が1971.5.1になっていますが、取手市のHPでは就任日は1971.3.14となっています。
こちらも有難うございます。更新しました。
全国の現役首長一覧 (評価版) を更新しました。なお、連続無投票については[114699]以降、新潟県から山梨県まで確認しました。
1948.8.20です。
道志村村議会会議録
道志村新村長の生年月日情報を有難うございました。会議録を引っ掛ける検索KWの指定はどうされたのでしょうか?
道志村にも直接問い合わせていたのですが、つい先ほどメールで回答がありました。生年月日間違いありません。
■北群馬郡榛東村
本姓は「猿渡」で「南」は旧姓の可能性があります。
本人は「南」を使っているので氏名欄はそのままとし、注釈を追記しました。なお、女性首長一覧にも注記を付けました。
■千葉市
神谷氏の1期就任日が「2021.3.22」になっていますが、選挙日の「2021.3.21」とするのが適切かと思います。
前任の熊谷・現千葉県知事の知事選立候補に伴う辞職での選挙による就任のため「任期の起算日」は選挙日になります。「当選の告示日」が2021.3.22なので、媒体によってはこれを就任日としているものも多数ありますが。
ご指摘と解説を有難うございます。この辺り私もよく分かっていなかったので助かりました。同様のケースが他にもあったように思うので、後ほど見返して調べようと思います。
(■取手市)
※全国の現役首長一覧ではなく若年首長一覧に対する指摘です
海老原一雄氏の就任日が1971.5.1になっていますが、取手市のHPでは就任日は1971.3.14となっています。
こちらも有難うございます。更新しました。
全国の現役首長一覧 (評価版) を更新しました。なお、連続無投票については[114699]以降、新潟県から山梨県まで確認しました。
| [114708] 2025年 7月 7日(月)16:20:05【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 7日(月)16:48:52 | N さん |
| 道志村長生年月日他 | |
[114707]グリグリさん
道志村新村長 出羽和平 (でわかずとし) 氏の生年月日は不明です。
1948.8.20です。
道志村村議会会議録
また、過去の選挙結果の調査の過程でいくつか気になった情報があったので、あわせて記載しておきます。
■北群馬郡榛東村
本姓は「猿渡」で「南」は旧姓の可能性があります。
本人HPなどで公表しているわけではないですが、群馬県市町村長選挙データ集では「猿渡千晴」として当選者の記載があります。
また、群馬県報などに、氏名変更の手続きを行った痕跡もあります。
■千葉市
神谷氏の1期就任日が「2021.3.22」になっていますが、選挙日の「2021.3.21」とするのが適切かと思います。
前任の熊谷・現千葉県知事の知事選立候補に伴う辞職での選挙による就任のため「任期の起算日」は選挙日になります。「当選の告示日」が2021.3.22なので、媒体によってはこれを就任日としているものも多数ありますが。
(■取手市)
※全国の現役首長一覧ではなく若年首長一覧に対する指摘です
海老原一雄氏の就任日が1971.5.1になっていますが、取手市のHPでは就任日は1971.3.14となっています。
道志村新村長 出羽和平 (でわかずとし) 氏の生年月日は不明です。
1948.8.20です。
道志村村議会会議録
また、過去の選挙結果の調査の過程でいくつか気になった情報があったので、あわせて記載しておきます。
■北群馬郡榛東村
本姓は「猿渡」で「南」は旧姓の可能性があります。
本人HPなどで公表しているわけではないですが、群馬県市町村長選挙データ集では「猿渡千晴」として当選者の記載があります。
また、群馬県報などに、氏名変更の手続きを行った痕跡もあります。
■千葉市
神谷氏の1期就任日が「2021.3.22」になっていますが、選挙日の「2021.3.21」とするのが適切かと思います。
前任の熊谷・現千葉県知事の知事選立候補に伴う辞職での選挙による就任のため「任期の起算日」は選挙日になります。「当選の告示日」が2021.3.22なので、媒体によってはこれを就任日としているものも多数ありますが。
(■取手市)
※全国の現役首長一覧ではなく若年首長一覧に対する指摘です
海老原一雄氏の就任日が1971.5.1になっていますが、取手市のHPでは就任日は1971.3.14となっています。
| [114707] 2025年 7月 7日(月)15:21:49【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 7日(月)15:35:42 | オーナー グリグリ |
| 全国の現役首長一覧 (評価版) 更新 | |
昨日の選挙結果として、当別町 (現職再選2期目) と道志村 (新人当選) を更新しました。道志村新村長 出羽和平 (でわかずとし) 氏の生年月日は不明です。[114699]不明者リストのうち、大川市の江藤市長の生年月日は1947年7月6日、下仁田町の岩崎町長の生年月日は1950年2月1日と分かりました (市町への問合せ結果) 。
| [114706] 2025年 7月 7日(月)14:31:15【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 7日(月)17:57:32 | しまなみ さん |
| 素数の次は、フィボナッチ数。 | |
随分前に素数人口を出してネタ切れしていましたが、
「そう言えばこれがあるじゃん」と言うものを思いつきました。
題名の通り、フィボナッチ数です。
フィボナッチ数はフィボナッチ数列の数で、簡単に言えば
「前2つの数字の和の並び」な訳です。
さて、フィボナッチ数と市町村の人口を比較してみようと思って、
「まあ1個くらいピッタリなものあるでしょう」と思ったのですが......ピッタリなんかありませんでした(爆散)
しかし、かなり近い数値は存在していたのと、このままだと個人的に満足できないので、企画を強行します。
さてさて...次はどの数にしようか、迷いますね。
【1】
一般項にとても数学を真面目にやっている人とは思えないミスを発見。
誤:Fn=(1/√5){(1+√5/2)^n-(1-√5/2)^n}=φ^n-(1-φ)^n/√5
正:Fn=(1/√5){((1+√5)/2)^n-((1-√5)/2)^n}=(φ^n-(1-φ)^n)/√5
1つの数ごとに( )で括ることを忘れていた!!!(爆散²)
これでまたミスをしていたら今度は「爆散²」をさらに^爆散²します。
ちなみに、訂正中に(φ^n-(1-φ)^n)/√5を(φ^n-(1-φ))^n/√5と書いており、(爆散²)^(爆散²)、つまり(爆散²)²を早速経験する羽目になるところでした。
「そう言えばこれがあるじゃん」と言うものを思いつきました。
題名の通り、フィボナッチ数です。
フィボナッチ数はフィボナッチ数列の数で、簡単に言えば
「前2つの数字の和の並び」な訳です。
(開く)フィボナッチ数についての詳しい説明
「まあ1個くらいピッタリなものあるでしょう」と思ったのですが......ピッタリなんかありませんでした(爆散)
しかし、かなり近い数値は存在していたのと、このままだと個人的に満足できないので、企画を強行します。
(開く)フィボナッチ数に近い人口【f(n) , 33≧n≧13】
【1】
一般項にとても数学を真面目にやっている人とは思えないミスを発見。
誤:Fn=(1/√5){(1+√5/2)^n-(1-√5/2)^n}=φ^n-(1-φ)^n/√5
正:Fn=(1/√5){((1+√5)/2)^n-((1-√5)/2)^n}=(φ^n-(1-φ)^n)/√5
1つの数ごとに( )で括ることを忘れていた!!!(爆散²)
これでまたミスをしていたら今度は「爆散²」をさらに^爆散²します。
ちなみに、訂正中に(φ^n-(1-φ)^n)/√5を(φ^n-(1-φ))^n/√5と書いており、(爆散²)^(爆散²)、つまり(爆散²)²を早速経験する羽目になるところでした。
| [114705] 2025年 7月 7日(月)04:26:09 | ワルイージ推し さん |
| ローソン | |
稚内にまたローソンできたってニュース見ました。
でもセブンイレブンはまだ稚内にはありません。
稚内にセブンできる
旭川にファミマできる
北海道のどこかにミニストップできる
どれが1番最初になるのでしょう?
個人的には(ミニストップ)派です。
ミニストップのソフト食べたいナァ…
(地元にはファミマ以外ある)
でもセブンイレブンはまだ稚内にはありません。
稚内にセブンできる
旭川にファミマできる
北海道のどこかにミニストップできる
どれが1番最初になるのでしょう?
個人的には(ミニストップ)派です。
ミニストップのソフト食べたいナァ…
(地元にはファミマ以外ある)
| [114704] 2025年 7月 6日(日)21:57:07 | MasAka さん |
| 次回オフ会@高知 | |
以下の文章はもともと第14回オフ会メーリングリストに投稿したものですが、グリグリさんから「落書き帳にも書いていただけませんか」とのお願いがありましたので転載します(一部、落書き帳への投稿向けにリンクを追加するなどの編集を加えています)。
--------(転載ここから)--------
さて、次回高知オフ、私は[off14:00116](オフ会メーリングリスト)に書いた通りTENGUはちょっと気になる存在なので、もしオプションで行くなら行ってみたいところです(時間が取れれば、ですが)。
それはさておき、宿泊場所を温泉宿にこだわるのであれば、菊人形さんが紹介した馬路温泉の公式サイトにリンクのバナーがあった「土佐遊湯連」(とさゆうゆれん)の中から選ぶのも手かも知れません。
ちなみに市区町村経県ランキングによると、高知県登録者73人中、未踏者の多い市町村ワースト10は下記の通りです(投稿日現在)。
この辺から選ぶと皆さんの市区町村版経県値アップにつながると思います(私も上表の10町村は全て未踏です)。ただし、梼原町はデスクトップ鉄さんがすでに宿泊されているようなので、宿泊者ゼロという条件にすると大月町(52人)も候補となるでしょう。
--------(転載ここまで)--------
--------(転載ここから)--------
さて、次回高知オフ、私は[off14:00116](オフ会メーリングリスト)に書いた通りTENGUはちょっと気になる存在なので、もしオプションで行くなら行ってみたいところです(時間が取れれば、ですが)。
それはさておき、宿泊場所を温泉宿にこだわるのであれば、菊人形さんが紹介した馬路温泉の公式サイトにリンクのバナーがあった「土佐遊湯連」(とさゆうゆれん)の中から選ぶのも手かも知れません。
ちなみに市区町村経県ランキングによると、高知県登録者73人中、未踏者の多い市町村ワースト10は下記の通りです(投稿日現在)。
| 順位 | 自治体名 | 未踏者数 |
| 1位 | 馬路村 | 64人 |
| 1位 | 大川村 | 64人 |
| 3位 | 北川村 | 63人 |
| 3位 | 三原村 | 63人 |
| 5位 | 土佐町 | 60人 |
| 6位 | 本山町 | 59人 |
| 7位 | 仁淀川町 | 58人 |
| 8位 | 越智町 | 57人 |
| 9位 | 梼原町 | 56人 |
| 9位 | 津野町 | 56人 |
--------(転載ここまで)--------
| [114703] 2025年 7月 6日(日)21:37:03 | らるふ さん |
| 石島のテレビ番組 | |
今日、TVerの検索をしていてたまたま見つけました。
RNC西日本テレビの「撮れ高できるまで帰シマせん!」という番組で、石島のロケ前半と後半。
6月29日と7月6日放送分です。
番組のクオリティは高いものとは言えませんが、県境や島のロケは石島ツアーに行かれた方には懐かしい映像かと思います。
撮れ高できるまで帰シマせん!石島前半
撮れ高できるまで帰シマせん!石島後半
RNC西日本テレビの「撮れ高できるまで帰シマせん!」という番組で、石島のロケ前半と後半。
6月29日と7月6日放送分です。
番組のクオリティは高いものとは言えませんが、県境や島のロケは石島ツアーに行かれた方には懐かしい映像かと思います。
撮れ高できるまで帰シマせん!石島前半
撮れ高できるまで帰シマせん!石島後半
| [114702] 2025年 7月 6日(日)20:58:37 | オーナー グリグリ |
| 第14回落書き帳公式オフ会記録リリース | |
ちょっと遅くなりましたが、オフ会の公式記録ページをリリースします。→ 第14回落書き帳公式オフ会記録
0次会、1次会、3次会と3回に分けて盛り上がりました。皆さんの感想記事もまとめてありますのであらためてオフ会の様子をご堪能ください。東京での宿泊形式でなかったことから写真は少ないですが、それでも十分様子が伺えるかと思います。まだオフ会を経験したことがない方、今回は残念ながら欠席だった方、次回は是非ともご参加ください。
[114628]に書きましたように、次回は今年の秋頃に高知県で開催となります。皆さん早め早めに参加準備できるよう、7月中に日程と開催場所を確定します。高知県へのアクセスは少し難易度が高くなると思いますが、一案として、高知や徳島などの複数の空港を集合場所としてレンタカーを準備し、複数人で移動できるような手段も検討する予定です。開催地については、温泉の馬路温泉などありますが、他県に比べると高知県は宴会に適した温泉宿が少なめです。他に、足摺岬、室戸岬方面もあります。
皆さんから「オフ会にここはどうですか?」という情報をお待ちしています。
0次会、1次会、3次会と3回に分けて盛り上がりました。皆さんの感想記事もまとめてありますのであらためてオフ会の様子をご堪能ください。東京での宿泊形式でなかったことから写真は少ないですが、それでも十分様子が伺えるかと思います。まだオフ会を経験したことがない方、今回は残念ながら欠席だった方、次回は是非ともご参加ください。
[114628]に書きましたように、次回は今年の秋頃に高知県で開催となります。皆さん早め早めに参加準備できるよう、7月中に日程と開催場所を確定します。高知県へのアクセスは少し難易度が高くなると思いますが、一案として、高知や徳島などの複数の空港を集合場所としてレンタカーを準備し、複数人で移動できるような手段も検討する予定です。開催地については、温泉の馬路温泉などありますが、他県に比べると高知県は宴会に適した温泉宿が少なめです。他に、足摺岬、室戸岬方面もあります。
皆さんから「オフ会にここはどうですか?」という情報をお待ちしています。
| [114701] 2025年 7月 6日(日)06:35:49【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 6日(日)06:41:48 | かぱぷう さん |
| メンバー紹介編集担当よりお願い | |
落書き帳メンバー各位
本日は皆様にお願いがあり、この場を借りさせていただきます。
先月末にオーナー様からメンバー紹介記事について相談のメールをいただいた折、かねてより感じていた「今後、果たしてこのまま私がメンバー紹介編集担当を引き受けていいものだろうか?」という疑念が頭をもたげました。
もともとズボラな性格ゆえ遅筆傾向であったところに、最近は仕事が忙しくなり編集担当の役を全うできていない状況で御迷惑をお掛けしているのが心苦しく(「十番勝負に参加する時間はあるくせに」なんて突っ込みはどうかご容赦ください…)思っております。
それに加え、最近は文章作成力と空想力が低下しており、紹介文の執筆が後に後にとなってしまう有様です。
お願いとは…
どなたか、メンバー紹介編集担当を引き受けていただける方はいらっしゃいませんでしょうか。
長らく同じ者が作文する故にマンネリになっているところ、新風を吹き込んでいただける方にお引き受けいただけると幸いです。ご検討の程、よろしくお願いいたします。
本日は皆様にお願いがあり、この場を借りさせていただきます。
先月末にオーナー様からメンバー紹介記事について相談のメールをいただいた折、かねてより感じていた「今後、果たしてこのまま私がメンバー紹介編集担当を引き受けていいものだろうか?」という疑念が頭をもたげました。
もともとズボラな性格ゆえ遅筆傾向であったところに、最近は仕事が忙しくなり編集担当の役を全うできていない状況で御迷惑をお掛けしているのが心苦しく(「十番勝負に参加する時間はあるくせに」なんて突っ込みはどうかご容赦ください…)思っております。
それに加え、最近は文章作成力と空想力が低下しており、紹介文の執筆が後に後にとなってしまう有様です。
お願いとは…
どなたか、メンバー紹介編集担当を引き受けていただける方はいらっしゃいませんでしょうか。
長らく同じ者が作文する故にマンネリになっているところ、新風を吹き込んでいただける方にお引き受けいただけると幸いです。ご検討の程、よろしくお願いいたします。
| [114700] 2025年 7月 5日(土)21:31:34【1】訂正年月日 【1】2025年 7月 6日(日)05:26:45 | かぱぷう さん |
| 近況報告?? | |
十番勝負の解答書き込み以外ではすっかりご無沙汰モードになっております。4月から仕事がシフト制の職場になり不規則勤務となり乱れた生活リズムとなっていますが、一応は元気にやっております。
メンバー紹介のページを開くと表示される過去2年間に書き込みのあるメンバーの紹介文のうち、原稿準備中だった方の紹介記事を作成しアップいたしました。対象の方におかれましては、お待たせをしてしまいましたことお詫びいたします。
第14回オフ会は大盛況だったようで、嬉しい限りです。おがちゃんさん、幹事の大役をお疲れ様でございました。大変ながらも充足感いっぱいではなかろうかと拝察します。
秋の次回オフ会は福岡から比較的近場の高知県で開催とのこと。ぜひとも予定を調整して参加したいと思っております。
経県値市区町村版の積み増しも少しずつ進めています。5月は山口県周防大島町、6月は大分県姫島村を訪問しました。私は経県値マップのメモ欄に、各自治体で初めて乗降した駅と初めて訪問した郵便局を入力しているのですが、姫島村に「〒姫島」と打ち込むときはテンションが上がりました。ただし、どちらも主眼が郵便局訪問でして、姫島に至っては滞在時間は駆け足の30分と島の魅力を味わう間もない有様。これで訪問といえるか怪しいのですが、マイルールは郵便局で旅行貯金した自治体は訪問とみなしていますのでご容赦ください(笑)。
メンバー紹介のページを開くと表示される過去2年間に書き込みのあるメンバーの紹介文のうち、原稿準備中だった方の紹介記事を作成しアップいたしました。対象の方におかれましては、お待たせをしてしまいましたことお詫びいたします。
第14回オフ会は大盛況だったようで、嬉しい限りです。おがちゃんさん、幹事の大役をお疲れ様でございました。大変ながらも充足感いっぱいではなかろうかと拝察します。
秋の次回オフ会は福岡から比較的近場の高知県で開催とのこと。ぜひとも予定を調整して参加したいと思っております。
経県値市区町村版の積み増しも少しずつ進めています。5月は山口県周防大島町、6月は大分県姫島村を訪問しました。私は経県値マップのメモ欄に、各自治体で初めて乗降した駅と初めて訪問した郵便局を入力しているのですが、姫島村に「〒姫島」と打ち込むときはテンションが上がりました。ただし、どちらも主眼が郵便局訪問でして、姫島に至っては滞在時間は駆け足の30分と島の魅力を味わう間もない有様。これで訪問といえるか怪しいのですが、マイルールは郵便局で旅行貯金した自治体は訪問とみなしていますのでご容赦ください(笑)。
… スポンサーリンク …




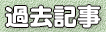





![]](./i/rp.png)







