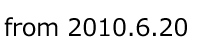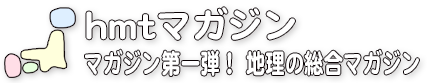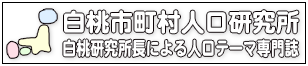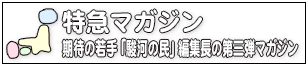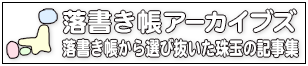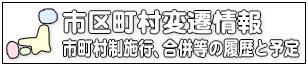雑学 市区町村名の画数 がリリースされました[96956]。
これに伴って、地名漢字に関する投稿記事が賑やかになっています。
地名漢字論を進めるために、[96956]の末尾に示されたページや、最近の記事が役立つことは もちろんですが、落書き帳の過去記事も、有益な材料です。
最初の試みとして、10年前に盛り上がった「塚」に関する記事を集めてみました。
原則として記事番号順ですが、記事中で引用された記事(若番号)は、親記事の後に付けてあります。
これに伴って、地名漢字に関する投稿記事が賑やかになっています。
地名漢字論を進めるために、[96956]の末尾に示されたページや、最近の記事が役立つことは もちろんですが、落書き帳の過去記事も、有益な材料です。
最初の試みとして、10年前に盛り上がった「塚」に関する記事を集めてみました。
原則として記事番号順ですが、記事中で引用された記事(若番号)は、親記事の後に付けてあります。
| 記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
|---|---|---|
| [65899] | 2008年7月30日 | 鳴子こけし |
| [65903] | 2008年7月31日 | Issie |
| [65924] | 2008年8月4日 | 鳴子こけし |
| [65927] | 2008年8月4日 | Issie |
| [65929] | 2008年8月4日 | むっくん |
| [56558] | 2007年1月31日 | だいてん |
| [65930] | 2008年8月4日 | Issie |
| [65931] | 2008年8月5日 | YSK |
| [65935] | 2008年8月5日 | 右左府 |
| [65937] | 2008年8月5日 | ニジェガロージェッツ |
| [14857] | 2003年5月7日 | special-week |
| [15608] | 2003年5月20日 | ニジェガロージェッツ |
| [65946] | 2008年8月6日 | 鳴子こけし |
| [65948] | 2008年8月6日 | Issie |
| [65951] | 2008年8月6日 | 般若堂そんぴん |
| [65953] | 2008年8月6日 | EMM |
| [65954] | 2008年8月6日 | Issie |
| [65959] | 2008年8月7日 | 油天神山 |
| [65962] | 2008年8月7日 | hmt |
| [65964] | 2008年8月7日 | hmt |
| [65967] | 2008年8月7日 | 伊豆之国 |
| [65968] | 2008年8月7日 | Issie |
| [65971] | 2008年8月8日 | 鳴子こけし |
| [65972] | 2008年8月8日 | hmt |
| [66013] | 2008年8月12日 | 88 |
| [65899] 2008年 7月 30日(水)14:09:01 | 鳴子こけし さん |
| 塚 | |
こんにちは。約一週間ぶりの鳴子こけしです。
一つ思ったのですが、平塚市や宝塚市等の『塚』の字は、『丶がある塚』なのでしょうか?それとも、『丶がない塚』なのでしょうか?
どうやら、『丶がある塚』は機種依存文字らしいのですが、表示ができないために便宜上『丶のない塚』を使っている、とも考えられます。正確なところはどうなのでしょう?
一つ思ったのですが、平塚市や宝塚市等の『塚』の字は、『丶がある塚』なのでしょうか?それとも、『丶がない塚』なのでしょうか?
どうやら、『丶がある塚』は機種依存文字らしいのですが、表示ができないために便宜上『丶のない塚』を使っている、とも考えられます。正確なところはどうなのでしょう?
| [65903] 2008年 7月 31日(木)00:06:34【1】 | Issie さん |
| つか | |
[65899] 鳴子こけし さん
『丶がある塚』なのでしょうか?それとも、『丶がない塚』なのでしょうか?
本来は「丶のある塚」が「正しい字体」で,「丶のない塚」は「俗字」とされていました。
それが,1981年に常用漢字が制定された時に「丶のない塚」が常用漢字表に掲載され,その後ろに「丶のある塚」がカッコ付きで「いわゆる康煕字典体」として掲載されています(常用漢字表)。
つまり,現行の常用漢字表では「丶のない塚」が“標準字体”であり,「丶のある塚」は“旧字体”扱いなのですね。
常用漢字以前の当用漢字表には「丶のない塚」も「丶のある塚」も掲載されていなかったので,その立場での“標準的な字体”というものは存在せず,慣用で「丶のある塚」が“正字”とされる一方で,実際には“俗字”である「丶のない塚」が広く用いられていたものが,常用漢字表への切り替えで通常の使用の場では「丶のない塚」に統一されたものと思われます。
地名で用いられる「塚」の字体についても基本的にはこの流れに乗っているのではないかと思います。
「法人」としての自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り,常用漢字表への移行とともに“自動的”に標準字体である「丶のない塚」に統一されたと考えていいのでないでしょうか。
『丶がある塚』なのでしょうか?それとも、『丶がない塚』なのでしょうか?
本来は「丶のある塚」が「正しい字体」で,「丶のない塚」は「俗字」とされていました。
それが,1981年に常用漢字が制定された時に「丶のない塚」が常用漢字表に掲載され,その後ろに「丶のある塚」がカッコ付きで「いわゆる康煕字典体」として掲載されています(常用漢字表)。
つまり,現行の常用漢字表では「丶のない塚」が“標準字体”であり,「丶のある塚」は“旧字体”扱いなのですね。
常用漢字以前の当用漢字表には「丶のない塚」も「丶のある塚」も掲載されていなかったので,その立場での“標準的な字体”というものは存在せず,慣用で「丶のある塚」が“正字”とされる一方で,実際には“俗字”である「丶のない塚」が広く用いられていたものが,常用漢字表への切り替えで通常の使用の場では「丶のない塚」に統一されたものと思われます。
地名で用いられる「塚」の字体についても基本的にはこの流れに乗っているのではないかと思います。
「法人」としての自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り,常用漢字表への移行とともに“自動的”に標準字体である「丶のない塚」に統一されたと考えていいのでないでしょうか。
| [65924] 2008年 8月 4日(月)17:31:42 | 鳴子こけし さん |
| 丶 | |
[65899]Issieさん
「法人」としての自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り,常用漢字表への移行とともに“自動的”に標準字体である「丶のない塚」に統一されたと考えていいのでないでしょうか。
でも戸塚駅は『丶のある塚』だったぞ。と、思った所で、「ん?駅?」と思い直す…。
と言う訳で、調べてみました『駅名“塚”事情』。
・調べ方
Yahoo!路線情報の“出発駅”の欄に『塚』を入れて『塚』の付く駅を調べる。
(因みに、路線情報はこんな事にしか使っていません。逆転駅名や二字駅名の時もお世話になりました。悪しからず。)
『丶』が付いているかどうかは“JR時刻表(8月号)”で調べました。(載っていない駅も有りましたが。)
そして、調べた結果です。
・『丶』有り…32駅
・『丶』無し…41駅
こんな結果になりました。JRに関して言えば、29駅全駅が『丶』有りの塚でした。近場の駅は現地確認をしたいと思います。
以上。8月初書き込みの鳴子こけしでした。
「法人」としての自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り,常用漢字表への移行とともに“自動的”に標準字体である「丶のない塚」に統一されたと考えていいのでないでしょうか。
でも戸塚駅は『丶のある塚』だったぞ。と、思った所で、「ん?駅?」と思い直す…。
と言う訳で、調べてみました『駅名“塚”事情』。
・調べ方
Yahoo!路線情報の“出発駅”の欄に『塚』を入れて『塚』の付く駅を調べる。
(因みに、路線情報はこんな事にしか使っていません。逆転駅名や二字駅名の時もお世話になりました。悪しからず。)
『丶』が付いているかどうかは“JR時刻表(8月号)”で調べました。(載っていない駅も有りましたが。)
そして、調べた結果です。
・『丶』有り…32駅
・『丶』無し…41駅
こんな結果になりました。JRに関して言えば、29駅全駅が『丶』有りの塚でした。近場の駅は現地確認をしたいと思います。
以上。8月初書き込みの鳴子こけしでした。
| [65927] 2008年 8月 4日(月)21:38:58 | Issie さん |
| 塚のある市区村 | |
[65924] 鳴子こけし さん
戸塚駅は『丶のある塚』だったぞ
JR東日本のページ を見てみたら,ここでは「戸塚」と,タイトルにJISコード(?)の文字を使っているので(当該ページからここへコピー&ペーストしました),実際にどの文字を使っているかはネット上では確認できないようですね。
ともかく,「塚」という文字を含む 平塚市,貝塚市,宝塚市,飯塚市,諸塚村(宮崎県),そして 戸塚区 のそれぞれについてHPで確認してみました。
幸いなことに,宝塚市以外はHPのトップにそれぞれのロゴが画像ファイルで貼り付けられています。その文字を見ると,いずれも「丶のない塚」が使われています。もっとも,ロゴは“デザインされた文字”で,必ずしも“標準字体”とは限りませんから,それぞれのページから刊行物(広報)や各種申請書類の pdfファイル でも確認してみましたが,通常の印刷字体(ゴチック体など)でも「丶のない塚」が使用されています。
というわけですから,これらの自治体において“標準字体”は「丶のない塚」で統一されている,と見てよいと思われます。
「ローマ字のつづり方の実施について」(昭和29年内閣訓令第1号)や,少し以前に話題になった「横書きの句点」の例を出すまでもなく,文部(科学)省が“標準”と定めた表記法が,他の省庁(自治省や外務省など)の系列では必ずしも実行されていないことが少なからずあるのですが,「塚」に関しては各自治体で常用漢字表の字体が採用されているのですね。
それにしても,「塚」を含む市区町村がこれだけしかない(残存していない)とは少し意外でした。
戸塚駅は『丶のある塚』だったぞ
JR東日本のページ を見てみたら,ここでは「戸塚」と,タイトルにJISコード(?)の文字を使っているので(当該ページからここへコピー&ペーストしました),実際にどの文字を使っているかはネット上では確認できないようですね。
ともかく,「塚」という文字を含む 平塚市,貝塚市,宝塚市,飯塚市,諸塚村(宮崎県),そして 戸塚区 のそれぞれについてHPで確認してみました。
幸いなことに,宝塚市以外はHPのトップにそれぞれのロゴが画像ファイルで貼り付けられています。その文字を見ると,いずれも「丶のない塚」が使われています。もっとも,ロゴは“デザインされた文字”で,必ずしも“標準字体”とは限りませんから,それぞれのページから刊行物(広報)や各種申請書類の pdfファイル でも確認してみましたが,通常の印刷字体(ゴチック体など)でも「丶のない塚」が使用されています。
というわけですから,これらの自治体において“標準字体”は「丶のない塚」で統一されている,と見てよいと思われます。
「ローマ字のつづり方の実施について」(昭和29年内閣訓令第1号)や,少し以前に話題になった「横書きの句点」の例を出すまでもなく,文部(科学)省が“標準”と定めた表記法が,他の省庁(自治省や外務省など)の系列では必ずしも実行されていないことが少なからずあるのですが,「塚」に関しては各自治体で常用漢字表の字体が採用されているのですね。
それにしても,「塚」を含む市区町村がこれだけしかない(残存していない)とは少し意外でした。
| [65929] 2008年 8月 4日(月)22:54:54【1】 | むっくん さん |
| 宝塚市&北京オリンピック | |
[65899]鳴子こけしさん
[65927]Issieさん
宝塚市については以前宝塚市民のだいてんさんが[56558]にて、
宝塚の「塚」は、実際には9画目の10画目のはらいのあたりに点が1つある
と書かれています。今はどうなっているのかはよく分かりませんが。
[65923]hmt さん
毎日新聞によりますと、北京オリンピックの開会式での日本の順番は23番目となったようです。
先頭はギリシャ、日本の直前の22番目にはイスラエル、日本の直後の24番目は台湾、フランスは123番目、アメリカは139番目、韓国は176番目、北朝鮮は177番目、最後に開催国の中国となるようです。
21世紀中国総研の世界の国・地域名(日中英対照表)によりますと、イスラエルの一文字目はおそらく3画ですので、一文字目が4画の日本より先に来ることは納得できます。
ただ例えば毎日新聞でも韓国と北朝鮮の順番について
両国とも1文字目は簡体字でともに12画。2文字目の画数では本来、両国が続く順番にはならないが、大会組織委の資料では順番の決定理由には触れていない。
と触れられているように、やはり明瞭でない部分もあるようです。
[65927]Issieさん
宝塚市については以前宝塚市民のだいてんさんが[56558]にて、
宝塚の「塚」は、実際には9画目の10画目のはらいのあたりに点が1つある
と書かれています。今はどうなっているのかはよく分かりませんが。
[65923]hmt さん
毎日新聞によりますと、北京オリンピックの開会式での日本の順番は23番目となったようです。
先頭はギリシャ、日本の直前の22番目にはイスラエル、日本の直後の24番目は台湾、フランスは123番目、アメリカは139番目、韓国は176番目、北朝鮮は177番目、最後に開催国の中国となるようです。
21世紀中国総研の世界の国・地域名(日中英対照表)によりますと、イスラエルの一文字目はおそらく3画ですので、一文字目が4画の日本より先に来ることは納得できます。
ただ例えば毎日新聞でも韓国と北朝鮮の順番について
両国とも1文字目は簡体字でともに12画。2文字目の画数では本来、両国が続く順番にはならないが、大会組織委の資料では順番の決定理由には触れていない。
と触れられているように、やはり明瞭でない部分もあるようです。
| [56558] 2007年 1月 31日(水)01:10:24 | だいてん さん |
| 再チャレンジ・そして正式表示 | |
[56554]みかちゅうさん
グリグリさんの地元である佐倉市を解答しなかった場合、無条件に失格となります。
あ、そういえば・・・(汗)
このままでは済まされません。出入禁止になってしまいます。
というわけで、もう一度挑戦しました。
もちろん前回回答できなかった15市は、その県のトップに入力して。
「ヶ」と「ケ」の違いを無視できるようになったこともあり、今度は誤答も全くなく、完答することができました!
やりすぎですね。
でもまたやると思います。
ところで、市名の正式な表記についていくつか投稿があるようなので私も口出ししてみようかと。
普通(普通とは何か、と言われると難しいですが)の表記とは違う表記をする市をまとめてみました。
以下のもの以外にありますでしょうか?
・龍ケ崎、袖ケ浦、鎌ケ谷は「ヶ」ではなく「ケ」を使う。
・龍ケ崎は「竜」ではなく「龍」を使う。
・四條畷、五條は「条」ではなく「條」を使う。
以上はパソコンで容易に表示できるもの。以下はちょっと面倒なもの。
・芦別、芦屋の「芦」の「戸」の部分は、実際には1画目は右から左にはらい、最後の4画目は1画目の左端からはらう。
・鯖江の「鯖」の右下の「月」は、実際には「円」。
・飛騨の「騨」の右上の「ツ」は、実際には「口口」。
・宝塚の「塚」は、実際には9画目の10画目のはらいのあたりに点が1つある。
これが、[56551]k-aceさんや[56554]みかちゅうさんによると、vistaでは飛騨の「騨」が表示できるようになり、なぜか葛城の「葛」が表示しづらくなった、と。
塩竈の「竈」すら表示できるんですから、いろいろ表示できるようにしておいてもらいたいものですがねえ。
特に宝塚市民としては、切実な願いです(笑)
グリグリさんの地元である佐倉市を解答しなかった場合、無条件に失格となります。
あ、そういえば・・・(汗)
このままでは済まされません。出入禁止になってしまいます。
というわけで、もう一度挑戦しました。
もちろん前回回答できなかった15市は、その県のトップに入力して。
「ヶ」と「ケ」の違いを無視できるようになったこともあり、今度は誤答も全くなく、完答することができました!
やりすぎですね。
でもまたやると思います。
ところで、市名の正式な表記についていくつか投稿があるようなので私も口出ししてみようかと。
普通(普通とは何か、と言われると難しいですが)の表記とは違う表記をする市をまとめてみました。
以下のもの以外にありますでしょうか?
・龍ケ崎、袖ケ浦、鎌ケ谷は「ヶ」ではなく「ケ」を使う。
・龍ケ崎は「竜」ではなく「龍」を使う。
・四條畷、五條は「条」ではなく「條」を使う。
以上はパソコンで容易に表示できるもの。以下はちょっと面倒なもの。
・芦別、芦屋の「芦」の「戸」の部分は、実際には1画目は右から左にはらい、最後の4画目は1画目の左端からはらう。
・鯖江の「鯖」の右下の「月」は、実際には「円」。
・飛騨の「騨」の右上の「ツ」は、実際には「口口」。
・宝塚の「塚」は、実際には9画目の10画目のはらいのあたりに点が1つある。
これが、[56551]k-aceさんや[56554]みかちゅうさんによると、vistaでは飛騨の「騨」が表示できるようになり、なぜか葛城の「葛」が表示しづらくなった、と。
塩竈の「竈」すら表示できるんですから、いろいろ表示できるようにしておいてもらいたいものですがねえ。
特に宝塚市民としては、切実な願いです(笑)
| [65930] 2008年 8月 4日(月)23:26:09 | Issie さん |
| Oh! Takarazuka | |
[65929] むっくん さん
宝塚市については以前宝塚市民のだいてんさんが[56558]にて、
宝塚の「塚」は、実際には9画目の10画目のはらいのあたりに点が1つある
と書かれています。今はどうなっているのかはよく分かりませんが。
[65927] で「宝塚市以外」と書いたのは,つまりこの市のHPだけ,トップページのロゴが「たからづか」とひらがなで表記されていて判断できなかったからです。
そこでたとえば,ここ にある「戸籍関係証明交付申請書」の pdfファイル を拡大してみると,あて先の「宝塚市長」にも,本籍地の「宝塚市」という書き出しも,「丶のない塚」が使われています。市民はともかく,少なくとも“宝塚市役所”では「丶のない塚」を“公式”の表記としているものと思われます。
ところが,トップページの左側にある「ふるさと納税」を呼びかけるバナーの文字は,何となく「丶」があるようにも見える気がしなくもないですね。解像度の低い“画像”ですから,それ以上解読することはできませんが。
宝塚市については以前宝塚市民のだいてんさんが[56558]にて、
宝塚の「塚」は、実際には9画目の10画目のはらいのあたりに点が1つある
と書かれています。今はどうなっているのかはよく分かりませんが。
[65927] で「宝塚市以外」と書いたのは,つまりこの市のHPだけ,トップページのロゴが「たからづか」とひらがなで表記されていて判断できなかったからです。
そこでたとえば,ここ にある「戸籍関係証明交付申請書」の pdfファイル を拡大してみると,あて先の「宝塚市長」にも,本籍地の「宝塚市」という書き出しも,「丶のない塚」が使われています。市民はともかく,少なくとも“宝塚市役所”では「丶のない塚」を“公式”の表記としているものと思われます。
ところが,トップページの左側にある「ふるさと納税」を呼びかけるバナーの文字は,何となく「丶」があるようにも見える気がしなくもないですね。解像度の低い“画像”ですから,それ以上解読することはできませんが。
| [65931] 2008年 8月 5日(火)01:24:18 | YSK さん |
| 旧藪塚本町 | |
6月中旬の尾瀬フィールドワーク以降、諸事情によりフィールドワーク活動と自ホームページの更新作業等のすべてを休止しております。7日には立秋を迎えることから、そろそろホームページのタイトルロゴの更新あたりから活動を再開したいなとは思っております。そうです、もう残暑の季節も目の前です。
「塚」における「丶」のある・ないについての話題がまとまっておりますが、新・太田市となった旧藪塚本町の「塚」は「丶」のある「ひげ塚」を採用していました。太田市のホームページ内でも本来は「ひげ塚」だが、ホームページ上では便宜的に「丶」のない「塚」を使用している旨説明されています。
「塚」における「丶」のある・ないについての話題がまとまっておりますが、新・太田市となった旧藪塚本町の「塚」は「丶」のある「ひげ塚」を採用していました。太田市のホームページ内でも本来は「ひげ塚」だが、ホームページ上では便宜的に「丶」のない「塚」を使用している旨説明されています。
| [65935] 2008年 8月 5日(火)18:00:04【1】 | 右左府 さん |
| 塚 | |
塚の字の点の有無が話題になってますね。
記憶が曖昧なのですが、確か以前公式HPかどこかで、宝塚市と貝塚市に関しては「ひげ塚」をロゴなどに使用していたのを見た記憶があるんです。(記憶がかなりおぼろげなので、あまり信用しないで下さい……。)それで、「宝塚って点のある塚だったんだ」などと驚いたのを覚えています。
現在はどちらも公式HPでは一見「ひげ塚」は見当たりませんが、刊行物などを探してみたらありました。
「宝塚市勢要覧2006」このPDF版では、すべての「塚」が「ひげ塚」になっています。HTML版も、画像処理されている文字は「塚」とともに「ひげ塚」が混在しています。
また、「広報たからづか」でもほとんどが「ひげ塚」です。裏表紙の編集発行者欄にある「宝塚市役所」やその住所「宝塚市東洋町…」の文字も「ひげ塚」で表記されています。
貝塚市の方も、「貝塚市第4次総合計画」には一貫して「ひげ塚」が使用されています。
他の「塚」を含む自治体もささっと各種刊行物を確認しましたが、こちらは点の無い「塚」しか見当たりませんでした。
記憶が曖昧なのですが、確か以前公式HPかどこかで、宝塚市と貝塚市に関しては「ひげ塚」をロゴなどに使用していたのを見た記憶があるんです。(記憶がかなりおぼろげなので、あまり信用しないで下さい……。)それで、「宝塚って点のある塚だったんだ」などと驚いたのを覚えています。
現在はどちらも公式HPでは一見「ひげ塚」は見当たりませんが、刊行物などを探してみたらありました。
「宝塚市勢要覧2006」このPDF版では、すべての「塚」が「ひげ塚」になっています。HTML版も、画像処理されている文字は「塚」とともに「ひげ塚」が混在しています。
また、「広報たからづか」でもほとんどが「ひげ塚」です。裏表紙の編集発行者欄にある「宝塚市役所」やその住所「宝塚市東洋町…」の文字も「ひげ塚」で表記されています。
貝塚市の方も、「貝塚市第4次総合計画」には一貫して「ひげ塚」が使用されています。
他の「塚」を含む自治体もささっと各種刊行物を確認しましたが、こちらは点の無い「塚」しか見当たりませんでした。
| [65937] 2008年 8月 5日(火)21:53:27 | ニジェガロージェッツ さん |
| 宝塚 | |
宝塚の「塚」の字が話題になっていますが,落書き帳では5年前にもspecial-weekさんが[14857]にて話題にされていました。
小生も[15608]にて反応しておりました。どちらもアーカイブ愛ヒメと書く訳 ―地名は当用漢字を超える―にも収録していただいております。
宝塚市の場合は,「塚」の字に「丶のある塚」を正式なものとしていました。震災の数年前の平成2~3年ごろだったかと記憶していますが,神戸新聞に宝塚の「塚」の字を話題とする記事があり,宝塚市役所としては「丶のある塚」を正しい字体とする見解が述べられていました。ただし,市民が「丶のない塚」を使用するのも間違いとはしない旨の付記がありました。
当時知人に宝塚市民がおり,彼が住所に「丶のある塚」を書いていたのを見たので尋ねてみると,「書く『塚』の字を見れば,本物の宝塚の人間かどうかが判る」と言っていました。落書き帳でも,地元のだいてんさんが[56558]にて
塩竈の「竈」すら表示できるんですから、いろいろ表示できるようにしておいてもらいたいものですがねえ。
特に宝塚市民としては、切実な願いです(笑)
とおっしゃっておられることから,やはり宝塚では『塚』の字には「丶」を書くのに,ひとかたならぬ拘りがあるのでは,と感じた次第です。
ところが,[65930]Issieさんの記事には,
市民はともかく,少なくとも“宝塚市役所”では「丶のない塚」を“公式”の表記としているものと思われます。
とあり,私が一昔以上前に読んだ神戸新聞の記事とは正反対の考察を述べられています。
市民のネット利用に便宜を図って公開している「戸籍関係証明交付申請書」のpdfファイルだけからでは結論付けるのは無理があるようにも感じますが,神戸新聞の記事が書かれた(ネット利用など一般ではなかった)時代からは市長も変わっており,広報(になるのかな?)の担当者も変わっていることでしょう。
時代背景や自治体の担当者が変わることで,注意しないと気づかないような「塚」の字程度では,その表記についての公式見解が変わることがあるのかもしれません。
(地方自治や,その法的な事柄には全く疎いもので・・・)
話は変わって,うちの近所に神戸市長田区腕塚町なる町名があります。
「塚」の字が気になったので,その1丁目から10丁目までを歩いてみました(ヒマかい!)
神戸市が電柱などに設置している縦長の大きな町名街区表示板には全て「丶のある塚」でした。また各戸の表札脇などに設置している小さな住居表示板にまで「丶のある塚」を書く拘りようです。
腕塚町一帯は平成7年の震災で壊滅的被害をうけたところですから,これらの表示板は震災後の新しいものです。「塚」の字が「丶のない塚」として常用漢字に加わった昭和56年以降のものであることは疑いありません。神戸市も何かこだわりがあるのか(笑
こうなると,長田区大塚町や兵庫区塚本通,中央区割塚通,旗塚通,東灘区御影塚町も行って見てこんとアカンかな?
小生も[15608]にて反応しておりました。どちらもアーカイブ愛ヒメと書く訳 ―地名は当用漢字を超える―にも収録していただいております。
宝塚市の場合は,「塚」の字に「丶のある塚」を正式なものとしていました。震災の数年前の平成2~3年ごろだったかと記憶していますが,神戸新聞に宝塚の「塚」の字を話題とする記事があり,宝塚市役所としては「丶のある塚」を正しい字体とする見解が述べられていました。ただし,市民が「丶のない塚」を使用するのも間違いとはしない旨の付記がありました。
当時知人に宝塚市民がおり,彼が住所に「丶のある塚」を書いていたのを見たので尋ねてみると,「書く『塚』の字を見れば,本物の宝塚の人間かどうかが判る」と言っていました。落書き帳でも,地元のだいてんさんが[56558]にて
塩竈の「竈」すら表示できるんですから、いろいろ表示できるようにしておいてもらいたいものですがねえ。
特に宝塚市民としては、切実な願いです(笑)
とおっしゃっておられることから,やはり宝塚では『塚』の字には「丶」を書くのに,ひとかたならぬ拘りがあるのでは,と感じた次第です。
ところが,[65930]Issieさんの記事には,
市民はともかく,少なくとも“宝塚市役所”では「丶のない塚」を“公式”の表記としているものと思われます。
とあり,私が一昔以上前に読んだ神戸新聞の記事とは正反対の考察を述べられています。
市民のネット利用に便宜を図って公開している「戸籍関係証明交付申請書」のpdfファイルだけからでは結論付けるのは無理があるようにも感じますが,神戸新聞の記事が書かれた(ネット利用など一般ではなかった)時代からは市長も変わっており,広報(になるのかな?)の担当者も変わっていることでしょう。
時代背景や自治体の担当者が変わることで,注意しないと気づかないような「塚」の字程度では,その表記についての公式見解が変わることがあるのかもしれません。
(地方自治や,その法的な事柄には全く疎いもので・・・)
話は変わって,うちの近所に神戸市長田区腕塚町なる町名があります。
「塚」の字が気になったので,その1丁目から10丁目までを歩いてみました(ヒマかい!)
神戸市が電柱などに設置している縦長の大きな町名街区表示板には全て「丶のある塚」でした。また各戸の表札脇などに設置している小さな住居表示板にまで「丶のある塚」を書く拘りようです。
腕塚町一帯は平成7年の震災で壊滅的被害をうけたところですから,これらの表示板は震災後の新しいものです。「塚」の字が「丶のない塚」として常用漢字に加わった昭和56年以降のものであることは疑いありません。神戸市も何かこだわりがあるのか(笑
こうなると,長田区大塚町や兵庫区塚本通,中央区割塚通,旗塚通,東灘区御影塚町も行って見てこんとアカンかな?
| [14857] 2003年 5月 7日(水)18:34:04 | special-week さん |
| こだわる自治体の漢字表記 | |
自治体名称の漢字表記にはかなりこだわりがあります。もちろん、茅ヶ崎市や駒ケ根市のようにヶとケの違いはアーカイブにもなっているので、それはhttp://uub.jp/arc/arc60.html をご覧になっていただければよいと思うのであえて言及いたしません。
今回問題にしたいのは、宝塚市の「塚」や芦別市と芦屋市の「芦」の字の違いです。と言っても、この書き込みを見ただけでは「何のこと?」と疑問の方もいらっしゃるでしょう。
それなので、まずhttp://www.city.takarazuka.hyogo.jp/ (宝塚市ホームページ)をご覧ください。左上に宝塚市という表記がありますが、よくよく見てみると字が違います。そうなんです。宝塚市の「塚」は特別な字なんですね。
芦別市http://www.city.ashibetsu.hokkaido.jp/Cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AM02000
芦屋市http://www.city.ashiya.hyogo.jp/
この2つの公式ホームページを見ると芦別市と芦屋市の違いが分かると思います。「芦」の字が違いますね。こういった漢字は、普通のパソコンでは表示できません。それなので、宝塚市さん、芦屋市さん、変えてください。とお願いしても無理でしょうね。長年使ってきた字ですから。
どうして最初から普通の字を使わなかったんだろう?
| [15608] 2003年 5月 20日(火)22:58:18 | ニジェガロージェッツ さん |
| 「塚」 と 「岡」 | |
このところ、ロシア関連ばかりレスしていたので、少々和風の話題を。
[14857]special-week さん
それなので、まずhttp://www.city.takarazuka.hyogo.jp/ (宝塚市ホームページ)をご覧ください。左上に宝塚市という表記がありますが、よくよく見てみると字が違います。そうなんです。宝塚市の「塚」は特別な字なんですね。
亀レスで申し訳ございません。
宝塚市の「塚」の文字ですが、ご指摘のように現在の「常用漢字表」のなかの「塚」の字とは異なっており、旧字体の「塚」(「豕」のうち「彡」の部分のまん中に点が入っている)です。
つまり「宝塚」の場合、「宝」は新字体、「塚」は旧字体、という変則的な自治体名です。
ところが、この「塚」の字は1981年10月に従来の「当用漢字」1850字が、「常用漢字」1945字に改訂された際、追加となった95字のうちの1字です。
ということは、1981年以前の「当用漢字」の時代(1946年から1981年)には、現在の「塚」の字は公式には存在せず、単なる略字だったということでしょうか。宝塚市が誕生した1954年当時は、今でも宝塚市が公式に使っている「点つきの塚」が正しい字であったのでしょう。
この旧当用漢字外の文字で、新たに加えられた95字の中には、地理でよく使われるところでは、「塚」の他に「崎」「岬」「杉」「渓」「潟」「堀」「桟」「縄」「垣」「屯」「竜」「磨」「仙」等でしょうか。(1978年中学校卒業の小生は、これらの文字を国語で習っていません)
しかし、一般広く使用されている字でも、常用漢字に追加されなかった字が多くあります。
最も使用頻度が高いのは[15376]にて、あんどれさんもご説明されています 「岡」ではないでしょうか?
県名で「岡山」「福岡」「静岡」があり、県庁所在地では「盛岡」が加わり、あと人口10万以上の市名では「岡崎」「長岡」「高岡」「延岡」と続きます。
この「岡」の字がなぜ常用漢字から漏れたかの経緯は存じませんが、推測するとすれば
といったところでしょうか?
(ならば一層のこと、静岡市と清水市が合併したのを期に「静丘市」とやってたら???)
あと、「岡」以外に常用漢字表にない文字で、府県名に用いられているのは
「愛媛」の「媛」、大阪の「阪」、奈良、神奈川の「奈」、岐阜の「阜」、山梨の「梨」、埼玉の「埼」、栃木の「栃」、「茨城」の「茨」でしょうか。
[14857]special-week さん
それなので、まずhttp://www.city.takarazuka.hyogo.jp/ (宝塚市ホームページ)をご覧ください。左上に宝塚市という表記がありますが、よくよく見てみると字が違います。そうなんです。宝塚市の「塚」は特別な字なんですね。
亀レスで申し訳ございません。
宝塚市の「塚」の文字ですが、ご指摘のように現在の「常用漢字表」のなかの「塚」の字とは異なっており、旧字体の「塚」(「豕」のうち「彡」の部分のまん中に点が入っている)です。
つまり「宝塚」の場合、「宝」は新字体、「塚」は旧字体、という変則的な自治体名です。
ところが、この「塚」の字は1981年10月に従来の「当用漢字」1850字が、「常用漢字」1945字に改訂された際、追加となった95字のうちの1字です。
ということは、1981年以前の「当用漢字」の時代(1946年から1981年)には、現在の「塚」の字は公式には存在せず、単なる略字だったということでしょうか。宝塚市が誕生した1954年当時は、今でも宝塚市が公式に使っている「点つきの塚」が正しい字であったのでしょう。
この旧当用漢字外の文字で、新たに加えられた95字の中には、地理でよく使われるところでは、「塚」の他に「崎」「岬」「杉」「渓」「潟」「堀」「桟」「縄」「垣」「屯」「竜」「磨」「仙」等でしょうか。(1978年中学校卒業の小生は、これらの文字を国語で習っていません)
しかし、一般広く使用されている字でも、常用漢字に追加されなかった字が多くあります。
最も使用頻度が高いのは[15376]にて、あんどれさんもご説明されています 「岡」ではないでしょうか?
県名で「岡山」「福岡」「静岡」があり、県庁所在地では「盛岡」が加わり、あと人口10万以上の市名では「岡崎」「長岡」「高岡」「延岡」と続きます。
この「岡」の字がなぜ常用漢字から漏れたかの経緯は存じませんが、推測するとすれば
| 1. | 「おか」の字は「丘」がある。 |
| 2. | 「海」に対する「おか」は「陸」。(陸を「おか」と訓読みするのは常用漢字表には、ない) |
| 3. | 「岡目八目」の岡ように「かたわら、そば」を表す「おか」は「傍」。(傍を「おか」と訓読みするのは常用漢字表には、ない) |
(ならば一層のこと、静岡市と清水市が合併したのを期に「静丘市」とやってたら???)
あと、「岡」以外に常用漢字表にない文字で、府県名に用いられているのは
「愛媛」の「媛」、大阪の「阪」、奈良、神奈川の「奈」、岐阜の「阜」、山梨の「梨」、埼玉の「埼」、栃木の「栃」、「茨城」の「茨」でしょうか。
| [65946] 2008年 8月 6日(水)18:53:56 | 鳴子こけし さん |
| 現地確認第一弾&塚のみならず | |
今日は海へ山へだった鳴子こけしです。
さて、[65924]の予告通りに、現地確認第一弾に行ってきました。
・戸塚駅(JR東日本)
とりあえず、見るべきは駅名標です。戸塚駅。確かに有りました『丶』。
『ひげ塚』、駅名標にしっかり書いてあって一先ず安心。
・東戸塚駅(JR東日本)
戸塚に有って東戸塚に無い訳がないですから、矢張り有りました。
ここで買った切符にもちゃんと『塚』に『丶』が有りました。
・和田塚(江ノ島電鉄)
有りません。『丶』が有りません。
しかし、下に書いてある中国語表記にはちゃんと『ひげ塚』が。
中国語には『丶無し塚』はないのでしょうか?
せっかく江ノ電に乗ったので、七里ヶ浜駅で途中下車。ところが、住所表示を見ればそこは『七里ガ浜』。
どうやら、名称の字違いは『塚』だけの問題ではないようですね。
・相模大塚(相模鉄道)
矢張りここにも有りませんでした。私鉄はあまりこだわらないのでしょうか。
・平塚(JR東日本)
駅名標を見てみれば、あれ?無い?。
確かに、“JR時刻表”の索引地図では普通の『塚』だったのですよ。(戸塚と東戸塚は『ひげ塚』でした。)
索引地図が基準?それとも駅名標を基準に索引地図を作成しているのでしょうか?
それにしても、JRもあまりこだわっていないようで…。
今日廻れたのはここまでです。悪しからず。
さて、[65924]の予告通りに、現地確認第一弾に行ってきました。
・戸塚駅(JR東日本)
とりあえず、見るべきは駅名標です。戸塚駅。確かに有りました『丶』。
『ひげ塚』、駅名標にしっかり書いてあって一先ず安心。
・東戸塚駅(JR東日本)
戸塚に有って東戸塚に無い訳がないですから、矢張り有りました。
ここで買った切符にもちゃんと『塚』に『丶』が有りました。
・和田塚(江ノ島電鉄)
有りません。『丶』が有りません。
しかし、下に書いてある中国語表記にはちゃんと『ひげ塚』が。
中国語には『丶無し塚』はないのでしょうか?
せっかく江ノ電に乗ったので、七里ヶ浜駅で途中下車。ところが、住所表示を見ればそこは『七里ガ浜』。
どうやら、名称の字違いは『塚』だけの問題ではないようですね。
・相模大塚(相模鉄道)
矢張りここにも有りませんでした。私鉄はあまりこだわらないのでしょうか。
・平塚(JR東日本)
駅名標を見てみれば、あれ?無い?。
確かに、“JR時刻表”の索引地図では普通の『塚』だったのですよ。(戸塚と東戸塚は『ひげ塚』でした。)
索引地図が基準?それとも駅名標を基準に索引地図を作成しているのでしょうか?
それにしても、JRもあまりこだわっていないようで…。
今日廻れたのはここまでです。悪しからず。
| [65948] 2008年 8月 6日(水)19:50:58【1】 | Issie さん |
| 冢 | |
[65946] 鳴子こけし さん
中国語には『丶無し塚』はないのでしょうか?
恐らく,これを“標準字体”としているのは日本の「常用漢字表」だけだと思います。
前にも触れた通り,「当用漢字表」の時代にはこの漢字は「表外字」でしたから,これによって指定された標準字体は存在せず,一般の慣用として「丶のある塚」が「正字」とされていました。
今でも多くのところで「丶のある塚」が使用されているのは,この“慣用”がいまだに生きている表れかもしれません(…というより,常用漢字表では「丶のない塚」の方が“標準字体”であることが知られていないのかも)。
中国ではどうか,というと,試しに中国語の漢字字典である 『中華古漢語字典』上海人民出版社,1997年(タイトルはもちろん簡体字で表記されています)で探してみたら,「塚」という字そのものが収録されていません。
(中国(大陸)では,現代語による出版物はもちろん,古漢語(日本で言う漢文)による古典作品もどんどん簡体字化して横組みで出版しています。この漢字字書でも収録される親字は簡体字の字体で掲載されています。)
日本の側の漢字字典(『新字鑑』高等教育研究会,1939年初版,1957年改訂増補)で見てみたら,そもそも「塚」という字自体が「丶」の有無にかかわらず「冢」という字(丶がある)の“俗字”であるとのこと。
そこで再度,中国側の字書で探したら「冢」zhong という字のところに“異体字”として「丶のある塚」が掲載されていました。
日本の“新字体”(当用漢字表,常用漢字表の字体),中国(大陸)の“簡体字”による異同がからまなくても,日中で漢字のデザインが違うことはままあります。
前にも触れたことですが,江ノ電の 和田塚駅 の手前の 鎌倉駅。中国語表記の「鎌」は日本語表記のそれとは違って,“つくり”の部分が「兼」ではなく「廉」になっています(“金へん”は簡体字のそれ)。
日本と中国(大陸)とでは標準の字体が違うのですね。
中国語には『丶無し塚』はないのでしょうか?
恐らく,これを“標準字体”としているのは日本の「常用漢字表」だけだと思います。
前にも触れた通り,「当用漢字表」の時代にはこの漢字は「表外字」でしたから,これによって指定された標準字体は存在せず,一般の慣用として「丶のある塚」が「正字」とされていました。
今でも多くのところで「丶のある塚」が使用されているのは,この“慣用”がいまだに生きている表れかもしれません(…というより,常用漢字表では「丶のない塚」の方が“標準字体”であることが知られていないのかも)。
中国ではどうか,というと,試しに中国語の漢字字典である 『中華古漢語字典』上海人民出版社,1997年(タイトルはもちろん簡体字で表記されています)で探してみたら,「塚」という字そのものが収録されていません。
(中国(大陸)では,現代語による出版物はもちろん,古漢語(日本で言う漢文)による古典作品もどんどん簡体字化して横組みで出版しています。この漢字字書でも収録される親字は簡体字の字体で掲載されています。)
日本の側の漢字字典(『新字鑑』高等教育研究会,1939年初版,1957年改訂増補)で見てみたら,そもそも「塚」という字自体が「丶」の有無にかかわらず「冢」という字(丶がある)の“俗字”であるとのこと。
そこで再度,中国側の字書で探したら「冢」zhong という字のところに“異体字”として「丶のある塚」が掲載されていました。
日本の“新字体”(当用漢字表,常用漢字表の字体),中国(大陸)の“簡体字”による異同がからまなくても,日中で漢字のデザインが違うことはままあります。
前にも触れたことですが,江ノ電の 和田塚駅 の手前の 鎌倉駅。中国語表記の「鎌」は日本語表記のそれとは違って,“つくり”の部分が「兼」ではなく「廉」になっています(“金へん”は簡体字のそれ)。
日本と中国(大陸)とでは標準の字体が違うのですね。
| [65951] 2008年 8月 6日(水)22:51:18 | 般若堂そんぴん さん |
| 塚,冢 | |
[65948] Issieさん
中国語簡体字・繁体字,双方の入力メソッドで「zhong」と入力すると,「丶のある塚」の方が「冢」よりも早く出てきました.ということは,中国語圏でも需要がある文字(字体)かも.
中国語簡体字・繁体字,双方の入力メソッドで「zhong」と入力すると,「丶のある塚」の方が「冢」よりも早く出てきました.ということは,中国語圏でも需要がある文字(字体)かも.
| [65953] 2008年 8月 6日(水)23:45:31 | EMM さん |
| 冢を使った書き込みはわ塚 | |
[65948] Issieさん
[65951] 般若堂そんぴんさん
落書き帳には「冢」の字を使用している過去記事がしっかりありまして…拙稿[65454]であります。
(冢で検索すると、検索結果に文字化けした記事が含まれてしまう症状がきっちり出てしまうため、さらなる過去にこの字が使用されている過去記事があるのかどうかは不明)
ちなみに旧美川町の藤冢神社、ネット上などでは「藤塚神社と紹介されていることが多い(しかも、リンクした検索結果のトップの方に並ぶのは白山市HP、白山市観光案内HP、石川県HP、北國新聞社HP、朝日新聞HPと言う面々)です。
しかし、実際に神社に行ってみると拝殿の扁額にはしっかり「藤冢神社」と書かれているので、「冢」の字の方が多分正式なんだと思います。
日本で「冢」の字が使われる事例ってまだあるんでしょうか?
[65951] 般若堂そんぴんさん
落書き帳には「冢」の字を使用している過去記事がしっかりありまして…拙稿[65454]であります。
(冢で検索すると、検索結果に文字化けした記事が含まれてしまう症状がきっちり出てしまうため、さらなる過去にこの字が使用されている過去記事があるのかどうかは不明)
ちなみに旧美川町の藤冢神社、ネット上などでは「藤塚神社と紹介されていることが多い(しかも、リンクした検索結果のトップの方に並ぶのは白山市HP、白山市観光案内HP、石川県HP、北國新聞社HP、朝日新聞HPと言う面々)です。
しかし、実際に神社に行ってみると拝殿の扁額にはしっかり「藤冢神社」と書かれているので、「冢」の字の方が多分正式なんだと思います。
日本で「冢」の字が使われる事例ってまだあるんでしょうか?
| [65954] 2008年 8月 6日(水)23:45:48 | Issie さん |
| Re:塚,冢 | |
[65951] 般若堂そんぴん さん
中国語簡体字・繁体字,双方の入力メソッドで「zhong」と入力すると,「丶のある塚」の方が「冢」よりも早く出てきました.
考えて見れば『中華古漢語字典』は中国語にとっての「古語辞典」であって,現代語に対する資料としては不適切でしたね。そこで,zhong という発音もわかったので『岩波中国語辞典・簡体字版』1990年 を見てみましたが,この程度の大きさの辞書では「塚,冢」のいずれも掲載されず…。
そういえば,「塚」の“音”が「チョウ」だとは知りませんでした。現代日本語でこの漢字を音で読むことはほとんどないですよね。漢文を読むための字書である『新字鑑』には音で読む(四書五経などに出典がある)熟語がいくつか収録されているのですが,現代日本語ではまず用いられない。
現代中国語ではどうなのか。もしかしたら「塚」という文字は事実上,日本語の固有名詞を中国語で表記するため(だけ)に必要な文字だったりして…。
中国語簡体字・繁体字,双方の入力メソッドで「zhong」と入力すると,「丶のある塚」の方が「冢」よりも早く出てきました.
考えて見れば『中華古漢語字典』は中国語にとっての「古語辞典」であって,現代語に対する資料としては不適切でしたね。そこで,zhong という発音もわかったので『岩波中国語辞典・簡体字版』1990年 を見てみましたが,この程度の大きさの辞書では「塚,冢」のいずれも掲載されず…。
そういえば,「塚」の“音”が「チョウ」だとは知りませんでした。現代日本語でこの漢字を音で読むことはほとんどないですよね。漢文を読むための字書である『新字鑑』には音で読む(四書五経などに出典がある)熟語がいくつか収録されているのですが,現代日本語ではまず用いられない。
現代中国語ではどうなのか。もしかしたら「塚」という文字は事実上,日本語の固有名詞を中国語で表記するため(だけ)に必要な文字だったりして…。
| [65959] 2008年 8月 7日(木)11:08:34 | 油天神山 さん |
| つか(チョウ) | |
[65953]EMMさん
日本で「冢」の字が使われる事例ってまだあるんでしょうか?
[65954]Issieさん
そういえば,「塚」の“音”が「チョウ」だとは知りませんでした。現代日本語でこの漢字を音で読むことはほとんどないですよね。漢文を読むための字書である『新字鑑』には音で読む(四書五経などに出典がある)熟語がいくつか収録されているのですが,現代日本語ではまず用いられない。
「陪冢(または陪塚、読みは「バイチョウ」または「バイヅカ」)」くらいですかねえ、現在の日本における「冢」の用例、それに「塚」を「チョウ」と読む用例は。
「陪冢・陪塚」とは巨大古墳の周辺に散在する小さな古墳を指します(本当はもっと厳密な定義があるようですが、説明できるほど理解できていないので割愛)。考古学への関心が高い現在でこそ一般の人の目に触れる機会も増えていますが、まあ考古学用語と言っていいでしょう。
この「ばいづか」という重箱読みが私にはどうにも気持ち悪くて、誤用じゃないかとも思ったのですが、調べてみると広辞苑の第1版(1955年)にも「ばいちょう[陪冢・陪塚]」の項の最後に「ばいづか」とありましたから、昨日今日使われだした読みではないようです。
なにしろIssieさんですらご存じなかったという「塚」の音読みですから、知らずに重箱読みをする人は多く、いつしか誤用とは言えないほどに広がったとしても無理からぬことのように思えます。
日本で「冢」の字が使われる事例ってまだあるんでしょうか?
[65954]Issieさん
そういえば,「塚」の“音”が「チョウ」だとは知りませんでした。現代日本語でこの漢字を音で読むことはほとんどないですよね。漢文を読むための字書である『新字鑑』には音で読む(四書五経などに出典がある)熟語がいくつか収録されているのですが,現代日本語ではまず用いられない。
「陪冢(または陪塚、読みは「バイチョウ」または「バイヅカ」)」くらいですかねえ、現在の日本における「冢」の用例、それに「塚」を「チョウ」と読む用例は。
「陪冢・陪塚」とは巨大古墳の周辺に散在する小さな古墳を指します(本当はもっと厳密な定義があるようですが、説明できるほど理解できていないので割愛)。考古学への関心が高い現在でこそ一般の人の目に触れる機会も増えていますが、まあ考古学用語と言っていいでしょう。
この「ばいづか」という重箱読みが私にはどうにも気持ち悪くて、誤用じゃないかとも思ったのですが、調べてみると広辞苑の第1版(1955年)にも「ばいちょう[陪冢・陪塚]」の項の最後に「ばいづか」とありましたから、昨日今日使われだした読みではないようです。
なにしろIssieさんですらご存じなかったという「塚」の音読みですから、知らずに重箱読みをする人は多く、いつしか誤用とは言えないほどに広がったとしても無理からぬことのように思えます。
| [65962] 2008年 8月 7日(木)16:39:38 | hmt さん |
| 「丶」がある「塚」と「丶」がない「塚」 | |
平塚市や宝塚市等の「塚」の字についての疑問から発した話題、意外に盛り上がっています。過去記事
これまでに明らかになったことを整理してみます。
漢字の本筋としては、「つちへん」がなく「丶」がある「冢」という字A が“正字”とされていました。
「冢」の“俗字”である「つちへん」のある「塚」という字B が(日本では)普通に使われていました。
平塚市(1932)や宝塚市(1954)が誕生した時代には、当然この字が使われたと思われます。
1981年に常用漢字が制定され、いわゆる康熙字典体の「丶」がある字B に代って、「丶」がない「塚」という字C が採用されました。
常用漢字表の 前書き には、“この表は,固有名詞を対象とするものではない”と記されています。
従って[65903]にあるように、
自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り,常用漢字表への移行とともに“自動的”に標準字体である「丶のない塚」に統一された
とは考えにくいのですが、“法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安”とされる常用漢字の影響力が、固有名詞にも及ぶ事実は否定できません。
当事者である市民や市役所の使う地名は、旧字体を使用するという格別の信念を持って行動しない限り、次第に常用漢字体C に移ってゆくのが自然のなりゆきです。ましてや、地名は市民や市役所だけのものでなく、全国の人が使うものですから、地元の意向だけで旧字体B を墨守するわけにもゆきません。
常用漢字制度以外に、パソコンの普及による入力手段の影響もあるかもしれません。
常用漢字体C =「丶」がない「塚」は、JIS第一水準に入っており、普通のIMEにより「つか」から容易に変換入力できます。
旧字体B =「丶」がある「塚」は、 JIS第一水準・第二水準には含まれていないものの、IBM拡張文字コード表に含まれており、シフトJISコードFA9Cが付与されているので、多くのパソコンでは入力可能と思われます。しかしIMEによる標準的かな漢字変換でサポートされていなければ、普通の人は使いません。
# この落書き帳では、プレビューしてみたら文字化けして使えないことがわかりました。
かくして、常用漢字制定から28年目の現在、「丶」がない常用漢字体C の地位は圧倒的なものになりました。
市勢要覧[65935]で「丶」がある旧字体B へのこだわりを示していた宝塚市当局でさえも、戸籍関係証明申請書書式の例[65930]では、常用漢字体Cを使用することになりました。
結局、固有名詞を対象にしないと逃げた常用漢字表のために、一般の市民・国民の間だけでなく、市当局の内部でさえも、地名の表記が不統一になってしまったという事実が明らかになったわけです。
このような不統一は不都合なことでしょうか?
いやいや、もともと生きものである「地名表記」を「統一」するなど、望むべくして不可能なことである思われます。
「丶」があってもなくても、他の地名と誤認混同するおそれがなければ、よいではありませんか。
「丶」ありの旧字体Bにこだわる人はそれを貫くもよし。但し、ネットでは文字化けしたり、検索対象から脱落するおそれがあるのでご注意を。
これまでに明らかになったことを整理してみます。
漢字の本筋としては、「つちへん」がなく「丶」がある「冢」という字A が“正字”とされていました。
「冢」の“俗字”である「つちへん」のある「塚」という字B が(日本では)普通に使われていました。
平塚市(1932)や宝塚市(1954)が誕生した時代には、当然この字が使われたと思われます。
1981年に常用漢字が制定され、いわゆる康熙字典体の「丶」がある字B に代って、「丶」がない「塚」という字C が採用されました。
常用漢字表の 前書き には、“この表は,固有名詞を対象とするものではない”と記されています。
従って[65903]にあるように、
自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り,常用漢字表への移行とともに“自動的”に標準字体である「丶のない塚」に統一された
とは考えにくいのですが、“法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安”とされる常用漢字の影響力が、固有名詞にも及ぶ事実は否定できません。
当事者である市民や市役所の使う地名は、旧字体を使用するという格別の信念を持って行動しない限り、次第に常用漢字体C に移ってゆくのが自然のなりゆきです。ましてや、地名は市民や市役所だけのものでなく、全国の人が使うものですから、地元の意向だけで旧字体B を墨守するわけにもゆきません。
常用漢字制度以外に、パソコンの普及による入力手段の影響もあるかもしれません。
常用漢字体C =「丶」がない「塚」は、JIS第一水準に入っており、普通のIMEにより「つか」から容易に変換入力できます。
旧字体B =「丶」がある「塚」は、 JIS第一水準・第二水準には含まれていないものの、IBM拡張文字コード表に含まれており、シフトJISコードFA9Cが付与されているので、多くのパソコンでは入力可能と思われます。しかしIMEによる標準的かな漢字変換でサポートされていなければ、普通の人は使いません。
# この落書き帳では、プレビューしてみたら文字化けして使えないことがわかりました。
かくして、常用漢字制定から28年目の現在、「丶」がない常用漢字体C の地位は圧倒的なものになりました。
市勢要覧[65935]で「丶」がある旧字体B へのこだわりを示していた宝塚市当局でさえも、戸籍関係証明申請書書式の例[65930]では、常用漢字体Cを使用することになりました。
結局、固有名詞を対象にしないと逃げた常用漢字表のために、一般の市民・国民の間だけでなく、市当局の内部でさえも、地名の表記が不統一になってしまったという事実が明らかになったわけです。
このような不統一は不都合なことでしょうか?
いやいや、もともと生きものである「地名表記」を「統一」するなど、望むべくして不可能なことである思われます。
「丶」があってもなくても、他の地名と誤認混同するおそれがなければ、よいではありませんか。
「丶」ありの旧字体Bにこだわる人はそれを貫くもよし。但し、ネットでは文字化けしたり、検索対象から脱落するおそれがあるのでご注意を。
| [65964] 2008年 8月 7日(木)19:18:25 | hmt さん |
| 土を盛り上げた大きな墓「塚」 | |
[65948] Issie さん
そもそも「塚」という字自体が「丶」の有無にかかわらず「冢」という字(丶がある)の“俗字”であるとのこと。
「冢」は、土を盛り上げた大きな墓の意味ですが、この字を構成要素に分解すると、「ワ冠」と「豕」と「丶」になります。
いけにえの豚(豕)が「丶」で表される「足を縛られた形」で埋められ、その上の「ワ冠」は土で「覆う」ことを示しています。
俗字とされる「塚」は、この土を明示したものです。
なお、「塚」よりも更に大きな墓は、「墳」と呼びます。
「塚」は、一里塚のような、墓以外の土盛りにも使われます。
「冢」の「ワ冠」は、土で盛り上げて「覆う」だけですが、1画多い「ウ冠」になると、建物の「四方に垂れる屋根」の形です。
屋根の下で「豕」を飼っているのが「家」。「冢」とは「丶」の位置が違うだけで、意味はだいぶ変ったようですが、こちらもいけにえを捧げて神霊を祀った建物かもしれません。
中国語の漢字字典である 『中華古漢語字典』1997年で探してみたら,「塚」という字そのものが収録されていません。
中国では1955/12/22に発表された「異字体整理表」により「塚」を使わず「冢」に整理したそうです。諸橋:大漢和辞典13巻1174頁による。
[65954] Issie さん
「塚」の“音”が「チョウ」だとは知りませんでした。現代日本語でこの漢字を音で読むことはほとんどないですよね。
現代日本語における「塚」は、人名・地名で「つか」と読む場合が圧倒的ですが、[65959] 油天神山さん が示された「陪塚」(バイチョウ、[64972]で田道間守の墓をリンク)のほかに、「塚墓(チョウボ)」というような使い方もあります。京都新聞記事
[65946] 鳴子こけし さん
前報[65962]において、一般の市民・国民の間だけでなく、市当局の内部でさえも、自治体名の表記が不統一になっている現状と それを是認する発言をしましたが、駅名については、自治体の名前以上に当事者まかせと思われます。
駅名標現地確認の結果は、戸塚・東戸塚が旧字体、平塚が常用漢字体で、交通新聞社の「JR時刻表」と一致していたわけですか。
索引地図が基準?それとも駅名標を基準に索引地図を作成しているのでしょうか?
そりゃあ、もちろん現地の駅名標基準でしょう。部外者である交通新聞社の時刻表が基準になるわけはありません。
念のため古いJR時刻表(2004年4月)を見たら、戸塚・東戸塚も「丶」がない常用漢字体を使っていました。
日本国有鉄道時代に編纂された「停車場一覧」は、戸塚駅・平塚駅・宝塚駅共に旧字体B。これは1972年だから当然。
東戸塚駅は、常用漢字表が行なわれた前年の1980年開業。
JR東日本HP、JR西日本HP 共に常用漢字体C を使っていますね。
「会社として」の使い方、「それぞれの駅の現場として」の使い方、それらが統一されているようには思われません。
要するに、「丶」のある旧字体B も「丶」のない常用漢字体C も“同じ字”で誤認混同のおそれはないから、そんな違いを気にする必要はないということだと思います。
そもそも「塚」という字自体が「丶」の有無にかかわらず「冢」という字(丶がある)の“俗字”であるとのこと。
「冢」は、土を盛り上げた大きな墓の意味ですが、この字を構成要素に分解すると、「ワ冠」と「豕」と「丶」になります。
いけにえの豚(豕)が「丶」で表される「足を縛られた形」で埋められ、その上の「ワ冠」は土で「覆う」ことを示しています。
俗字とされる「塚」は、この土を明示したものです。
なお、「塚」よりも更に大きな墓は、「墳」と呼びます。
「塚」は、一里塚のような、墓以外の土盛りにも使われます。
「冢」の「ワ冠」は、土で盛り上げて「覆う」だけですが、1画多い「ウ冠」になると、建物の「四方に垂れる屋根」の形です。
屋根の下で「豕」を飼っているのが「家」。「冢」とは「丶」の位置が違うだけで、意味はだいぶ変ったようですが、こちらもいけにえを捧げて神霊を祀った建物かもしれません。
中国語の漢字字典である 『中華古漢語字典』1997年で探してみたら,「塚」という字そのものが収録されていません。
中国では1955/12/22に発表された「異字体整理表」により「塚」を使わず「冢」に整理したそうです。諸橋:大漢和辞典13巻1174頁による。
[65954] Issie さん
「塚」の“音”が「チョウ」だとは知りませんでした。現代日本語でこの漢字を音で読むことはほとんどないですよね。
現代日本語における「塚」は、人名・地名で「つか」と読む場合が圧倒的ですが、[65959] 油天神山さん が示された「陪塚」(バイチョウ、[64972]で田道間守の墓をリンク)のほかに、「塚墓(チョウボ)」というような使い方もあります。京都新聞記事
[65946] 鳴子こけし さん
前報[65962]において、一般の市民・国民の間だけでなく、市当局の内部でさえも、自治体名の表記が不統一になっている現状と それを是認する発言をしましたが、駅名については、自治体の名前以上に当事者まかせと思われます。
駅名標現地確認の結果は、戸塚・東戸塚が旧字体、平塚が常用漢字体で、交通新聞社の「JR時刻表」と一致していたわけですか。
索引地図が基準?それとも駅名標を基準に索引地図を作成しているのでしょうか?
そりゃあ、もちろん現地の駅名標基準でしょう。部外者である交通新聞社の時刻表が基準になるわけはありません。
念のため古いJR時刻表(2004年4月)を見たら、戸塚・東戸塚も「丶」がない常用漢字体を使っていました。
日本国有鉄道時代に編纂された「停車場一覧」は、戸塚駅・平塚駅・宝塚駅共に旧字体B。これは1972年だから当然。
東戸塚駅は、常用漢字表が行なわれた前年の1980年開業。
JR東日本HP、JR西日本HP 共に常用漢字体C を使っていますね。
「会社として」の使い方、「それぞれの駅の現場として」の使い方、それらが統一されているようには思われません。
要するに、「丶」のある旧字体B も「丶」のない常用漢字体C も“同じ字”で誤認混同のおそれはないから、そんな違いを気にする必要はないということだと思います。
| [65967] 2008年 8月 7日(木)22:22:59 | 伊豆之国 さん |
| 宝塚歌劇&渋民村 | |
[65964]他 hmtさん
[65946]他 鳴子こけしさん
[65937] ニジェガロージェッツさん
[65935] 右左府さん
[65927]他 Issieさん
‥「塚」の字体の件ですが、私がしばしば引用している「時刻表名探偵」(昭和54年初版)には、著者の石野哲氏が利用していた戸塚駅の「塚」の字体がその当時「テンなし」になっていたことが書かれているほか、「鶯谷」の駅名表示板で「鶯」の字が「鴬」になっていたことや、五能線の「艫作(へなし)」の「艫」が「舟へんに戸」という字体になっていて、「『蘆→芦』の類推と思うが、おそらく地元では「艫」などという難しい字を書いている人はいないのではないか」という推測が書かれていました。
そういえば、「逗子」や「辻堂」の「しんにゅう」は現在のJRの駅名板や路線図などではテンが二つになっていますが、国鉄時代はテンが一つになっていたような記憶があり、また総武線の千葉以東が未電化だった少年時代に銚子方面に行ったとき、「干潟」駅の駅名板の「潟」の字が「さんずいに写」になっていた(新潟方面ではメジャーだったらしいのですが‥)のを見たことがあります。
ところで、「テンなしの塚」は確かに早くから流通していたようですが、「テンの有無」といえば、切磋琢磨の「琢」や石川啄木の「啄」のつくりはどちらも「テンあり」だったはずなのに、今の活字ではいつの間にか「テン」が取れているようです。特に「テンなし」の「啄木」には、いまだに違和感を禁じえないのですが。その啄木も、今では「盛岡市出身」になってしまったのですね‥
さて、啄木が一時期を過ごした「函館」の話。今日のTV「ケンミンSHOW」で、北海道函館の七夕のことが出てきましたが、その中で「子供たちへの注意」を書いた紙に「校区内では‥」ということが書かれていました。以前にも話題になった「校区」という呼び名、西日本方面のものと思うのですが、北海道でも普通に使っているのでしょうか。
「塚」に戻りますが、これも私が過去に取り上げた「忘れられた日本史」([63973])の最後のところで「『宝塚』の成立」について書かれています。そこにはこの本が書かれた頃(昭和40年代)の国鉄宝塚駅の写真があり、それを見ると随分小ぢんまりした駅であったようです(それでも当時は福知山線で唯一の特急停車駅であったと記憶しています)。ところで「宝塚歌劇」という月刊誌が出ているのですが、その「塚」は「テンあり」の字体になっていました。その宝塚出身の「鉄腕アトム」手塚治虫氏。直接関係ありませんが、この「手塚」さんは関東周辺に多い苗字で、とりわけ栃木県に多く全国の2割以上を占めます。宇都宮から「日光の手前」にかけての範囲に特に多いようです。
[65946]他 鳴子こけしさん
[65937] ニジェガロージェッツさん
[65935] 右左府さん
[65927]他 Issieさん
‥「塚」の字体の件ですが、私がしばしば引用している「時刻表名探偵」(昭和54年初版)には、著者の石野哲氏が利用していた戸塚駅の「塚」の字体がその当時「テンなし」になっていたことが書かれているほか、「鶯谷」の駅名表示板で「鶯」の字が「鴬」になっていたことや、五能線の「艫作(へなし)」の「艫」が「舟へんに戸」という字体になっていて、「『蘆→芦』の類推と思うが、おそらく地元では「艫」などという難しい字を書いている人はいないのではないか」という推測が書かれていました。
そういえば、「逗子」や「辻堂」の「しんにゅう」は現在のJRの駅名板や路線図などではテンが二つになっていますが、国鉄時代はテンが一つになっていたような記憶があり、また総武線の千葉以東が未電化だった少年時代に銚子方面に行ったとき、「干潟」駅の駅名板の「潟」の字が「さんずいに写」になっていた(新潟方面ではメジャーだったらしいのですが‥)のを見たことがあります。
ところで、「テンなしの塚」は確かに早くから流通していたようですが、「テンの有無」といえば、切磋琢磨の「琢」や石川啄木の「啄」のつくりはどちらも「テンあり」だったはずなのに、今の活字ではいつの間にか「テン」が取れているようです。特に「テンなし」の「啄木」には、いまだに違和感を禁じえないのですが。その啄木も、今では「盛岡市出身」になってしまったのですね‥
さて、啄木が一時期を過ごした「函館」の話。今日のTV「ケンミンSHOW」で、北海道函館の七夕のことが出てきましたが、その中で「子供たちへの注意」を書いた紙に「校区内では‥」ということが書かれていました。以前にも話題になった「校区」という呼び名、西日本方面のものと思うのですが、北海道でも普通に使っているのでしょうか。
「塚」に戻りますが、これも私が過去に取り上げた「忘れられた日本史」([63973])の最後のところで「『宝塚』の成立」について書かれています。そこにはこの本が書かれた頃(昭和40年代)の国鉄宝塚駅の写真があり、それを見ると随分小ぢんまりした駅であったようです(それでも当時は福知山線で唯一の特急停車駅であったと記憶しています)。ところで「宝塚歌劇」という月刊誌が出ているのですが、その「塚」は「テンあり」の字体になっていました。その宝塚出身の「鉄腕アトム」手塚治虫氏。直接関係ありませんが、この「手塚」さんは関東周辺に多い苗字で、とりわけ栃木県に多く全国の2割以上を占めます。宇都宮から「日光の手前」にかけての範囲に特に多いようです。
| [65968] 2008年 8月 7日(木)22:53:30【2】 | Issie さん |
| 私はカモメ | |
手塚治虫の漫画を読んでいると,フキダシの外や背景に書き込まれた文字に時折,私たちが学校で教わる字とは違う形の字が書かれていることがあります。
たとえば,この人が書く「画」という字には特徴があって,いわゆる旧字体(畫)ではなく現行の字体(画)に近いのだけれども,やっぱり違う(かなり後の1970年代の作品にも見られたように思います)。私たちには少し違和感のある字体だけど,別に手塚治虫個人の独創によるものでも,クセ字でもなく,この人が学校教育を受けた時代に通用していた手書きの略字体の1つなのだと思います。
1949年に「当用漢字字体表」が“内閣告示”として出されるにあたって,それらの略字体の中から選ばれたのが「画」という形。それでも手塚治虫は,手書きの文字としては「画」とは違う形の字を使い続けていたのですね。
まあ,「塚」についていろいろと書いてきたわけですが,私の基本的な立場は,
[65964] hmt さん
要するに、「丶」のある旧字体B も「丶」のない常用漢字体C も“同じ字”で誤認混同のおそれはないから、そんな違いを気にする必要はないということだと思います。
この通りなのです。
すでに何度も例として持ち出しているものを,またも持ち出してしまうのですが,「鴎」についても“誤差”の範囲。繰り返しになりますが,私は「区+鳥」による「鴎外」表記容認派です。
ただ,「竜」と「龍」ほど形が違い,しかも両方の形が広く併用されているとなると,その辺りの自信が…。私としては“現行の標準字体”である「竜」に統一したいところですが(たとえば「竜野」「坂本竜馬」…),悩み深いものがあります。
(今現在生存し活動しておられる個人や団体のアイデンティティは最大限尊重されるべきですが,“歴史上の人物”や“公共の所有物としての地名”については「一般的な規範に従った表記」が優先されるべきだと考えています。「橋本龍太郎」さんは,グレーゾーンかなぁ。)
※念のために確認したら,「龍」は1981年に「人名漢字許容字体」に,2004年には「人名漢字」に追加されているのですね。ならば,“人名”である「龍太郎」さんは,問題なしか(厳密には,今,モニターに表示されている形(龍)とは微妙に違うのですが)。
ま,いろいろ言っても,結局のところは,実際の使われ方を尊重するということになるでしょう。
[65967] 伊豆之国 さん
この「手塚」さんは関東周辺に多い苗字
この人の作品の『陽だまりの樹』の基本的設定が“史実”をもとにしたものであるならば,ご先祖は 常陸府中(石岡)藩 の藩医で江戸出身ということになっていますね。関東系の人なのかもしれません。
たとえば,この人が書く「画」という字には特徴があって,いわゆる旧字体(畫)ではなく現行の字体(画)に近いのだけれども,やっぱり違う(かなり後の1970年代の作品にも見られたように思います)。私たちには少し違和感のある字体だけど,別に手塚治虫個人の独創によるものでも,クセ字でもなく,この人が学校教育を受けた時代に通用していた手書きの略字体の1つなのだと思います。
1949年に「当用漢字字体表」が“内閣告示”として出されるにあたって,それらの略字体の中から選ばれたのが「画」という形。それでも手塚治虫は,手書きの文字としては「画」とは違う形の字を使い続けていたのですね。
まあ,「塚」についていろいろと書いてきたわけですが,私の基本的な立場は,
[65964] hmt さん
要するに、「丶」のある旧字体B も「丶」のない常用漢字体C も“同じ字”で誤認混同のおそれはないから、そんな違いを気にする必要はないということだと思います。
この通りなのです。
すでに何度も例として持ち出しているものを,またも持ち出してしまうのですが,「鴎」についても“誤差”の範囲。繰り返しになりますが,私は「区+鳥」による「鴎外」表記容認派です。
ただ,「竜」と「龍」ほど形が違い,しかも両方の形が広く併用されているとなると,その辺りの自信が…。私としては“現行の標準字体”である「竜」に統一したいところですが(たとえば「竜野」「坂本竜馬」…),悩み深いものがあります。
(今現在生存し活動しておられる個人や団体のアイデンティティは最大限尊重されるべきですが,“歴史上の人物”や“公共の所有物としての地名”については「一般的な規範に従った表記」が優先されるべきだと考えています。「橋本龍太郎」さんは,グレーゾーンかなぁ。)
※念のために確認したら,「龍」は1981年に「人名漢字許容字体」に,2004年には「人名漢字」に追加されているのですね。ならば,“人名”である「龍太郎」さんは,問題なしか(厳密には,今,モニターに表示されている形(龍)とは微妙に違うのですが)。
ま,いろいろ言っても,結局のところは,実際の使われ方を尊重するということになるでしょう。
[65967] 伊豆之国 さん
この「手塚」さんは関東周辺に多い苗字
この人の作品の『陽だまりの樹』の基本的設定が“史実”をもとにしたものであるならば,ご先祖は 常陸府中(石岡)藩 の藩医で江戸出身ということになっていますね。関東系の人なのかもしれません。
| [65971] 2008年 8月 8日(金)09:04:15 | 鳴子こけし さん |
| 現地確認第二弾 | |
[65964]hmtさん
そりゃあ、もちろん現地の駅名標基準でしょう。部外者である交通新聞社の時刻表が基準になるわけはありません。
えっと、“索引地図が基準?”は軽い冗談で…(←言い逃れ)
しかし、再度平塚駅に行ってみたら、『ひげ塚』が有ったんですよ。違う駅名標に。
同じ駅の中で字Bと字Cの両方が使われてる???
因みに今回は『雪が谷大塚(東急池上線)』『塚田(東武野田線)』『竹ノ塚(東武伊勢崎線』『八塚(東武伊勢崎線)』に行きましたが、4駅とも『丶無し塚』でした。
そりゃあ、もちろん現地の駅名標基準でしょう。部外者である交通新聞社の時刻表が基準になるわけはありません。
えっと、“索引地図が基準?”は軽い冗談で…(←言い逃れ)
しかし、再度平塚駅に行ってみたら、『ひげ塚』が有ったんですよ。違う駅名標に。
同じ駅の中で字Bと字Cの両方が使われてる???
因みに今回は『雪が谷大塚(東急池上線)』『塚田(東武野田線)』『竹ノ塚(東武伊勢崎線』『八塚(東武伊勢崎線)』に行きましたが、4駅とも『丶無し塚』でした。
| [65972] 2008年 8月 8日(金)14:11:57 | hmt さん |
| 「丶」がない「塚」の公式デビューは 1977年 | |
[65967] 伊豆之国 さん
「時刻表名探偵」(昭和54年初版)には、著者の石野哲氏が利用していた戸塚駅の「塚」の字体がその当時「テンなし」になっていたことが書かれている
常用漢字が制定された1981年の2年前に、既に「丶」がない「塚」(常用漢字体C)が使われていたわけです。
このあたりの事情について、補足説明しておきます。
昭和21年(1946)に制定された1850字の当用漢字は、漢字の使用を制限する色彩の濃いものでした。
この政策はそれなりの成果を挙げたものの、国語表現に加えられた束縛等についての批判もありました。
当用漢字から30年を経た昭和50年代になると、使用頻度の大きく、造語力のある漢字を中心とし、社会生活で用いる漢字の目安となるリストへの見直しが行なわれました。
こうして、第12期国語審議会は、昭和52年1月21日に、1900字からなる「新漢字表試案」を発表しました。
「時刻表名探偵」は、まさにこの時代の作品でした。
この「新漢字表試案」(1977)は、当用漢字1850字に新たな83字を加え、33字を削除したものです。
文化庁の注記 によって、個々の文字の出入りを確認することができますが、新規83文字の49番目に「塚」を確認することができます。
おそらくこれが、「丶」がない「塚」が公式にデビューした時でしょう。
なお、“人名・地名などの固有名詞に用いる漢字は取り上げなかった”としているので、公式には戸塚・平塚・宝塚などの地名表記とは無縁ということになります。その点は、常用漢字と同じ。
「常用漢字表」(1981)では、この「新漢字表試案」になかった45字が更に追加されています。リンク文書参照。
「時刻表名探偵」(昭和54年初版)には、著者の石野哲氏が利用していた戸塚駅の「塚」の字体がその当時「テンなし」になっていたことが書かれている
常用漢字が制定された1981年の2年前に、既に「丶」がない「塚」(常用漢字体C)が使われていたわけです。
このあたりの事情について、補足説明しておきます。
昭和21年(1946)に制定された1850字の当用漢字は、漢字の使用を制限する色彩の濃いものでした。
この政策はそれなりの成果を挙げたものの、国語表現に加えられた束縛等についての批判もありました。
当用漢字から30年を経た昭和50年代になると、使用頻度の大きく、造語力のある漢字を中心とし、社会生活で用いる漢字の目安となるリストへの見直しが行なわれました。
こうして、第12期国語審議会は、昭和52年1月21日に、1900字からなる「新漢字表試案」を発表しました。
「時刻表名探偵」は、まさにこの時代の作品でした。
この「新漢字表試案」(1977)は、当用漢字1850字に新たな83字を加え、33字を削除したものです。
文化庁の注記 によって、個々の文字の出入りを確認することができますが、新規83文字の49番目に「塚」を確認することができます。
おそらくこれが、「丶」がない「塚」が公式にデビューした時でしょう。
なお、“人名・地名などの固有名詞に用いる漢字は取り上げなかった”としているので、公式には戸塚・平塚・宝塚などの地名表記とは無縁ということになります。その点は、常用漢字と同じ。
「常用漢字表」(1981)では、この「新漢字表試案」になかった45字が更に追加されています。リンク文書参照。
| [66013] 2008年 8月 12日(火)20:40:21 | 88 さん |
| 「丶あり塚」 と 「丶なし塚」 | |
[65903] Issie さん
(引用者前略)・・・常用漢字表への切り替えで通常の使用の場では「丶のない塚」に統一されたものと思われます。
地名で用いられる「塚」の字体についても基本的にはこの流れに乗っているのではないかと思います。
「法人」としての自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り,常用漢字表への移行とともに“自動的”に標準字体である「丶のない塚」に統一されたと考えていいのでないでしょうか。
地名以外に関しては、無条件で「丶のない塚」に統一された、との話はよく理解できます。地名に関しては、「『法人』としての自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り」ということも、現実にありそうで理解できます。
[65962] 2008 年 8 月 7 日 (木) 16:39:38 hmt さん
常用漢字表の 前書き には、“この表は,固有名詞を対象とするものではない”と記されています。
私も、この「固有名詞を対象とするものではない」という一言がずっと引っかかっています。固有名詞はいわゆる「旧字体のまま」と考えていたのですが、現実には改称を含めなんらの手続きがなく、新字体に置き換わっているのが実態です。最近では、確固たる自信はありませんが、私はそれなりに整理して次のように仮説をたてました。
・以前からある固有名詞はこの際新字体に置き換える。ただし、特定の意思を表示して旧字体を使用することを妨げない。
・今後新たに固有名詞を定めようとする場合には、対象としない。
これにより、「丶あり塚」は原則として『自動的に』「丶なし塚」に置き換えられ(「條」→「条」なども同様)、ただし、特段の意思表示を示したものは従前どおりいわゆる「旧字体」を引続き使用している(例:奈良県五條市)という仮説です。(同様の考え方が、当用漢字の導入時にもなかったのでしょうか?)
――――――――――――――――――――――――――――――
官報情報検索サービス(テキスト版、イメージ版)による確認した結果です。
(6)は、イメージ版の政令を見ると明らかに「丶あり」です。テキスト版では異体字のため、「宝#市」と表記されます。
(1)~(5)は、イメージ版では文字が潰れてしまい判別できません。テキスト形式では、「丶なし」です。このため、イメージ版でも「丶なし」であるとは想像しますが、はっきりわかりません。上記で「▲」は「丶なし塚」、「■」は「丶あり塚」です。
直近の特例市の指定でも、敢えて「丶あり塚」を使用しており、インターネット版「官報」で頻出している法務省告示の「日本国に帰化を許可する件」でも、宝づか市居住の人は「丶あり塚」を使用しています。これらから、おそらく「丶あり塚」が正式であろうと「推測します」(正式な根拠ではありませんが)。
前述の私の仮説でもある、「『宝づか市』が敢えて『丶あり塚』を使用する意思表示をしている」ことを確認したかったのですが、十分検証できず、上記仮説は推測の域を出ませんでした。
[65927][65930] でIssie さんが各自治体のHPでの表示を検証されていますが、現実に自治体で事務を行う段階で、例えば自治体名の字体が違うからといって受理できないと言うと事務が進みませんから、「許容」しているだけであると考えます。塩竈市が、「塩釜市」を許容しているように(塩竈市HP「竈」の字の書き方)。[65930] でIssie さんが
「戸籍関係証明交付申請書」の pdfファイル を拡大してみると,あて先の「宝塚市長」にも,本籍地の「宝塚市」という書き出しも,「丶のない塚」が使われています。市民はともかく,少なくとも“宝塚市役所”では「丶のない塚」を“公式”の表記としているものと思われます。
と述べておられますが、自治体の名称を「正式に」規定しているのは、改称であれば自治体の条例、新設合併であれば総務省等の告示ですから、ご紹介の戸籍の例は、「"公式"の表記」ではなく、単に「公式HPに掲載されているもの」に過ぎないでしょう。この例は、
のいずれかでしょう。
自治体の、「『そういう部署』の担当者以外は、表記や正式な町名などに無頓着」で、公式HPなどでは誤りが多いことを拙稿[59202] の「余談・・・・「公式文書」」の箇所でも述べております。公式HPに表現されているだけでは信憑性に乏しく、「本当の根拠」を追究することの重要性と困難さを改めて感じます。
なお、本稿は「自治体名」(行政地名)の議論であり、自治体名はきちんと一つに規定されているはずであるので答は2つとないはずだ、ということ、「地名」は揺らぎ等で表記の幅もあるであろうことを意識したうえでの投稿ですので、念のため申し添えます。
(引用者前略)・・・常用漢字表への切り替えで通常の使用の場では「丶のない塚」に統一されたものと思われます。
地名で用いられる「塚」の字体についても基本的にはこの流れに乗っているのではないかと思います。
「法人」としての自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り,常用漢字表への移行とともに“自動的”に標準字体である「丶のない塚」に統一されたと考えていいのでないでしょうか。
地名以外に関しては、無条件で「丶のない塚」に統一された、との話はよく理解できます。地名に関しては、「『法人』としての自治体がその字体に特別なこだわりを見せない限り」ということも、現実にありそうで理解できます。
[65962] 2008 年 8 月 7 日 (木) 16:39:38 hmt さん
常用漢字表の 前書き には、“この表は,固有名詞を対象とするものではない”と記されています。
私も、この「固有名詞を対象とするものではない」という一言がずっと引っかかっています。固有名詞はいわゆる「旧字体のまま」と考えていたのですが、現実には改称を含めなんらの手続きがなく、新字体に置き換わっているのが実態です。最近では、確固たる自信はありませんが、私はそれなりに整理して次のように仮説をたてました。
・以前からある固有名詞はこの際新字体に置き換える。ただし、特定の意思を表示して旧字体を使用することを妨げない。
・今後新たに固有名詞を定めようとする場合には、対象としない。
これにより、「丶あり塚」は原則として『自動的に』「丶なし塚」に置き換えられ(「條」→「条」なども同様)、ただし、特段の意思表示を示したものは従前どおりいわゆる「旧字体」を引続き使用している(例:奈良県五條市)という仮説です。(同様の考え方が、当用漢字の導入時にもなかったのでしょうか?)
――――――――――――――――――――――――――――――
官報情報検索サービス(テキスト版、イメージ版)による確認した結果です。
| 施行年月日 | 自治体名 | 変更種別 | 変更対象自治体名 | 告示等年月日 | 告示等番号 | |
| (1) | S26.3.15 | 川辺郡宝▲町 | 町制/改称 | 川辺郡小浜村 | S26.5.4 | 総理府告示第106号 |
| (2) | S29.4.1 | 宝▲市 | 新設/市制 | 武庫郡良元村,川辺郡宝▲町 | S29.3.29 | 総理府告示第315号 |
| (3) | S30.3.10 | 宝▲市 | 編入 | 宝▲市,川辺郡長尾村 | S30.3.10 | 総理府告示第343号 |
| (4) | S30.3.14 | 宝▲市 | 編入 | 宝▲市,川辺郡西谷村 | S30.3.14 | 総理府告示第348号 |
| (5) | S30.4.1 | 伊丹市 | 境界変更 | 伊丹市,宝▲市の一部 | S30.3.31 | 総理府告示第1031号 |
| (6) | H15.4.1 | 宝■市 | 特例市 | 特例市に指定 | H14.12.13 | 政令第372号 |
(1)~(5)は、イメージ版では文字が潰れてしまい判別できません。テキスト形式では、「丶なし」です。このため、イメージ版でも「丶なし」であるとは想像しますが、はっきりわかりません。上記で「▲」は「丶なし塚」、「■」は「丶あり塚」です。
直近の特例市の指定でも、敢えて「丶あり塚」を使用しており、インターネット版「官報」で頻出している法務省告示の「日本国に帰化を許可する件」でも、宝づか市居住の人は「丶あり塚」を使用しています。これらから、おそらく「丶あり塚」が正式であろうと「推測します」(正式な根拠ではありませんが)。
前述の私の仮説でもある、「『宝づか市』が敢えて『丶あり塚』を使用する意思表示をしている」ことを確認したかったのですが、十分検証できず、上記仮説は推測の域を出ませんでした。
[65927][65930] でIssie さんが各自治体のHPでの表示を検証されていますが、現実に自治体で事務を行う段階で、例えば自治体名の字体が違うからといって受理できないと言うと事務が進みませんから、「許容」しているだけであると考えます。塩竈市が、「塩釜市」を許容しているように(塩竈市HP「竈」の字の書き方)。[65930] でIssie さんが
「戸籍関係証明交付申請書」の pdfファイル を拡大してみると,あて先の「宝塚市長」にも,本籍地の「宝塚市」という書き出しも,「丶のない塚」が使われています。市民はともかく,少なくとも“宝塚市役所”では「丶のない塚」を“公式”の表記としているものと思われます。
と述べておられますが、自治体の名称を「正式に」規定しているのは、改称であれば自治体の条例、新設合併であれば総務省等の告示ですから、ご紹介の戸籍の例は、「"公式"の表記」ではなく、単に「公式HPに掲載されているもの」に過ぎないでしょう。この例は、
| ・ | 正式には『丶あり塚』であるのは承知しているが、市民の便宜上、また、漢字変換の都合上(「丶あり塚」だと文字化けしやすいことがある)、あえて『丶なし塚』で代用した。 |
| ・ | 様式作成者(またはHP担当者)が何も考えずに「丶なし塚」を使用しただけである。 |
自治体の、「『そういう部署』の担当者以外は、表記や正式な町名などに無頓着」で、公式HPなどでは誤りが多いことを拙稿[59202] の「余談・・・・「公式文書」」の箇所でも述べております。公式HPに表現されているだけでは信憑性に乏しく、「本当の根拠」を追究することの重要性と困難さを改めて感じます。
なお、本稿は「自治体名」(行政地名)の議論であり、自治体名はきちんと一つに規定されているはずであるので答は2つとないはずだ、ということ、「地名」は揺らぎ等で表記の幅もあるであろうことを意識したうえでの投稿ですので、念のため申し添えます。
この特集記事はあなたのお気に召しましたか。よろしければ推奨してください。→ ★推奨します★(元祖いいね)
推奨するためには、メンバー登録が必要です。→ メンバー登録のご案内