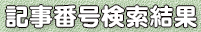… スポンサーリンク …
| [66993] 2008年 10月 12日(日)12:52:25 | hmt さん |
| 国土面積統計の変遷(1) 内務省地理局の時代には伊能忠敬の測量結果に依存 | |
[66937] オーナー グリグリさん
都道府県市区町村の面積データを更新いたしました。
この機会に、国土面積統計の変遷を探ってみました。
最初の手がかりは、国土地理院プレスリリース です。
国土面積の公表は、明治15年(1882)に内閣統計局によって初めて実施され、人口統計と並ぶ古い歴史を持っています。昭和35年(1960)からは国土地理院が、『全国都道府県市区町村別面積調』として毎年公表しています。
「有史以前」の人口統計 において、明治23年(市制・町村制が実施された翌年)10月に、39市・15859町村 の前年末現住人口データが、内務省告示34号 で発表されたことを記しました。
手始めに 2匹目の泥鰌狙いで法令全書を調査しましたが、成果なし。そもそもイロハ順索引に「面積」がない!
日本法令索引とその明治前期編で「面積」や「統計」を検索した結果も、めぼしい成果なし。
今度は、統計局HPを見ます。トップ>日本統計年鑑>第1章 国土・気象>解説 に進むと
面積
国土交通省国土地理院が昭和30年以来毎年10月1日現在で取りまとめている「全国都道府県市区町村別面積調」による。
との記載。これは“昭和35年以来”の誤記でしょうが、それ以前のことはわかりません。
そこで 「明治 面積」で統計局HP内検索をかけると、前記のページと同じ表題だが内容は別のページ がヒットし、その中に資料解説がありました。
「日本帝国統計年鑑」
この年鑑は,明治15年(1882)に第1回「統計年鑑」として刊行され,59回まで継続したが,戦争のため一時中断しその後,昭和24年(1949)から「日本統計年鑑」として毎年刊行されており,今日に至っている。【引用者注:平成20年第57回】
この“明治15年”第1回「統計年鑑」が、国土面積を公表した最初の資料と思われます。
そこで近代デジタルライブラリーを探すと、明治時代のものはないが、大正元年~15年の15冊が収録されていました。
この大正時代の資料と統計局HPの記載をベースに、国土面積統計の変遷史を組み立ててみました。
最初は、内務省地理局による国土面積統計
明治15年の統計年鑑に掲載された最初の国土面積を直接確認することはまだできていませんが、30年後の 日本帝国第三十一統計年鑑(大正元年) に掲載された「周囲及面積」のうち、内地の部分 38万2415km2 とほぼ同じであろうと推測します。
【法定停電のため近代デジタルライブラリーは13日18時まで使えません】
説明
表中載する所の数は…文政年間伊能忠敬著す所の実測録及大図(3万6千分1)を本とし算出し、未測のものは他の諸図に拠り其大概を補ふ。但し伊豆相模武蔵安房上総の五箇国は内務省元地理局の実測に拠り…
官制が慌しく変動した明治初期から地理司や測量司はありましたが、明治7年(1874)に 内務省地理寮 が発足(1877地理局)。
この役所で全国大三角測量が開始されましたが、成果が利用できたのは南関東のみ。ほぼ全国をカバーする測量結果は、伊能忠敬の実測録頼りの状態であったことが、上記の説明文からわかります。
余談ですが、上記の面積表において、本州と四国の属島数に端数があったことにお気づきでしょうか?
説明文より
属島の数に端数あるは一島にして両地に属するものあるに由る 即ち本州と四国の間にある石島是なり
2県にまたがる島 の中で唯一の有人島・石島 でした。
都道府県市区町村の面積データを更新いたしました。
この機会に、国土面積統計の変遷を探ってみました。
最初の手がかりは、国土地理院プレスリリース です。
国土面積の公表は、明治15年(1882)に内閣統計局によって初めて実施され、人口統計と並ぶ古い歴史を持っています。昭和35年(1960)からは国土地理院が、『全国都道府県市区町村別面積調』として毎年公表しています。
「有史以前」の人口統計 において、明治23年(市制・町村制が実施された翌年)10月に、39市・15859町村 の前年末現住人口データが、内務省告示34号 で発表されたことを記しました。
手始めに 2匹目の泥鰌狙いで法令全書を調査しましたが、成果なし。そもそもイロハ順索引に「面積」がない!
日本法令索引とその明治前期編で「面積」や「統計」を検索した結果も、めぼしい成果なし。
今度は、統計局HPを見ます。トップ>日本統計年鑑>第1章 国土・気象>解説 に進むと
面積
国土交通省国土地理院が昭和30年以来毎年10月1日現在で取りまとめている「全国都道府県市区町村別面積調」による。
との記載。これは“昭和35年以来”の誤記でしょうが、それ以前のことはわかりません。
そこで 「明治 面積」で統計局HP内検索をかけると、前記のページと同じ表題だが内容は別のページ がヒットし、その中に資料解説がありました。
「日本帝国統計年鑑」
この年鑑は,明治15年(1882)に第1回「統計年鑑」として刊行され,59回まで継続したが,戦争のため一時中断しその後,昭和24年(1949)から「日本統計年鑑」として毎年刊行されており,今日に至っている。【引用者注:平成20年第57回】
この“明治15年”第1回「統計年鑑」が、国土面積を公表した最初の資料と思われます。
そこで近代デジタルライブラリーを探すと、明治時代のものはないが、大正元年~15年の15冊が収録されていました。
この大正時代の資料と統計局HPの記載をベースに、国土面積統計の変遷史を組み立ててみました。
最初は、内務省地理局による国土面積統計
明治15年の統計年鑑に掲載された最初の国土面積を直接確認することはまだできていませんが、30年後の 日本帝国第三十一統計年鑑(大正元年) に掲載された「周囲及面積」のうち、内地の部分 38万2415km2 とほぼ同じであろうと推測します。
【法定停電のため近代デジタルライブラリーは13日18時まで使えません】
| 土地 | 属島数 | 本地面積 | + | 属島面積 | = | 合計(方里) | (km2) | % |
| 本州 | 165.5 | 14492.21 | + | 78.91 | = | 14571.12 | 224737.2 | 58.77 |
| 四国 | 74.5 | 1151.24 | + | 29.43 | = | 1180.67 | 18210.0 | 4.76 |
| 九州 | 150 | 2311.86 | + | 305.68 | = | 2617.54 | 40371.6 | 10.56 |
| 北海道本地 | 13 | 5056.78 | + | 27.09 | = | 5083.87 | 78410.9 | 20.50 |
| 千島31島 | 1011.49 | = | 1011.49 | 15600.7 | 4.08 | |||
| 佐渡 | 56.33 | = | 56.33 | 868.8 | 0.23 | |||
| 隠岐 | 1 | 21.88 | + | 0.01 | = | 21.89 | 337.6 | 0.09 |
| 淡路 | 1 | 36.55 | + | 0.14 | = | 36.69 | 565.9 | 0.15 |
| 壱岐 | 1 | 8.55 | + | 0.08 | = | 8.63 | 133.1 | 0.03 |
| 対馬 | 5 | 43.95 | + | 0.77 | = | 44.72 | 689.7 | 0.18 |
| 琉球55島 | 156.91 | = | 156.91 | 2420.1 | 0.63 | |||
| 小笠原20島 | 4.5 | = | 4.5 | 69.4 | 0.02 | |||
| 合計 | 412 | 24352.25 | + | 442.11 | = | 24794.36 | 382415.1 | 100.00 |
表中載する所の数は…文政年間伊能忠敬著す所の実測録及大図(3万6千分1)を本とし算出し、未測のものは他の諸図に拠り其大概を補ふ。但し伊豆相模武蔵安房上総の五箇国は内務省元地理局の実測に拠り…
官制が慌しく変動した明治初期から地理司や測量司はありましたが、明治7年(1874)に 内務省地理寮 が発足(1877地理局)。
この役所で全国大三角測量が開始されましたが、成果が利用できたのは南関東のみ。ほぼ全国をカバーする測量結果は、伊能忠敬の実測録頼りの状態であったことが、上記の説明文からわかります。
余談ですが、上記の面積表において、本州と四国の属島数に端数があったことにお気づきでしょうか?
説明文より
属島の数に端数あるは一島にして両地に属するものあるに由る 即ち本州と四国の間にある石島是なり
2県にまたがる島 の中で唯一の有人島・石島 でした。
| [66996] 2008年 10月 12日(日)15:08:16 | YT さん |
| 面積の国土面積統計 | |
[66993] hmtさん
以前近代以前の日本の人口統計の全国国別人口表の方に明治15年の統計年鑑記載の面積を載せました。一応現物からコピーをとったもの(6頁~11頁、「面積国別」)から作成していますが、現物では各旧国毎に本地と属島別に面積が集計されています。ただ明治22年ぐらいまで統計年鑑をめくりましたが、国別面積は、明治15年のものしか確認できていません。
以下は5頁目「面積及周囲」に記載のものです(周囲、百分率は省略)。
府県別の面積は明治15年版には記載されておらず、明治16年版以降はコンスタントに記載されているようです。
以前近代以前の日本の人口統計の全国国別人口表の方に明治15年の統計年鑑記載の面積を載せました。一応現物からコピーをとったもの(6頁~11頁、「面積国別」)から作成していますが、現物では各旧国毎に本地と属島別に面積が集計されています。ただ明治22年ぐらいまで統計年鑑をめくりましたが、国別面積は、明治15年のものしか確認できていません。
以下は5頁目「面積及周囲」に記載のものです(周囲、百分率は省略)。
| 土地 | 属島ノ数 | 面積 | ||
| 本地 | 属島 | 合計 | ||
| 方里 | 方里 | 方里 | ||
| 本地 | 893 | 14,494.49 | 76.20 | 14,570.69 |
| 佐渡 | 5 | 56.33 | 0.01 | 56.34 |
| 隠岐 | 31 | 21.88 | 0.17 | 22.05 |
| 淡路 | 2 | 36.55 | 0.18 | 36.73 |
| 四国 | 233 | 1,151.24 | 30.18 | 1,181.42 |
| 九州 | 569 | 2,311.86 | 308.91 | 2,620.77 |
| 壱岐 | 17 | 8.55 | 0.26 | 8.81 |
| 対馬 | 81 | 43.95 | 0.38 | 44.33 |
| 琉球五十五島 | - | 156.91 | - | 156.91 |
| 北海道本地 | 16 | 5,056.78 | 50.92 | 5,107.70 |
| 千島三十島 | - | 986.23 | - | 986.23 |
| 小笠原十七島 | - | 4.65 | - | 4.65 |
| 総計 | 1,847 | 24,329.42 | 467.21 | 24,796.63 |
府県別の面積は明治15年版には記載されておらず、明治16年版以降はコンスタントに記載されているようです。
| [66997] 2008年 10月 12日(日)15:22:20 | YT さん |
| 追記 | |
| [66998] 2008年 10月 12日(日)16:32:31 | YT さん |
| 明治5年?明治8年の府県別面積 | |
いやあ、調べればもっと古いデータが存在するものですね。
さっき大隈重信文書を検索してみたところ、明治8年の府県別面積が以下の史料に町反で載っていました(90~93頁)。人口の方は明治5年の府県別本籍人口と一致します。
第一回統計表
ただ旧国別面積は不明ですし、北海道が除外されています。
[66996]で述べた明治15年の統計年鑑ですが、北海道本地と千島三十島に関しては、旧国別面積が示されておりません。というわけで北海道の旧国別面積のデータは入手できておりません(郡の面積を足せば概算できますが)。
他の史料では、[66954]のリンク先の『日本地誌提要』(明治7年,人口は明治6年1月1日調)にせよ『共武政表』(明治8年(データの年次は主に明治6年頃)、12年(版は明治11年、人口は明治12年1月1日調)、13年(版は明治12年、人口は明治13年1月1日調)、14年(版は明治13年、人口は明治14年1月1日調))にせよ、東西南北の幅は書いてあっても面積は測定していないようです。
それにしても属島の数が[66993]と[66996]でなんでこんなに違うんでしょう?
大隈重信文書、自分は詳しい経緯を知りませんが、貴重な一級史料のようですね。
さっき大隈重信文書を検索してみたところ、明治8年の府県別面積が以下の史料に町反で載っていました(90~93頁)。人口の方は明治5年の府県別本籍人口と一致します。
第一回統計表
ただ旧国別面積は不明ですし、北海道が除外されています。
[66996]で述べた明治15年の統計年鑑ですが、北海道本地と千島三十島に関しては、旧国別面積が示されておりません。というわけで北海道の旧国別面積のデータは入手できておりません(郡の面積を足せば概算できますが)。
他の史料では、[66954]のリンク先の『日本地誌提要』(明治7年,人口は明治6年1月1日調)にせよ『共武政表』(明治8年(データの年次は主に明治6年頃)、12年(版は明治11年、人口は明治12年1月1日調)、13年(版は明治12年、人口は明治13年1月1日調)、14年(版は明治13年、人口は明治14年1月1日調))にせよ、東西南北の幅は書いてあっても面積は測定していないようです。
それにしても属島の数が[66993]と[66996]でなんでこんなに違うんでしょう?
大隈重信文書、自分は詳しい経緯を知りませんが、貴重な一級史料のようですね。
| [67006] 2008年 10月 13日(月)14:25:05【1】 | hmt さん |
| 面積単位の換算 | |
[66996] YT さん
明治15年統計年鑑の国土面積未確認と記したら、早速のレスをいただき、ありがとうございます。
明治15年の国土面積総計は 24,796.63方里で、大正元年記載の値から内地分を合計した 24,794.36方里[66993]と大差なかったものの、内訳に違いがありますね。
例えば、30年前の明治15年に 893もあった本州の属島数[66998]が 大正元年には 165.5と減少しているのに、属島面積は 逆に 76.20→ 78.91方里と増加。
[66997] YT さん
1方里が何平方キロメートルなのか悩みますが・・・
メートル法基準なら15.4234711 km2ですが、ここ【注】とかだと15.3664 km2で換算していますし。
【注】熊本県統計調査課のページ(統計年報の引用と思われます)。
1方里が15.3664 km2という値は、1里≒3.92 kmという概略値を二乗した値と思われ、YT さんが記された15.4234711 km2の方が、1方里に近い値です。
「方里」とは、もちろん「平方里」の意味で、1里=36町、1町=60間、1間=6尺という 6進法に近い距離単位の体系から 1里=6の4乗×10尺ということになります。
明治24年(1891)に制定された 度量衡法 の第二条に、
棒【メートル原器】の面に記したる標線間の摂氏0.15度に於ける長さ 33分の10 を尺とし
とあるように 1尺=33分の10メートルですから、1里=6の4乗÷330=3.9272727…km です。
これから、前記のとおり 1方里は 約15.4234711 km2 となります。
私が[66993]で付け加えておいた km2 への換算には、上記の計算式を使っています。
けれども、伊能忠敬が測量した時代はもとより、国土面積24,796.63方里と発表した明治15年も、尺とメートルとの関係が厳密に定義された1891年より前のことです。1尺=33分の10メートルでよいのか?
実は、伊能忠敬が測量器具の長さの検定に使用したと伝えられる「折衷尺」が 伊能忠敬遺品目録 の74番に掲載されています。そして、大辞林の「折衷尺」の説明文には
現在に残る遺品によればその一尺は 30.304センチメートル。明治時代に曲尺(かねじやく)を定めるのに最も有力な根拠となった。
と記されています。
33分の10メートルと比べると10万分の3くらい違いますが、ほぼ同じ。
明治前期の面積単位も、これで換算して大きな誤りはないと思われます。
厳密に考えると、「折衷尺」の材料である木の線膨張係数は金属に比べればずっと小さいが、それでも繊維方向で 100万分の2くらいありますから夏と冬では基準となる「ものさし」の長さが変ります。
湿度の影響もあると思うので、あまり細かい差異を問題にしても無意味でしょう。
更に言えば、面積統計自体、地図上で一部の地域について測定し、それを集計したものですが、古い時代のデータでは、測地の誤差と面積測定の誤差は大きいものと思われます。
どの桁までを信用してよいのか、疑えばきりがないでしょう。
明治15年統計年鑑の国土面積未確認と記したら、早速のレスをいただき、ありがとうございます。
明治15年の国土面積総計は 24,796.63方里で、大正元年記載の値から内地分を合計した 24,794.36方里[66993]と大差なかったものの、内訳に違いがありますね。
例えば、30年前の明治15年に 893もあった本州の属島数[66998]が 大正元年には 165.5と減少しているのに、属島面積は 逆に 76.20→ 78.91方里と増加。
[66997] YT さん
1方里が何平方キロメートルなのか悩みますが・・・
メートル法基準なら15.4234711 km2ですが、ここ【注】とかだと15.3664 km2で換算していますし。
【注】熊本県統計調査課のページ(統計年報の引用と思われます)。
1方里が15.3664 km2という値は、1里≒3.92 kmという概略値を二乗した値と思われ、YT さんが記された15.4234711 km2の方が、1方里に近い値です。
「方里」とは、もちろん「平方里」の意味で、1里=36町、1町=60間、1間=6尺という 6進法に近い距離単位の体系から 1里=6の4乗×10尺ということになります。
明治24年(1891)に制定された 度量衡法 の第二条に、
棒【メートル原器】の面に記したる標線間の摂氏0.15度に於ける長さ 33分の10 を尺とし
とあるように 1尺=33分の10メートルですから、1里=6の4乗÷330=3.9272727…km です。
これから、前記のとおり 1方里は 約15.4234711 km2 となります。
私が[66993]で付け加えておいた km2 への換算には、上記の計算式を使っています。
けれども、伊能忠敬が測量した時代はもとより、国土面積24,796.63方里と発表した明治15年も、尺とメートルとの関係が厳密に定義された1891年より前のことです。1尺=33分の10メートルでよいのか?
実は、伊能忠敬が測量器具の長さの検定に使用したと伝えられる「折衷尺」が 伊能忠敬遺品目録 の74番に掲載されています。そして、大辞林の「折衷尺」の説明文には
現在に残る遺品によればその一尺は 30.304センチメートル。明治時代に曲尺(かねじやく)を定めるのに最も有力な根拠となった。
と記されています。
33分の10メートルと比べると10万分の3くらい違いますが、ほぼ同じ。
明治前期の面積単位も、これで換算して大きな誤りはないと思われます。
厳密に考えると、「折衷尺」の材料である木の線膨張係数は金属に比べればずっと小さいが、それでも繊維方向で 100万分の2くらいありますから夏と冬では基準となる「ものさし」の長さが変ります。
湿度の影響もあると思うので、あまり細かい差異を問題にしても無意味でしょう。
更に言えば、面積統計自体、地図上で一部の地域について測定し、それを集計したものですが、古い時代のデータでは、測地の誤差と面積測定の誤差は大きいものと思われます。
どの桁までを信用してよいのか、疑えばきりがないでしょう。
| [67042] 2008年 10月 16日(木)23:06:51 | hmt さん |
| 国土面積統計の変遷(2) 明治8年 第1回統計表 の謎 | |
[66998] YT さん
大隈重信文書を検索してみたところ、明治8年の府県別面積が以下の史料に町反で載っていました(90~93頁)。
リンク先からView Openすると、84コマの大きなpdf文書が現れました。なんと!左縦書きですね。
(4コマ)明治8年5月 統計寮
総例 昨年中我寮に於て作為せし諸表を蒐輯して1冊とし之を第1回統計表とす
[66993]を書いた時は、統計院(明治18年12月統計局)による「第一統計年鑑」(明治15年)が最初の公表だと思っていましたが、それよりも前に統計寮による資料があったのですね。
(9コマ)第13 庁位置戸口面積表【説明】
戸数人口は明治5年戸籍表に拠ると雖も社寺は原書に従て之を除き庁の位置は6年末の査定に従ふ…
面積は仮に耕地山野の両反別(5年の調査に係る)を以て推算表出す
(48、49コマ)第13 庁位置戸口面積表【本表】
東京府、京都府、大坂府の3府に続いて、茨城県、磐前県、石川県、岩手県、浜松県、…広島県とイロハ順で60県。
総計面積 3,478,490町17087、戸数 6,886,994、人員 31,912,264となっています。
明治15年統計院の面積算出は“伊能忠敬ノ大国三万六千分ノ一ヲ本トシテ算出シ”[66997]と、現在の面積調と同じく地図に基づいて測定する方法でしたが、こちらは“耕地山野の両反別”調査に基づくというから、いわば「検地方式」のようです。
面積には、“(明治)5年の調査”を使っていますが、他の項目では明治6~7年のデータもあり、府県別は明治8年という発行の時期を反映したものとなっています。
具体的な例で説明すると、明治5年の“耕地山野の両反別”調査の際に存在した(第一次)香川県は消滅しており、讃岐の値は、阿波・淡路と共に名東県に含まれています。
[66998]で指摘されているように、当時は開拓使が管轄していた 北海道 が除外されています。
もちろん、千島も含まれていません(千島樺太交換条約[43845]は第1回統計表の発行と同じ明治8年5月)。
沖縄は、明治5年に琉球王国を廃止して設置した琉球藩の時代。明治12年3月の琉球処分[9303]より前で、これも除外。
そして、もう一つ除外されていたのが小笠原。幕末の回収後に始まった日本統治も、生麦事件の影響で早々と撤退。明治8年は、ようやく明治丸を派遣して再度小笠原領有の動きを始めた時期でした。[26683]
第1回統計表の面積単位に使われた「町」は、1町=10反=100畝(せ)=3000歩です。
1歩(1坪)は1間四方で、メートル法ならば33分の60mの2乗ですから、約3.3058m2。地価について“3.3平方メートルあたり○○円”という表現は今でも使われています。
律令時代には、長さの単位「町」と関連した「1町四方の面積」すなわち3600歩でしたが、中世以後3000歩に変化。
[67006]同様に、事実上現在と同じメートル法換算が通用すると考えると、面積の1町=0.009917355…km2(約1ヘクタール)。
63府県総計 347万8490町17を換算すると 3万4497.4 km2
アレレ!?
北海道などが除外されているにしても、この面積は明らかに小さすぎます。
明治15年統計年鑑面積[66996] から北海道千島琉球小笠原を除いた 18541.14方里、つまり 285968.74km2の 12%しかありません。
区域の変化のなさそうないくつかの県を選んで、県の面積も比較してみましたが、いずれも9~13%程度であり、何か共通の問題がありそうですが、解決の糸口は見えず謎のまま。
どこかで一桁間違えた? まさかね。
大隈重信文書を検索してみたところ、明治8年の府県別面積が以下の史料に町反で載っていました(90~93頁)。
リンク先からView Openすると、84コマの大きなpdf文書が現れました。なんと!左縦書きですね。
(4コマ)明治8年5月 統計寮
総例 昨年中我寮に於て作為せし諸表を蒐輯して1冊とし之を第1回統計表とす
[66993]を書いた時は、統計院(明治18年12月統計局)による「第一統計年鑑」(明治15年)が最初の公表だと思っていましたが、それよりも前に統計寮による資料があったのですね。
(9コマ)第13 庁位置戸口面積表【説明】
戸数人口は明治5年戸籍表に拠ると雖も社寺は原書に従て之を除き庁の位置は6年末の査定に従ふ…
面積は仮に耕地山野の両反別(5年の調査に係る)を以て推算表出す
(48、49コマ)第13 庁位置戸口面積表【本表】
東京府、京都府、大坂府の3府に続いて、茨城県、磐前県、石川県、岩手県、浜松県、…広島県とイロハ順で60県。
総計面積 3,478,490町17087、戸数 6,886,994、人員 31,912,264となっています。
明治15年統計院の面積算出は“伊能忠敬ノ大国三万六千分ノ一ヲ本トシテ算出シ”[66997]と、現在の面積調と同じく地図に基づいて測定する方法でしたが、こちらは“耕地山野の両反別”調査に基づくというから、いわば「検地方式」のようです。
面積には、“(明治)5年の調査”を使っていますが、他の項目では明治6~7年のデータもあり、府県別は明治8年という発行の時期を反映したものとなっています。
具体的な例で説明すると、明治5年の“耕地山野の両反別”調査の際に存在した(第一次)香川県は消滅しており、讃岐の値は、阿波・淡路と共に名東県に含まれています。
[66998]で指摘されているように、当時は開拓使が管轄していた 北海道 が除外されています。
もちろん、千島も含まれていません(千島樺太交換条約[43845]は第1回統計表の発行と同じ明治8年5月)。
沖縄は、明治5年に琉球王国を廃止して設置した琉球藩の時代。明治12年3月の琉球処分[9303]より前で、これも除外。
そして、もう一つ除外されていたのが小笠原。幕末の回収後に始まった日本統治も、生麦事件の影響で早々と撤退。明治8年は、ようやく明治丸を派遣して再度小笠原領有の動きを始めた時期でした。[26683]
第1回統計表の面積単位に使われた「町」は、1町=10反=100畝(せ)=3000歩です。
1歩(1坪)は1間四方で、メートル法ならば33分の60mの2乗ですから、約3.3058m2。地価について“3.3平方メートルあたり○○円”という表現は今でも使われています。
律令時代には、長さの単位「町」と関連した「1町四方の面積」すなわち3600歩でしたが、中世以後3000歩に変化。
[67006]同様に、事実上現在と同じメートル法換算が通用すると考えると、面積の1町=0.009917355…km2(約1ヘクタール)。
63府県総計 347万8490町17を換算すると 3万4497.4 km2
アレレ!?
北海道などが除外されているにしても、この面積は明らかに小さすぎます。
明治15年統計年鑑面積[66996] から北海道千島琉球小笠原を除いた 18541.14方里、つまり 285968.74km2の 12%しかありません。
区域の変化のなさそうないくつかの県を選んで、県の面積も比較してみましたが、いずれも9~13%程度であり、何か共通の問題がありそうですが、解決の糸口は見えず謎のまま。
どこかで一桁間違えた? まさかね。
| [67048] 2008年 10月 17日(金)13:58:43【1】 | hmt さん |
| 国土面積統計の変遷(2.1) 租税寮の面積調査では「網走番外地」は対象外 | |
明治8年第1回統計表に記された63府県の面積総計は、僅かに 347万8490町= 3万4497.4 km2でした[67042]。
[67044] YT さん
単に統計が揃っていないだけのようです。
大体、耕地345万9978.5706町に対して山野が30万8857.3102町のはずがありませんね。
例えば石川県の面積が僅かに1574町(15.6km2)となっており、山野面積だけでは説明できない統計の不備があるようです。
しかし、この統計の更に根本的な問題は、これが「国土面積」を対象とした調査でなかった点にあるようです。
統計表を読み直しているうちに、次の記載に行き当たりました。
(7/84コマ)第12 戸口反別比較表【説明】戸口反別は明治5年租税寮の調査に原き 人口の数は同年戸籍寮の表に拠る
“租税寮の調査”--そうか、これは民有地の地租を対象にした調査だったのか。してみると、官有地は対象外かも…
44~47コマ 第12 戸口反別比較表(明治5年租税寮、明治6年地理寮調査)の一部(合計とkm2換算値を追加)
殆んどが官有地だった北海道は、面積調査の対象外であったことがわかります。
他の府県についても、山野のみならず、耕地を含めた官有地が含まれておらず、「国土面積」ではなかったと思われます。
[66993]の最初に掲げた国土地理院のプレスリリースが、“国土面積の公表は、明治15年(1882)に内閣統計局によって初めて実施され”となっていたことにも納得。
[67042]で「検地方式」と書きましたが、地積の積算によって日本の面積を求めることはできないことは既に言及していました。
[66539]hmt
地積を積算すれば、市区町村の面積、ひいては「日本の面積」が算出できるだろう…と思うのは、誤った考えなのですね。
個々の地積の不正確さもさることながら、「登記のない土地」(「無番地」)が存在するわけです。[48795] 88 さん
今回のような形で実例が登場することは、全く予測していませんでした。
【1】
統計の不備の例示を変更。更に記せば、熊谷県の耕地と山野面積(明治5年、44コマ)を合計すると160206町ですが、48コマでは60206町となっている(新潟県についても同様)など、明らかな誤記もあります。
[67044] YT さん
単に統計が揃っていないだけのようです。
大体、耕地345万9978.5706町に対して山野が30万8857.3102町のはずがありませんね。
例えば石川県の面積が僅かに1574町(15.6km2)となっており、山野面積だけでは説明できない統計の不備があるようです。
しかし、この統計の更に根本的な問題は、これが「国土面積」を対象とした調査でなかった点にあるようです。
統計表を読み直しているうちに、次の記載に行き当たりました。
(7/84コマ)第12 戸口反別比較表【説明】戸口反別は明治5年租税寮の調査に原き 人口の数は同年戸籍寮の表に拠る
“租税寮の調査”--そうか、これは民有地の地租を対象にした調査だったのか。してみると、官有地は対象外かも…
44~47コマ 第12 戸口反別比較表(明治5年租税寮、明治6年地理寮調査)の一部(合計とkm2換算値を追加)
| 耕地 | 山野 | 合計(町) | (km2) | |
| 明治5年開拓使 | … | … | ||
| 明治5年総計 | 3250921 | 156698 | 3407619 | 33795 |
| 明治6年開拓使 | 1407 | … | 1407 | 14 |
| 明治6年総計 | 3450079 | 308857 | 3758936 | 37279 |
殆んどが官有地だった北海道は、面積調査の対象外であったことがわかります。
他の府県についても、山野のみならず、耕地を含めた官有地が含まれておらず、「国土面積」ではなかったと思われます。
[66993]の最初に掲げた国土地理院のプレスリリースが、“国土面積の公表は、明治15年(1882)に内閣統計局によって初めて実施され”となっていたことにも納得。
[67042]で「検地方式」と書きましたが、地積の積算によって日本の面積を求めることはできないことは既に言及していました。
[66539]hmt
地積を積算すれば、市区町村の面積、ひいては「日本の面積」が算出できるだろう…と思うのは、誤った考えなのですね。
個々の地積の不正確さもさることながら、「登記のない土地」(「無番地」)が存在するわけです。[48795] 88 さん
今回のような形で実例が登場することは、全く予測していませんでした。
【1】
統計の不備の例示を変更。更に記せば、熊谷県の耕地と山野面積(明治5年、44コマ)を合計すると160206町ですが、48コマでは60206町となっている(新潟県についても同様)など、明らかな誤記もあります。
| [67056] 2008年 10月 18日(土)21:23:00 | hmt さん |
| 国土面積統計の変遷(3) 陸地測量部の時代 | |
明治8年の統計寮時代[67042][67048]の面積は国土全体でなかったようなので、また明治10年代に戻り、[66993]の続きを記します。
この時代に 内務省地理局の仕事は、参謀本部陸地測量部に引き継がれ、全国測量と基本図の作成が行なわれ、その成果に基づいて道府県面積・市町村面積も求められました。
最初に 組織のこと。
近代国家の歩みを始めた明治政府には、測地・地図つくりの仕事をする部門が、前回記した内務省地理局のほかに、もう一つありました。
それは、軍事作戦を遂行する土地の情報を知る必要のある陸軍でした。
現実に西南戦争を経験し、その後も内乱の危険に直面していた陸軍が、短期間に作り上げた迅速測図[44237][65097]のことは、これまでに何回も話題にしました。人口がらみで話題になった共武政表や徴発物件表[63483]も、同じく作戦目的の資料でした。
民政と軍事作戦と目的は違うものの、地図作りに使う測地技術は共通です。
地理局と参謀本部は技術や成果を共有していたようですが、明治17年(1884)6月の太政官達により、測量事業は陸軍に一本化されることになりました[44653]。内務省所属大三角測量事務ヲ参謀本部ニ引渡
参謀本部測量局は 明治21年(1888)に陸地測量部になり、1945年まではこの組織による日本の地図作りが進められます。
1885年に2万分の1で作成が開始された正式測図ですが、1890年には5万分の1が基本図になり、1924年に内地全域の測量が完成しました。
参謀本部陸地測量部の所管になった面積データの調製も、当然これに歩調を合わせて進められました。
[66993]で 大正元年(1912)の統計年鑑に掲載された国土面積表を引用しました。
リンクを開いた方はお気づきでしょうが、日本全体の「周囲及面積」に続いて「道府県面積」の表があります。
そして道府県面積データは、「周囲及面積」で説明された内務省地理局による面積と併記して、“参謀本部に於て調製したる面積”が記されています。
後者の説明文を読むと、明治31年に参謀本部で実測図と輯製20万分1図を本として調製したものを最初として、それ以後逐次実測結果を盛り込んでいったことがわかります。
大正10年(1921)12月刊行の「日本帝国第四十統計年鑑」になると、北海道・鹿児島・沖縄の3地域を除く全国測量ができあがり、府県別面積データは、ようやく伊能忠敬から脱却した参謀本部の値を単独で表示できる段階になりました。
そして、全国5万分1地形図完成後の大正15年(1926)に刊行された 第四十五回日本帝国統計年鑑 に至り、上記3地域の面積も参謀本部実測地に改められ、47道府県面積合計は 24718.849方里= 38万1250.45km2という値(大正14年10月1日現在)が得られました。
大正2年統計年鑑の値に比べて 1165km2の減少。道府県別に見ると数百km2以上の増減も数県あり、特に北海道面積の減少 5733km2が目立ちます。面積の測定はなかなか難しいようです。
この時代に 内務省地理局の仕事は、参謀本部陸地測量部に引き継がれ、全国測量と基本図の作成が行なわれ、その成果に基づいて道府県面積・市町村面積も求められました。
最初に 組織のこと。
近代国家の歩みを始めた明治政府には、測地・地図つくりの仕事をする部門が、前回記した内務省地理局のほかに、もう一つありました。
それは、軍事作戦を遂行する土地の情報を知る必要のある陸軍でした。
現実に西南戦争を経験し、その後も内乱の危険に直面していた陸軍が、短期間に作り上げた迅速測図[44237][65097]のことは、これまでに何回も話題にしました。人口がらみで話題になった共武政表や徴発物件表[63483]も、同じく作戦目的の資料でした。
民政と軍事作戦と目的は違うものの、地図作りに使う測地技術は共通です。
地理局と参謀本部は技術や成果を共有していたようですが、明治17年(1884)6月の太政官達により、測量事業は陸軍に一本化されることになりました[44653]。内務省所属大三角測量事務ヲ参謀本部ニ引渡
参謀本部測量局は 明治21年(1888)に陸地測量部になり、1945年まではこの組織による日本の地図作りが進められます。
1885年に2万分の1で作成が開始された正式測図ですが、1890年には5万分の1が基本図になり、1924年に内地全域の測量が完成しました。
参謀本部陸地測量部の所管になった面積データの調製も、当然これに歩調を合わせて進められました。
[66993]で 大正元年(1912)の統計年鑑に掲載された国土面積表を引用しました。
リンクを開いた方はお気づきでしょうが、日本全体の「周囲及面積」に続いて「道府県面積」の表があります。
そして道府県面積データは、「周囲及面積」で説明された内務省地理局による面積と併記して、“参謀本部に於て調製したる面積”が記されています。
後者の説明文を読むと、明治31年に参謀本部で実測図と輯製20万分1図を本として調製したものを最初として、それ以後逐次実測結果を盛り込んでいったことがわかります。
大正10年(1921)12月刊行の「日本帝国第四十統計年鑑」になると、北海道・鹿児島・沖縄の3地域を除く全国測量ができあがり、府県別面積データは、ようやく伊能忠敬から脱却した参謀本部の値を単独で表示できる段階になりました。
そして、全国5万分1地形図完成後の大正15年(1926)に刊行された 第四十五回日本帝国統計年鑑 に至り、上記3地域の面積も参謀本部実測地に改められ、47道府県面積合計は 24718.849方里= 38万1250.45km2という値(大正14年10月1日現在)が得られました。
大正2年統計年鑑の値に比べて 1165km2の減少。道府県別に見ると数百km2以上の増減も数県あり、特に北海道面積の減少 5733km2が目立ちます。面積の測定はなかなか難しいようです。
| [67057] 2008年 10月 18日(土)21:28:48 | hmt さん |
| 国土面積統計の変遷(4) 道府県面積など | |
明治15年(1882)の第一統計年鑑には「面積国別」はあっても、府県別面積がなかったのですが、その翌年の「第二統計年鑑」になると、「府県及開拓使 郡区町村(数) 並 面積」(明治14年12月調)が掲載されています([66996] YTさん)。
東京府から沖縄県までの3府38県に続いて開拓使札幌本庁・函館支庁・根室支庁まで総計 37区 796郡 11870町 58260村で、総面積 24794.51方里。
この総面積は、当然のことながら[66996]掲載と同じ形式の「周囲及面積」の表の総計面積と一致します。
[66998] YT さんで
それにしても属島の数が[66993]と[66996]でなんでこんなに違うんでしょう?
と指摘された件に関連し、この第二統計年鑑の「周囲及面積」表を見ると、属島の数を含めて大正元年年鑑[66993]の値とほぼ一致しています(千島・小笠原と北海道属島の面積は[66996]の値)。
ついでに、大正時代の統計年鑑の府県別面積に使われた府県の順番を記しておきます。
大正元年(1912)と2年に使われた順番は、5区 + 沖縄県・北海道。
本州中区(東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 長野 山梨 静岡 愛知 三重 岐阜 滋賀 福井 石川 富山)
本州北区(新潟 福島 宮城 山形 秋田 岩手 青森)
本州西区(京都 大阪 奈良 和歌山 兵庫 岡山 広島 山口 島根 鳥取)
四国区(徳島 香川 愛媛 高知)
九州区(長崎 佐賀 福岡 熊本 大分 宮崎 鹿児島)
沖縄県 北海道
大正3年から、第1回国勢調査が行なわれた大正9年(1920)までの統計年鑑では、北海道 + 9区 + 沖縄県という北から南への区分による配列が使われました。
北海道
東北区(青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島)
関東区(茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川)
北陸区(新潟 富山 石川 福井)
東山区(長野 岐阜 滋賀)
東海区(山梨 静岡 愛知 三重)
近畿区(京都 兵庫 大阪 奈良 和歌山)
中国区(鳥取 島根 岡山 広島 山口)
四国区(徳島 香川 愛媛 高知)
九州区(大分 福岡 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島)
沖縄県
現在の都道府県コード順に近いものになっていますが、東山区・東海区は現在の配列と異なります。
近畿区では、大阪府と兵庫県とが逆転。兵庫県の方が大阪府よりも北にあるから?
九州区は、四国区に最も近い大分県から始まっており、これも現在と相違。
[34038] Issie さん
現在「公共団体コード」で行われている都道府県の配列は,少なくとも1920年の第1回国勢調査以来,その報告書で用いられているものです。
国勢調査報告書を機会に、上記の区分を「8地方区分」ごとに修正して、現在の順番になったのでしょうか。
なお、統計年鑑における面積データの配列は、大正10年(1921)刊行のものから面積順に変っています。
それはさておき
第32~第35統計年鑑(大正2~5年)には「郡面積」の表があります。
当然、「市面積」も欲しいところですが、
市は本調査以後其の境域に変更あるのみならず其の後新設の市も亦少なからずして共に前述の事情に依り其の面積を知り難きにより市の面積は総て之を省略せり
と、お手上げ気味です(大正5年統計年鑑)。
それでも、陸地測量部は 5万分1地形図に基づいて測定したデータを、「昭和10年全国市町村別面積調」として発表。
これが、“20世紀前半以前における唯一の市町村面積に関する資料”とのことです(統計局HPの 資料解説 による)。
東京府から沖縄県までの3府38県に続いて開拓使札幌本庁・函館支庁・根室支庁まで総計 37区 796郡 11870町 58260村で、総面積 24794.51方里。
この総面積は、当然のことながら[66996]掲載と同じ形式の「周囲及面積」の表の総計面積と一致します。
[66998] YT さんで
それにしても属島の数が[66993]と[66996]でなんでこんなに違うんでしょう?
と指摘された件に関連し、この第二統計年鑑の「周囲及面積」表を見ると、属島の数を含めて大正元年年鑑[66993]の値とほぼ一致しています(千島・小笠原と北海道属島の面積は[66996]の値)。
ついでに、大正時代の統計年鑑の府県別面積に使われた府県の順番を記しておきます。
大正元年(1912)と2年に使われた順番は、5区 + 沖縄県・北海道。
本州中区(東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 栃木 群馬 長野 山梨 静岡 愛知 三重 岐阜 滋賀 福井 石川 富山)
本州北区(新潟 福島 宮城 山形 秋田 岩手 青森)
本州西区(京都 大阪 奈良 和歌山 兵庫 岡山 広島 山口 島根 鳥取)
四国区(徳島 香川 愛媛 高知)
九州区(長崎 佐賀 福岡 熊本 大分 宮崎 鹿児島)
沖縄県 北海道
大正3年から、第1回国勢調査が行なわれた大正9年(1920)までの統計年鑑では、北海道 + 9区 + 沖縄県という北から南への区分による配列が使われました。
北海道
東北区(青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島)
関東区(茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川)
北陸区(新潟 富山 石川 福井)
東山区(長野 岐阜 滋賀)
東海区(山梨 静岡 愛知 三重)
近畿区(京都 兵庫 大阪 奈良 和歌山)
中国区(鳥取 島根 岡山 広島 山口)
四国区(徳島 香川 愛媛 高知)
九州区(大分 福岡 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島)
沖縄県
現在の都道府県コード順に近いものになっていますが、東山区・東海区は現在の配列と異なります。
近畿区では、大阪府と兵庫県とが逆転。兵庫県の方が大阪府よりも北にあるから?
九州区は、四国区に最も近い大分県から始まっており、これも現在と相違。
[34038] Issie さん
現在「公共団体コード」で行われている都道府県の配列は,少なくとも1920年の第1回国勢調査以来,その報告書で用いられているものです。
国勢調査報告書を機会に、上記の区分を「8地方区分」ごとに修正して、現在の順番になったのでしょうか。
なお、統計年鑑における面積データの配列は、大正10年(1921)刊行のものから面積順に変っています。
それはさておき
第32~第35統計年鑑(大正2~5年)には「郡面積」の表があります。
当然、「市面積」も欲しいところですが、
市は本調査以後其の境域に変更あるのみならず其の後新設の市も亦少なからずして共に前述の事情に依り其の面積を知り難きにより市の面積は総て之を省略せり
と、お手上げ気味です(大正5年統計年鑑)。
それでも、陸地測量部は 5万分1地形図に基づいて測定したデータを、「昭和10年全国市町村別面積調」として発表。
これが、“20世紀前半以前における唯一の市町村面積に関する資料”とのことです(統計局HPの 資料解説 による)。
| [67072] 2008年 10月 20日(月)19:37:32 | hmt さん |
| 国土面積統計の変遷(5) 昭和24年に復刊した日本統計年鑑 そのデータはまだ戦前 | |
明治15年に始まった「日本帝国統計年鑑」は、大東亜戦争中に第59回で中断しました。
総理庁統計局により復刊したのは、OCCUPIED JAPAN時代の昭和24年(1949)です。
再出発した第1回「日本統計年鑑」ですが、「周囲及面積」は(昭和15年)とあるように、まだ戦前のデータを使って編修したものです。[66993] [66996]と同様に、面積の部分を引用。
--------------------------------------------------------------------------------------
参謀本部陸地測量部の5万分の1の地形図上における昭和15年1月26日の調査を基礎として算出した。陸地の外満干両潮界間の面積1/2及び湖水・潟湖の面積も含む。…
註A)次の未確定地域(11719.1)を含む。(面積 方粁)【簡略化した地名で記載し、面積省略】
a)国後郡……占守郡(千島)と歯舞諸島 b)竹島 c)鹿児島県大島郡
--------------------------------------------------------------------------------------
この昭和24年日本統計年鑑に記載された北海道の面積 7万8561km2 については疑問があります。
上記の数値は、昭和10年統計年鑑の8万8775 km2から1万0214 km2少なくなっています。
これは北海道のうち、敗戦によって施政権を失った地域の面積約10300 km2とほぼ対応しています。
その地域とは、まさに上記の註A)a)に記された“未確定地域”である、国後、色丹、紗那、択捉、蕊取、得撫、新知、占守の8郡と歯舞諸島なのですが、註には“次の未確定地域を含む”と記されています。これはおかしい。
参考までに、上記地域を面積と共に列挙しておきます。
「歯舞群島」は、根室半島の先端部にあった根室国花咲郡歯舞村(現・根室市)の飛び地。主な島は5つあり、合計面積は旧歯舞村の面積165 km2のうち100km2を占めます。
従来は「歯舞諸島」の名が知られていましたが、今年の3月から「歯舞群島」を公式名とすることになりました。発表
…と、島群コレクションのコメントを入れようかと思いましたが、集録対象外でした。
色丹島は、元は同じく根室国花咲郡に属していましたが、明治19年に千島国に所属変更。[66996]で千島三十島となっていたのが、[66993]になると千島31島になっていたのは、このためでした。
その「千島国」は、明治2年 に国後・択捉・振別(1923年択捉郡に編入)・紗那・蕊取の5郡で設置。
北海道の未確定地域の途中ですが、長くなったので記事を分けます。
総理庁統計局により復刊したのは、OCCUPIED JAPAN時代の昭和24年(1949)です。
再出発した第1回「日本統計年鑑」ですが、「周囲及面積」は(昭和15年)とあるように、まだ戦前のデータを使って編修したものです。[66993] [66996]と同様に、面積の部分を引用。
--------------------------------------------------------------------------------------
参謀本部陸地測量部の5万分の1の地形図上における昭和15年1月26日の調査を基礎として算出した。陸地の外満干両潮界間の面積1/2及び湖水・潟湖の面積も含む。…
| 地名 | 属島数 | 面積(方粁) | 千分比 |
| 全国 | 3340 | 369859.51 | 1000.00 |
| 北海道 | 86 | 78561.27 | 212.41 |
| 本州 | 1364 | 230448.30 | 623.07 |
| 四国 | 471 | 18771.45 | 50.75 |
| 九州 | 1419 | 42078.49 | 113.77 |
a)国後郡……占守郡(千島)と歯舞諸島 b)竹島 c)鹿児島県大島郡
--------------------------------------------------------------------------------------
この昭和24年日本統計年鑑に記載された北海道の面積 7万8561km2 については疑問があります。
上記の数値は、昭和10年統計年鑑の8万8775 km2から1万0214 km2少なくなっています。
これは北海道のうち、敗戦によって施政権を失った地域の面積約10300 km2とほぼ対応しています。
その地域とは、まさに上記の註A)a)に記された“未確定地域”である、国後、色丹、紗那、択捉、蕊取、得撫、新知、占守の8郡と歯舞諸島なのですが、註には“次の未確定地域を含む”と記されています。これはおかしい。
参考までに、上記地域を面積と共に列挙しておきます。
| 島名 | 郡 | 村 | 1935面積 | 1992面積 |
| 歯舞群島 | 花咲郡 | 歯舞村 | 101.60 | 99.94 |
| 色丹島 | 色丹郡 | 色丹村 | 255.12 | 253.33 |
| 国後島 | 国後郡 | 泊村・留夜別村 | 1500.04 | 1498.83 |
| 択捉島 | 3139.00 | 3184.04 | ||
| 紗那郡 | 紗那村 | 959.5 | ||
| 択捉郡 | 留別村 | 1429.7 | ||
| 蕊取郡 | 蕊取村 | 749.7 | ||
| 北方四島合計 | 4995.76 | 5036.14 |
「歯舞群島」は、根室半島の先端部にあった根室国花咲郡歯舞村(現・根室市)の飛び地。主な島は5つあり、合計面積は旧歯舞村の面積165 km2のうち100km2を占めます。
従来は「歯舞諸島」の名が知られていましたが、今年の3月から「歯舞群島」を公式名とすることになりました。発表
…と、島群コレクションのコメントを入れようかと思いましたが、集録対象外でした。
色丹島は、元は同じく根室国花咲郡に属していましたが、明治19年に千島国に所属変更。[66996]で千島三十島となっていたのが、[66993]になると千島31島になっていたのは、このためでした。
その「千島国」は、明治2年 に国後・択捉・振別(1923年択捉郡に編入)・紗那・蕊取の5郡で設置。
北海道の未確定地域の途中ですが、長くなったので記事を分けます。
| [67073] 2008年 10月 20日(月)19:50:52 | hmt さん |
| 国土面積統計の変遷(6) 昭和24年に復刊した日本統計年鑑 戦争で失った地域 | |
(承前)
昭和24年当時、北海道の「未確定地域」には、更に以下の3郡がありました。
これは、明治8年の千島樺太両島交換条約によって得た地域で、条約 には「千島群島 クリールアイランズ」と書いてあります。
そして、翌明治9年 千島国に編入 されています。
開拓使管下クリル諸島自今千島国に併せ得撫新知占守の三郡を被置候條此旨布告候事
ところで、日本統計年鑑が復刊した昭和24年から3年後の1952年、サンフランシスコ平和条約第2条で、日本は「千島列島」の領有権を放棄しました。
この「千島列島」は、「千島国」や「千島31島」全体ではなく、明治8年に得た「クリル諸島」、つまり“得撫・新知・占守の三郡”を指すものと解釈されています。
北方領土のことはこのくらいにして、
昭和24年の国土面積 36万9860 km2は、戦前の昭和10年の値に比べて 1万2686 km2減少しています。
最も大口の減少は上記の北海道 1万0214 km2ですが、それに次ぐものは、面積リストから県の名ごと丸々消えてしまった沖縄県で 2386km2。そして小笠原諸島を失った東京都の 103 m2減少。
昭和24年というと、1953年のクリスマスプレゼントだった奄美復帰より前(更に言えばトカラ復帰1952よりも前)ですから、鹿児島県大島郡にはごく一部(上三島)を除いて日本の施政権が及んでいませんでした。しかし、昭和24年統計年鑑註A)c)に記されているように、鹿児島県大島郡(1289km2)は、上記の国土面積に含まれています。この取扱はちょっと不統一。
日本統計年鑑昭和24年版を出典とする都道府県別面積は、帝国書院「中学校社会科地図帳」1950年版[25914] にも出ていました。この地図帳では、沖縄・小笠原・奄美の範囲をカバーする地図はなく、完全に無視。北海道を見ると、真っ白なクナシリと水晶島の手前に国境線。
日本統計年鑑昭和24年版の「周囲及面積」には、「旧領土及未確定地域」もありました。参考までに、その面積(昭和13年末調)を掲げます。
合計 305,546.27(km2)
千島 10,213.77
樺太 36,090.30
小笠原 102.94
朝鮮 220,791.81
琉球 2,386.24
台湾本島 35,834.35
澎湖島 126.86
関東州 3,462.45
南洋群島 2,148.80
昭和24年当時、北海道の「未確定地域」には、更に以下の3郡がありました。
| 得撫島など | 得撫郡 | 1468.6 | |
| 新知島など | 新知郡 | 540.7 | |
| 占守島など | 占守郡 | 3310.1 | |
| 千島列島合計 | 5319.6 |
これは、明治8年の千島樺太両島交換条約によって得た地域で、条約 には「千島群島 クリールアイランズ」と書いてあります。
そして、翌明治9年 千島国に編入 されています。
開拓使管下クリル諸島自今千島国に併せ得撫新知占守の三郡を被置候條此旨布告候事
ところで、日本統計年鑑が復刊した昭和24年から3年後の1952年、サンフランシスコ平和条約第2条で、日本は「千島列島」の領有権を放棄しました。
この「千島列島」は、「千島国」や「千島31島」全体ではなく、明治8年に得た「クリル諸島」、つまり“得撫・新知・占守の三郡”を指すものと解釈されています。
北方領土のことはこのくらいにして、
昭和24年の国土面積 36万9860 km2は、戦前の昭和10年の値に比べて 1万2686 km2減少しています。
最も大口の減少は上記の北海道 1万0214 km2ですが、それに次ぐものは、面積リストから県の名ごと丸々消えてしまった沖縄県で 2386km2。そして小笠原諸島を失った東京都の 103 m2減少。
昭和24年というと、1953年のクリスマスプレゼントだった奄美復帰より前(更に言えばトカラ復帰1952よりも前)ですから、鹿児島県大島郡にはごく一部(上三島)を除いて日本の施政権が及んでいませんでした。しかし、昭和24年統計年鑑註A)c)に記されているように、鹿児島県大島郡(1289km2)は、上記の国土面積に含まれています。この取扱はちょっと不統一。
日本統計年鑑昭和24年版を出典とする都道府県別面積は、帝国書院「中学校社会科地図帳」1950年版[25914] にも出ていました。この地図帳では、沖縄・小笠原・奄美の範囲をカバーする地図はなく、完全に無視。北海道を見ると、真っ白なクナシリと水晶島の手前に国境線。
日本統計年鑑昭和24年版の「周囲及面積」には、「旧領土及未確定地域」もありました。参考までに、その面積(昭和13年末調)を掲げます。
合計 305,546.27(km2)
千島 10,213.77
樺太 36,090.30
小笠原 102.94
朝鮮 220,791.81
琉球 2,386.24
台湾本島 35,834.35
澎湖島 126.86
関東州 3,462.45
南洋群島 2,148.80
… スポンサーリンク …