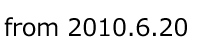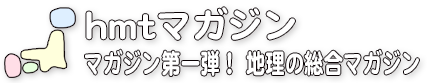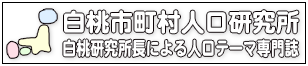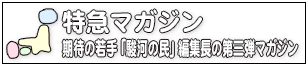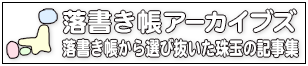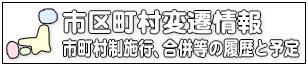幕末期の江戸・四谷にあった 美濃国高須藩江戸屋敷 で育った4人の兄弟を主人公として、約150年前、彼らが生きた激動の政権交代時代を描いてみました。
高須というのは、木曽川・長良川・揖斐川(木曽三川)が作り出した沖積地(濃尾平野)の地名で、美濃国下石津郡に高須町がありました。岐阜県海津郡を経て、現在は海津市になっています。
高須藩は石高3万石の小大名でしたが、徳川御三家・尾張藩62万石の後継者確保の役割を負っており、徳川慶勝(と茂栄)は本家を継ぐことになりました。明治維新に際して、慶勝は新政府側として働きました。
弟の松平容保は 同じく親藩の会津藩28万石を継ぎ、幕末の京都守護の大役を果たしたものの、戊辰戦争では朝敵にされてしまいました。
更に下の弟・松平定敬も譜代大名の桑名藩を継ぎ、19歳で京都所司代。平和な時代ならば老中への出世コースでしょうが、時代は試練を与えます。彼は戊辰戦争で降伏を決めた桑名藩と別行動を取り、北越で抗戦した後、箱館・上海へ。
4兄弟の置かれた政治環境に大きな影響を及ぼしたのが、母方の従兄弟という関係にある一橋慶喜です。
慶喜が15代将軍に就任した結果、尾張藩主を引退していた茂栄は、慶勝の計らいで御三卿・一橋家の家督を継ぐことになり、徳川家の代表として戊辰戦争後始末の任に当たりました。
明治10年西南戦争で定敬の長い戦いもやっと終り、翌明治11年には4兄弟の再会が実現しました。
銀座の写真館での記念撮影[86738]を経て、本所横網町の慶勝邸での会食ということになりました。
高須というのは、木曽川・長良川・揖斐川(木曽三川)が作り出した沖積地(濃尾平野)の地名で、美濃国下石津郡に高須町がありました。岐阜県海津郡を経て、現在は海津市になっています。
高須藩は石高3万石の小大名でしたが、徳川御三家・尾張藩62万石の後継者確保の役割を負っており、徳川慶勝(と茂栄)は本家を継ぐことになりました。明治維新に際して、慶勝は新政府側として働きました。
弟の松平容保は 同じく親藩の会津藩28万石を継ぎ、幕末の京都守護の大役を果たしたものの、戊辰戦争では朝敵にされてしまいました。
更に下の弟・松平定敬も譜代大名の桑名藩を継ぎ、19歳で京都所司代。平和な時代ならば老中への出世コースでしょうが、時代は試練を与えます。彼は戊辰戦争で降伏を決めた桑名藩と別行動を取り、北越で抗戦した後、箱館・上海へ。
4兄弟の置かれた政治環境に大きな影響を及ぼしたのが、母方の従兄弟という関係にある一橋慶喜です。
慶喜が15代将軍に就任した結果、尾張藩主を引退していた茂栄は、慶勝の計らいで御三卿・一橋家の家督を継ぐことになり、徳川家の代表として戊辰戦争後始末の任に当たりました。
明治10年西南戦争で定敬の長い戦いもやっと終り、翌明治11年には4兄弟の再会が実現しました。
銀座の写真館での記念撮影[86738]を経て、本所横網町の慶勝邸での会食ということになりました。
| [86697] 2014年 11月 19日(水)19:45:33 | hmt さん |
| 津の守坂 (1)美濃高須藩 | |
丸ノ内線が通る新宿通を四谷三丁目から少し東に進むと「津の守坂入口」という交差点があります。
北の合羽坂下に向う道が途中から下り坂になり、その西側が 松平摂津守の上屋敷跡 であったことに由来する地名です。
その地点から一つ東側の通りにある新宿歴史博物館で開催中の特別展 高須四兄弟 新宿荒木町に生れた幕末維新 を先週見てきました。
高須四兄弟については、hmtマガジン 「府県」の誕生から廃藩置県まで に収録した 記事 の中で、次のように紹介しています。
余談ですが、3万石の小藩ながら、高須松平家出身の4兄弟は 幕末の歴史を彩りました。尾張藩主になった徳川慶勝は、議定として慶応3年師走の小御所会議[75495]に出席し、翌年正月には、徳川慶喜逃亡後の大阪城[43497]を新政府代表として受け取りました。それより前、慶応2年末に徳川慶喜の徳川宗家相続に伴い、一橋家を継いだのが 弟の徳川茂徳です。更に下の弟の 会津藩主・松平容保と 桑名藩主・松平定敬とは 幕末京都で治安維持の役目を担い、戊辰戦争の 朝敵 にされてしまいました。戦後、慶勝と茂徳とは、容保と定敬の助命に奔走し、明治11年に4兄弟は再会を果たしたそうです。
「津の守」と呼ばれた大名の家に生まれ、それぞれ別の大名の家督を継ぎながら幕末の動乱期を生きぬいた兄弟。
落書き帳の過去記事と関連させながら、関係する地名を交えながらこの記事を書いてみます。
松平摂津守、末尾を取れば「津の守」ですが、何故に摂津の略称が「津」なのか? Issieさんの解説[21549]をご覧ください。
もちろん江戸時代の難波の津は大坂奉行管轄下の幕府直轄領であり摂津守の領地ではありません。参考[72856]
では松平摂津守とは いかなる大名で、領地はどこだったのか?
徳川家康が天下を取った後で、この国の支配権を自分の子孫に確実に伝える仕組みの一つとして、後継者の予備軍である御三家の制度を作ったことはよく知られています。徳川御三家の筆頭が尾張家ですが、尾張家としてもその役目を確実に果すためには血統を伝える分家が必要になります。このようにして尾張家にも3つの分家が作られました。それぞれの江戸屋敷の所在地【いずれも現在の新宿区内】から、四谷家・大久保家・川田久保家と呼ばれましたが2家はスペアの役割を果して消滅し、幕末期に尾張本家以外に残っていたのは四谷家だけです。
この四谷家の当主には 松平摂津守として信濃国に3万石を与えられ、元禄13年(1700)に 本拠が美濃国高須に移されました。
「高須」は岐阜県海津市役所の所在地で、約60年前の昭和合併で海津町になる前は海津郡高須町でした。
# 播磨坂に名を残す松平播磨守は水戸藩の分家で常陸府中(石岡)2万石の殿様とか[72799]。
展覧会の主役は江戸四谷にあった高須藩江戸上屋敷とその地で育った4兄弟であり、美濃高須藩の所領には殆ど触れられていなかったのですが、折角の機会なので美濃国の南端である高須輪中について少し記しておきます。
高須という地名は、横須賀関連で話題にした 須賀地名 の仲間で、河岸や海岸に土砂が堆積して形成された微高地に由来します。
木曽三川が作った濃尾平野に住みついた人々は、毎年のように繰り返される洪水被害に遭いながらも、自然堤防や人工堤防を利用して水利用を進めてきました。鎌倉時代中期の文献に高洲阿弥陀寺などの記錄があります。
現在高洲輪中の中央を流れている大江川は 木曽川・長良川の旧河道でしたが、天正14年(1586)の大洪水の結果、ほぼ現在に近い東寄りの流路に変ったとのことです。
江戸時代になると、名古屋を居城とする尾張徳川家の御囲堤が慶長14年(1609)に完成。これにより尾張側は保護されたものの 美濃側の洪水は一層深刻な状態になり、水害対策に財政破綻した小笠原氏は転封を願い出る事態になりました。
木曽三川については、木曽川下流河川事務所が発行している『KISSO』という刊行物があり、1991年の創刊号から最新号(92号)まで閲覧することができます。バックナンバーリスト
歴史ドキュメントや歴史記録の長期連載もあり、読み応えのある資料ですが、その56号p.10を見ると、60余万石の美濃国のうち約20万石が幕府直轄領、約15万石が尾張藩領で、残る約25万石が大垣藩・高須藩など10藩の大名領と70余の旗本領とに細分され、錯綜状態であったと記されています。高須藩領は図示された海津町域に限っても34%に過ぎません。
美濃高須藩は3万石の小藩であり、木曽川の治水を自力で遂行できる財力も、複雑な利害関係をまとめる力もなく、幕府の力に頼らざるを得ません。
幸いなことに 幕府領になったこの地に美濃郡代として着任したが、見沼代用水[67644]でも登場した 井沢弥惣兵衛為永でした。彼は 将軍吉宗の命を受けて、享保20年(1735)笠松陣屋着任後の短期間に綿密な現地調査に基づく三川分流計画を立案しました。
この建言は為永の在世中直ちに実施されるには至りませんでしたが、1747年には奥州二本松藩による第1回の木曽川改修御手伝普請が実施されました。
二本松藩は多数の藩士を現地に派遣したものの、既に幕府により請負業者が配置されており、工事期間2ヶ月。
第2回の御手伝普請が薩摩藩による有名な 宝暦治水工事(1754-1755)です。
この時は地元農民を雇用して施工する「村方請負」が指定されました。
薩摩藩は難工事箇所を町方請負とするよう請願したが数箇所しか認められず、派遣された薩摩藩士947名、現地雇用を含めて2千人とも伝えられる大工事になりました。工事期間は2期にわたり 1年3ヶ月(実質10ヶ月)。
1766年の第3回(萩藩・岩国藩・若狭藩)工事では過酷だった宝暦の事例を踏まえた反省から、町方請負や幕府が施工する「お金御手伝」が取り入れられ、更に第4回から第16回まで続いた御手伝普請は、藩が直接施工せず費用負担だけを求めれれる方向に変質して行ったとのことです。16回の普請で御手伝(1~4回)を求められた藩の合計は48藩。
資料をリンクしておきますが、細かい字で判読困難な部分があります。56号 p.10-12, 57号 p.9-14
対象が本題の高須藩から少し拡大してしまいましたが、高須輪中付近の江戸時代の治水事業について記しました。
江戸時代の藩は独立国のように扱われる一面がある反面、美濃のような複雑な地を水害から守るためには、幕府の権威による「御手伝普請」という強制的な経済協力制度も必要でした。
江戸時代初期、金鯱の名古屋城造営の時とは制度が変っていますが、豊かな田園に恵まれることになった美濃高須藩の姿を見ると、親藩大名を優遇する政策という点では類似するように思いました。
美濃高須藩より後の時代になりますが、明治以降も国営の治水工事が引き続き実施されました。
この木曽川改修工事の時期は、1889年に全国で実施された 町村制施行と重なっていました。
これが、他の府県で行なわれた「明治大合併」を 岐阜県では同時に実施できなかった一因であろうと思われます[79347]。
更に濃尾地震・日清戦争もあり、とうとう明治30年の「郡と町村とをひっくるめた再編成」[70814][70820]にずれ込みました。
岐阜県には、この明治30年再編成で、海西郡と下石津郡に由来する新郡名として「海津」 が誕生しました。
この地名は 昭和大合併での海津町に引き継がれました。
海津町誕生当時の「高須輪中」は、東の木曽川・長良川と西の揖斐川とに挟まれた“陸の孤島”に近い状態でした。
しかし、1980年以降に木曽三川の長大橋が相次いで開通し、この豊かな穀倉地帯は陸上交通も便利になりました。
鉄道は通っておらず、私には行けない場所だったのですが、2年前岐阜オフ会の翌日に EMM号に同乗する機会を得て、この地域を訪問することができました[82265]。
平成大合併で市になる際に、一旦は「ひらなみ市」[9775]が選定されました。
落書き帳でも賛否両論ありましたが、結局は海津市に落ち着いた[28842]ことは、みなさんの記憶する通りです。
北の合羽坂下に向う道が途中から下り坂になり、その西側が 松平摂津守の上屋敷跡 であったことに由来する地名です。
その地点から一つ東側の通りにある新宿歴史博物館で開催中の特別展 高須四兄弟 新宿荒木町に生れた幕末維新 を先週見てきました。
高須四兄弟については、hmtマガジン 「府県」の誕生から廃藩置県まで に収録した 記事 の中で、次のように紹介しています。
余談ですが、3万石の小藩ながら、高須松平家出身の4兄弟は 幕末の歴史を彩りました。尾張藩主になった徳川慶勝は、議定として慶応3年師走の小御所会議[75495]に出席し、翌年正月には、徳川慶喜逃亡後の大阪城[43497]を新政府代表として受け取りました。それより前、慶応2年末に徳川慶喜の徳川宗家相続に伴い、一橋家を継いだのが 弟の徳川茂徳です。更に下の弟の 会津藩主・松平容保と 桑名藩主・松平定敬とは 幕末京都で治安維持の役目を担い、戊辰戦争の 朝敵 にされてしまいました。戦後、慶勝と茂徳とは、容保と定敬の助命に奔走し、明治11年に4兄弟は再会を果たしたそうです。
「津の守」と呼ばれた大名の家に生まれ、それぞれ別の大名の家督を継ぎながら幕末の動乱期を生きぬいた兄弟。
落書き帳の過去記事と関連させながら、関係する地名を交えながらこの記事を書いてみます。
松平摂津守、末尾を取れば「津の守」ですが、何故に摂津の略称が「津」なのか? Issieさんの解説[21549]をご覧ください。
もちろん江戸時代の難波の津は大坂奉行管轄下の幕府直轄領であり摂津守の領地ではありません。参考[72856]
では松平摂津守とは いかなる大名で、領地はどこだったのか?
徳川家康が天下を取った後で、この国の支配権を自分の子孫に確実に伝える仕組みの一つとして、後継者の予備軍である御三家の制度を作ったことはよく知られています。徳川御三家の筆頭が尾張家ですが、尾張家としてもその役目を確実に果すためには血統を伝える分家が必要になります。このようにして尾張家にも3つの分家が作られました。それぞれの江戸屋敷の所在地【いずれも現在の新宿区内】から、四谷家・大久保家・川田久保家と呼ばれましたが2家はスペアの役割を果して消滅し、幕末期に尾張本家以外に残っていたのは四谷家だけです。
この四谷家の当主には 松平摂津守として信濃国に3万石を与えられ、元禄13年(1700)に 本拠が美濃国高須に移されました。
「高須」は岐阜県海津市役所の所在地で、約60年前の昭和合併で海津町になる前は海津郡高須町でした。
# 播磨坂に名を残す松平播磨守は水戸藩の分家で常陸府中(石岡)2万石の殿様とか[72799]。
展覧会の主役は江戸四谷にあった高須藩江戸上屋敷とその地で育った4兄弟であり、美濃高須藩の所領には殆ど触れられていなかったのですが、折角の機会なので美濃国の南端である高須輪中について少し記しておきます。
高須という地名は、横須賀関連で話題にした 須賀地名 の仲間で、河岸や海岸に土砂が堆積して形成された微高地に由来します。
木曽三川が作った濃尾平野に住みついた人々は、毎年のように繰り返される洪水被害に遭いながらも、自然堤防や人工堤防を利用して水利用を進めてきました。鎌倉時代中期の文献に高洲阿弥陀寺などの記錄があります。
現在高洲輪中の中央を流れている大江川は 木曽川・長良川の旧河道でしたが、天正14年(1586)の大洪水の結果、ほぼ現在に近い東寄りの流路に変ったとのことです。
江戸時代になると、名古屋を居城とする尾張徳川家の御囲堤が慶長14年(1609)に完成。これにより尾張側は保護されたものの 美濃側の洪水は一層深刻な状態になり、水害対策に財政破綻した小笠原氏は転封を願い出る事態になりました。
木曽三川については、木曽川下流河川事務所が発行している『KISSO』という刊行物があり、1991年の創刊号から最新号(92号)まで閲覧することができます。バックナンバーリスト
歴史ドキュメントや歴史記録の長期連載もあり、読み応えのある資料ですが、その56号p.10を見ると、60余万石の美濃国のうち約20万石が幕府直轄領、約15万石が尾張藩領で、残る約25万石が大垣藩・高須藩など10藩の大名領と70余の旗本領とに細分され、錯綜状態であったと記されています。高須藩領は図示された海津町域に限っても34%に過ぎません。
美濃高須藩は3万石の小藩であり、木曽川の治水を自力で遂行できる財力も、複雑な利害関係をまとめる力もなく、幕府の力に頼らざるを得ません。
幸いなことに 幕府領になったこの地に美濃郡代として着任したが、見沼代用水[67644]でも登場した 井沢弥惣兵衛為永でした。彼は 将軍吉宗の命を受けて、享保20年(1735)笠松陣屋着任後の短期間に綿密な現地調査に基づく三川分流計画を立案しました。
この建言は為永の在世中直ちに実施されるには至りませんでしたが、1747年には奥州二本松藩による第1回の木曽川改修御手伝普請が実施されました。
二本松藩は多数の藩士を現地に派遣したものの、既に幕府により請負業者が配置されており、工事期間2ヶ月。
第2回の御手伝普請が薩摩藩による有名な 宝暦治水工事(1754-1755)です。
この時は地元農民を雇用して施工する「村方請負」が指定されました。
薩摩藩は難工事箇所を町方請負とするよう請願したが数箇所しか認められず、派遣された薩摩藩士947名、現地雇用を含めて2千人とも伝えられる大工事になりました。工事期間は2期にわたり 1年3ヶ月(実質10ヶ月)。
1766年の第3回(萩藩・岩国藩・若狭藩)工事では過酷だった宝暦の事例を踏まえた反省から、町方請負や幕府が施工する「お金御手伝」が取り入れられ、更に第4回から第16回まで続いた御手伝普請は、藩が直接施工せず費用負担だけを求めれれる方向に変質して行ったとのことです。16回の普請で御手伝(1~4回)を求められた藩の合計は48藩。
資料をリンクしておきますが、細かい字で判読困難な部分があります。56号 p.10-12, 57号 p.9-14
対象が本題の高須藩から少し拡大してしまいましたが、高須輪中付近の江戸時代の治水事業について記しました。
江戸時代の藩は独立国のように扱われる一面がある反面、美濃のような複雑な地を水害から守るためには、幕府の権威による「御手伝普請」という強制的な経済協力制度も必要でした。
江戸時代初期、金鯱の名古屋城造営の時とは制度が変っていますが、豊かな田園に恵まれることになった美濃高須藩の姿を見ると、親藩大名を優遇する政策という点では類似するように思いました。
美濃高須藩より後の時代になりますが、明治以降も国営の治水工事が引き続き実施されました。
この木曽川改修工事の時期は、1889年に全国で実施された 町村制施行と重なっていました。
これが、他の府県で行なわれた「明治大合併」を 岐阜県では同時に実施できなかった一因であろうと思われます[79347]。
更に濃尾地震・日清戦争もあり、とうとう明治30年の「郡と町村とをひっくるめた再編成」[70814][70820]にずれ込みました。
岐阜県には、この明治30年再編成で、海西郡と下石津郡に由来する新郡名として「海津」 が誕生しました。
この地名は 昭和大合併での海津町に引き継がれました。
海津町誕生当時の「高須輪中」は、東の木曽川・長良川と西の揖斐川とに挟まれた“陸の孤島”に近い状態でした。
しかし、1980年以降に木曽三川の長大橋が相次いで開通し、この豊かな穀倉地帯は陸上交通も便利になりました。
鉄道は通っておらず、私には行けない場所だったのですが、2年前岐阜オフ会の翌日に EMM号に同乗する機会を得て、この地域を訪問することができました[82265]。
平成大合併で市になる際に、一旦は「ひらなみ市」[9775]が選定されました。
落書き帳でも賛否両論ありましたが、結局は海津市に落ち着いた[28842]ことは、みなさんの記憶する通りです。
| [86719] 2014年 11月 23日(日)22:45:16【2】 | hmt さん |
| 津の守坂 (2)屋敷があった荒木町、4兄弟長兄の徳川慶勝 | |
今回のシリーズ。そのタイトル・津の守坂(つのかみざか)は、現在の新宿区荒木町にあります。
執筆の動機は、江戸時代 この地に上屋敷を構えていた尾張徳川家の分家・松平摂津守家(四谷家=高須松平家)とその屋敷に生れた四兄弟をテーマにした特別展でした。しかし、前回[86697]は 所領であった美濃高須や、木曽三川の治水工事に筆を費やし、特別展で紹介された江戸屋敷や人物について語るには至りませんでした。
高須松平家。それは治水の面で幕府から多大の支援を得ていただけでなく、「江戸定府」で参勤交代の義務を免れていた特殊な大名でした。
江戸で育って一生を江戸で暮す定めですから、美濃でなく江戸こそが「津の守」兄弟のふるさとなのでした。
江戸の武家地には町名がないので、荒木町という地名が現れるのは明治の地図です。
『明治十一年実測東亰全図』[78145]を見ると、陸軍士官学校になった尾張徳川家の上屋敷跡【市ヶ谷台】の南西に 四ツ谷荒木町の文字と高須藩上屋敷庭園跡の泉水が見えます。
市民に開放された庭園は新しい木【アラキ】で整備され、明治時代 この付近は芝居小屋・料理屋・芸者屋のある盛り場になったようです。「策(むち)の池」の一部と津の守弁天の祠は現存。
なお、現在の新宿西口・昔の角筈村にあった高須藩下屋敷にも「策(むち)の井」があり、こちらは[44125]で触れています。
[86697]で記したように、四谷家つまり松平摂津守家の最大の責務は尾張徳川家の後継者確保なのですが、実際問題としては 実子による相続だけで続けることは困難です。
8代将軍吉宗の政策に反対して敗れた第7代尾張藩主宗春の後 第8代尾張藩主になった宗勝は、四谷家第3代でした。これは当初目論見通りのスペア役を果たしたように見えます。
しかし 実は四谷家の実子ではなく、スペアのスペアである川田久保家からの養子だったのです。
大名家というのは、こんな具合に複雑な養子関係によりようやく維持されていました。
四谷家第9代の義和(よしなり)は水戸徳川家第6代治保(はるもり)の次男でした。つまり幕末近くの四谷家は、尾張の分家ながら 水戸の血筋 になっていたわけです。
高須藩第10代の松平義建(よしたつ)は 義和の嫡男で、その正室・規姫(のりひめ)も水戸家から来た従姉妹【治保の孫、有名な徳川斉昭(水戸家第9代)の姉】でした。
この夫婦の子が 12代将軍家慶の時代に尾張家14代を継ぐことになる徳川慶恕(よしくみ)、つまり高須四兄弟の長兄・慶勝です。
彼は御三家筆頭の立場ですが尊皇攘夷派で、安政5年(1858)に 大老井伊直弼が勅許を得ずに日米修好通商条約を調印すると 徳川斉昭・一橋慶喜[43497]・松平慶永【春嶽】らと共に江戸城に押しかけて(不時登城)これを糾弾しました。
しかし、この抗議行動は当局側の弾圧【安政の大獄】を招き、慶勝も戸山の下屋敷での幽閉蟄居処分を受けました。
多趣味な文化人の彼は戸山謹慎の期間も有効に活用したのではないでしょうか。
書や博物学【注】だけでなく、写真術の研究家でもあり、撮影だけでなく自ら調合した薬品で現像も行いました。
【注】博物学への傾倒
昆虫標本の作成。植物の精密なスケッチ。 四兄弟の写真 の背景に『草花図画帖』収録の作品が使われています。
慶勝(よしかつ)という名は、万延元年(1860)の復権【注】後に改めた名で、14代将軍家茂の補佐になり、将軍上洛に先立ち文久3年(1863)から朝廷と幕府を一体とする安定体制を築くべく京都での国事周旋活動を始めます。
【注】謹慎を解かれたが慶喜・慶永との面会・文通は禁止。正式の赦免は文久2年(1862)。
京都では異母弟の会津藩主・松平容保が京都守護職として黒谷の金戒光明寺に陣を構えており、この会津と薩摩が組んだクーデターから長州追放、禁門の変、第一次長州征伐へと政局が動き、慶勝は征討軍総督を勤めました。
慶勝は参謀になった薩摩藩・西郷に交渉させ、内部対立のあった長州藩相手に戦わずして決着させました。これは将軍後見役だった慶喜から見れば生ぬるい処置であり、後に復活した長州によって徳川政権が崩壊するに至った原因であったとも言えます。
慶勝は慶応3年(1867)の大政奉還後の上洛時に新政府の議定に任命され、小御所会議に出席。徳川慶喜【母方の従兄弟】に辞官納地を催告する役目を負わされました。そして鳥羽伏見の戦い後には慶喜逃亡後の大阪城受け取り。徳川御三家の筆頭として体制を守るべき尾張家なのに、新政府側としてこのような役割になってしまったのは残念なことだったでしょう。
新政府の地方官として府県と並列する「藩」という言葉が登場したのは慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)の政体書でした。
この時点で正式の改称があったわけではないと思いますが、幕藩体制時代から慣習的に呼ばれていたと思われる「尾張藩」が、新政府の地方組織である「藩」として再発足したので、便宜上これから先は「名古屋藩」と呼ぶことにします。名古屋藩という呼び方は、明治4年の廃藩置県で「名古屋県」に改められるまで使われました。
…というわけで、幕藩体制下において大名家系を存続させるスペアとしての存在意義を失った高須藩は、明治3年12月23日に廃止され、名古屋藩に編入合併される形で幕を閉じることになりました。太政官布告 M3-979 及び 980
執筆の動機は、江戸時代 この地に上屋敷を構えていた尾張徳川家の分家・松平摂津守家(四谷家=高須松平家)とその屋敷に生れた四兄弟をテーマにした特別展でした。しかし、前回[86697]は 所領であった美濃高須や、木曽三川の治水工事に筆を費やし、特別展で紹介された江戸屋敷や人物について語るには至りませんでした。
高須松平家。それは治水の面で幕府から多大の支援を得ていただけでなく、「江戸定府」で参勤交代の義務を免れていた特殊な大名でした。
江戸で育って一生を江戸で暮す定めですから、美濃でなく江戸こそが「津の守」兄弟のふるさとなのでした。
江戸の武家地には町名がないので、荒木町という地名が現れるのは明治の地図です。
『明治十一年実測東亰全図』[78145]を見ると、陸軍士官学校になった尾張徳川家の上屋敷跡【市ヶ谷台】の南西に 四ツ谷荒木町の文字と高須藩上屋敷庭園跡の泉水が見えます。
市民に開放された庭園は新しい木【アラキ】で整備され、明治時代 この付近は芝居小屋・料理屋・芸者屋のある盛り場になったようです。「策(むち)の池」の一部と津の守弁天の祠は現存。
なお、現在の新宿西口・昔の角筈村にあった高須藩下屋敷にも「策(むち)の井」があり、こちらは[44125]で触れています。
[86697]で記したように、四谷家つまり松平摂津守家の最大の責務は尾張徳川家の後継者確保なのですが、実際問題としては 実子による相続だけで続けることは困難です。
8代将軍吉宗の政策に反対して敗れた第7代尾張藩主宗春の後 第8代尾張藩主になった宗勝は、四谷家第3代でした。これは当初目論見通りのスペア役を果たしたように見えます。
しかし 実は四谷家の実子ではなく、スペアのスペアである川田久保家からの養子だったのです。
大名家というのは、こんな具合に複雑な養子関係によりようやく維持されていました。
四谷家第9代の義和(よしなり)は水戸徳川家第6代治保(はるもり)の次男でした。つまり幕末近くの四谷家は、尾張の分家ながら 水戸の血筋 になっていたわけです。
高須藩第10代の松平義建(よしたつ)は 義和の嫡男で、その正室・規姫(のりひめ)も水戸家から来た従姉妹【治保の孫、有名な徳川斉昭(水戸家第9代)の姉】でした。
この夫婦の子が 12代将軍家慶の時代に尾張家14代を継ぐことになる徳川慶恕(よしくみ)、つまり高須四兄弟の長兄・慶勝です。
彼は御三家筆頭の立場ですが尊皇攘夷派で、安政5年(1858)に 大老井伊直弼が勅許を得ずに日米修好通商条約を調印すると 徳川斉昭・一橋慶喜[43497]・松平慶永【春嶽】らと共に江戸城に押しかけて(不時登城)これを糾弾しました。
しかし、この抗議行動は当局側の弾圧【安政の大獄】を招き、慶勝も戸山の下屋敷での幽閉蟄居処分を受けました。
多趣味な文化人の彼は戸山謹慎の期間も有効に活用したのではないでしょうか。
書や博物学【注】だけでなく、写真術の研究家でもあり、撮影だけでなく自ら調合した薬品で現像も行いました。
【注】博物学への傾倒
昆虫標本の作成。植物の精密なスケッチ。 四兄弟の写真 の背景に『草花図画帖』収録の作品が使われています。
慶勝(よしかつ)という名は、万延元年(1860)の復権【注】後に改めた名で、14代将軍家茂の補佐になり、将軍上洛に先立ち文久3年(1863)から朝廷と幕府を一体とする安定体制を築くべく京都での国事周旋活動を始めます。
【注】謹慎を解かれたが慶喜・慶永との面会・文通は禁止。正式の赦免は文久2年(1862)。
京都では異母弟の会津藩主・松平容保が京都守護職として黒谷の金戒光明寺に陣を構えており、この会津と薩摩が組んだクーデターから長州追放、禁門の変、第一次長州征伐へと政局が動き、慶勝は征討軍総督を勤めました。
慶勝は参謀になった薩摩藩・西郷に交渉させ、内部対立のあった長州藩相手に戦わずして決着させました。これは将軍後見役だった慶喜から見れば生ぬるい処置であり、後に復活した長州によって徳川政権が崩壊するに至った原因であったとも言えます。
慶勝は慶応3年(1867)の大政奉還後の上洛時に新政府の議定に任命され、小御所会議に出席。徳川慶喜【母方の従兄弟】に辞官納地を催告する役目を負わされました。そして鳥羽伏見の戦い後には慶喜逃亡後の大阪城受け取り。徳川御三家の筆頭として体制を守るべき尾張家なのに、新政府側としてこのような役割になってしまったのは残念なことだったでしょう。
新政府の地方官として府県と並列する「藩」という言葉が登場したのは慶応4年閏4月21日(1868年6月11日)の政体書でした。
この時点で正式の改称があったわけではないと思いますが、幕藩体制時代から慣習的に呼ばれていたと思われる「尾張藩」が、新政府の地方組織である「藩」として再発足したので、便宜上これから先は「名古屋藩」と呼ぶことにします。名古屋藩という呼び方は、明治4年の廃藩置県で「名古屋県」に改められるまで使われました。
…というわけで、幕藩体制下において大名家系を存続させるスペアとしての存在意義を失った高須藩は、明治3年12月23日に廃止され、名古屋藩に編入合併される形で幕を閉じることになりました。太政官布告 M3-979 及び 980
| [86730] 2014年 11月 25日(火)23:01:47 | hmt さん |
| 津の守坂 (3)高須の松平義比から尾張の徳川茂徳へ、隠居玄同から御三卿の一橋茂栄へ | |
徳川慶勝に続く高須松平家4兄弟の2人目は、10代義建の五男【夭折2人あり実質三男】として誕生した茂栄(もちはる)です。
幼名鎮三郎。元服後は建重・義比・茂徳・玄同・茂栄など多数の名が使われていますが、便宜上統一して使う場合は、慶応元年に最終的な名になった茂栄にします。
過去記事では 尾張藩主時代の「徳川茂徳」を使っていました。今回の御三卿当主の実名も、正式には「徳川茂栄」ですが「一橋茂栄」という形で使われることが多いと思います。
部屋住みのまま一生を過ごす可能性もあった分家の五男。それが3万石の高須藩主「松平義比」(よしちか)に始まり、約62万石の尾張藩主徳川茂徳(もちなが)へ、そして御三卿の一橋茂栄へと 3つの家を相続するに至ったのは大出世です。
それは激動の幕末の中心で活躍した人物だからですが、彼の名をあまり知らなかったのは 私だけではないと思います。
彼が高須藩11代の跡継ぎになれたのは、長兄の慶勝が名古屋の本家を継ぎ、その次の武成(たけしげ)が石見国浜田藩を継いだためでした。
なお 慶勝と武成は正妻の子ですが、茂栄は異母弟です。慶勝・茂栄・容保・定敬は4兄弟と言ってもすべて腹違いでした。
安政の大獄の時代、一橋派の兄・慶勝が戸山に謹慎させられ 尾張家15代を継いだ彼は 14代将軍家茂の偏諱を得て徳川茂徳と改名しました。慶勝に続き 四谷家は尾張家のスペアの役割を担ったわけですが、前藩主の政策を支持する家臣団の統制にも苦労があり 彼にとって 本家藩主の荷は重かったようです。
結局尾張藩の実権は 復権した やりての兄に握られてしまったようで、文久3年(1863)には 33歳で隠居。玄同はその号でした。
14代将軍家茂から再度の偏諱による 茂栄 の名を賜った慶応元年(1865)には35歳。この頃には 15歳年下の将軍と親しい関係にあったようで、第二次長州征伐で上洛した家茂の補佐役的な立場で働きました。
この年横浜に赴任してきた英国公使のパークスは、外国嫌いの孝明天皇が拒否している通商条約の批准を求め、条約4カ国(英仏米蘭)の連合艦隊を兵庫に送り込み、日本を威嚇しました。
これに対する幕府と朝廷の二元外交。対応はモタモタし、遂に家茂が辞任まで言い出して条約勅許を求める状況になり、孝明天皇も止むなく3港開港の通商条約を許すことになりました。パークスの軍事力示威作戦が成功したわけです。
茂栄は この間 苦悶する家茂と 朝廷との間の調整に尽力。家茂からは「今後親とも思う」という心情が伝えられました。
茂栄は江戸に帰った後、大阪城での日々を偲んで家茂像を描きました。
茂栄自身が撮影した写真が残されていますが、残念ながらその画像は Webで未発見です。現物は天璋院に献上後焼失。
茂栄が描いた顔に御用絵師が陣羽織の立姿の体を加えたものと考えられており、首の角度が不自然です。
和宮はこの絵を「異風」であるとして不満であり、茂栄は書き直した束帯姿の画像を贈りました。 こちらの絵は Wikipediaに掲載されています。
茂栄への処遇として、家茂は生前に清水家相続の内命を与えていました。御三家の元当主が御三卿になるのは異例ですが、家茂は親しい茂栄を側に置きたかったようです。家茂の死によってこの話は中止されましたが、兄慶勝の請願もあり、慶喜が将軍になったために空席になった一橋家相続ということになりました。清水家を継いだのは慶喜の弟・徳川昭武[43497]でした。
そして慶応4年(1868)の戊辰戦争。その後始末の段階で、茂栄は徳川本家の総代として 嘆願活動の中心になりました。
3月には江尻まで出向いて、東征大総督の有栖川宮から朝敵になった慶喜への寛大な処分の了承を得ました。
徳川家の存続についても田安亀之助[85225]による相続が認められ、駿府70万石を確保することができました。
御三卿は将軍の家族という立場だったのですが、一橋家は田安家と共に明治元年(1868)5月に至り初めて藩屏に列し、徳川宗家から独立した藩【一橋藩・田安藩】が成立しました。
しかし、3つ目の藩主になった茂栄の「一橋藩主」時代は束の間に終りました。
翌明治2年に出願した版籍奉還願に対する新政府の回答は、諸藩と違う形の処置でした。
茂栄はそれに従い、家政に従事する家臣138人を残し、他の1432人の家臣には暇を出し最寄りの地方役所所属とすることになりました。年貢も地方役所が徴収。新政府による「廃藩」のテストケースにされたようです。
藩知事表 に続く 151コマには一橋茂栄の名が見えます。
しかし、その頭に「知事」が付けられていないことにより、一橋藩が廃藩されたことが示されています。
幼名鎮三郎。元服後は建重・義比・茂徳・玄同・茂栄など多数の名が使われていますが、便宜上統一して使う場合は、慶応元年に最終的な名になった茂栄にします。
過去記事では 尾張藩主時代の「徳川茂徳」を使っていました。今回の御三卿当主の実名も、正式には「徳川茂栄」ですが「一橋茂栄」という形で使われることが多いと思います。
部屋住みのまま一生を過ごす可能性もあった分家の五男。それが3万石の高須藩主「松平義比」(よしちか)に始まり、約62万石の尾張藩主徳川茂徳(もちなが)へ、そして御三卿の一橋茂栄へと 3つの家を相続するに至ったのは大出世です。
それは激動の幕末の中心で活躍した人物だからですが、彼の名をあまり知らなかったのは 私だけではないと思います。
彼が高須藩11代の跡継ぎになれたのは、長兄の慶勝が名古屋の本家を継ぎ、その次の武成(たけしげ)が石見国浜田藩を継いだためでした。
なお 慶勝と武成は正妻の子ですが、茂栄は異母弟です。慶勝・茂栄・容保・定敬は4兄弟と言ってもすべて腹違いでした。
安政の大獄の時代、一橋派の兄・慶勝が戸山に謹慎させられ 尾張家15代を継いだ彼は 14代将軍家茂の偏諱を得て徳川茂徳と改名しました。慶勝に続き 四谷家は尾張家のスペアの役割を担ったわけですが、前藩主の政策を支持する家臣団の統制にも苦労があり 彼にとって 本家藩主の荷は重かったようです。
結局尾張藩の実権は 復権した やりての兄に握られてしまったようで、文久3年(1863)には 33歳で隠居。玄同はその号でした。
14代将軍家茂から再度の偏諱による 茂栄 の名を賜った慶応元年(1865)には35歳。この頃には 15歳年下の将軍と親しい関係にあったようで、第二次長州征伐で上洛した家茂の補佐役的な立場で働きました。
この年横浜に赴任してきた英国公使のパークスは、外国嫌いの孝明天皇が拒否している通商条約の批准を求め、条約4カ国(英仏米蘭)の連合艦隊を兵庫に送り込み、日本を威嚇しました。
これに対する幕府と朝廷の二元外交。対応はモタモタし、遂に家茂が辞任まで言い出して条約勅許を求める状況になり、孝明天皇も止むなく3港開港の通商条約を許すことになりました。パークスの軍事力示威作戦が成功したわけです。
茂栄は この間 苦悶する家茂と 朝廷との間の調整に尽力。家茂からは「今後親とも思う」という心情が伝えられました。
茂栄は江戸に帰った後、大阪城での日々を偲んで家茂像を描きました。
茂栄自身が撮影した写真が残されていますが、残念ながらその画像は Webで未発見です。現物は天璋院に献上後焼失。
茂栄が描いた顔に御用絵師が陣羽織の立姿の体を加えたものと考えられており、首の角度が不自然です。
和宮はこの絵を「異風」であるとして不満であり、茂栄は書き直した束帯姿の画像を贈りました。 こちらの絵は Wikipediaに掲載されています。
茂栄への処遇として、家茂は生前に清水家相続の内命を与えていました。御三家の元当主が御三卿になるのは異例ですが、家茂は親しい茂栄を側に置きたかったようです。家茂の死によってこの話は中止されましたが、兄慶勝の請願もあり、慶喜が将軍になったために空席になった一橋家相続ということになりました。清水家を継いだのは慶喜の弟・徳川昭武[43497]でした。
そして慶応4年(1868)の戊辰戦争。その後始末の段階で、茂栄は徳川本家の総代として 嘆願活動の中心になりました。
3月には江尻まで出向いて、東征大総督の有栖川宮から朝敵になった慶喜への寛大な処分の了承を得ました。
徳川家の存続についても田安亀之助[85225]による相続が認められ、駿府70万石を確保することができました。
御三卿は将軍の家族という立場だったのですが、一橋家は田安家と共に明治元年(1868)5月に至り初めて藩屏に列し、徳川宗家から独立した藩【一橋藩・田安藩】が成立しました。
しかし、3つ目の藩主になった茂栄の「一橋藩主」時代は束の間に終りました。
翌明治2年に出願した版籍奉還願に対する新政府の回答は、諸藩と違う形の処置でした。
茂栄はそれに従い、家政に従事する家臣138人を残し、他の1432人の家臣には暇を出し最寄りの地方役所所属とすることになりました。年貢も地方役所が徴収。新政府による「廃藩」のテストケースにされたようです。
藩知事表 に続く 151コマには一橋茂栄の名が見えます。
しかし、その頭に「知事」が付けられていないことにより、一橋藩が廃藩されたことが示されています。
| [86738] 2014年 11月 30日(日)13:12:07 | hmt さん |
| 津の守坂 (4)松平容保 - 京都守護職としての栄光から戊辰戦争の敗戦へ | |
江戸四谷の屋敷で育ち、幕末の動乱期を生きた 高須藩四兄弟の物語 を続けます。
四兄弟の父である美濃国高須の10代藩主松平摂津守義建は 10男9女をつくり、うち6男1女が成人しました。
この6人の男子がすべて大名家の当主になったという事実は、優れた資質の家系と共に 運にも恵まれたことを思わせます。
もっとも、万延元年(1960)に最後の13代高須藩主になった十男義勇は 僅か2歳で相続しました。版籍奉還の明治2年には 11歳でした。そして石見国浜田藩を継いでいた三男武成[86730]は、義勇誕生よりも10年以上前に23歳で死んでいます。
このような事情を見ると、大名家というのは、家系を断絶させないだけでも 精一杯の努力を求めれていたようです。
その中で 立場の異なる4藩主として幕末が明治に変る時代に居合わせて 激動する世の中を生き抜き、平和が戻った明治11年(1878)実父義建の十七回忌に洋服姿で再会して、四兄弟の記念写真 を残していることは 感動的なエピソードであると思います。この時の年齢は、【右から】徳川慶勝(よしかつ)[86719] 55歳、一橋茂栄(もちはる)[86730] 48歳、松平容保(かたもり) 44歳、松平定敬(さだあき) 33歳でした。
ちょんまげ時代に戻ります。高須四兄弟の中でも最も知られているのは義建七男の松平容保です。
12歳で父の弟である会津松平家藩主容敬の養子になり、18歳で家督相続。この家は2代将軍秀忠の御落胤である保科正之[79357]を祖とする御家門です。養子に入った容保は、将軍に忠勤を励むべしという会津松平家「家訓」(かきん)を殊更に重視する姿勢を取りました。
容保が会津28万石の藩主になった翌年の嘉永6年(1853)は ペリー来航の年で、江戸を防衛すべく急遽築造された「品川台場」[80264]に配備されたのは 川越・会津・忍の3藩でした。彼としては、これが対外的な初仕事でしょう。
もっと大きな役目を負わされたのは、文久2年(1862)に命じられた京都守護職【注】です。家臣団からは反対されましたが、政事総裁【注】の松平春嶽らに「家訓」を引用して説得され、止むなく受諾するに至ったとか。
【注】
幕末に新設された幕府の3要職。将軍後見職 一橋慶喜、政事総裁[72830] 松平春嶽、京都守護職 松平容保
容保が藩兵千人を率いて上洛し、黒谷の金戒光明寺を本陣としたことは[86719]にも記しました。
将軍上洛の道中警護役だった壬生浪士組を会津藩の配下として、都の治安維持にあたったことはよく知られています。
# 近藤勇の浪士組に「新選組」の名を与えたのは、八月十八日の政変(後出)での働きを評価したものです。
温厚な人柄の容保は 孝明天皇からは絶大な信頼を得ており、御前で馬揃えを披露したした際の写真で着用しているのは、下賜された大和錦で仕立てた陣羽織であるとか。
雨天の中の馬揃えで体調を崩し、寝込んでいた容保にもたらされたのが、天皇が尊攘派公家への対応に苦労しているという薩摩藩からの情報でした。これにより薩摩藩と会津藩とは協力することになり、文久3年(1863)八月十八日の政変で 朝廷から長州勢力を一掃し、政局は大きく動きました。天皇は容保に感謝して 宸翰と御製を贈りました。
元治元年(1864)の京阪方面は「一会桑体制」呼ばれる一橋慶喜・松平容保・松平定敬のトリオが実権を握ったように思われていました。
しかし、禁門の変の後、第一次長州征伐は生ぬるい決着に終りました。一橋慶喜は、長州征討軍総督徳川慶勝[86719]を批判し、「総督の鋭気は薄く、薩摩芋に酔うのは酒に酔うより始末が悪い」と評したそうです。
薩長同盟が成立するのは あと1年余り先のこと になりますが、時の流れはこの頃から少し変り、会津に不運が訪れてきたようです。禁門の変に際して参内した時も両側から支えられてやっと歩ける状態だったようで、どうも雨中の馬揃えで崩した体調も不安です。脱線しますが、1863年の雨中馬揃えから私が連想するのは、1943年10月に雨中の神宮外苑で行なわれた出陣学徒壮行会です。動画
決定的な不幸は、慶応2年(1866)夏に将軍家茂、その年の暮に孝明天皇と、2人のトップを相次いで失ったことでした。公武合体路線で仕事を進めてきた容保としては、頼みの綱を2本ともに断たれたも同然です。
将軍慶喜は大政奉還で逆転を狙ったものの、王政復古の大号令に始まる倒幕運動は大波になり、軍事的にも幕府軍が鳥羽伏見で大敗しました。
容保は慶喜との同道を求められて大阪城から江戸に戻り、ここで隠居して会津に戻ることを命じられました。
慶喜からも見捨てられた容保。この後で繰り広げられる会津戦争において、容保は「前藩主」として総指揮にあたったわけです。
結果はご承知のとおりの完敗ですが、容保以下の藩士一同は、武士の誇りとして戦わずに降伏することなど できなかったのでしょう。
降伏後の容保は江戸での幽閉を経て明治5年に赦免されました。
明治13年から日光東照宮などの宮司となり、藩祖の保科正之を祀る土津神社の宮司も兼任しました。
この間の明治9年、新選組の後援者であった小島鹿之助[33902]と佐藤彦五郎[78819]の求めに応じた容保は、近藤勇・土方歳三の名誉回復のための篆額を書いています。石碑は高幡不動にあります。
四兄弟の父である美濃国高須の10代藩主松平摂津守義建は 10男9女をつくり、うち6男1女が成人しました。
この6人の男子がすべて大名家の当主になったという事実は、優れた資質の家系と共に 運にも恵まれたことを思わせます。
もっとも、万延元年(1960)に最後の13代高須藩主になった十男義勇は 僅か2歳で相続しました。版籍奉還の明治2年には 11歳でした。そして石見国浜田藩を継いでいた三男武成[86730]は、義勇誕生よりも10年以上前に23歳で死んでいます。
このような事情を見ると、大名家というのは、家系を断絶させないだけでも 精一杯の努力を求めれていたようです。
その中で 立場の異なる4藩主として幕末が明治に変る時代に居合わせて 激動する世の中を生き抜き、平和が戻った明治11年(1878)実父義建の十七回忌に洋服姿で再会して、四兄弟の記念写真 を残していることは 感動的なエピソードであると思います。この時の年齢は、【右から】徳川慶勝(よしかつ)[86719] 55歳、一橋茂栄(もちはる)[86730] 48歳、松平容保(かたもり) 44歳、松平定敬(さだあき) 33歳でした。
ちょんまげ時代に戻ります。高須四兄弟の中でも最も知られているのは義建七男の松平容保です。
12歳で父の弟である会津松平家藩主容敬の養子になり、18歳で家督相続。この家は2代将軍秀忠の御落胤である保科正之[79357]を祖とする御家門です。養子に入った容保は、将軍に忠勤を励むべしという会津松平家「家訓」(かきん)を殊更に重視する姿勢を取りました。
容保が会津28万石の藩主になった翌年の嘉永6年(1853)は ペリー来航の年で、江戸を防衛すべく急遽築造された「品川台場」[80264]に配備されたのは 川越・会津・忍の3藩でした。彼としては、これが対外的な初仕事でしょう。
もっと大きな役目を負わされたのは、文久2年(1862)に命じられた京都守護職【注】です。家臣団からは反対されましたが、政事総裁【注】の松平春嶽らに「家訓」を引用して説得され、止むなく受諾するに至ったとか。
【注】
幕末に新設された幕府の3要職。将軍後見職 一橋慶喜、政事総裁[72830] 松平春嶽、京都守護職 松平容保
容保が藩兵千人を率いて上洛し、黒谷の金戒光明寺を本陣としたことは[86719]にも記しました。
将軍上洛の道中警護役だった壬生浪士組を会津藩の配下として、都の治安維持にあたったことはよく知られています。
# 近藤勇の浪士組に「新選組」の名を与えたのは、八月十八日の政変(後出)での働きを評価したものです。
温厚な人柄の容保は 孝明天皇からは絶大な信頼を得ており、御前で馬揃えを披露したした際の写真で着用しているのは、下賜された大和錦で仕立てた陣羽織であるとか。
雨天の中の馬揃えで体調を崩し、寝込んでいた容保にもたらされたのが、天皇が尊攘派公家への対応に苦労しているという薩摩藩からの情報でした。これにより薩摩藩と会津藩とは協力することになり、文久3年(1863)八月十八日の政変で 朝廷から長州勢力を一掃し、政局は大きく動きました。天皇は容保に感謝して 宸翰と御製を贈りました。
元治元年(1864)の京阪方面は「一会桑体制」呼ばれる一橋慶喜・松平容保・松平定敬のトリオが実権を握ったように思われていました。
しかし、禁門の変の後、第一次長州征伐は生ぬるい決着に終りました。一橋慶喜は、長州征討軍総督徳川慶勝[86719]を批判し、「総督の鋭気は薄く、薩摩芋に酔うのは酒に酔うより始末が悪い」と評したそうです。
薩長同盟が成立するのは あと1年余り先のこと になりますが、時の流れはこの頃から少し変り、会津に不運が訪れてきたようです。禁門の変に際して参内した時も両側から支えられてやっと歩ける状態だったようで、どうも雨中の馬揃えで崩した体調も不安です。脱線しますが、1863年の雨中馬揃えから私が連想するのは、1943年10月に雨中の神宮外苑で行なわれた出陣学徒壮行会です。動画
決定的な不幸は、慶応2年(1866)夏に将軍家茂、その年の暮に孝明天皇と、2人のトップを相次いで失ったことでした。公武合体路線で仕事を進めてきた容保としては、頼みの綱を2本ともに断たれたも同然です。
将軍慶喜は大政奉還で逆転を狙ったものの、王政復古の大号令に始まる倒幕運動は大波になり、軍事的にも幕府軍が鳥羽伏見で大敗しました。
容保は慶喜との同道を求められて大阪城から江戸に戻り、ここで隠居して会津に戻ることを命じられました。
慶喜からも見捨てられた容保。この後で繰り広げられる会津戦争において、容保は「前藩主」として総指揮にあたったわけです。
結果はご承知のとおりの完敗ですが、容保以下の藩士一同は、武士の誇りとして戦わずに降伏することなど できなかったのでしょう。
降伏後の容保は江戸での幽閉を経て明治5年に赦免されました。
明治13年から日光東照宮などの宮司となり、藩祖の保科正之を祀る土津神社の宮司も兼任しました。
この間の明治9年、新選組の後援者であった小島鹿之助[33902]と佐藤彦五郎[78819]の求めに応じた容保は、近藤勇・土方歳三の名誉回復のための篆額を書いています。石碑は高幡不動にあります。
| [86741] 2014年 12月 1日(月)20:59:38【1】 | hmt さん |
| 津の守坂 (5)京都だけじゃない 越後・蝦夷・九州まで波瀾万丈 - 松平定敬の生涯 | |
高須四兄弟の中で最若年の松平定敬(さだあき)は、安政6年(1859)14歳の時に伊勢桑名松平越中守家 13代を相続しました。亡くなった前藩主定猷(さだみち)の男子【後に14代となる定教】が幼少のために、これも幼い女子・初姫の婿になる約束で迎えられました。
この家は 16世紀の松平定勝を祖とする松山藩主家「久松松平氏」の分家です。説明のため、ちょっと歴史を遡ります。
定勝の母・於大の方は水野氏の出で、松平家に嫁いでいた天文11年に後の徳川家康の母になりましたが、今川氏との関係で離縁されました。再婚先の久松家で定勝の母になったのは永禄3年(1560)で、この年の桶狭間の戦いにより状況が変りました。
今川氏から自立した家康は 於大【伝通院】を母として迎え入れ、その息子【つまり家康の異母弟】の定勝に松平の姓を与えて家臣としました。この家系を久松松平家と呼びます。
桑名には、この松平隠岐守定勝が元和2年(1616)に入っています。しかしこの本家は、次の代に伊予松山に移りました。
桑名城主の後任として美濃大垣から移って来たのが松平越中守定綱【定勝の三男、分家の藩祖】です。
久松松平家【定勝系、定綱系】は家康の男系の子孫ではないので、親藩ではなく譜代大名とされるようです。
定綱系は 桑名の後、3代目が越後高田に、7代目が陸奥白河に移封されました。9代藩主が寛政の改革で知られる老中・松平定信[45967]【8代将軍吉宗の次男で田安家の始祖になった宗武の子】です。定信が老中に就任したことも、久松松平家が親藩でなく、譜代大名であることを裏付けているようです。10代定永に家督を譲った後、定信が要望していた桑名復帰が実現しました。
なお、藩主は桑名・高田・白河・桑名を問わず 通しの歴代数で表示しています。
[86738] hmt
「一会桑体制」呼ばれる一橋慶喜・松平容保・松平定敬のトリオ
「一会桑」とは、言うまでもなく「一橋・会津・桑名」のことです。
一橋慶喜が元治元年(1864)3月に将軍後見職を辞して新たに就任したのは、「禁裏御守衛総督兼摂海防禦指揮」という新設ポストでした。摂海というのは大阪湾のことです。
【注】この人事異動を忘れていた[86719]の訂正
西郷吉之助と組んで第一次長州征伐を決着させた征討軍総督・徳川慶勝を批判した慶喜の【将軍後見役だった】は誤記です。
その翌月に京都所司代に任命されたのが桑名藩主・松平定敬でした。
先代藩主の定猷が安政5年から高松藩・松江藩と共に命じられていた京都警衛の役目は定敬にも引き継がれていましたが、まだ 19歳であった定敬は 若年を理由に 京都所司代の重責【注】を固辞しました。しかし、兄の会津藩主・松平容保(30歳)が一旦任命された軍事総裁職から京都守護職に復帰するということでもあり 断りきれなかったようです。
【注】京都所司代
京都所司代は、幕末に新設され軍事的な組織である京都守護職などと違い、朝廷と幕府との間の連絡ルートである基本的な行政組織です。3万石以上の譜代大名が任命されていました。伊勢国の他に越後国【柏崎】に飛地がある桑名藩は6万石で、家格は十分にありました。
こうして発足した「一会桑体制」。若い定敬にとって それからの4年間は厳しい政治体験の場になりました。
幕府に属してはいるが江戸の幕閣とは距離を置き、朝廷上層部に食い入ってこれと協調。国政参加を求める諸藩の力はできるだけ排除。このような姿勢で禁門の変、長州征伐と進んできたのですが、第二次長州征伐の処理を機に「一会桑」の足並みは乱れ、この政権は崩壊しました。
孝明天皇の崩御後、京都における幕府の権力は失墜。慶喜は大政奉還で逆転を狙うも、倒幕の動きを止めることはできず、戊辰戦争に突入。
鳥羽・伏見の戦いで、桑名藩兵は会津藩兵と共に 主力として薩長軍と激突したが大敗。
その後、定敬は容保と同様に慶喜に従って江戸に同行させられました。
置き去りにされた本国の桑名では意見が割れましたが、結局先代藩主の実子定教を擁立し、新政府に恭順。無血開城しました。
慶喜に従って江戸に着いた定敬は、兄の容保と共に抗戦を主張したものの、恭順することに決めた慶喜に見捨てられました。
ここで、桑名藩飛地の越後柏崎が表に出てきました。
定敬は柏崎に移って、長岡藩の河井継之助と同盟し、北越戦争を戦ったのですね。
本国の桑名は恭順しているのに、前?藩主の定敬が柏崎で新政府軍に抗戦するという分裂状態。
しかし、結局は敗れて会津へ、更に箱館へと落ち延びました。
桑名の家老・酒井孫八郎は、藩の存続のために決意を固め、五稜郭に乗り込んで定敬を連れ出し江戸に出頭させようとしました(明治2年4月)。ところが定敬もさるもの、そのまま米国船で上海まで密航して逃亡。
それも路銀が尽きて、5月には市ヶ谷尾張藩邸に入って遂に新政府に降伏。
展覧会の図録p.64には、一橋茂栄[86730]【中立的立場】から徳川慶勝[86719]【新政府側】に宛てた明治2年7月1日付書簡が残っており、市ヶ谷邸での定敬の様子を心配していると記されていました。処分は死一等を減じ永禁錮でした。
最終的には桑名藩預けになり、明治5年正月免罪。翌月には、安政6年には3歳であった婚約者初子と結ばれました。
明治10年西南戦争。定敬は桑名の士族を募集して、今度は官軍として薩摩を討つために九州に赴きました。応募者350名。
これで定敬の長い戦いはやっと終り、翌明治11年には4兄弟の再会、銀座の写真館での記念撮影[86738]、本所横網町の慶勝邸での会食ということになりました。
明治27年から容保の後任として日光東照宮宮司に就任。
明治41年(1908) 63歳で没す。4兄弟の中で一番長生きでした【慶勝60歳、茂栄54歳、容保59歳】。
この家は 16世紀の松平定勝を祖とする松山藩主家「久松松平氏」の分家です。説明のため、ちょっと歴史を遡ります。
定勝の母・於大の方は水野氏の出で、松平家に嫁いでいた天文11年に後の徳川家康の母になりましたが、今川氏との関係で離縁されました。再婚先の久松家で定勝の母になったのは永禄3年(1560)で、この年の桶狭間の戦いにより状況が変りました。
今川氏から自立した家康は 於大【伝通院】を母として迎え入れ、その息子【つまり家康の異母弟】の定勝に松平の姓を与えて家臣としました。この家系を久松松平家と呼びます。
桑名には、この松平隠岐守定勝が元和2年(1616)に入っています。しかしこの本家は、次の代に伊予松山に移りました。
桑名城主の後任として美濃大垣から移って来たのが松平越中守定綱【定勝の三男、分家の藩祖】です。
久松松平家【定勝系、定綱系】は家康の男系の子孫ではないので、親藩ではなく譜代大名とされるようです。
定綱系は 桑名の後、3代目が越後高田に、7代目が陸奥白河に移封されました。9代藩主が寛政の改革で知られる老中・松平定信[45967]【8代将軍吉宗の次男で田安家の始祖になった宗武の子】です。定信が老中に就任したことも、久松松平家が親藩でなく、譜代大名であることを裏付けているようです。10代定永に家督を譲った後、定信が要望していた桑名復帰が実現しました。
なお、藩主は桑名・高田・白河・桑名を問わず 通しの歴代数で表示しています。
[86738] hmt
「一会桑体制」呼ばれる一橋慶喜・松平容保・松平定敬のトリオ
「一会桑」とは、言うまでもなく「一橋・会津・桑名」のことです。
一橋慶喜が元治元年(1864)3月に将軍後見職を辞して新たに就任したのは、「禁裏御守衛総督兼摂海防禦指揮」という新設ポストでした。摂海というのは大阪湾のことです。
【注】この人事異動を忘れていた[86719]の訂正
西郷吉之助と組んで第一次長州征伐を決着させた征討軍総督・徳川慶勝を批判した慶喜の【将軍後見役だった】は誤記です。
その翌月に京都所司代に任命されたのが桑名藩主・松平定敬でした。
先代藩主の定猷が安政5年から高松藩・松江藩と共に命じられていた京都警衛の役目は定敬にも引き継がれていましたが、まだ 19歳であった定敬は 若年を理由に 京都所司代の重責【注】を固辞しました。しかし、兄の会津藩主・松平容保(30歳)が一旦任命された軍事総裁職から京都守護職に復帰するということでもあり 断りきれなかったようです。
【注】京都所司代
京都所司代は、幕末に新設され軍事的な組織である京都守護職などと違い、朝廷と幕府との間の連絡ルートである基本的な行政組織です。3万石以上の譜代大名が任命されていました。伊勢国の他に越後国【柏崎】に飛地がある桑名藩は6万石で、家格は十分にありました。
こうして発足した「一会桑体制」。若い定敬にとって それからの4年間は厳しい政治体験の場になりました。
幕府に属してはいるが江戸の幕閣とは距離を置き、朝廷上層部に食い入ってこれと協調。国政参加を求める諸藩の力はできるだけ排除。このような姿勢で禁門の変、長州征伐と進んできたのですが、第二次長州征伐の処理を機に「一会桑」の足並みは乱れ、この政権は崩壊しました。
孝明天皇の崩御後、京都における幕府の権力は失墜。慶喜は大政奉還で逆転を狙うも、倒幕の動きを止めることはできず、戊辰戦争に突入。
鳥羽・伏見の戦いで、桑名藩兵は会津藩兵と共に 主力として薩長軍と激突したが大敗。
その後、定敬は容保と同様に慶喜に従って江戸に同行させられました。
置き去りにされた本国の桑名では意見が割れましたが、結局先代藩主の実子定教を擁立し、新政府に恭順。無血開城しました。
慶喜に従って江戸に着いた定敬は、兄の容保と共に抗戦を主張したものの、恭順することに決めた慶喜に見捨てられました。
ここで、桑名藩飛地の越後柏崎が表に出てきました。
定敬は柏崎に移って、長岡藩の河井継之助と同盟し、北越戦争を戦ったのですね。
本国の桑名は恭順しているのに、前?藩主の定敬が柏崎で新政府軍に抗戦するという分裂状態。
しかし、結局は敗れて会津へ、更に箱館へと落ち延びました。
桑名の家老・酒井孫八郎は、藩の存続のために決意を固め、五稜郭に乗り込んで定敬を連れ出し江戸に出頭させようとしました(明治2年4月)。ところが定敬もさるもの、そのまま米国船で上海まで密航して逃亡。
それも路銀が尽きて、5月には市ヶ谷尾張藩邸に入って遂に新政府に降伏。
展覧会の図録p.64には、一橋茂栄[86730]【中立的立場】から徳川慶勝[86719]【新政府側】に宛てた明治2年7月1日付書簡が残っており、市ヶ谷邸での定敬の様子を心配していると記されていました。処分は死一等を減じ永禁錮でした。
最終的には桑名藩預けになり、明治5年正月免罪。翌月には、安政6年には3歳であった婚約者初子と結ばれました。
明治10年西南戦争。定敬は桑名の士族を募集して、今度は官軍として薩摩を討つために九州に赴きました。応募者350名。
これで定敬の長い戦いはやっと終り、翌明治11年には4兄弟の再会、銀座の写真館での記念撮影[86738]、本所横網町の慶勝邸での会食ということになりました。
明治27年から容保の後任として日光東照宮宮司に就任。
明治41年(1908) 63歳で没す。4兄弟の中で一番長生きでした【慶勝60歳、茂栄54歳、容保59歳】。
| [86747] 2014年 12月 4日(木)20:25:50 | hmt さん |
| 津の守坂 (6)錦の御旗 | |
[86742] グリグリさん
幕末の幕府と朝廷と諸藩の勢力関係はなかなか理解が難しいのですが、
この勢力関係に決定的な影響力を及ぼした「切り札」が、鳥羽伏見の戦いで掲げられた「錦の御旗」ではないかと思います。
国立公文書館デジタルアーカイブの絵巻物にある「戊辰所用錦旗及軍旗真図」の解説によると、その起源は承久の乱(1221年)に際して後鳥羽上皇が官軍の将に授与した旗で、赤地錦に金銀で日像・月像を刺繍したり、描いたりと伝えられます。
戊辰戦争で使われたものは、明治天皇の権威に基づく真正の錦旗ではなく、岩倉具視の策謀により薩摩と長州とが勝手に作ったものでした。しかし、当時は存在しなかった「真正の錦旗」を見た人は もちろん居ませんから、「錦の御旗は天皇の旗で、我は官軍である」と新政府軍が言えば、これに反論はできません。
「十六弁八重表菊紋」が天皇専用(親王も不可)という定めは明治2年太政官布告802号でしたが、それ以前の戊辰戦争に際して、日・月像以外の 菊の紋章像の錦旗も使われたようです。
承久の乱の時の鎌倉武士は、本物の錦旗を見せられても怯むことなく、武力で朝廷側を制圧しました。
それなのに、戊辰戦争では贋物の錦旗にしてやられたのは何故か?
それは、「錦旗」を含む尊王論という概念が 幕末の武士の中に ある程度浸透していたからです。
そして、この概念を日本中の知識人に広めた本こそ、水戸光圀が編纂を開始した『大日本史』でした。
「錦旗」は水戸黄門によって「印籠」と同じような力を持つことになりました。
しかし この「無敵兵器」が向けられた相手は、 水戸家出身の徳川慶喜 を総大将とする幕府軍であり、幕府実働部隊の司令官は 「水戸の血筋」[86714]を引く高須松平家出身の会津藩主・桑名藩主 でした。
水戸学という「教養が邪魔して」朝廷に刃向かうことができず、賊軍として敗れるに至ったとは、何とも皮肉な結果でした。
2001年の「911事件」の際、柳井駐米大使はアーミテージ国務副長官に「Show the flag」と言われたとのこと。
洋の東西を問わず、「旗」が軍事行動を目に見える形で示す重要な道具であることを、この時にも痛感しました。
それはさておき。幕末に朝敵にされたのは会津だけではありません。孝明天皇の時代には長州が賊軍で会津が官軍でした。
でも、最終的には最後に「勝てば官軍」で、贋物の錦旗もその正当性が追認され、♪宮さん、宮さん、お馬の前にヒラヒラするのは、なんじゃいな、トコトンヤレ、トンヤレナ ♪あれは朝敵征伐せよとの錦の御旗じゃ知らないか、トコトンヤレ、トンヤレナ という行進曲により、薩長軍が全国を席巻することになりました。
幕末の幕府と朝廷と諸藩の勢力関係はなかなか理解が難しいのですが、
この勢力関係に決定的な影響力を及ぼした「切り札」が、鳥羽伏見の戦いで掲げられた「錦の御旗」ではないかと思います。
国立公文書館デジタルアーカイブの絵巻物にある「戊辰所用錦旗及軍旗真図」の解説によると、その起源は承久の乱(1221年)に際して後鳥羽上皇が官軍の将に授与した旗で、赤地錦に金銀で日像・月像を刺繍したり、描いたりと伝えられます。
戊辰戦争で使われたものは、明治天皇の権威に基づく真正の錦旗ではなく、岩倉具視の策謀により薩摩と長州とが勝手に作ったものでした。しかし、当時は存在しなかった「真正の錦旗」を見た人は もちろん居ませんから、「錦の御旗は天皇の旗で、我は官軍である」と新政府軍が言えば、これに反論はできません。
「十六弁八重表菊紋」が天皇専用(親王も不可)という定めは明治2年太政官布告802号でしたが、それ以前の戊辰戦争に際して、日・月像以外の 菊の紋章像の錦旗も使われたようです。
承久の乱の時の鎌倉武士は、本物の錦旗を見せられても怯むことなく、武力で朝廷側を制圧しました。
それなのに、戊辰戦争では贋物の錦旗にしてやられたのは何故か?
それは、「錦旗」を含む尊王論という概念が 幕末の武士の中に ある程度浸透していたからです。
そして、この概念を日本中の知識人に広めた本こそ、水戸光圀が編纂を開始した『大日本史』でした。
「錦旗」は水戸黄門によって「印籠」と同じような力を持つことになりました。
しかし この「無敵兵器」が向けられた相手は、 水戸家出身の徳川慶喜 を総大将とする幕府軍であり、幕府実働部隊の司令官は 「水戸の血筋」[86714]を引く高須松平家出身の会津藩主・桑名藩主 でした。
水戸学という「教養が邪魔して」朝廷に刃向かうことができず、賊軍として敗れるに至ったとは、何とも皮肉な結果でした。
2001年の「911事件」の際、柳井駐米大使はアーミテージ国務副長官に「Show the flag」と言われたとのこと。
洋の東西を問わず、「旗」が軍事行動を目に見える形で示す重要な道具であることを、この時にも痛感しました。
それはさておき。幕末に朝敵にされたのは会津だけではありません。孝明天皇の時代には長州が賊軍で会津が官軍でした。
でも、最終的には最後に「勝てば官軍」で、贋物の錦旗もその正当性が追認され、♪宮さん、宮さん、お馬の前にヒラヒラするのは、なんじゃいな、トコトンヤレ、トンヤレナ ♪あれは朝敵征伐せよとの錦の御旗じゃ知らないか、トコトンヤレ、トンヤレナ という行進曲により、薩長軍が全国を席巻することになりました。
| [86748] 2014年 12月 4日(木)20:45:36 | hmt さん |
| 津の守坂 (7)敗れた容保・慶喜の名誉回復 | |
戊辰戦争敗戦後の会津藩は、明治2年11月にまだ赤子だった容保の嫡男・容大による家名存続が許されました。三戸県内に3万石の斗南藩が成立し、残りは江刺県に編入されました。記事。
容保個人について言うと、明治5年 38歳で自由の身になり、翌年六男の恒雄が会津の邸で誕生しました。
明治23年に陸軍省から鶴ケ城跡を払下げられています(56歳)。
会津の御薬園[79710]で誕生した松平恒雄は 外交官試験を首席で合格し、ロンドン海軍軍縮会議(1922)首席全権など活躍。
昭和3年に松平恒雄の長女と昭和天皇の弟である秩父宮との御成婚が決定しました。
皇太后【貞明皇后】の強い意向があったと伝えられますが、元会津藩関係者にとっては、これが“朝敵”から完全に名誉回復した出来事として 喜びをもって受け止められたことと思います。
八重の桜の主人公・新島八重(84)の喜びの1首。
いくとせか みねにかかれる 村雲の はれて嬉しき 光をそ見る
秩父宮妃の名は、読みは異なるものの 貞明皇后【さだこ】と同じ「節子」という字であったため、「勢津子」と改められました。
皇室ゆかり「伊勢」と、「会津」とを結びつけた名だそうです。
松平恒雄は、戦後の新憲法による第1回参議院議員選挙で、福島地方区から当選。初代参議院議長に選ばれました。
なお、福島県との関係を言うと、1976年から12年間福島県知事を務めた松平勇雄は、松平恒雄の甥【容保の次男の子】です。
松平恒雄の孫【長男一郎の子】は徳川恒孝(つねなり)として宗家を継いでします。
家達の後を継いだ家正の子が24歳で早世したためです。
徳川家の当主:初代家康、2代秀忠、3代家光、4第家綱、5代【館林】綱吉、6代【甲府】家宣、7代家継、8代【紀州】吉宗、9代家重、10代家治、11代【一橋】家斉、12代家慶、13代家定、14代【紀州】家茂、15代【(水戸→)一橋】慶喜、16代【田安】家達、17代家正、18代【会津】恒孝。
15代慶喜から16代田安亀之助への相続は[86730]で触れ、8歳の家達が静岡藩知事だった明治3年の蓬萊橋視察は[85225]に記しました。
徳川慶喜は 静岡から東京に移り住んだ翌年、明治31年(1898)に皇居に参内して明治天皇に拝謁しました。勝海舟の下工作があったのでしょうが、有栖川宮威仁親王【熾仁親王の弟】の仲介により大政奉還以来の顔合わせが実現したとされます。
こうして徳川宗家のご隠居だった慶喜は、明治35年(1902)に宗家とは別の「徳川慶喜家」を興すことを認められ、「公爵」を授けられ、貴族院議員になりました。
[43497]では“長~い長~い余生”と書きましたが、公爵家を七男慶久に譲って再び隠居するまでの8年間は政界復帰していました。
慶喜の小石川第六天町[70277]の宏壮な屋敷には、孫の喜久子【慶久の次女で 後の高松宮妃】、喜佐子【『徳川慶喜家の子ども部屋』の著者】など 大勢の家族が暮らしていました。
高須四兄弟と従兄弟の徳川慶喜とが登場する雑情報。思いがけず長い連載になりました。
書きながら気を使わされたのが、「実名」(じつみょう)または「名乗」(なのり)です。
4兄弟の徳川慶勝と一橋茂栄。「慶」は 12代将軍家慶、「茂」は 14代将軍家茂の偏諱ですから「よし」・「もち」と読めますが、茂栄の「はる」は読めません。松平容保は有名なので「かたもり」と読めますが、普通なら無理。松平定敬の「あき」も読めません。
慶喜も「慶」は 12代将軍の偏諱だからよいが、「喜」を「のぶ」と読めるのは有名人だから。
[43834]には、よしひさ」という別の読み方も一般的に知られていたと記しました。Wikipediaによると、将軍在職中の幕府公式文書に記錄が残る他、本人の署名や英字新聞に「Yoshihisa」の表記が残っているそうです。
容保個人について言うと、明治5年 38歳で自由の身になり、翌年六男の恒雄が会津の邸で誕生しました。
明治23年に陸軍省から鶴ケ城跡を払下げられています(56歳)。
会津の御薬園[79710]で誕生した松平恒雄は 外交官試験を首席で合格し、ロンドン海軍軍縮会議(1922)首席全権など活躍。
昭和3年に松平恒雄の長女と昭和天皇の弟である秩父宮との御成婚が決定しました。
皇太后【貞明皇后】の強い意向があったと伝えられますが、元会津藩関係者にとっては、これが“朝敵”から完全に名誉回復した出来事として 喜びをもって受け止められたことと思います。
八重の桜の主人公・新島八重(84)の喜びの1首。
いくとせか みねにかかれる 村雲の はれて嬉しき 光をそ見る
秩父宮妃の名は、読みは異なるものの 貞明皇后【さだこ】と同じ「節子」という字であったため、「勢津子」と改められました。
皇室ゆかり「伊勢」と、「会津」とを結びつけた名だそうです。
松平恒雄は、戦後の新憲法による第1回参議院議員選挙で、福島地方区から当選。初代参議院議長に選ばれました。
なお、福島県との関係を言うと、1976年から12年間福島県知事を務めた松平勇雄は、松平恒雄の甥【容保の次男の子】です。
松平恒雄の孫【長男一郎の子】は徳川恒孝(つねなり)として宗家を継いでします。
家達の後を継いだ家正の子が24歳で早世したためです。
徳川家の当主:初代家康、2代秀忠、3代家光、4第家綱、5代【館林】綱吉、6代【甲府】家宣、7代家継、8代【紀州】吉宗、9代家重、10代家治、11代【一橋】家斉、12代家慶、13代家定、14代【紀州】家茂、15代【(水戸→)一橋】慶喜、16代【田安】家達、17代家正、18代【会津】恒孝。
15代慶喜から16代田安亀之助への相続は[86730]で触れ、8歳の家達が静岡藩知事だった明治3年の蓬萊橋視察は[85225]に記しました。
徳川慶喜は 静岡から東京に移り住んだ翌年、明治31年(1898)に皇居に参内して明治天皇に拝謁しました。勝海舟の下工作があったのでしょうが、有栖川宮威仁親王【熾仁親王の弟】の仲介により大政奉還以来の顔合わせが実現したとされます。
こうして徳川宗家のご隠居だった慶喜は、明治35年(1902)に宗家とは別の「徳川慶喜家」を興すことを認められ、「公爵」を授けられ、貴族院議員になりました。
[43497]では“長~い長~い余生”と書きましたが、公爵家を七男慶久に譲って再び隠居するまでの8年間は政界復帰していました。
慶喜の小石川第六天町[70277]の宏壮な屋敷には、孫の喜久子【慶久の次女で 後の高松宮妃】、喜佐子【『徳川慶喜家の子ども部屋』の著者】など 大勢の家族が暮らしていました。
高須四兄弟と従兄弟の徳川慶喜とが登場する雑情報。思いがけず長い連載になりました。
書きながら気を使わされたのが、「実名」(じつみょう)または「名乗」(なのり)です。
4兄弟の徳川慶勝と一橋茂栄。「慶」は 12代将軍家慶、「茂」は 14代将軍家茂の偏諱ですから「よし」・「もち」と読めますが、茂栄の「はる」は読めません。松平容保は有名なので「かたもり」と読めますが、普通なら無理。松平定敬の「あき」も読めません。
慶喜も「慶」は 12代将軍の偏諱だからよいが、「喜」を「のぶ」と読めるのは有名人だから。
[43834]には、よしひさ」という別の読み方も一般的に知られていたと記しました。Wikipediaによると、将軍在職中の幕府公式文書に記錄が残る他、本人の署名や英字新聞に「Yoshihisa」の表記が残っているそうです。
この特集記事はあなたのお気に召しましたか。よろしければ推奨してください。→ ★推奨します★(元祖いいね)
推奨するためには、メンバー登録が必要です。→ メンバー登録のご案内