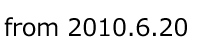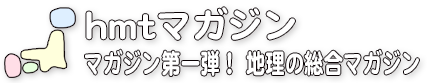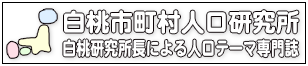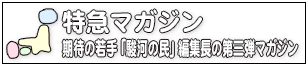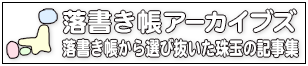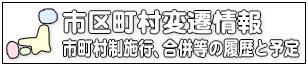47都道府県の中で、最大の領域を持つものはどこでしょうか?
北海道? 確かに陸上面積は最大です。
しかし、東西・南北共に 千数百kmという拡がりを 太平洋上に展開する東京都は、北海道や沖縄県を はるかにしのぐ 広大な領域を持っています。
海域は「都道府県の面積」に含まれていませんが、領海や排他的経済水域EEZ として、我が国の重要な領域として認識されています。
関連アーカイブズ 国家の領土、その現況と変遷
遠く離れた南の島々がなぜ東京都なのか? という素朴な疑問からスタートして、「東京都島嶼部」と総称される伊豆諸島と小笠原諸島に関する記事を集めました。
但し、閲覧の便宜んために、3つの特集に分けました。
東京都に属する 南の島々:
この特集です。東京都島嶼部全般に関係する記事と共に、硫黄島、そして沖ノ鳥島に関する個別記事も集めました。
伊豆諸島(伊豆七島・青ヶ島・南方四島):
現在の伊豆諸島を、昔は「伊豆七島」と呼んでいました。七島とはどこだったのでしょうか?
小笠原諸島:
世界遺産に指定された小笠原群島を主とする記事です。南硫黄島や、世界遺産区域外の南鳥島にも言及しています。
北海道? 確かに陸上面積は最大です。
しかし、東西・南北共に 千数百kmという拡がりを 太平洋上に展開する東京都は、北海道や沖縄県を はるかにしのぐ 広大な領域を持っています。
海域は「都道府県の面積」に含まれていませんが、領海や排他的経済水域EEZ として、我が国の重要な領域として認識されています。
関連アーカイブズ 国家の領土、その現況と変遷
遠く離れた南の島々がなぜ東京都なのか? という素朴な疑問からスタートして、「東京都島嶼部」と総称される伊豆諸島と小笠原諸島に関する記事を集めました。
但し、閲覧の便宜んために、3つの特集に分けました。
東京都に属する 南の島々:
この特集です。東京都島嶼部全般に関係する記事と共に、硫黄島、そして沖ノ鳥島に関する個別記事も集めました。
伊豆諸島(伊豆七島・青ヶ島・南方四島):
現在の伊豆諸島を、昔は「伊豆七島」と呼んでいました。七島とはどこだったのでしょうか?
小笠原諸島:
世界遺産に指定された小笠原群島を主とする記事です。南硫黄島や、世界遺産区域外の南鳥島にも言及しています。
| 記事番号 | 記事日付 | 記事タイトル・発言者 |
|---|---|---|
| [339] | 2001年8月29日 | Issie |
| [71887] | 2009年9月6日 | hmt |
| [71888] | 2009年9月6日 | hmt |
| [56190] | 2007年1月12日 | hmt |
| [67184] | 2008年11月3日 | hmt |
| [67185] | 2008年11月3日 | hmt |
| [29851] | 2004年6月29日 | hmt |
| [33445] | 2004年9月26日 | hmt |
| [56162] | 2007年1月11日 | hmt |
| [59286] | 2007年6月20日 | hmt |
| [74102] | 2010年2月5日 | hmt |
| [344] | 2001年8月30日 | Issie |
| [26266] | 2004年3月16日 | hmt |
| [29173] | 2004年6月10日 | hmt |
| [65212] | 2008年5月21日 | hmt |
| [339] 2001年 8月 29日(水)21:58:13 | Issie さん |
| RE:離島 | |
伊豆諸島や小笠原が「東京都」なのは,
一言で言ってしまえば「どこも面倒を見てくれなかった」からです。
伊豆諸島は当然「伊豆国」の一部でしたから
(ただし,古代以来どの「郡」にも所属したことがありません)
廃藩置県後は伊豆半島とともに「足柄県」に属し,
これが廃止されると“伊豆の一部”として「静岡県」に編入されました。
けれども静岡県はこの離島を管轄することを嫌がって,
結局,当時の「東京府」にお鉢が回ってきたわけです。
当時の東京府は,たとえば警察が内務省直属の警視庁の管轄だったりして
「府」の権限が弱く,政府の影響力が強かったせいもあったのか,
伊豆七島や小笠原を管轄するハメにもなったのかもしれません。
(なお現在の警視庁は制度上では,たとえば山梨県警察本部と同格の
都知事管下の地方警察本部に過ぎません。
警察組織内部での格付けはあるかもしれませんが。)
> 中央直轄にしたほうがいいのではないでしょうか
これは,今の地方自治の発想からは決してあり得ません。
日米の軍事関係者が駐在しているだけの南鳥島や,
ただの“岩”に過ぎず人の住みようのない沖ノ鳥島
(波に削られそうになって,あわてて護岸工事をしたわけだけど)
などはともかく,“住民”のいる父島や母島,
そして「小笠原村」の区域を中央政府直轄にすることは
現行憲法および地方自治法の精神からして決して認められません。
この地域の住民にも,国内あらゆる地域の住民と同じく
“都道府県レベル”の地方自治に参加する権利があるからです。
中央直轄にして,「東京都」への自治へ参加する権利を剥奪することは
あってはならないことです。
(実は,ソ連によって占領されるまで,
ウルップ島以北の中・北千島の住民には
結局最後まで自治権が与えられませんでした。
つまり,「町」も「村」も“自治体”の地位を与えられなかったのです。
言うまでもなく現行憲法・地方自治法ではなく,
明治憲法下での話ですが。)
なお,壱岐・対馬や奄美には現在でも長崎県や鹿児島県の「支庁」が
設置されています(長崎県は五島にも)。
沖縄県も宮古・八重山にそれぞれ支庁が設置されています。
また,かつては佐渡にも新潟県の支庁が設けられていましたが,
その後新潟県はこのような出先機関を全廃しました。
ただし,これらは「地方自治法」の規定に基づき
県の行政事務を分掌する“出張所”として。
地方自治法では“市町村レベル”と“都道府県レベル”での自治,
具体的にはそれぞれの議会と首長しか想定していません。
もし「支庁」レベルの議会を必要とするなら,この法律の改正が必要でしょう。
でも,今の流れは都道府県・市町村それぞれに
今よりも大きな単位への統合をめざす動きの方が主流に思われます。
私は,どちらかというとあまり積極的にはなれないのですが。
一言で言ってしまえば「どこも面倒を見てくれなかった」からです。
伊豆諸島は当然「伊豆国」の一部でしたから
(ただし,古代以来どの「郡」にも所属したことがありません)
廃藩置県後は伊豆半島とともに「足柄県」に属し,
これが廃止されると“伊豆の一部”として「静岡県」に編入されました。
けれども静岡県はこの離島を管轄することを嫌がって,
結局,当時の「東京府」にお鉢が回ってきたわけです。
当時の東京府は,たとえば警察が内務省直属の警視庁の管轄だったりして
「府」の権限が弱く,政府の影響力が強かったせいもあったのか,
伊豆七島や小笠原を管轄するハメにもなったのかもしれません。
(なお現在の警視庁は制度上では,たとえば山梨県警察本部と同格の
都知事管下の地方警察本部に過ぎません。
警察組織内部での格付けはあるかもしれませんが。)
> 中央直轄にしたほうがいいのではないでしょうか
これは,今の地方自治の発想からは決してあり得ません。
日米の軍事関係者が駐在しているだけの南鳥島や,
ただの“岩”に過ぎず人の住みようのない沖ノ鳥島
(波に削られそうになって,あわてて護岸工事をしたわけだけど)
などはともかく,“住民”のいる父島や母島,
そして「小笠原村」の区域を中央政府直轄にすることは
現行憲法および地方自治法の精神からして決して認められません。
この地域の住民にも,国内あらゆる地域の住民と同じく
“都道府県レベル”の地方自治に参加する権利があるからです。
中央直轄にして,「東京都」への自治へ参加する権利を剥奪することは
あってはならないことです。
(実は,ソ連によって占領されるまで,
ウルップ島以北の中・北千島の住民には
結局最後まで自治権が与えられませんでした。
つまり,「町」も「村」も“自治体”の地位を与えられなかったのです。
言うまでもなく現行憲法・地方自治法ではなく,
明治憲法下での話ですが。)
なお,壱岐・対馬や奄美には現在でも長崎県や鹿児島県の「支庁」が
設置されています(長崎県は五島にも)。
沖縄県も宮古・八重山にそれぞれ支庁が設置されています。
また,かつては佐渡にも新潟県の支庁が設けられていましたが,
その後新潟県はこのような出先機関を全廃しました。
ただし,これらは「地方自治法」の規定に基づき
県の行政事務を分掌する“出張所”として。
地方自治法では“市町村レベル”と“都道府県レベル”での自治,
具体的にはそれぞれの議会と首長しか想定していません。
もし「支庁」レベルの議会を必要とするなら,この法律の改正が必要でしょう。
でも,今の流れは都道府県・市町村それぞれに
今よりも大きな単位への統合をめざす動きの方が主流に思われます。
私は,どちらかというとあまり積極的にはなれないのですが。
| [71887] 2009年 9月 6日(日)16:05:37 | hmt さん |
| 支庁を考える (11)東京都島嶼部の4支庁 南の島がなぜ「東京」なのか | |
「支庁」の中で最も有名な存在は北海道の支庁。現在の4代目支庁(根拠は1948年北海道条例)の前身の3代目支庁(根拠は1897年勅令)[71731] から数えれば、112年の歴史があります。
現在では殆んど忘れられた存在が 山間地域の12支庁[71798]。
1926年に 郡役所廃止を受けて 内務省告示で設けられた 25支庁[730] の半数を占めていましたが、その殆んどは 戦時中の1942年に全国に設けられた地方事務所という名の中に埋没しました。
そして、北海道ほど有名ではないが、地理に関心をもつ人ならば気になる存在が、東京都大島支庁[71478][71480]。
今回は、北海道・山間地域と並ぶ第3の支庁設置区域である「島」の中でも、最も知られた存在の伊豆諸島・小笠原諸島の支庁を、その前身である「島庁」と共に探ります。
公職選挙法 第十三条 (小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第一で定め、(後略)
別表第一 (第十三条関係)
東京都第三区 品川区 大田区(中略) 大島支庁管内 三宅支庁管内 八丈支庁管内 小笠原支庁管内
国会議員選挙の区割りに登場する「支庁」は、北海道[71744]以外では、この4支庁だけです。
伊豆大島は、本土から25kmほどですが、それでも熱海沖の初島のように、小舟で渡れる本土付属島とは異なる外洋の島です。ましてや、三宅島や八丈島は黒潮の只中の更に南の島。
伊豆七島 という呼び名が示すように、律令時代から「伊豆国」に属すとされていましたが、本土側の「国地」とは異なる世界の「島地」を構成していました。
# 現在は「伊豆諸島」と呼んでいますが、歴史的な呼び名の「伊豆七島」を使います。
明治9年(1876)に足柄県[24127]が解体されると、伊豆国は静岡県管内に統合され、伊豆七島もこれに従って一旦は静岡県管内になりました。
同じ年、小笠原諸島の日本帰属が国際的に認められました[26683]。政府は、とりあえず小笠原を内務省の直轄にし、更に府県に引き取らせて「本国化」することを考えました。
しかし、「伊豆国」ではないし八丈島の数倍も遠い小笠原を、静岡県に押し付けるわけにはゆかない。
そこで白羽の矢が立ったのが東京府でした。政府の影響力が強かった東京府は、離島の管轄を嫌がった静岡県に代って、伊豆七島(1878)と小笠原(1880)とを引き受けるハメになりました。[339] Issie さん
管内に離島を持つことは、自治体にとっては経済的な負担になります。
地方税収入などほんの僅かなのに、交通・教育・福祉…などの整備義務を負うことになります。
無人島でも、沖ノ鳥島の海岸管理のように莫大な費用が必要な例があります[26266]。
ともかくも、伊豆七島と小笠原は明治11~13年に東京府の直轄行政区域になりました。
この年代は、北海道や離島を含む全国に郡区町村編制法が施行された時期ですが、ここだけは「郡」が編制されない特異な地域でした。郡区町村一覧 には、“七島 伊豆国”として、東京府直轄の 24村を記載。小笠原島は、まだ登場していません。
市区町村変遷履歴情報 を眺めると、伊豆諸島における近代的町村の記録は、日露戦争後の明治41年(1908)に始まり、島によって段階的に村落自治体制の近代化が行なわれたことを読み取ることができます。
島嶼町村制が施行されたのは、大島・八丈島が 1908年、そして三宅島など5島が 1923年でした。
青ヶ島と小笠原諸島に近代の村が設置されたのは、普通町村制の段階になった1940年。
そして八丈小島は、地方自治法になってからでした。
このような段階的移行状況を 全国的に2つの表にまとめた資料が、[65198]88 さんにあります。
後の表では、東京府伊豆大島・八丈島の島嶼町村制→町村制への移行が、正しい日付の S15(1940).4.1に記されていますが、最初の表では 伊豆(*3) (*4) の列が「町村」になる日付が T9.4.1 になっています。単純誤記でしょうが、例外的に認められる「資料価値の高い記事の訂正」[69571]に該当するように思われます。オーナー グリグリさんへの申請をご検討ください。
現在では殆んど忘れられた存在が 山間地域の12支庁[71798]。
1926年に 郡役所廃止を受けて 内務省告示で設けられた 25支庁[730] の半数を占めていましたが、その殆んどは 戦時中の1942年に全国に設けられた地方事務所という名の中に埋没しました。
そして、北海道ほど有名ではないが、地理に関心をもつ人ならば気になる存在が、東京都大島支庁[71478][71480]。
今回は、北海道・山間地域と並ぶ第3の支庁設置区域である「島」の中でも、最も知られた存在の伊豆諸島・小笠原諸島の支庁を、その前身である「島庁」と共に探ります。
公職選挙法 第十三条 (小選挙区選出)議員の選挙区は、別表第一で定め、(後略)
別表第一 (第十三条関係)
東京都第三区 品川区 大田区(中略) 大島支庁管内 三宅支庁管内 八丈支庁管内 小笠原支庁管内
国会議員選挙の区割りに登場する「支庁」は、北海道[71744]以外では、この4支庁だけです。
伊豆大島は、本土から25kmほどですが、それでも熱海沖の初島のように、小舟で渡れる本土付属島とは異なる外洋の島です。ましてや、三宅島や八丈島は黒潮の只中の更に南の島。
伊豆七島 という呼び名が示すように、律令時代から「伊豆国」に属すとされていましたが、本土側の「国地」とは異なる世界の「島地」を構成していました。
# 現在は「伊豆諸島」と呼んでいますが、歴史的な呼び名の「伊豆七島」を使います。
明治9年(1876)に足柄県[24127]が解体されると、伊豆国は静岡県管内に統合され、伊豆七島もこれに従って一旦は静岡県管内になりました。
同じ年、小笠原諸島の日本帰属が国際的に認められました[26683]。政府は、とりあえず小笠原を内務省の直轄にし、更に府県に引き取らせて「本国化」することを考えました。
しかし、「伊豆国」ではないし八丈島の数倍も遠い小笠原を、静岡県に押し付けるわけにはゆかない。
そこで白羽の矢が立ったのが東京府でした。政府の影響力が強かった東京府は、離島の管轄を嫌がった静岡県に代って、伊豆七島(1878)と小笠原(1880)とを引き受けるハメになりました。[339] Issie さん
管内に離島を持つことは、自治体にとっては経済的な負担になります。
地方税収入などほんの僅かなのに、交通・教育・福祉…などの整備義務を負うことになります。
無人島でも、沖ノ鳥島の海岸管理のように莫大な費用が必要な例があります[26266]。
ともかくも、伊豆七島と小笠原は明治11~13年に東京府の直轄行政区域になりました。
この年代は、北海道や離島を含む全国に郡区町村編制法が施行された時期ですが、ここだけは「郡」が編制されない特異な地域でした。郡区町村一覧 には、“七島 伊豆国”として、東京府直轄の 24村を記載。小笠原島は、まだ登場していません。
市区町村変遷履歴情報 を眺めると、伊豆諸島における近代的町村の記録は、日露戦争後の明治41年(1908)に始まり、島によって段階的に村落自治体制の近代化が行なわれたことを読み取ることができます。
島嶼町村制が施行されたのは、大島・八丈島が 1908年、そして三宅島など5島が 1923年でした。
青ヶ島と小笠原諸島に近代の村が設置されたのは、普通町村制の段階になった1940年。
そして八丈小島は、地方自治法になってからでした。
このような段階的移行状況を 全国的に2つの表にまとめた資料が、[65198]88 さんにあります。
後の表では、東京府伊豆大島・八丈島の島嶼町村制→町村制への移行が、正しい日付の S15(1940).4.1に記されていますが、最初の表では 伊豆(*3) (*4) の列が「町村」になる日付が T9.4.1 になっています。単純誤記でしょうが、例外的に認められる「資料価値の高い記事の訂正」[69571]に該当するように思われます。オーナー グリグリさんへの申請をご検討ください。
| [71888] 2009年 9月 6日(日)16:16:37 | hmt さん |
| 支庁を考える (12)東京都島嶼部の4支庁 3島庁から4支庁へ、そして現在の組織規程 | |
前報[71887]では、郡区町村編制法時代の明治11年に 東京府管下になりながら 郡が編制されなかった 伊豆諸島にも、20世紀になると島嶼町村制が段階的に施行され(大島・八丈の2島は1908年、三宅など5島は1923年)、村落自治体制近代化への動きが始まったことを記しました。
日本統治の日が浅い小笠原は、東京府小笠原出張所による直轄統治体制でしたが、明治19年(1886)にこれが小笠原島庁と改称され、島司が置かれました。こちらは日露戦争後の島嶼町村制からも取り残され、町村制が施行されるのは大東亜戦争直前の 1940年になります。
伊豆諸島では、明治14年(1881)に東京府が各島に島役所を設置し、地役人・名主制を復活しました。しかし、この島役所体制は 本地で郡制が整備されてきた明治33年(1900)になるとを廃止されて、大島島庁と八丈島島庁とが設置されました。島地指定に関する勅令
大島・八丈島以外の三宅島など5島は旧体制のまま?
日露戦争後の時代になると、沖縄県及島嶼町村制の制定を受けた 島庁ヲ置ク島地指定ノ件(明治42年勅令第54号、M42/4/1施行) 中野文庫 により、改めて全国8地域が指定されました。
下記東京府以外で指定された島地は、長崎県対馬島・島根県隠岐島・鹿児島県大島郡・沖縄県宮古郡・沖縄県八重山郡です。
東京府【島庁名 管轄区域】
小笠原島庁 小笠原島、南鳥島、中ノ鳥島
八丈島庁 八丈島、小島、青ヶ島、鳥島
大島島庁 大島
今度は「八丈島庁」と1900年よりも1文字だけ短い名になっているのはともかく、疑問点があります。
中ノ鳥島という怪しい存在[65212]までも記されているのに、三宅島など伊豆諸島中の5島は、相変わらず大島支庁の管轄区域に含まれていません。5島が東京府大島島庁の管下になったのは1920年で、1923年には島嶼町村制施行地にもなりました。
全国13地域の島に支庁ができた1926年に、東京府の3島庁は、大島支庁・八丈支庁・小笠原支庁と改称。
戦時中の昭和18年(1943)4月に三宅支庁分立で4支庁となる。その年の7月に東京都制施行。
戦後、小笠原は米軍統治に置かれた後、1968年に返還[53248]。
伊豆諸島[24269]も短期間ながら特定外周領域[56190]になりました。
日本国憲法・地方自治法に基づく戦後の体制では、もちろん北海道を含む各地と共通の地方自治法155条第1項に根拠を置く制度[71744]に移行しました。
東京都組織規程第34条による、東京都の「支庁」に関する規定。
地方行政機関の名称、所在地及び所掌事務は別表四のとおりとする。
北海道HP には、支庁が地域名であることを思わせる記載がありましたが、東京都4支庁についてはこのような記載はなく、都庁の純然たる出先機関であると思われます。
リンクした別表四も、いかにも役所(出先機関)のリストというスタイルです。
東京都島嶼部に設けられた4支庁。そこには、歴史的に「郡」がないという特殊な事情があります。
しかし、もちろん「支庁」は「郡」と同じものではなく、「住所表記上の上位階層」にはなりません。
また、北海道の支庁のような道公認の「地域」[71705] でもありません。
だから「東京都新島村が大島支庁に属している」という関係はないのでしょう。
地方自治法上で「市町村を包括する」広域の地方公共団体は、もちろん都道府県であり、支庁ではありません。
日本統治の日が浅い小笠原は、東京府小笠原出張所による直轄統治体制でしたが、明治19年(1886)にこれが小笠原島庁と改称され、島司が置かれました。こちらは日露戦争後の島嶼町村制からも取り残され、町村制が施行されるのは大東亜戦争直前の 1940年になります。
伊豆諸島では、明治14年(1881)に東京府が各島に島役所を設置し、地役人・名主制を復活しました。しかし、この島役所体制は 本地で郡制が整備されてきた明治33年(1900)になるとを廃止されて、大島島庁と八丈島島庁とが設置されました。島地指定に関する勅令
大島・八丈島以外の三宅島など5島は旧体制のまま?
日露戦争後の時代になると、沖縄県及島嶼町村制の制定を受けた 島庁ヲ置ク島地指定ノ件(明治42年勅令第54号、M42/4/1施行) 中野文庫 により、改めて全国8地域が指定されました。
下記東京府以外で指定された島地は、長崎県対馬島・島根県隠岐島・鹿児島県大島郡・沖縄県宮古郡・沖縄県八重山郡です。
東京府【島庁名 管轄区域】
小笠原島庁 小笠原島、南鳥島、中ノ鳥島
八丈島庁 八丈島、小島、青ヶ島、鳥島
大島島庁 大島
今度は「八丈島庁」と1900年よりも1文字だけ短い名になっているのはともかく、疑問点があります。
中ノ鳥島という怪しい存在[65212]までも記されているのに、三宅島など伊豆諸島中の5島は、相変わらず大島支庁の管轄区域に含まれていません。5島が東京府大島島庁の管下になったのは1920年で、1923年には島嶼町村制施行地にもなりました。
全国13地域の島に支庁ができた1926年に、東京府の3島庁は、大島支庁・八丈支庁・小笠原支庁と改称。
戦時中の昭和18年(1943)4月に三宅支庁分立で4支庁となる。その年の7月に東京都制施行。
戦後、小笠原は米軍統治に置かれた後、1968年に返還[53248]。
伊豆諸島[24269]も短期間ながら特定外周領域[56190]になりました。
日本国憲法・地方自治法に基づく戦後の体制では、もちろん北海道を含む各地と共通の地方自治法155条第1項に根拠を置く制度[71744]に移行しました。
東京都組織規程第34条による、東京都の「支庁」に関する規定。
地方行政機関の名称、所在地及び所掌事務は別表四のとおりとする。
北海道HP には、支庁が地域名であることを思わせる記載がありましたが、東京都4支庁についてはこのような記載はなく、都庁の純然たる出先機関であると思われます。
リンクした別表四も、いかにも役所(出先機関)のリストというスタイルです。
東京都島嶼部に設けられた4支庁。そこには、歴史的に「郡」がないという特殊な事情があります。
しかし、もちろん「支庁」は「郡」と同じものではなく、「住所表記上の上位階層」にはなりません。
また、北海道の支庁のような道公認の「地域」[71705] でもありません。
だから「東京都新島村が大島支庁に属している」という関係はないのでしょう。
地方自治法上で「市町村を包括する」広域の地方公共団体は、もちろん都道府県であり、支庁ではありません。
| [56190] 2007年 1月 12日(金)18:15:48【1】 | hmt さん |
| 日本から政治的行政的に分離された「外周領域」 | |
[56162]で、第二次大戦の末期に、硫黄島を含む小笠原諸島から、民間人の強制疎開が行なわれたことを記しました。
実は、小笠原からの住民引揚は、これが始めてのことではなかったのでした。
既に[26683]で書いたことなのですが、幕末の1861年(文久元年)に老中安藤信正は外国奉行水野忠徳を咸臨丸で派遣して小笠原を回収させ、翌年には八丈島からの移民を送り込み開拓を始めました。
ところがその1862年に起きた生麦事件[54415]の賠償金をめぐり、英国との間に確執があり、真っ先に攻撃される虞のある小笠原は、早々に開拓を放棄して本土に引き揚げてしまったのです。
この時には、旗本の奥方の疎開騒ぎ[33902]があったくらいで、江戸が襲われることも心配されました。
小笠原は、明治8年になってようやく再回収され、翌1876年には日本の小笠原領有が国際的に認められました。
19世紀の話はこのくらいにして、本題である第二次大戦の敗戦によって失なわれた「日本の外周領域」のことに入ります。
小笠原諸島では、1944年に軍属以外の6886人が本土に引き揚げ[56162]。
優勢な米軍は、1945年2月に硫黄島に上陸。栗林部隊2万人が必死に抵抗するも3月には玉砕。
当時の大本営発表では「いおうとう」でした。国土地理院の「いおうじま」や米軍の「Iwo Jima」と違うのは、厚木(あつき)[22152]や物干場(ぶっかんじょう)[38388]のような軍隊方言のせいでしょうか?
父島・母島の生存者は、8月の日本敗戦によって本土に送還されました。
沖縄での地上戦は、3月26日の慶良間諸島(4月1日 沖縄本島)上陸に始まり、6月23日に組織的な戦闘が終了しました。
「鉄の雨」が降り注いだ3ヶ月間に、多数の民間人を含む20万人の犠牲者を出し、日本の行政機能は事実上壊滅ました。
敗戦後、戦場になった沖縄と小笠原を含めたいくつかの島々の行政が、連合国軍総司令部(GHQ)の覚書(指令のMemorandum)によって日本から切り離されます。
「特定外周領域の日本政府よりの政治的行政的分離に関する件 Govermental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan」というタイトルで、SCAPIN-677 と呼ばれています。SCAP=連合国軍最高司令官(日本の新聞では「マ元帥」と表記)の Instruction Noteという意味です。
この覚書の第3条の中で、「日本の地域から除かれる地域」として列挙された3項目の中に
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原および火山(硫黄)列島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島
があり、“北緯30度以南の琉球列島”の中には、沖縄、奄美群島、トカラ列島の「下七島」が含まれます。
(b)項において、伊豆諸島も日本の地域から除かれています。これに関連して、2004年1月29 日(SCAPIN-677発令58周年)に、[24269]「伊豆諸島が日本でなかった53日」という記事を書きました。この記事に対する Issieさんのレス[24274]にあるように、 SCAPIN-841 による修正によって、伊豆諸島が日本に戻りました。
(b)項には、南方諸島[53392]の名も見えます。(対日講和条約第3条や小笠原返還協定 第1条第2項では、小笠原を含む広い意味で使われています。)
沖縄県に所属するものの、「大東島群」(沖ノ鳥島やパラオ列島に連なる)は、別に挙げられています。
幻の「中ノ鳥島」([26266]の末尾)が、顔を出しているところはご愛嬌。
(a)鬱陵島、竹島、済州島や(c)千島列島、歯舞島群、色丹島が日本に含まれていないことは、領土問題についての韓国やロシアの主張の一つの根拠になっているのでしょうが、もともと SCAPIN-677 は、第6条に明記されているように、最終的な帰属を定めるものではない暫定的な性格のものだから、領土問題にこれを持ち出すのは筋違いということになります。
ついでに言えば、 SCAPIN-677 によれば、鬱陵島・済州島は、第4条の朝鮮とは区別された存在ですね。
原文を読もうと思ったら 画像 がありましたが、読みにくい。
外務省HPの中の 日露領土関係文書IIIの12番目は、全文ではありませんが、よく読めます。
1946年(昭和21年)1月29日に発令された SCAPIN-677 は、2月2日にGHQの民間情報教育局(CIE)から発表され、奄美復帰年表 では、「二・二宣言」と呼ばれています。
昭和21年2月3日毎日新聞(大阪)には、「日本領域マ司令部指定」という記事がありますが、読んでみると、“日本領域として特に指定された島嶼に 千島諸島 および北緯30度以北の琉球諸島を含んでいるが…”とあります。
これは明らかな誤報です。電話送稿で「対馬」と「千島」を取り違えたのでしょう。
実は、小笠原からの住民引揚は、これが始めてのことではなかったのでした。
既に[26683]で書いたことなのですが、幕末の1861年(文久元年)に老中安藤信正は外国奉行水野忠徳を咸臨丸で派遣して小笠原を回収させ、翌年には八丈島からの移民を送り込み開拓を始めました。
ところがその1862年に起きた生麦事件[54415]の賠償金をめぐり、英国との間に確執があり、真っ先に攻撃される虞のある小笠原は、早々に開拓を放棄して本土に引き揚げてしまったのです。
この時には、旗本の奥方の疎開騒ぎ[33902]があったくらいで、江戸が襲われることも心配されました。
小笠原は、明治8年になってようやく再回収され、翌1876年には日本の小笠原領有が国際的に認められました。
19世紀の話はこのくらいにして、本題である第二次大戦の敗戦によって失なわれた「日本の外周領域」のことに入ります。
小笠原諸島では、1944年に軍属以外の6886人が本土に引き揚げ[56162]。
優勢な米軍は、1945年2月に硫黄島に上陸。栗林部隊2万人が必死に抵抗するも3月には玉砕。
当時の大本営発表では「いおうとう」でした。国土地理院の「いおうじま」や米軍の「Iwo Jima」と違うのは、厚木(あつき)[22152]や物干場(ぶっかんじょう)[38388]のような軍隊方言のせいでしょうか?
父島・母島の生存者は、8月の日本敗戦によって本土に送還されました。
沖縄での地上戦は、3月26日の慶良間諸島(4月1日 沖縄本島)上陸に始まり、6月23日に組織的な戦闘が終了しました。
「鉄の雨」が降り注いだ3ヶ月間に、多数の民間人を含む20万人の犠牲者を出し、日本の行政機能は事実上壊滅ました。
敗戦後、戦場になった沖縄と小笠原を含めたいくつかの島々の行政が、連合国軍総司令部(GHQ)の覚書(指令のMemorandum)によって日本から切り離されます。
「特定外周領域の日本政府よりの政治的行政的分離に関する件 Govermental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan」というタイトルで、SCAPIN-677 と呼ばれています。SCAP=連合国軍最高司令官(日本の新聞では「マ元帥」と表記)の Instruction Noteという意味です。
この覚書の第3条の中で、「日本の地域から除かれる地域」として列挙された3項目の中に
(b)北緯30度以南の琉球(南西)列島(口之島を含む)、伊豆、南方、小笠原および火山(硫黄)列島、及び大東群島、沖ノ鳥島、南鳥島、中ノ鳥島を含むその他の外廓太平洋全諸島
があり、“北緯30度以南の琉球列島”の中には、沖縄、奄美群島、トカラ列島の「下七島」が含まれます。
(b)項において、伊豆諸島も日本の地域から除かれています。これに関連して、2004年1月29 日(SCAPIN-677発令58周年)に、[24269]「伊豆諸島が日本でなかった53日」という記事を書きました。この記事に対する Issieさんのレス[24274]にあるように、 SCAPIN-841 による修正によって、伊豆諸島が日本に戻りました。
(b)項には、南方諸島[53392]の名も見えます。(対日講和条約第3条や小笠原返還協定 第1条第2項では、小笠原を含む広い意味で使われています。)
沖縄県に所属するものの、「大東島群」(沖ノ鳥島やパラオ列島に連なる)は、別に挙げられています。
幻の「中ノ鳥島」([26266]の末尾)が、顔を出しているところはご愛嬌。
(a)鬱陵島、竹島、済州島や(c)千島列島、歯舞島群、色丹島が日本に含まれていないことは、領土問題についての韓国やロシアの主張の一つの根拠になっているのでしょうが、もともと SCAPIN-677 は、第6条に明記されているように、最終的な帰属を定めるものではない暫定的な性格のものだから、領土問題にこれを持ち出すのは筋違いということになります。
ついでに言えば、 SCAPIN-677 によれば、鬱陵島・済州島は、第4条の朝鮮とは区別された存在ですね。
原文を読もうと思ったら 画像 がありましたが、読みにくい。
外務省HPの中の 日露領土関係文書IIIの12番目は、全文ではありませんが、よく読めます。
1946年(昭和21年)1月29日に発令された SCAPIN-677 は、2月2日にGHQの民間情報教育局(CIE)から発表され、奄美復帰年表 では、「二・二宣言」と呼ばれています。
昭和21年2月3日毎日新聞(大阪)には、「日本領域マ司令部指定」という記事がありますが、読んでみると、“日本領域として特に指定された島嶼に 千島諸島 および北緯30度以北の琉球諸島を含んでいるが…”とあります。
これは明らかな誤報です。電話送稿で「対馬」と「千島」を取り違えたのでしょう。
| [67184] 2008年 11月 3日(月)17:31:06 | hmt さん |
| 日本が広がる? 11月中にも大陸棚の認定範囲を国連に申請 (1)領海と排他的経済水域 | |
「都道府県市区町村」の区域を越えた場所ですが、日本の主権的権利を行使することができる区域の拡張を図る動きが報道されています。
時事通信2008/10/31
政府は10月31日、沖ノ鳥島などの海域に広がる大陸棚について、国土の倍に当たる約74万km2を新たに日本の主権的権利が及ぶ範囲として認めるよう、11月中にも国連に申請することを決めた。
これまでにも境界線の話題などに関連して、海を自国の領域に取り込むことについて触れてきましたが、この機会にもう一度その歴史を振り返ります。
「地先の海」は沿岸国の領域であり、これから「領海」という概念ができました。
着弾距離である海岸から1リーグ(3海里)を領海とする説が 1702年に提唱され、多くの国に認められてきたようです。
これは海岸防備という観点に基づくものですが、例えば浦賀水道にあたってみると、最も狭い部分で4海里弱。両岸に砲台があれば3海里の射程でも十分に防ぐことができるわけです。
ペリーの黒船は、嘉永6年(1853)最初の来航時には湾外の浦賀沖に停泊し、久里浜に上陸しました。
当時の日本には、はっきしした国際法の意識はなかったかもしれませんが、たぶん黒船は領海に侵入しなかったのでしょう。
しかし、翌1854年に再来日した折には、領海内に入った9隻の大艦隊が江戸湾に集結して威嚇。武蔵国久良岐郡横浜村に上陸して日本國米利堅合衆國和親條約(日米和親条約)を締結しました。
明治になってからですが、1870年の普仏戦争に際しての局外中立に関する 太政官布告明治3年546号 において、着弾距離による領海3海里説を追認したものと考えられる“三里”が使われています。
港内及び内海は勿論に候へども外海之儀は凡三里(陸地より砲丸の達する距離)以内両国交戦に及び候儀は不相成
その後大砲の射程距離は伸び(現代のミサイルならば100km先の敵艦も狙えるかもしれません)、次第に 12海里が優勢になってきました。日本も 1977年の領海法で 12海里を採用しました。
この流れは国際的にも追認されており、海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約 1982)も 12海里になっています。
第2次大戦後は、海岸防備という観点以外に、大陸棚の鉱物資源や水産資源を確保するための動きが出始めました。1945年米国による大陸棚宣言。1952年チリ、ペルー、エクアドルによるサンチアゴ宣言。
いろいろな駆け引きを経て、現在は領海12海里と共に、排他的経済水域(EEZ)200海里が国際的に定着しています。
領海 12海里の起算となる基線は、もともとは海岸の低潮線、湾港若しくは湾内等に引かれる直線でしたが、国連海洋法条約の批准に伴ない整備された 「領海及び接続水域に関する法律」によって、1997年から「直線基線」が採用されています。[57494]
同じ法律により導入された排他的経済水域(Exclusive Economic Zone)の限界も、同じ基線から 200海里までです。日本の 200海里管轄海域の面積は 447万km2、これは国土面積の 11.8倍にあたり、世界第6位の広さです。
上記面積が出ている 日本の領海等概念図 を見ると、気になる箇所があります。それは沖ノ鳥島と本土との間に開いている穴。
実は、最初に紹介した報道で記した「大陸棚」 74万km2とは、この穴を埋め、更に小笠原諸島と南鳥島との間も埋めてしまって、日本の領域を一体化する区域なのです。
時事通信2008/10/31
政府は10月31日、沖ノ鳥島などの海域に広がる大陸棚について、国土の倍に当たる約74万km2を新たに日本の主権的権利が及ぶ範囲として認めるよう、11月中にも国連に申請することを決めた。
これまでにも境界線の話題などに関連して、海を自国の領域に取り込むことについて触れてきましたが、この機会にもう一度その歴史を振り返ります。
「地先の海」は沿岸国の領域であり、これから「領海」という概念ができました。
着弾距離である海岸から1リーグ(3海里)を領海とする説が 1702年に提唱され、多くの国に認められてきたようです。
これは海岸防備という観点に基づくものですが、例えば浦賀水道にあたってみると、最も狭い部分で4海里弱。両岸に砲台があれば3海里の射程でも十分に防ぐことができるわけです。
ペリーの黒船は、嘉永6年(1853)最初の来航時には湾外の浦賀沖に停泊し、久里浜に上陸しました。
当時の日本には、はっきしした国際法の意識はなかったかもしれませんが、たぶん黒船は領海に侵入しなかったのでしょう。
しかし、翌1854年に再来日した折には、領海内に入った9隻の大艦隊が江戸湾に集結して威嚇。武蔵国久良岐郡横浜村に上陸して日本國米利堅合衆國和親條約(日米和親条約)を締結しました。
明治になってからですが、1870年の普仏戦争に際しての局外中立に関する 太政官布告明治3年546号 において、着弾距離による領海3海里説を追認したものと考えられる“三里”が使われています。
港内及び内海は勿論に候へども外海之儀は凡三里(陸地より砲丸の達する距離)以内両国交戦に及び候儀は不相成
その後大砲の射程距離は伸び(現代のミサイルならば100km先の敵艦も狙えるかもしれません)、次第に 12海里が優勢になってきました。日本も 1977年の領海法で 12海里を採用しました。
この流れは国際的にも追認されており、海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約 1982)も 12海里になっています。
第2次大戦後は、海岸防備という観点以外に、大陸棚の鉱物資源や水産資源を確保するための動きが出始めました。1945年米国による大陸棚宣言。1952年チリ、ペルー、エクアドルによるサンチアゴ宣言。
いろいろな駆け引きを経て、現在は領海12海里と共に、排他的経済水域(EEZ)200海里が国際的に定着しています。
領海 12海里の起算となる基線は、もともとは海岸の低潮線、湾港若しくは湾内等に引かれる直線でしたが、国連海洋法条約の批准に伴ない整備された 「領海及び接続水域に関する法律」によって、1997年から「直線基線」が採用されています。[57494]
同じ法律により導入された排他的経済水域(Exclusive Economic Zone)の限界も、同じ基線から 200海里までです。日本の 200海里管轄海域の面積は 447万km2、これは国土面積の 11.8倍にあたり、世界第6位の広さです。
上記面積が出ている 日本の領海等概念図 を見ると、気になる箇所があります。それは沖ノ鳥島と本土との間に開いている穴。
実は、最初に紹介した報道で記した「大陸棚」 74万km2とは、この穴を埋め、更に小笠原諸島と南鳥島との間も埋めてしまって、日本の領域を一体化する区域なのです。
| [67185] 2008年 11月 3日(月)18:38:25 | hmt さん |
| 日本が広がる? 11月中にも大陸棚の認定範囲を国連に申請(2) 国連海洋法条約の「大陸棚」 | |
[67184]に引き続き、時の話題になった「大陸棚」に移ります。
先に、1945年 米国のトルーマン大統領が出した大陸棚宣言に触れました。国際社会は、この時にはこの考えを承認するに至りませんでしたが、各国で対立する利害の中、1958年の第1次国連海洋法会議において、「大陸棚に関する条約」等のジュネーブ海洋法4条約が採択され、1964年に発効しました。
しかし、「天然資源の開発可能な水深」という定義は 技術力に依存するので 適切な基準でない という批判もあり、第2次、第3次の会議を経て、ようやく1982年に既出の 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約) が採択されました。1994年発効。わが国も1996年批准。
この条約は、第二部で 領海及び接続水域、第三部で 国際海峡(津軽海峡など)、第五部で 排他的経済水域を規定していますが、第六部は 大陸棚です。
大陸棚の定義を見ると、“海面下の区域の海底及びその下であって…”と、海底と海底下が大前提となっており、その探査及び天然資源開発のための主権的権利を認めています。
排他的経済水域が“海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源…)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利”と、水産資源をも対象としているのに対して、大陸棚は鉱物資源に限られているようです。
海上保安レポート2005年版 記載の解説に図示されているように、国連海洋法条約の「大陸棚」は、これまで地学的に理解してきた大陸棚と違い、大陸斜面脚部から60海里という棚の下までを含まれています。
レポート中の「大陸棚の限界の延長」から引用します。
---------------------------------------------------------
大陸棚の限界を200海里を超えて設定するためには、「国連大陸棚の限界に関する委員会」へ、大陸棚の地形・地質に関するデータ等、大陸棚の限界に関する情報を提出し、審査を受ける必要があり、我が国の場合は平成21年5月までに提出しなければなりません。
---------------------------------------------------------
報道された“11月中に国連に申請”は、海上保安庁がかねて行なってきた調査 がまとまり、来年5月の期限を半年前倒しで提出するものと理解されます。
なお、最初に国連への申請を出したのはロシア(2001/12)で、審査の結果、科学的根拠が不十分で、翌年に詳細な情報の再提出が勧告されています(北極海・オホーツク海北部)。また、ベーリング海・オホーツク海南部・バレンツ海については関係国との協議・調整が勧告されました。
調査には、2隻の大型測量船(拓洋と昭洋)などを使い、九州・パラオ海嶺南部、大東島周辺海域及び南鳥島周辺海域などで実施したとあります。
小さな図ですが、2005年版レポートに、沖ノ鳥島の東西南北と小笠原南鳥島間が赤で示されているのがわかります。
日本海溝と南鳥島東側は、今回申請する「大陸棚」でないかもしれません。
伊豆諸島、南方四島、小笠原群島と硫黄島 と、かつて落書き帳の話題にした島々を含む伊豆・小笠原海嶺。
そして、大東島[56334]、沖ノ鳥島 の九州・パラオ海嶺。
日本の拡大には、この2つの海嶺が ずいぶん役立っていることを改めて認識しました。
先に、1945年 米国のトルーマン大統領が出した大陸棚宣言に触れました。国際社会は、この時にはこの考えを承認するに至りませんでしたが、各国で対立する利害の中、1958年の第1次国連海洋法会議において、「大陸棚に関する条約」等のジュネーブ海洋法4条約が採択され、1964年に発効しました。
しかし、「天然資源の開発可能な水深」という定義は 技術力に依存するので 適切な基準でない という批判もあり、第2次、第3次の会議を経て、ようやく1982年に既出の 海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約) が採択されました。1994年発効。わが国も1996年批准。
この条約は、第二部で 領海及び接続水域、第三部で 国際海峡(津軽海峡など)、第五部で 排他的経済水域を規定していますが、第六部は 大陸棚です。
大陸棚の定義を見ると、“海面下の区域の海底及びその下であって…”と、海底と海底下が大前提となっており、その探査及び天然資源開発のための主権的権利を認めています。
排他的経済水域が“海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源(生物資源…)の探査、開発、保存及び管理のための主権的権利”と、水産資源をも対象としているのに対して、大陸棚は鉱物資源に限られているようです。
海上保安レポート2005年版 記載の解説に図示されているように、国連海洋法条約の「大陸棚」は、これまで地学的に理解してきた大陸棚と違い、大陸斜面脚部から60海里という棚の下までを含まれています。
レポート中の「大陸棚の限界の延長」から引用します。
---------------------------------------------------------
大陸棚の限界を200海里を超えて設定するためには、「国連大陸棚の限界に関する委員会」へ、大陸棚の地形・地質に関するデータ等、大陸棚の限界に関する情報を提出し、審査を受ける必要があり、我が国の場合は平成21年5月までに提出しなければなりません。
---------------------------------------------------------
報道された“11月中に国連に申請”は、海上保安庁がかねて行なってきた調査 がまとまり、来年5月の期限を半年前倒しで提出するものと理解されます。
なお、最初に国連への申請を出したのはロシア(2001/12)で、審査の結果、科学的根拠が不十分で、翌年に詳細な情報の再提出が勧告されています(北極海・オホーツク海北部)。また、ベーリング海・オホーツク海南部・バレンツ海については関係国との協議・調整が勧告されました。
調査には、2隻の大型測量船(拓洋と昭洋)などを使い、九州・パラオ海嶺南部、大東島周辺海域及び南鳥島周辺海域などで実施したとあります。
小さな図ですが、2005年版レポートに、沖ノ鳥島の東西南北と小笠原南鳥島間が赤で示されているのがわかります。
日本海溝と南鳥島東側は、今回申請する「大陸棚」でないかもしれません。
伊豆諸島、南方四島、小笠原群島と硫黄島 と、かつて落書き帳の話題にした島々を含む伊豆・小笠原海嶺。
そして、大東島[56334]、沖ノ鳥島 の九州・パラオ海嶺。
日本の拡大には、この2つの海嶺が ずいぶん役立っていることを改めて認識しました。
| [29851] 2004年 6月 29日(火)00:02:08【1】 | hmt さん |
| 列島・諸島・群島 | |
[29813] 作々さん
「列島・諸島・群島」コレクションというのは如何でしょうか。この3つ、定義が曖昧なところもあって、混合して使用されているのもあるようなんですが。
「列島・諸島・群島」に一応の区別はあるのでしょうが、おっしゃる通り、別名として同じように使用される例が多数あります。例えば八重山列島、八重山群島、八重山諸島は同じ「島群」(以下、この言葉を使います)です。
他方、小笠原諸島と小笠原群島とは区別して用いられます。
すなわち、小笠原群島は3列島(北から聟島列島・父島列島・母島列島)の総称ですが、小笠原諸島はこの3列島と硫黄列島(火山列島)を含む4列島に、更に西之島と西之島新島(両島は地続きになった)・南鳥島・沖ノ鳥島を含めて用いられます。南鳥島・沖ノ鳥島は “地理的には” かなり離れていますが、 “行政的に” 小笠原諸島に含まれているのだと理解します。
例えば我が地元(鹿児島)を例に少し書きますと、
南西諸島 なんせいしょとう 薩南諸島,琉球諸島
薩南諸島 さつなんしょとう 大隅諸島,吐喝喇列島,奄美諸島
大隅諸島 おおすみしょとう 種子島,屋久島,口永良部島
「南西諸島」 という呼び名は、もともと海上保安庁で使われていたものが広く使われるようになったようです。帝国書院の「復刻版地図帳」[25914]により記載状況を調べると、1934年版と1950年版には見当たらず、1973年版には記載されています。
鹿児島県の薩南諸島には 作々さんの挙げられた3島群と 三島村所属の上三島が含まれます。1946年に北緯30度線で分断された際に 日本に残った「上三島」[24269]は、現在では大隅諸島に含めることもあるようですが、戦前は「吐喝喇列島(川辺十島)」に含まれていました。なお、草冠のある字は JIS外で表示できないために、作々さんにならって「喝」で代用しました。
ついでに触れておきますが、種子島北端や上三島と同緯度にあるにもかかわらず、草垣群島は薩南諸島に含まれません。薩摩半島西側の笠沙町に属するために“薩南”ではないのでしょう。しかし、甑島列島・宇治群島・草垣群島を総称する“薩西諸島”という呼び名は聞いたことがありません。
【1】脱字修正のついでに補足
種子島等は大隅国なので 大隅諸島と呼ばれるのは 当然として、ここや奄美の島々の総称が “薩南”諸島 であるのは何故でしょうか? 長期にわたる薩摩政権支配の間に“(広義の)薩摩の南部”という認識が生まれていたのでしょうか。
南西諸島ファミリーにおいて、島群の包括関係は 最大4階層の複雑な入れ子構造です。
勿論最初は「日本列島」
ア! 第0階層 日本列島を含めれば5階層でした。
第1階層 南西諸島の内訳=薩南諸島 + 琉球諸島
第2階層 薩南諸島の内訳=大隅諸島 + 上三島 + 吐喝喇列島 + 奄美群島
第2階層 琉球諸島の内訳=沖縄諸島 + 先島諸島 + 大東諸島
第3階層 沖縄諸島の内訳=沖縄島 + 伊平屋伊是名諸島 + 与勝諸島 + 慶良間諸島 + 久米島等
第3階層 先島諸島の内訳=宮古群島 + 八重山群島 + 尖閣列島
島群の呼び名や包括関係については、「島嶼大事典」(日外アソシエーツ1991)の呼び名と包括関係を用いましたが、歴史的な変化があります。
例えば1934年版では、前記のように南西諸島はなくて薩南諸島・琉球(諸島という字が入っていない)になっており、小笠原諸島は現在の小笠原群島の範囲で、同じ大きさの字で硫黄列島が別に存在します。この 1934年版を良く見ると、この 2島群と伊豆七島(現在の伊豆諸島)を含む図のタイトルは「豆南諸島」となっています。
豆南諸島の名は[19744]kenさんに登場し、本を引用した紹介文が記されています。
孀婦岩、須美寿島、ベヨネーズ列岩、鳥島という名前は聞いたことがあるかもしれない。これらの無人島群が豆南諸島。
昔、広い範囲で使われていた「豆南諸島」が、近年のダイバー用語では狭い意味で復活したのでしょうか。
これらの無人島群については、この落書き帳だけで通用する呼び名として、私が命名した「南方四島」[22460]もあります。
そうそう、南方と言えば、伊豆諸島と小笠原諸島の総称としての「南方諸島」の名が平凡社の「日本大地図帳」等に見えます。
これを使うと、南方諸島ファミリーは
第1階層 南方諸島の内訳=伊豆諸島 + 小笠原諸島
第2階層 伊豆諸島の内訳=伊豆七島 + 式根島・青ヶ島・鳥島等
第2階層 小笠原諸島の内訳=小笠原群島 + 硫黄列島 + 西之島等
第3階層 小笠原群島の内訳=聟島列島 + 父島列島 + 母島列島
「復刻版地図帳」に戻って、戦後の1950年版では、ユーラシア図の中に琉球列島・小笠原列島の名が見えます。日本の統治下でなかったので、日本図の部には出ていないのですね。
1973年版になると、現在とほぼ同じ伊豆諸島・小笠原諸島・(やや小さい字で)硫黄諸島になっています。
「列島・諸島・群島」コレクションというのは如何でしょうか。この3つ、定義が曖昧なところもあって、混合して使用されているのもあるようなんですが。
「列島・諸島・群島」に一応の区別はあるのでしょうが、おっしゃる通り、別名として同じように使用される例が多数あります。例えば八重山列島、八重山群島、八重山諸島は同じ「島群」(以下、この言葉を使います)です。
他方、小笠原諸島と小笠原群島とは区別して用いられます。
すなわち、小笠原群島は3列島(北から聟島列島・父島列島・母島列島)の総称ですが、小笠原諸島はこの3列島と硫黄列島(火山列島)を含む4列島に、更に西之島と西之島新島(両島は地続きになった)・南鳥島・沖ノ鳥島を含めて用いられます。南鳥島・沖ノ鳥島は “地理的には” かなり離れていますが、 “行政的に” 小笠原諸島に含まれているのだと理解します。
例えば我が地元(鹿児島)を例に少し書きますと、
南西諸島 なんせいしょとう 薩南諸島,琉球諸島
薩南諸島 さつなんしょとう 大隅諸島,吐喝喇列島,奄美諸島
大隅諸島 おおすみしょとう 種子島,屋久島,口永良部島
「南西諸島」 という呼び名は、もともと海上保安庁で使われていたものが広く使われるようになったようです。帝国書院の「復刻版地図帳」[25914]により記載状況を調べると、1934年版と1950年版には見当たらず、1973年版には記載されています。
鹿児島県の薩南諸島には 作々さんの挙げられた3島群と 三島村所属の上三島が含まれます。1946年に北緯30度線で分断された際に 日本に残った「上三島」[24269]は、現在では大隅諸島に含めることもあるようですが、戦前は「吐喝喇列島(川辺十島)」に含まれていました。なお、草冠のある字は JIS外で表示できないために、作々さんにならって「喝」で代用しました。
ついでに触れておきますが、種子島北端や上三島と同緯度にあるにもかかわらず、草垣群島は薩南諸島に含まれません。薩摩半島西側の笠沙町に属するために“薩南”ではないのでしょう。しかし、甑島列島・宇治群島・草垣群島を総称する“薩西諸島”という呼び名は聞いたことがありません。
【1】脱字修正のついでに補足
種子島等は大隅国なので 大隅諸島と呼ばれるのは 当然として、ここや奄美の島々の総称が “薩南”諸島 であるのは何故でしょうか? 長期にわたる薩摩政権支配の間に“(広義の)薩摩の南部”という認識が生まれていたのでしょうか。
南西諸島ファミリーにおいて、島群の包括関係は 最大4階層の複雑な入れ子構造です。
勿論最初は「日本列島」
ア! 第0階層 日本列島を含めれば5階層でした。
第1階層 南西諸島の内訳=薩南諸島 + 琉球諸島
第2階層 薩南諸島の内訳=大隅諸島 + 上三島 + 吐喝喇列島 + 奄美群島
第2階層 琉球諸島の内訳=沖縄諸島 + 先島諸島 + 大東諸島
第3階層 沖縄諸島の内訳=沖縄島 + 伊平屋伊是名諸島 + 与勝諸島 + 慶良間諸島 + 久米島等
第3階層 先島諸島の内訳=宮古群島 + 八重山群島 + 尖閣列島
島群の呼び名や包括関係については、「島嶼大事典」(日外アソシエーツ1991)の呼び名と包括関係を用いましたが、歴史的な変化があります。
例えば1934年版では、前記のように南西諸島はなくて薩南諸島・琉球(諸島という字が入っていない)になっており、小笠原諸島は現在の小笠原群島の範囲で、同じ大きさの字で硫黄列島が別に存在します。この 1934年版を良く見ると、この 2島群と伊豆七島(現在の伊豆諸島)を含む図のタイトルは「豆南諸島」となっています。
豆南諸島の名は[19744]kenさんに登場し、本を引用した紹介文が記されています。
孀婦岩、須美寿島、ベヨネーズ列岩、鳥島という名前は聞いたことがあるかもしれない。これらの無人島群が豆南諸島。
昔、広い範囲で使われていた「豆南諸島」が、近年のダイバー用語では狭い意味で復活したのでしょうか。
これらの無人島群については、この落書き帳だけで通用する呼び名として、私が命名した「南方四島」[22460]もあります。
そうそう、南方と言えば、伊豆諸島と小笠原諸島の総称としての「南方諸島」の名が平凡社の「日本大地図帳」等に見えます。
これを使うと、南方諸島ファミリーは
第1階層 南方諸島の内訳=伊豆諸島 + 小笠原諸島
第2階層 伊豆諸島の内訳=伊豆七島 + 式根島・青ヶ島・鳥島等
第2階層 小笠原諸島の内訳=小笠原群島 + 硫黄列島 + 西之島等
第3階層 小笠原群島の内訳=聟島列島 + 父島列島 + 母島列島
「復刻版地図帳」に戻って、戦後の1950年版では、ユーラシア図の中に琉球列島・小笠原列島の名が見えます。日本の統治下でなかったので、日本図の部には出ていないのですね。
1973年版になると、現在とほぼ同じ伊豆諸島・小笠原諸島・(やや小さい字で)硫黄諸島になっています。
| [33445] 2004年 9月 26日(日)19:11:38 | hmt さん |
| 島群コレクション関係 | |
上島諸島の読みについては [33439] で記しました。
走島群島の「鴻ノ石島」は「鴻ノ石」(こうのせき)です。
安芸群島の「能見島」は「能美島」の誤記でしょうが、普通は単独ではなく、「江田島・東能美島・西能美島」 http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/200304/shima-hon.htm のような形で使われるようです。
大東諸島の「東大東島」は「北大東島」です。
江ノ島列島…主島自体に「江ノ島」と「江島」の両方の書き方があるようですが、リンクされた地図では江島となっています。
烏帽子列島は松島群島の中に含まれるので、松島群島の「主な島々」に記載したらと思われます。
「主な」に該当するかどうかは疑問ですが。
防予諸島…柱島群島を含むとするのは、地理的には妥当だと考えますが、そのように記された資料はあるでしょうか?
沖縄諸島の「主な島々」に久米島、伊江島を追加するのが適切かと思います。
以下は未収録の島群です。
南方諸島
小学館の「日本列島大地図館」に、伊豆諸島と小笠原諸島の総称としての「南方諸島」の名が見えます。
(hmtが[29851]で平凡社の「日本大地図帳」と書いたのは誤記です。)
また 1946年の使用例ですが、[24274]Issieさん の引用文中に、次の言い方がなされています。
伊豆諸島及び嬬婦岩を含むそれ以北の南方諸島
豆南諸島
[19744]kenさん によると、“孀婦岩を調べていると「豆南諸島」という名称が頻発”するそうです。例えば引用文。
ダイバーなら孀婦岩、須美寿島、ベヨネーズ列岩、鳥島という名前は聞いたことがあるかもしれない。これらの無人島群が豆南諸島。
“釣り関係のサイトにも頻出”しているそうです。
現在の用法では上記のように狭い範囲ですが、かつては現在の伊豆諸島・小笠原諸島の総称として使われていました。例えば帝国書院の「復刻版地図帳」1934年版[29851]。
東京諸島
[24183]で書いたように、あまり聞いたことのない名称ですが、伊豆諸島・小笠原諸島を含めた地域のようです。
東京諸島観光連盟 という用法があります。
走島群島の「鴻ノ石島」は「鴻ノ石」(こうのせき)です。
安芸群島の「能見島」は「能美島」の誤記でしょうが、普通は単独ではなく、「江田島・東能美島・西能美島」 http://www.gsi.go.jp/KOKUJYOHO/MENCHO/200304/shima-hon.htm のような形で使われるようです。
大東諸島の「東大東島」は「北大東島」です。
江ノ島列島…主島自体に「江ノ島」と「江島」の両方の書き方があるようですが、リンクされた地図では江島となっています。
烏帽子列島は松島群島の中に含まれるので、松島群島の「主な島々」に記載したらと思われます。
「主な」に該当するかどうかは疑問ですが。
防予諸島…柱島群島を含むとするのは、地理的には妥当だと考えますが、そのように記された資料はあるでしょうか?
沖縄諸島の「主な島々」に久米島、伊江島を追加するのが適切かと思います。
以下は未収録の島群です。
南方諸島
小学館の「日本列島大地図館」に、伊豆諸島と小笠原諸島の総称としての「南方諸島」の名が見えます。
(hmtが[29851]で平凡社の「日本大地図帳」と書いたのは誤記です。)
また 1946年の使用例ですが、[24274]Issieさん の引用文中に、次の言い方がなされています。
伊豆諸島及び嬬婦岩を含むそれ以北の南方諸島
豆南諸島
[19744]kenさん によると、“孀婦岩を調べていると「豆南諸島」という名称が頻発”するそうです。例えば引用文。
ダイバーなら孀婦岩、須美寿島、ベヨネーズ列岩、鳥島という名前は聞いたことがあるかもしれない。これらの無人島群が豆南諸島。
“釣り関係のサイトにも頻出”しているそうです。
現在の用法では上記のように狭い範囲ですが、かつては現在の伊豆諸島・小笠原諸島の総称として使われていました。例えば帝国書院の「復刻版地図帳」1934年版[29851]。
東京諸島
[24183]で書いたように、あまり聞いたことのない名称ですが、伊豆諸島・小笠原諸島を含めた地域のようです。
東京諸島観光連盟 という用法があります。
| [56162] 2007年 1月 11日(木)22:51:27 | hmt さん |
| 硫黄島からの手紙 | |
沖縄での地上戦の直前、1945年2月~3月に行なわれた激戦で知られる硫黄島が、久しぶりに思い出されています。
読売新聞 によると、硫黄島では、火山活動による隆起により、60年前に米軍が波止場建設のために並べた沈没船が海面上に姿を現しているとのことです。
硫黄島は摺鉢山以外は平坦であり、だからこそ飛行場を確保するために日米の激戦が行なわれたのですが、その南北にある南硫黄島と北硫黄島は、海上に突き出た800~900mの険しい山です。
この硫黄列島は、「火山列島」とも呼ばれますが、特に南硫黄島周辺にある海底火山「福徳岡ノ場」 ([23901]の84)の火山活動では、1904年、1914年、1986年と再三にわたり新島の形成が確認され、「新硫黄島」と呼ばれました。しかし、いずれも数ヶ月ないし数年の寿命で水没しました。参考:2005年海底噴火の写真
火山噴火による新しい国土の誕生はめったにありませんが、硫黄列島(24~25N)の北への延長線上(27N)にある西之島に隣接した場所で、1973年の海底噴火により新島が誕生し、「西之島新島」と名付けられました。翌年には更に拡がって旧島と接続し、1977年には湾口が閉じるなど、完全に一体化しましたが、波浪による侵食を受けているようです。海洋情報部
火山活動で何度か新島が形成され、自らの爆発や波浪の浸食で消滅する例は、更に北の「明神礁」でも繰り返され、青ヶ島からも遠望できたそうです。1952年の観測船・第五海洋丸の遭難事件は有名で、この後に登場した「ゴジラ」でも、その仕業かと疑われています。
明神礁カルデラ の外輪山・ベヨネース列岩(南方四島[22460])は1846年に発見したフランス軍艦の名に由来するようですが、別名の「ハロース」は外来語ではなく、“波浪の巣”とか。
火山の話はこのくらいにして硫黄島に戻ると、ここには米国と開戦する前年・1940年に町村制が施行されて「硫黄島村」 が生まれていました。
# “島嶼町村制施行”と書いてありますが、この勅令はこの1940年に廃止されているので、“町村制施行”の誤記だと思います。
硫黄島定住の歴史を遡ると、1889年に父島の漁師が入植するも挫折。その後、硫黄採掘も試みられ、1891年小笠原島庁の所管になった後、入植者が定住したのは1904年。硫黄島の人口は1915年679名、1921年1039名、1940年1164名というから、結構にぎわっていたのに驚きます。
第二次大戦では小笠原は軍事基地化され、米軍侵攻の危険が迫った1944年には、一般島民の強制引揚げに伴ない、戦前の村々(父島、母島、硫黄島の合計5村)は現地から姿を消しました。但し、村役場と小笠原支庁は東京に移って存続しました。
小笠原支庁と村役場が廃止されたのは、平和条約の発効により、小笠原が正式に米国の信託統治領になった1952年とのことです。現在の北方領土6村のような形式的に存在する村というよりも、旧島民を対象とする避難状態(先年の三宅村と同様?)が続いていたのかもしれません。
父島・母島も空襲と艦砲射撃を受けましたが、沖縄のような民間人を巻き込む悲劇は回避されました。
余談:父島の爆撃に従事していた(パパ)ブッシュ中尉は、乗機が対空砲火により撃墜され、漂流後に潜水艦に救出された由。Biography
読売新聞 によると、硫黄島では、火山活動による隆起により、60年前に米軍が波止場建設のために並べた沈没船が海面上に姿を現しているとのことです。
硫黄島は摺鉢山以外は平坦であり、だからこそ飛行場を確保するために日米の激戦が行なわれたのですが、その南北にある南硫黄島と北硫黄島は、海上に突き出た800~900mの険しい山です。
この硫黄列島は、「火山列島」とも呼ばれますが、特に南硫黄島周辺にある海底火山「福徳岡ノ場」 ([23901]の84)の火山活動では、1904年、1914年、1986年と再三にわたり新島の形成が確認され、「新硫黄島」と呼ばれました。しかし、いずれも数ヶ月ないし数年の寿命で水没しました。参考:2005年海底噴火の写真
火山噴火による新しい国土の誕生はめったにありませんが、硫黄列島(24~25N)の北への延長線上(27N)にある西之島に隣接した場所で、1973年の海底噴火により新島が誕生し、「西之島新島」と名付けられました。翌年には更に拡がって旧島と接続し、1977年には湾口が閉じるなど、完全に一体化しましたが、波浪による侵食を受けているようです。海洋情報部
火山活動で何度か新島が形成され、自らの爆発や波浪の浸食で消滅する例は、更に北の「明神礁」でも繰り返され、青ヶ島からも遠望できたそうです。1952年の観測船・第五海洋丸の遭難事件は有名で、この後に登場した「ゴジラ」でも、その仕業かと疑われています。
明神礁カルデラ の外輪山・ベヨネース列岩(南方四島[22460])は1846年に発見したフランス軍艦の名に由来するようですが、別名の「ハロース」は外来語ではなく、“波浪の巣”とか。
火山の話はこのくらいにして硫黄島に戻ると、ここには米国と開戦する前年・1940年に町村制が施行されて「硫黄島村」 が生まれていました。
# “島嶼町村制施行”と書いてありますが、この勅令はこの1940年に廃止されているので、“町村制施行”の誤記だと思います。
硫黄島定住の歴史を遡ると、1889年に父島の漁師が入植するも挫折。その後、硫黄採掘も試みられ、1891年小笠原島庁の所管になった後、入植者が定住したのは1904年。硫黄島の人口は1915年679名、1921年1039名、1940年1164名というから、結構にぎわっていたのに驚きます。
第二次大戦では小笠原は軍事基地化され、米軍侵攻の危険が迫った1944年には、一般島民の強制引揚げに伴ない、戦前の村々(父島、母島、硫黄島の合計5村)は現地から姿を消しました。但し、村役場と小笠原支庁は東京に移って存続しました。
小笠原支庁と村役場が廃止されたのは、平和条約の発効により、小笠原が正式に米国の信託統治領になった1952年とのことです。現在の北方領土6村のような形式的に存在する村というよりも、旧島民を対象とする避難状態(先年の三宅村と同様?)が続いていたのかもしれません。
父島・母島も空襲と艦砲射撃を受けましたが、沖縄のような民間人を巻き込む悲劇は回避されました。
余談:父島の爆撃に従事していた(パパ)ブッシュ中尉は、乗機が対空砲火により撃墜され、漂流後に潜水艦に救出された由。Biography
| [59286] 2007年 6月 20日(水)14:11:21 | hmt さん |
| 「硫黄島」-その読み方の変遷史- | |
[59223] ほいほい さん
国土地理院が硫黄島の呼称を「いおうとう」に変更したそうです。
小笠原諸島地名事典 を参照しつつ、「硫黄島」の読み方の変遷を考察します。
最初は、イギリスの船乗りが「Sulphur Island」と名付け、幕府も「硫黄島」(おそらく「いおうじま」)と呼んだとのこと。
正式の命名は、明治24年9月9日勅令第190号 で、
東京府管下小笠原島南西沖(中略)に散在する3島嶼を小笠原島の所属とし其中央に在るものを硫黄島と(中略)称す
となっています。この勅令では読み方は明示されていませんが、「いおうじま」とルビをつけた新聞もあった由。
日本の大部分の島名では「島」を訓読みするので、初代の呼称は「いおうじま」だったと考えるのが自然でしょう。
旧海軍水路部がこの付近の海図を作製した年代はわかりませんが、アメリカ軍が「Iwo Jima」と呼んだのは、海図に記されたローマ字表記に基づくものとされます。
入植者が定着するようになったのは20世紀に入った1904年で、大戦前には人口が1000人以上という賑わいを見せ、1940年には「硫黄島村」も誕生しました[56162]。
この現地開拓者たちの間では「いおうとう」の呼び名が定着し、学校名や会社名もそのように呼んだということで(硫黄島同窓会)、村の名もそのように呼ばれたと思われます。
つまり、19世紀の「いおうじま」から、20世紀には(陸地の呼称は)2代目の「いおうとう」へと変りました。
硫黄島は、B29の基地があったテニアン島(マリアナ諸島)などに比べるとずっと小さな島であり、大規模な空軍基地はできませんが、摺鉢山以外は平坦であり、謂わばマリアナ諸島と日本との間にある貴重な「不沈空母」です。日本側にとっては哨戒・迎撃・マリアナ米軍基地の攻撃、長距離爆撃の米軍側にはB29不時着地の確保と、双方にとり軍事的価値がありました。
大戦末期になると、この島の確保を狙う米軍に対する守備隊が増強され、日本陸海軍だけでも2万人になりました。
この陸海軍も、現地住民と同じく「いおうとう」を使ったということで、[56190]で記した
当時の大本営発表では「いおうとう」でした。(中略)軍隊方言のせいでしょうか?
の最初の部分は正しく、後の推測は外れていたようです。
「Iwo Jima」に対す猛攻撃を加えた米軍に敗れた「いおうとう」の守備隊が玉砕したのは1945年3月。
米軍による占領→米国の信託統治領(1952)を経て日本復帰(1968)。復帰直後の地形図では「いおうとう」だったものが、「標準地名集」[53057]の1981年版では3代目の呼称「いおうじま」に変更されたとのことです。
[59277] Issie さん
新聞報道によると,「いおうとう」が「いおうじま」になってしまったのには「占領軍」が絡んでいるそうですね。
確かに、日刊スポーツ には、
明治時代から一部で「いおうじま」と呼ばれていたが、戦中から米軍などがこう呼んだことから、政府の関係省庁などに定着したとの説が強い。
と書いてありました。
しかし、占領時代がずっと過去のものになった時代の「標準地名集」での変更は、占領軍絡みよりも、海上保安庁水路部の 海図 (たぶん明治時代から一貫して「いおうじま」)と国土地理院の地形図とを整合させた結果 と見る方が妥当な解釈ではないでしょうか。
1980年頃から陸の呼び名も海に合わせて「いおうじま」に変りましたが、世間の注目は集めませんでした。
ところが、映画のおかげで突然「いおうじま」が話題になります(2006年)。
これが、寝ていた子を起こすことになり、小笠原村にいる硫黄島旧住民を中心に「いおうとう」だという声が沸き起こったのだと思われます。
国土地理院の発表 でも、“地元で旧島民が「いおうとう」と呼んでいた背景”に基づく、小笠原村からの修正要望に応じたものとされています。
# 小笠原村の管内ですが、現在は一般住民不在。海上自衛隊基地。
かくして、陸では4代目の呼称として「いおうとう」が復活。
海図も、明治以来の「いおうじま」から「いおうとう」へと変更。
「居住地名」は「地名調書」に拠るが、「自然地名」は必ずしも地元の小笠原村の作成した「地名調書」の通りにはならない[56419]という状態を続けていたのですが、この度は地元の要望を容れて、「いおうとう」に戻したというのは、何か格別の事情もあったのか?とも思われます。
以上、硫黄島の読み方の変遷史を綴ってみました。
おまけ
[59270] スピカ さん
鹿児島県三島村を構成する3島の1つを「硫黄島」と言い、こちらは「いおうじま」と読むそうです。
南九州の縄文早期文化を壊滅させた、6300年前の大噴火[24108]の跡を残す鬼界カルデラ の北縁・鹿児島県三島村の硫黄島(鬼界ヶ島)[56250] は、火山の名としては、「薩摩硫黄島」 と呼ばれます。[23902]のNo.102
1934年(昭和9年)から翌年にかけて、この火山で海底噴火があり、形成された岩礁は「昭和硫黄島」を形成しています。
同様に小さな岩礁ですが、地名コレクション収録の安永諸島[40149](桜島火山)の中にも、小さな硫黄島 があります。これも「いおうじま」。
沖縄県久米島町の「硫黄鳥島」の所属に関する記事[28741]もあります。
国土地理院が硫黄島の呼称を「いおうとう」に変更したそうです。
小笠原諸島地名事典 を参照しつつ、「硫黄島」の読み方の変遷を考察します。
最初は、イギリスの船乗りが「Sulphur Island」と名付け、幕府も「硫黄島」(おそらく「いおうじま」)と呼んだとのこと。
正式の命名は、明治24年9月9日勅令第190号 で、
東京府管下小笠原島南西沖(中略)に散在する3島嶼を小笠原島の所属とし其中央に在るものを硫黄島と(中略)称す
となっています。この勅令では読み方は明示されていませんが、「いおうじま」とルビをつけた新聞もあった由。
日本の大部分の島名では「島」を訓読みするので、初代の呼称は「いおうじま」だったと考えるのが自然でしょう。
旧海軍水路部がこの付近の海図を作製した年代はわかりませんが、アメリカ軍が「Iwo Jima」と呼んだのは、海図に記されたローマ字表記に基づくものとされます。
入植者が定着するようになったのは20世紀に入った1904年で、大戦前には人口が1000人以上という賑わいを見せ、1940年には「硫黄島村」も誕生しました[56162]。
この現地開拓者たちの間では「いおうとう」の呼び名が定着し、学校名や会社名もそのように呼んだということで(硫黄島同窓会)、村の名もそのように呼ばれたと思われます。
つまり、19世紀の「いおうじま」から、20世紀には(陸地の呼称は)2代目の「いおうとう」へと変りました。
硫黄島は、B29の基地があったテニアン島(マリアナ諸島)などに比べるとずっと小さな島であり、大規模な空軍基地はできませんが、摺鉢山以外は平坦であり、謂わばマリアナ諸島と日本との間にある貴重な「不沈空母」です。日本側にとっては哨戒・迎撃・マリアナ米軍基地の攻撃、長距離爆撃の米軍側にはB29不時着地の確保と、双方にとり軍事的価値がありました。
大戦末期になると、この島の確保を狙う米軍に対する守備隊が増強され、日本陸海軍だけでも2万人になりました。
この陸海軍も、現地住民と同じく「いおうとう」を使ったということで、[56190]で記した
当時の大本営発表では「いおうとう」でした。(中略)軍隊方言のせいでしょうか?
の最初の部分は正しく、後の推測は外れていたようです。
「Iwo Jima」に対す猛攻撃を加えた米軍に敗れた「いおうとう」の守備隊が玉砕したのは1945年3月。
米軍による占領→米国の信託統治領(1952)を経て日本復帰(1968)。復帰直後の地形図では「いおうとう」だったものが、「標準地名集」[53057]の1981年版では3代目の呼称「いおうじま」に変更されたとのことです。
[59277] Issie さん
新聞報道によると,「いおうとう」が「いおうじま」になってしまったのには「占領軍」が絡んでいるそうですね。
確かに、日刊スポーツ には、
明治時代から一部で「いおうじま」と呼ばれていたが、戦中から米軍などがこう呼んだことから、政府の関係省庁などに定着したとの説が強い。
と書いてありました。
しかし、占領時代がずっと過去のものになった時代の「標準地名集」での変更は、占領軍絡みよりも、海上保安庁水路部の 海図 (たぶん明治時代から一貫して「いおうじま」)と国土地理院の地形図とを整合させた結果 と見る方が妥当な解釈ではないでしょうか。
1980年頃から陸の呼び名も海に合わせて「いおうじま」に変りましたが、世間の注目は集めませんでした。
ところが、映画のおかげで突然「いおうじま」が話題になります(2006年)。
これが、寝ていた子を起こすことになり、小笠原村にいる硫黄島旧住民を中心に「いおうとう」だという声が沸き起こったのだと思われます。
国土地理院の発表 でも、“地元で旧島民が「いおうとう」と呼んでいた背景”に基づく、小笠原村からの修正要望に応じたものとされています。
# 小笠原村の管内ですが、現在は一般住民不在。海上自衛隊基地。
かくして、陸では4代目の呼称として「いおうとう」が復活。
海図も、明治以来の「いおうじま」から「いおうとう」へと変更。
「居住地名」は「地名調書」に拠るが、「自然地名」は必ずしも地元の小笠原村の作成した「地名調書」の通りにはならない[56419]という状態を続けていたのですが、この度は地元の要望を容れて、「いおうとう」に戻したというのは、何か格別の事情もあったのか?とも思われます。
以上、硫黄島の読み方の変遷史を綴ってみました。
おまけ
[59270] スピカ さん
鹿児島県三島村を構成する3島の1つを「硫黄島」と言い、こちらは「いおうじま」と読むそうです。
南九州の縄文早期文化を壊滅させた、6300年前の大噴火[24108]の跡を残す鬼界カルデラ の北縁・鹿児島県三島村の硫黄島(鬼界ヶ島)[56250] は、火山の名としては、「薩摩硫黄島」 と呼ばれます。[23902]のNo.102
1934年(昭和9年)から翌年にかけて、この火山で海底噴火があり、形成された岩礁は「昭和硫黄島」を形成しています。
同様に小さな岩礁ですが、地名コレクション収録の安永諸島[40149](桜島火山)の中にも、小さな硫黄島 があります。これも「いおうじま」。
沖縄県久米島町の「硫黄鳥島」の所属に関する記事[28741]もあります。
| [74102] 2010年 2月 5日(金)12:57:32【1】 | hmt さん |
| 火山名:福徳岡ノ場、別名:新硫黄島 | |
[74100] JOUTOU さん
南硫黄島近海で白煙、新島出現の可能性も(2月4日読売新聞)
少し気が早いのですが、仮にこの場所(硫黄島と南硫黄島の間)に新島ができたとしたら、何と命名するのか興味があります。
南硫黄島 は 東京の南 1200km以上。伊豆諸島・小笠原諸島と連なる島々の最南端です。その先はマリアナ諸島。
高さ 916mもあり、171mの大槌島[72964]よりも はるかに大きい 「海のピラミッド」は、手付かずの自然が残された 貴重な存在のようです。
2007年、硫黄島の読み方変更[59286] に合せて、こちらも「みなみいおうじま」から「みなみいおうとう」になりました。
なお、沖ノ鳥島と南鳥島とは、行政的には 東京都小笠原村に属していますが、地理的には 伊豆・小笠原からグアム島へと続く島列の西と東に およそ 1000kmも 離れています。
その南硫黄島の北東約5kmにある「福徳岡ノ場」([23901]の84)では、1904年以来、海底火山活動が繰り返し観測されており、最近では2005年の活動に際して [42817] KK さん の記事がありました。
1904年~1905年にかけてと 1914年~1916年にかけて、それに 1986年には新島「新硫黄島」が出現しています。とくに 1914年の噴火で出現した新島は高さ300m、周囲11.8kmと相当大きな島でしたが、残念ながら2年後には水没しています。
この記事にあるように、過去に島ができており、「新硫黄島」という名で呼ばれていました。
海洋情報部の 海域火山DB から 福徳岡ノ場 に入ると、“日本火山学会発行第四紀火山カタログより”として、“火山名:福徳岡ノ場、別名:新硫黄島”の概要が記されているので、関係者の間ではある程度認められた名前なのでしょう。
【追記】
「日本の第四紀火山カタログ」のWEB版[24080]を思い出し、“別名 新硫黄島”の記載を 原データ により確認。
火山噴出物により海の一部が陸地になり、日本の国土面積が増加するというのは、気分的には 楽しいことです。
しかし、火山の噴火で生まれた新島は、現実には 直ちに利用できる土地ではなく、災害の可能性も伴なう、どちらかというとマイナス面が目立つ自然現象です。
1914年(大正3年)の 桜島噴火 では、南東側火口からの溶岩は海を埋め、1月29日に桜島が大隅半島と陸続きになりました。しかし、北西や西側の集落が蒙った火砕流・溶岩流被害は甚大なものでした。
桜島の昭和溶岩流(1946)、島原市を襲った雲仙平成火砕流(1991)も海岸に達し、少しは日本の面積増加に寄与したかもしれませんが、もちろん被害の方が大でした。
今回の伊豆小笠原海域における海底噴火が報道される理由も、青ヶ島の南に出現した明神礁における第五海洋丸遭難(1952年)【 [23960]の75】 のような海難事故の防止が最大の眼目でしょう。
明神礁の外輪山は、ベヨネース列岩(19世紀にフランス船が命名)ですが、その別名は「ハロース」(波浪の巣)です。
火山で生まれてくる岩礁には、天敵として待ち構える波浪の攻撃にさらされる運命が待っており、自らの爆発でも破壊されます。
「明神礁」は 噴火を報告した漁船に因む名ですが、新しい島は 名前だけを残して 短期間で水没しました。
調査船の全乗員31名殉職という明神礁事件は、1954年の映画「ゴジラ」の中でも取り上げられていました。
大島・三宅島・御蔵島・八丈島・青ヶ島・ベヨネース列岩・鳥島の線を南に延長すると、父島などのある小笠原列島の線よりも少し西に外れた西之島を経て、火山列島(硫黄列島)に至ります。
その西之島近海の海底噴火で 1973年に形成された 西之島新島 は、翌年には更に拡がって西之島と繋がりましたが、国土面積に正式に編入されたのは 1988年でした[57361]。かなり長い間の様子を見て、永続的な陸地と認定されたのでしょう。
この島も波浪による侵食を受け続けていますが、20世紀生まれで、辛うじて生き残った貴重な存在です。[23960]の79
西之島もベヨネース列岩も間違いなく日本の領土ですが、南方四島[22460] 最大の島で、かつては気象観測が行われた鳥島でさえ 現在は利用はされていない のが現状です。[23960]の77
南硫黄島近海で白煙、新島出現の可能性も(2月4日読売新聞)
少し気が早いのですが、仮にこの場所(硫黄島と南硫黄島の間)に新島ができたとしたら、何と命名するのか興味があります。
南硫黄島 は 東京の南 1200km以上。伊豆諸島・小笠原諸島と連なる島々の最南端です。その先はマリアナ諸島。
高さ 916mもあり、171mの大槌島[72964]よりも はるかに大きい 「海のピラミッド」は、手付かずの自然が残された 貴重な存在のようです。
2007年、硫黄島の読み方変更[59286] に合せて、こちらも「みなみいおうじま」から「みなみいおうとう」になりました。
なお、沖ノ鳥島と南鳥島とは、行政的には 東京都小笠原村に属していますが、地理的には 伊豆・小笠原からグアム島へと続く島列の西と東に およそ 1000kmも 離れています。
その南硫黄島の北東約5kmにある「福徳岡ノ場」([23901]の84)では、1904年以来、海底火山活動が繰り返し観測されており、最近では2005年の活動に際して [42817] KK さん の記事がありました。
1904年~1905年にかけてと 1914年~1916年にかけて、それに 1986年には新島「新硫黄島」が出現しています。とくに 1914年の噴火で出現した新島は高さ300m、周囲11.8kmと相当大きな島でしたが、残念ながら2年後には水没しています。
この記事にあるように、過去に島ができており、「新硫黄島」という名で呼ばれていました。
海洋情報部の 海域火山DB から 福徳岡ノ場 に入ると、“日本火山学会発行第四紀火山カタログより”として、“火山名:福徳岡ノ場、別名:新硫黄島”の概要が記されているので、関係者の間ではある程度認められた名前なのでしょう。
【追記】
「日本の第四紀火山カタログ」のWEB版[24080]を思い出し、“別名 新硫黄島”の記載を 原データ により確認。
火山噴出物により海の一部が陸地になり、日本の国土面積が増加するというのは、気分的には 楽しいことです。
しかし、火山の噴火で生まれた新島は、現実には 直ちに利用できる土地ではなく、災害の可能性も伴なう、どちらかというとマイナス面が目立つ自然現象です。
1914年(大正3年)の 桜島噴火 では、南東側火口からの溶岩は海を埋め、1月29日に桜島が大隅半島と陸続きになりました。しかし、北西や西側の集落が蒙った火砕流・溶岩流被害は甚大なものでした。
桜島の昭和溶岩流(1946)、島原市を襲った雲仙平成火砕流(1991)も海岸に達し、少しは日本の面積増加に寄与したかもしれませんが、もちろん被害の方が大でした。
今回の伊豆小笠原海域における海底噴火が報道される理由も、青ヶ島の南に出現した明神礁における第五海洋丸遭難(1952年)【 [23960]の75】 のような海難事故の防止が最大の眼目でしょう。
明神礁の外輪山は、ベヨネース列岩(19世紀にフランス船が命名)ですが、その別名は「ハロース」(波浪の巣)です。
火山で生まれてくる岩礁には、天敵として待ち構える波浪の攻撃にさらされる運命が待っており、自らの爆発でも破壊されます。
「明神礁」は 噴火を報告した漁船に因む名ですが、新しい島は 名前だけを残して 短期間で水没しました。
調査船の全乗員31名殉職という明神礁事件は、1954年の映画「ゴジラ」の中でも取り上げられていました。
大島・三宅島・御蔵島・八丈島・青ヶ島・ベヨネース列岩・鳥島の線を南に延長すると、父島などのある小笠原列島の線よりも少し西に外れた西之島を経て、火山列島(硫黄列島)に至ります。
その西之島近海の海底噴火で 1973年に形成された 西之島新島 は、翌年には更に拡がって西之島と繋がりましたが、国土面積に正式に編入されたのは 1988年でした[57361]。かなり長い間の様子を見て、永続的な陸地と認定されたのでしょう。
この島も波浪による侵食を受け続けていますが、20世紀生まれで、辛うじて生き残った貴重な存在です。[23960]の79
西之島もベヨネース列岩も間違いなく日本の領土ですが、南方四島[22460] 最大の島で、かつては気象観測が行われた鳥島でさえ 現在は利用はされていない のが現状です。[23960]の77
| [344] 2001年 8月 30日(木)20:53:54 | Issie さん |
| 沖ノ鳥島 | |
>全都道府県に関してこういうのを集めよう。
とりあえず“暫定公開”しておきます。
http://www.tt.rim.or.jp/~ishato/tiri/kubun/kubun.htm
「県の下位区分」
凡例その他の説明文は,まだ未完成ですが,一応全都道府県分のデータがあります。
ご参考までに。
>あと、沖の鳥島は領土と認められるのでしょうか。国際法上の疑義はないのでしょうか。
これは,ないはずです。
沖ノ鳥島全体は珊瑚礁でほとんどが海面下にあるのですが,満潮時でも常時海面上にでている岩礁があって,これが国際法上の「領土」とされています。
これが波の侵食でなくなりそうになったのであわてて護岸工事をしたのです。
領有関係についても問題はないでしょう。
小笠原諸島の本体部(父島・母島など)については最初に定住したのがハワイ人であったにもかかわらず,19世紀末にイギリスや(すでにハワイを併合した)アメリカ合衆国の承認の下で日本による領有が認められています。
信州の戦国大名・小笠原家の家臣が発見したという「伝説」はともかく,最初にヨーロッパへ紹介したであろうポルトガルやスペインも(沖ノ鳥島の国際名はポルトガル語であるそうです)これに異議を唱えていません。
この延長で,南鳥島や沖ノ鳥島は1920年代末に「東京府小笠原支庁小笠原村」に編入されました。
太平洋戦争後,この領域を占領していたアメリカ合衆国から1968年に“返還”された後,日本政府は当然に沖ノ鳥島が日本の領土であると主張していますが,これに対してアメリカ合衆国は異議を唱えていません。
竹島や尖閣諸島とは違って,(少なくとも今のところは)日本以外のどの国もこの「島」の領有を主張していませんから,
ここが日本領であることは国際的に承認されていると理解されているはずです。
とりあえず“暫定公開”しておきます。
http://www.tt.rim.or.jp/~ishato/tiri/kubun/kubun.htm
「県の下位区分」
凡例その他の説明文は,まだ未完成ですが,一応全都道府県分のデータがあります。
ご参考までに。
>あと、沖の鳥島は領土と認められるのでしょうか。国際法上の疑義はないのでしょうか。
これは,ないはずです。
沖ノ鳥島全体は珊瑚礁でほとんどが海面下にあるのですが,満潮時でも常時海面上にでている岩礁があって,これが国際法上の「領土」とされています。
これが波の侵食でなくなりそうになったのであわてて護岸工事をしたのです。
領有関係についても問題はないでしょう。
小笠原諸島の本体部(父島・母島など)については最初に定住したのがハワイ人であったにもかかわらず,19世紀末にイギリスや(すでにハワイを併合した)アメリカ合衆国の承認の下で日本による領有が認められています。
信州の戦国大名・小笠原家の家臣が発見したという「伝説」はともかく,最初にヨーロッパへ紹介したであろうポルトガルやスペインも(沖ノ鳥島の国際名はポルトガル語であるそうです)これに異議を唱えていません。
この延長で,南鳥島や沖ノ鳥島は1920年代末に「東京府小笠原支庁小笠原村」に編入されました。
太平洋戦争後,この領域を占領していたアメリカ合衆国から1968年に“返還”された後,日本政府は当然に沖ノ鳥島が日本の領土であると主張していますが,これに対してアメリカ合衆国は異議を唱えていません。
竹島や尖閣諸島とは違って,(少なくとも今のところは)日本以外のどの国もこの「島」の領有を主張していませんから,
ここが日本領であることは国際的に承認されていると理解されているはずです。
| [26266] 2004年 3月 16日(火)13:58:00 | hmt さん |
| 岩の上に鳥が止まる広さがあれば「島」 | |
白川静「字統」より
「島・嶋」…もと海鳥の住む岩島をいう字。その大なるものを島といい、小なるものを嶼という。
[26206]では「島」を認定するにあたって考慮に入れる要素として、人手の関与や越えるべき水面を取り上げました。今回は島の大きさです。
「島」は「大陸」や「本土」に対する相対的概念で、その大きさの上限はほぼ明らかです。
世界的にはオーストラリアとグリーンランドとの間、国内では四国と択捉島の間に上限が引かれています。目的によっては沖縄本島と佐渡島との間で区別することもあるようです。
カナダ北端のエルズミア島。これは面積については本州と同じくらいの大きな島ですが住民は極めて少なく、離島扱いでしょうね。
問題は下限です。二見の夫婦岩は「島」なのか?
夫婦岩は島であろうとなかろうと観光的価値に変りがないでしょうが、「島」であるか否かで経済的価値が大きく変るのが沖ノ鳥島です。
日本政府は「沖ノ鳥島は島である」として、領海12海里および排他的経済水域 EEZ=exclusive economic zone 200海里を主張しています。沖ノ鳥島の存在は、日本の国土面積を上回る40万km2のEEZを我が国にもたらしています。
[26206]で引用した「国連海洋法条約」の島の定義は、1958年の領海条約の定義を踏襲したものですが、これが人工島を排除したわけは、海洋の経済的利用に関係するためでした。この条約は121条第1項の「自然に形成された陸地」の他にも第60条第8項で「人工島、施設及び構築物は、島の地位を有しない」と駄目押しをする念の入れようです。
しかし、この定義に大きさの規定は直接にはありません。だから「高潮時においても水面上にあれば、どんな小さな岩でも島である」ということになり、「水面上」を維持するために300億円を投じた護岸工事も行なわれました。
ところがこの条約の121条第3項には「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない」という規定があり、鳥が止まれても人が住めないような岩は(基線=低潮線から12海里の領海はOKでも)200海里のEEZ はダメとされているようです
沖ノ鳥島の排他的経済水域について1999年の国会質問での政府答弁がありますが、何となく苦しい感じです。 http://homepage3.nifty.com/boumurou/island/sp01/law.html 参照。
では、この「島」の実態は? というわけで写真を探したら……
ありました! http://vldb.gsi.go.jp/cgi/tr_table.pl?410 東露岩にある「一等三角点」(北露岩には三等三角点がある)。でも三角測量をするには3つの三角点が必要なのではないかな?
それはともかく、一番下の写真、コンクリートで固められた岩の小さいこと。まさに鳥が止まるのがやっと という大きさでした。これを「島」であると主張する日本政府の勇気に感服!
ところで、最初の位置図にあるように2つの露岩は東西に並んでいるのに東露岩と北露岩。なぜ?
実は西側に北露岩と南露岩があったのです。南露岩はキノコ状の岩が波浪で倒壊した状態で発見され、1937~1938年頃に波浪に流されて消失したようです。
このような事例もあるので、現在は辛うじて水面上を維持している2つの岩も危ない…というわけで実施されたのが1989年に完成した護岸工事でした。
http://www.takagigumi.jp/step17.html によると、略最高高潮面からの高さ僅かに16cmと6cmだったキノコ状の岩の周囲を消波ブロックと特殊なコンクリートで固めたとあります。一等三角点のある東露岩には、更にチタン製のフタをかぶせるという過保護ぶりです。
ほんの小さな岩ですが、200海里を確保しようと努力すると金食い虫になります。護岸の維持は本来自治体の仕事ですが、東京都にとってもその負担は大変というわけで、改正海岸法を受けた政令(1999/6/18)により、国の費用全額負担で直轄管理をすることになったそうです。 http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00037/k00290/river-hp/kasen/forefront/sea/0008.html
「国の直轄管理」と言われると、この“現代の天領”と自治体の小笠原村や東京都との関係がどうなったのか気になりますが、東京都に代わって国(建設省、現 国土交通省)が海岸の管理をするという意味で、東京都小笠原村沖ノ鳥島であることに変更はないようです。
沖ノ鳥島にあるのは護岸工事を施された2つの岩だけでしょうか?
いやいや http://homepage2.nifty.com/shot/okinotori.htm には、なんと3階建ての建物のある人工地盤が写っています。ここは重要な気象観測基地(無人)で、2003年2月までは ネットでリアルタイム気象観測データが公開されていました。
海岸保全に加えてこのような利用を含む実効支配の実績は、先に問題になった条約121条第3項の「経済的生活の維持」を裏付けるものとして役に立つのかもしれません。
海面上の岩のことばかり気にしていると沖ノ鳥島は小さな存在のように思われますが、海面下の実態は 深海からそびえ立つ雄大な海山です。
1996年の調査により、最終間氷期に形成された12万5000年前の珊瑚礁が、最終氷期に下降した海面レベルまで浸蝕され、更に7500年の温暖期に海中に沈んで、上にできた新しい珊瑚礁が現在の海面近くにほぼ平らな頂上を形成していることがわかりました。
海面上の小さな岩は、富士山の白雪や笠雲のような珊瑚礁で上部を覆われた古い巨大な山体の頂が、海上に突き出たものなのでした。
日本最南端の沖ノ鳥島のことを書いているうちに、幻の日本最東端の島 (サンズイのない)「中ノ鳥島」の存在(実は不存在)を知りました。
興味のある方は http://homepage3.nifty.com/boumurou/island/01/ganges.html をどうぞ。
「島・嶋」…もと海鳥の住む岩島をいう字。その大なるものを島といい、小なるものを嶼という。
[26206]では「島」を認定するにあたって考慮に入れる要素として、人手の関与や越えるべき水面を取り上げました。今回は島の大きさです。
「島」は「大陸」や「本土」に対する相対的概念で、その大きさの上限はほぼ明らかです。
世界的にはオーストラリアとグリーンランドとの間、国内では四国と択捉島の間に上限が引かれています。目的によっては沖縄本島と佐渡島との間で区別することもあるようです。
カナダ北端のエルズミア島。これは面積については本州と同じくらいの大きな島ですが住民は極めて少なく、離島扱いでしょうね。
問題は下限です。二見の夫婦岩は「島」なのか?
夫婦岩は島であろうとなかろうと観光的価値に変りがないでしょうが、「島」であるか否かで経済的価値が大きく変るのが沖ノ鳥島です。
日本政府は「沖ノ鳥島は島である」として、領海12海里および排他的経済水域 EEZ=exclusive economic zone 200海里を主張しています。沖ノ鳥島の存在は、日本の国土面積を上回る40万km2のEEZを我が国にもたらしています。
[26206]で引用した「国連海洋法条約」の島の定義は、1958年の領海条約の定義を踏襲したものですが、これが人工島を排除したわけは、海洋の経済的利用に関係するためでした。この条約は121条第1項の「自然に形成された陸地」の他にも第60条第8項で「人工島、施設及び構築物は、島の地位を有しない」と駄目押しをする念の入れようです。
しかし、この定義に大きさの規定は直接にはありません。だから「高潮時においても水面上にあれば、どんな小さな岩でも島である」ということになり、「水面上」を維持するために300億円を投じた護岸工事も行なわれました。
ところがこの条約の121条第3項には「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域又は大陸棚を有しない」という規定があり、鳥が止まれても人が住めないような岩は(基線=低潮線から12海里の領海はOKでも)200海里のEEZ はダメとされているようです
沖ノ鳥島の排他的経済水域について1999年の国会質問での政府答弁がありますが、何となく苦しい感じです。 http://homepage3.nifty.com/boumurou/island/sp01/law.html 参照。
では、この「島」の実態は? というわけで写真を探したら……
ありました! http://vldb.gsi.go.jp/cgi/tr_table.pl?410 東露岩にある「一等三角点」(北露岩には三等三角点がある)。でも三角測量をするには3つの三角点が必要なのではないかな?
それはともかく、一番下の写真、コンクリートで固められた岩の小さいこと。まさに鳥が止まるのがやっと という大きさでした。これを「島」であると主張する日本政府の勇気に感服!
ところで、最初の位置図にあるように2つの露岩は東西に並んでいるのに東露岩と北露岩。なぜ?
実は西側に北露岩と南露岩があったのです。南露岩はキノコ状の岩が波浪で倒壊した状態で発見され、1937~1938年頃に波浪に流されて消失したようです。
このような事例もあるので、現在は辛うじて水面上を維持している2つの岩も危ない…というわけで実施されたのが1989年に完成した護岸工事でした。
http://www.takagigumi.jp/step17.html によると、略最高高潮面からの高さ僅かに16cmと6cmだったキノコ状の岩の周囲を消波ブロックと特殊なコンクリートで固めたとあります。一等三角点のある東露岩には、更にチタン製のフタをかぶせるという過保護ぶりです。
ほんの小さな岩ですが、200海里を確保しようと努力すると金食い虫になります。護岸の維持は本来自治体の仕事ですが、東京都にとってもその負担は大変というわけで、改正海岸法を受けた政令(1999/6/18)により、国の費用全額負担で直轄管理をすることになったそうです。 http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00037/k00290/river-hp/kasen/forefront/sea/0008.html
「国の直轄管理」と言われると、この“現代の天領”と自治体の小笠原村や東京都との関係がどうなったのか気になりますが、東京都に代わって国(建設省、現 国土交通省)が海岸の管理をするという意味で、東京都小笠原村沖ノ鳥島であることに変更はないようです。
沖ノ鳥島にあるのは護岸工事を施された2つの岩だけでしょうか?
いやいや http://homepage2.nifty.com/shot/okinotori.htm には、なんと3階建ての建物のある人工地盤が写っています。ここは重要な気象観測基地(無人)で、2003年2月までは ネットでリアルタイム気象観測データが公開されていました。
海岸保全に加えてこのような利用を含む実効支配の実績は、先に問題になった条約121条第3項の「経済的生活の維持」を裏付けるものとして役に立つのかもしれません。
海面上の岩のことばかり気にしていると沖ノ鳥島は小さな存在のように思われますが、海面下の実態は 深海からそびえ立つ雄大な海山です。
1996年の調査により、最終間氷期に形成された12万5000年前の珊瑚礁が、最終氷期に下降した海面レベルまで浸蝕され、更に7500年の温暖期に海中に沈んで、上にできた新しい珊瑚礁が現在の海面近くにほぼ平らな頂上を形成していることがわかりました。
海面上の小さな岩は、富士山の白雪や笠雲のような珊瑚礁で上部を覆われた古い巨大な山体の頂が、海上に突き出たものなのでした。
日本最南端の沖ノ鳥島のことを書いているうちに、幻の日本最東端の島 (サンズイのない)「中ノ鳥島」の存在(実は不存在)を知りました。
興味のある方は http://homepage3.nifty.com/boumurou/island/01/ganges.html をどうぞ。
| [29173] 2004年 6月 10日(木)13:27:31【1】 | hmt さん |
| 日本最高峰?沖ノ鳥島 | |
[29124]sutekinaおじさんが根性で求めて下さった自治体の高低差とは直接関係ないのですが、土地の高さに関する話題。
日本で一番高い場所は、富士山ではなくて沖ノ鳥島だという説があります。
たしかに沖ノ鳥島は深海からそびえ立つ雄大な海山[26266]ですが、「沖ノ鳥島=日本最高峰」説の根拠は麓からの高さではなく、地球の中心から測った高さ(地心距離)です。
下表のデータは、大久保修平編著:地球が丸いってほんとうですか?(朝日新聞社)によりましたが、感覚的に比較しやすいように、地心から6370kmを超える高さ(m)を示しました。
地球楕円体が張り出した赤道海面の地心距離は6378.1kmで、北極海面の地心距離6356.7kmよりも21.3kmも大きくなっています。この傾向があるために、日本最南端の沖ノ鳥島は、海面すれすれの高さながら、日本最高峰?の地位を獲得しました。
地心距離をモノサシにした世界の高山ベスト10は、最高峰チンボラソをはじめとしてアンデスの山々が占めます。唯一アフリカから5位のキリマンジャロが参入。
標高(ジオイド面=仮想的な海面 からの高さ)では世界最高のエベレスト(ネパール語ではサガルマータ「大空の頭」、チベット語でチョモランマ「世界の母神」)は、32位だそうです。
日本で一番高い場所は、富士山ではなくて沖ノ鳥島だという説があります。
たしかに沖ノ鳥島は深海からそびえ立つ雄大な海山[26266]ですが、「沖ノ鳥島=日本最高峰」説の根拠は麓からの高さではなく、地球の中心から測った高さ(地心距離)です。
下表のデータは、大久保修平編著:地球が丸いってほんとうですか?(朝日新聞社)によりましたが、感覚的に比較しやすいように、地心から6370kmを超える高さ(m)を示しました。
| 山名 | 緯度 | 標高m | 地心距離-6370000m |
| 沖ノ鳥島 | 20゜25.5'N | 0 | 5595 |
| 富士山 | 35゜21.6'N | 3776 | 4833 |
| 宮之浦岳(屋久島) | 30゜20.2'N | 1935 | 4631 |
地球楕円体が張り出した赤道海面の地心距離は6378.1kmで、北極海面の地心距離6356.7kmよりも21.3kmも大きくなっています。この傾向があるために、日本最南端の沖ノ鳥島は、海面すれすれの高さながら、日本最高峰?の地位を獲得しました。
地心距離をモノサシにした世界の高山ベスト10は、最高峰チンボラソをはじめとしてアンデスの山々が占めます。唯一アフリカから5位のキリマンジャロが参入。
標高(ジオイド面=仮想的な海面 からの高さ)では世界最高のエベレスト(ネパール語ではサガルマータ「大空の頭」、チベット語でチョモランマ「世界の母神」)は、32位だそうです。
| 山名 | 緯度 | 標高m | 地心距離-6370000m |
| チンボラソ(エクアドル) | 1゜29'S | 6310 | 14458 |
| キリマンジャロ(タンザニア) | 3゜05'S | 5895 | 13952 |
| エベレスト(ネパール・チベット) | 27゜59'N | 8848 | 12270 |
| [65212] 2008年 5月 21日(水)23:38:28【1】 | hmt さん |
| 東経154度・日本最東端の「中ノ鳥島」 | |
[64955] むっくん さん
[65198] 88 さん
北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島 及 沖ノ鳥島
「中ノ鳥島」という地名が出てきたら、思わず反応してしまいます。
市区町村変遷情報の本筋からは離れている余談なので、あまり気にしないでください。
明治41年(1908)のことです。山田禎三郎という人物が東京府小笠原島々司あてにリン鉱石のある無人島發見届を出しました。
拙者儀明治四十年八月中北緯三十度五分東経百五十四度二分ノ所ニ於テ一島嶼ヲ探検シ…
地積八分通り迄燐鉱堆積し其厚さは平均六尺位…鳥類馬鹿鳥(白黒)一見数百万羽を算す…
この「発見」に基づいて、東京府知事から内務大臣(原敬)あてに「新島嶼ノ行政區劃ニ関シ」上申。
原内相から下記のように請議がなされて、閣議決定。
位置は (中略) 他日確定の必要があるが、帝国の版図に属すべきは論なきを以て 自今該島を 中ノ鳥島 と名け 東京府小笠原島庁の所管と為さんとす
このようにして明治末期に日本の領土にになった「中ノ鳥島」は、その後の海図(概位 30°51′N、154°16′E)にも記されました。その概略位置は、南鳥島の北、鳥島の東ですが、南鳥島 (153°59′ E )よりもやや東になるので、南洋群島や千島を除けば「日本最東端」ということになります。
町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件 という勅令の中で、「中ノ鳥島」が指定されたことは 冒頭に引用したとおりです。
しかし、戦後の1946年になると、最近の十島村の記事[65138]でも話題になった「SCAP=連合国軍最高司令官(日本の新聞では「マ元帥」と表記)の Instruction Note」 [56190]によって、この島は “日本の範囲から除かれる” ことになりました。
SCAPIN-677 の第3項には、「南鳥島、中ノ鳥島」と明記してあります。
【追記】
原文 の表記は「Marcus (Minami-tori) and Ganges (Nakano-tori) Islands」
予備知識なしにここまでお読みの方は、「中ノ鳥島」の存在について、何の疑問も抱かれないかもしれません。
しかし、一見実在したように記録されている「中ノ鳥島」は、架空の島だったのです。
この落書き帳の 過去記事 でも言及していますが、詳しくは 幻想諸島航海記 のPart 1、2、3、9 をご覧ください。
Part 1 に示されている海図を見ると、中ノ鳥島付近は6000m近い深海で、とても島がありそうもない場所です。
海図に [E.D.] とあるのは、Existence doubtful の意味だそうで、海軍水路部も 島の存在を疑っていたことがわかります。
水路部は 島の不存在を確認して 戦時中の1943年1月に海図から削除したとも伝えられますが、戦時中に わざわざ敵に教えることもないと、これは軍機告示で行なわれたので、戦後の占領軍指令では、まだ中ノ鳥島が存在している扱いで、外周領域にも含まれることになりました。昭和18年の勅令も戦時中の削除処置より後。
【追記】
怪しげな「発見報告」に基づいて、実在しない島を日本の領土に編入してしまった明治41年の「閣議決定」は、20世紀も終り頃(1998年)になってからの第142回国会で問われたことがあります。
参議院総務委員会会議録 の中から、吉岡議員の質問の一部を引用しておきます。
(前略)ないことがわかった後の処理がきちっとやられていない、これではまずいというのが私の感じです。
昭和十八年に海軍水路告示で、実在しないからとりあえず海軍の水路図誌からは外すと。しかし、一般にはあることになって残っていて、これが昭和二十一年になって初めて水路告示(注)で「精測ノ結果存在シテイナイコトガ認メラレタ依テ図誌ヨリ削除スル」、地図から外すということになっていることがわかりました。私はこれがわかるのに、ぼつぼつの調査ですが、数年かかりました。
そうなると、もとの閣議決定というのは、これは一体いつどういう手続でどういうふうに処理されたか。地図から一方的に消すだけで、対外的に日本領だと言っていた島をどういう処理をしたのか。これはいろんなところに聞いてもまだわかりません。
注:昭和21年11月22日 水路告示第46号「南方諸島―中ノ鳥島 不存在」
確認したわけではありませんが、1500万トンのリン鉱石をタネにした怪しげな投資話でもあったのでしょう。
領土拡張の雰囲気の中で、政府までもが、結果的は投資話を裏付けるために踊らされてしまった ことを想像させる昔話でした。
[65198] 88 さん
北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島 及 沖ノ鳥島
「中ノ鳥島」という地名が出てきたら、思わず反応してしまいます。
市区町村変遷情報の本筋からは離れている余談なので、あまり気にしないでください。
明治41年(1908)のことです。山田禎三郎という人物が東京府小笠原島々司あてにリン鉱石のある無人島發見届を出しました。
拙者儀明治四十年八月中北緯三十度五分東経百五十四度二分ノ所ニ於テ一島嶼ヲ探検シ…
地積八分通り迄燐鉱堆積し其厚さは平均六尺位…鳥類馬鹿鳥(白黒)一見数百万羽を算す…
この「発見」に基づいて、東京府知事から内務大臣(原敬)あてに「新島嶼ノ行政區劃ニ関シ」上申。
原内相から下記のように請議がなされて、閣議決定。
位置は (中略) 他日確定の必要があるが、帝国の版図に属すべきは論なきを以て 自今該島を 中ノ鳥島 と名け 東京府小笠原島庁の所管と為さんとす
このようにして明治末期に日本の領土にになった「中ノ鳥島」は、その後の海図(概位 30°51′N、154°16′E)にも記されました。その概略位置は、南鳥島の北、鳥島の東ですが、南鳥島 (153°59′ E )よりもやや東になるので、南洋群島や千島を除けば「日本最東端」ということになります。
町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件 という勅令の中で、「中ノ鳥島」が指定されたことは 冒頭に引用したとおりです。
しかし、戦後の1946年になると、最近の十島村の記事[65138]でも話題になった「SCAP=連合国軍最高司令官(日本の新聞では「マ元帥」と表記)の Instruction Note」 [56190]によって、この島は “日本の範囲から除かれる” ことになりました。
SCAPIN-677 の第3項には、「南鳥島、中ノ鳥島」と明記してあります。
【追記】
原文 の表記は「Marcus (Minami-tori) and Ganges (Nakano-tori) Islands」
予備知識なしにここまでお読みの方は、「中ノ鳥島」の存在について、何の疑問も抱かれないかもしれません。
しかし、一見実在したように記録されている「中ノ鳥島」は、架空の島だったのです。
この落書き帳の 過去記事 でも言及していますが、詳しくは 幻想諸島航海記 のPart 1、2、3、9 をご覧ください。
Part 1 に示されている海図を見ると、中ノ鳥島付近は6000m近い深海で、とても島がありそうもない場所です。
海図に [E.D.] とあるのは、Existence doubtful の意味だそうで、海軍水路部も 島の存在を疑っていたことがわかります。
水路部は 島の不存在を確認して 戦時中の1943年1月に海図から削除したとも伝えられますが、戦時中に わざわざ敵に教えることもないと、これは軍機告示で行なわれたので、戦後の占領軍指令では、まだ中ノ鳥島が存在している扱いで、外周領域にも含まれることになりました。昭和18年の勅令も戦時中の削除処置より後。
【追記】
怪しげな「発見報告」に基づいて、実在しない島を日本の領土に編入してしまった明治41年の「閣議決定」は、20世紀も終り頃(1998年)になってからの第142回国会で問われたことがあります。
参議院総務委員会会議録 の中から、吉岡議員の質問の一部を引用しておきます。
(前略)ないことがわかった後の処理がきちっとやられていない、これではまずいというのが私の感じです。
昭和十八年に海軍水路告示で、実在しないからとりあえず海軍の水路図誌からは外すと。しかし、一般にはあることになって残っていて、これが昭和二十一年になって初めて水路告示(注)で「精測ノ結果存在シテイナイコトガ認メラレタ依テ図誌ヨリ削除スル」、地図から外すということになっていることがわかりました。私はこれがわかるのに、ぼつぼつの調査ですが、数年かかりました。
そうなると、もとの閣議決定というのは、これは一体いつどういう手続でどういうふうに処理されたか。地図から一方的に消すだけで、対外的に日本領だと言っていた島をどういう処理をしたのか。これはいろんなところに聞いてもまだわかりません。
注:昭和21年11月22日 水路告示第46号「南方諸島―中ノ鳥島 不存在」
確認したわけではありませんが、1500万トンのリン鉱石をタネにした怪しげな投資話でもあったのでしょう。
領土拡張の雰囲気の中で、政府までもが、結果的は投資話を裏付けるために踊らされてしまった ことを想像させる昔話でした。
この特集記事はあなたのお気に召しましたか。よろしければ推奨してください。→ ★推奨します★(元祖いいね)
推奨するためには、メンバー登録が必要です。→ メンバー登録のご案内